更新日:2026年1月14日
ここから本文です。
研究員の部屋
- 「千葉氏ゆかりの地めぐり(千葉市内編)」(外山信司) →最新記事へ
- 中世の城跡をめぐる(遠山成一) →最新記事へ
- 令和5年度特別展「関東の30年戦争『享徳の乱』と千葉氏」-宗家の交代・本拠の変遷、そして戦国の世の胎動-」あ・ら・か・る・と →最新記事へ
- 令和4年度特別展「我、関東の将軍にならん-小弓公方足利義明と戦国期の千葉氏-」あ・ら・か・る・と(遠山成一) →最新記事へ
- 「小弓公方足利義明」異聞 →最新記事へ
- 『千葉氏史料集』編さんノート(坂井法曄) →最新記事へ 【NEW】
- 「新聞にみる千葉のむかし スペイン風邪の蔓延 ~大正7年パンデミックから何を学ぶ?~(大関真由美)
- 卯兵衛さんの旅~江戸の旅と信仰(白井千万子)
- 坂東巡礼~房総の札所めぐり(前) (後)(白井千万子)
- 千葉の例大祭~ハレの日と信仰(No.1) (No.2) (No.3) (No.4) (No.5) (No.6) (No.7)(白井千万子)
- 下総三山の七年祭り~ハレの日と信仰(No.1) (No.2) (No.3) (No.4) (No.5) (No.6) (No.7)(白井千万子)
- 亥鼻散策~亥鼻神明社からお茶の水へ~(No.1) (No.2) (No.3) (No.4)(白井千万子)
- さつまいも関連の書籍紹介 その1 その2 その3(白井千万子)
- 千葉の年中行事 ~正月の行事・盆の行事・その他の行事~ その1 その2 その3(白井千万子)
-
市史編纂事業と和田茂右衛門氏(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)(白井千万子)
- 「芋の記」にみる昆陽神社(土屋雅人)
- 徳川家康が宿泊した千葉御殿はどうなった!?(土屋雅人)
コラム:千葉氏ゆかりの地めぐり(千葉市内編)
外山 信司(郷土博物館総括主任研究員)
- 千葉神社(1) (2) (3) (4) (5)
- 宝幢院
- 大内氏の妙見信仰(1) (2)
- 大日寺跡(現在の通町公園)(1) (2) (3)
- 来迎寺跡(現在の道場北1丁目)(1) (2) (3) (4)
- 光明寺
- 宗胤寺跡(中央区中央4丁目)
- 御殿跡(中央区中央4丁目)
- 堀内(中央区中央・院内・本町付近)
- 【番外編】鎌倉に住んでいた千葉氏(神奈川県鎌倉市)
- 結城(中央区寒川・港町・神明町・新宿町付近)
- 本円寺・本敬寺(中央区本町1丁目)
- 中世の千葉まちの範囲(1) (2)
- 大和橋と市場町
- 羽衣の松
- お茶の水(1) (2)
- 七天王塚(1) (2) (3) (4)
- 智光院
- 胤重寺
- 高徳寺(1) (2)
- 東禅寺(1)
当コラムでは、千葉市内にある千葉氏ゆかりの史跡や神社・寺院、伝承地などについて紹介します。千葉の地は、中世には千葉庄(ちばのしょう)という荘園でした。桓武平氏の一族で、ここを本拠とし、名字として名乗ったのが千葉氏です。千葉庄の中心であり、当館が位置する中心市街地から取り上げていきたいと思います。近年はまち歩きブームですので、皆様がこれを参考に千葉市内を歩き、千葉氏の歴史に触れていただければ幸いです。
1 千葉神社(1)
千葉氏やその一族家臣が氏神・軍神として篤く信仰した妙見を祀る神社で、千葉妙見宮、妙見社と呼ばれ、千葉氏の妙見信仰の中心でした。『千学集抜粋』(『千学集抄』)によれば、平忠常の乱を起こしたことで知られる忠常の子である覚算が、長保2年(1000)に開いたとされますので、一千年以上の歴史を有することになります。
妙見は北極星や北斗七星が神格化されたものですが、仏教と習合して妙見菩薩とも称されました。妙見宮は、中世には別当寺である北斗山金剛授寺尊光院と一体化し、一族や家臣が建立した六院六坊という寺院が付属していました。金剛授寺の座主(住職)には、千葉家当主の子や千葉家当主に近い人物が就任し、代々の千葉家嫡子が元服するなど、千葉氏の精神的支配の中枢としての役割を果たしました。
関東に戦国時代の幕開けを告げた享徳の乱の後、千葉氏は本拠を本佐倉城(酒々井町・佐倉市)に移しましたが、妙見宮は本佐倉に移ることはなく千葉の地に留まり、現代に至るまで千葉の人々の信仰を集めています。
2 千葉神社(2)
千葉神社の祭神は、明治維新後の神仏分離によって天御中主命(あめのみなかぬしのみこと)とされましたが、江戸時代までは妙見でした。中世の北斗山金剛授寺尊光院が、近世には妙見寺と改称されたのも、そのことをよく示しています。
妙見が千葉氏の氏神・軍神であったことは広く知られていますが、戦国時代になって千葉氏が本拠を本佐倉城(酒々井町・佐倉市)に移しても、千葉氏と一緒に本佐倉へ移らなかったのはなぜでしょうか。
妙見は、常に北の空にある北極星や北斗七星が神格化された神であり、方位方向や進路を示す神でした。『千学集抜粋』には、平将門と千葉氏の祖である平良文が上野国に攻め入った際に、染谷川(群馬県高崎市)で「此の川わたすべし」と言う妙見に浅瀬を教えられ、合戦に勝つことができたとの話が記されています。この説話は妙見の本来の性質をよく示しています。
したがって、妙見は船を操る海の民(水運業者や漁業者)に信仰されていました。近世の史料ですが、千葉神社と関係が深い現登渡神社(とわたりじんじゃ、千葉市中央区登戸)の「妙見尊宝前」に、多くの登戸の船乗りたちが「大般若経」を奉納しています(日色義忠「善光寺蔵大般若経の調査について」『四街道市の文化財』20号、1994年)。さらに人生を導き、運を開く神として商工業者(商人や職人)にも信仰されました。現在も関西では、能勢妙見(大阪府豊能郡能勢町)が人々の信仰を広く集めています。
つまり、妙見には千葉氏の氏神・軍神のほかに、湊町・商業都市として発展していた千葉のまちに住む人々の神という面も併せ持っていたのです。だからこそ本佐倉に移ることなく、千葉に在り続けたのではないでしょうか。武神としてだけではない、妙見の多様な面にも注目していきたいと考えています。
3 千葉神社(3)
戦国時代の永正6年(1509)、連歌師の宗長は、原胤隆の小弓館(千葉市中央区生実町)や本行寺(千葉市中央区浜野町)で連歌を詠み、千葉を訪れています。この宗長の旅は、紀行文「東路(あずまじ)のつと」(『新編日本古典文学全集48 中世日記紀行集』小学館、1994年)に描かれています。
ちなみに、宗長は千葉一族の東常縁(とうのつねより)から「古今伝授」を受けた宗祇の高弟で、宗祇・肖柏とともに詠んだ「水無瀬三吟百韻」は、連歌の最高傑作とされています。
宗長は、11月14日・15日の妙見宮(もちろん現在の千葉神社です)の祭礼に出かけ、300頭の早馬が街中を疾走する勇壮な様子を見物し、16日には延年の猿楽を見ました。
この記述から、千葉氏が本佐倉城(酒々井町・佐倉市)に本拠を移しても、千葉が廃れた寒村になったのではなく、湊町・商業都市・門前町として賑わっていたことがわかります。この繁栄を支えていたのは、千葉の水運業者や漁業者、商工業者たちでしょう。彼らは『千学集抜粋』に「千葉百姓中」とみえます(この「百姓」とは農民という意味ではなく、武士以外の様々な人々を示します)。
この「千葉百姓中」の妙見への厚い信仰が、千葉氏が本佐倉城へ移った後も千葉妙見宮を支えたのです。武神・軍神ではない、民衆を導き、運を開く神としての妙見の在り方が表れていると考えられます。
そして、戦国時代には、千葉氏当主の嫡男は本佐倉城から千葉へ来て、妙見宮で元服することが習わしになっていたのです。
なお、千葉神社の大祭といえば、北斗七星を神格化した妙見にちなんで7月に七日間行われましたが(現在は8月に行われています)、11月15日前後の祭礼も、7月に劣らぬ大規模なものであったことがわかります。『千学集抜粋』には、11月の「望(もち)」の日、つまり旧暦では満月の日である15日に祭礼があったことが記されています。
4 千葉神社(4)
千葉妙見宮・尊光院金剛授寺のトップは座主(ざす)と呼ばれました。初代の座主は平忠常の子の覚算です。覚算が大僧正であったように、歴代の座主は僧正・僧都・法印といった位を持つ僧侶でした。「神仏習合」のあり方をよく示していますが、武神・軍神として千葉氏の信仰を集めたため、座主には歴代の千葉氏当主の子が就任することになっていました。その中で異色なのは第十二代の範覚です。
『千学集抜粋』には「原胤隆の子範覚、十三歳にて座主とならせられ、四十三歳にて遷化、御神の御奉公三十年也」とあります。つまり、範覚は千葉氏の子ではなく、小弓城(千葉市中央区生実町)の城主で、千葉氏の重臣として大きな勢力を有した原胤隆の子でした。胤隆は連歌師宗長を招いて小弓で連歌の宴を催した人物です(「東路のつと」)。
戦国時代の原氏は、千葉氏胤の子の胤高に始まります。胤高の孫の胤房は、享徳の乱で馬加康胤を擁立し、千葉宗家の胤直たちを滅亡させた人物として知られています。千葉氏が本拠を本佐倉城(酒々井町・佐倉市)に移すと、千葉の地は原氏の支配下に置かれました。戦国時代の千葉氏が「香取の海」(現在の利根川水系に当たる、銚子から霞ケ浦・北浦・印旛沼・手賀沼などに至る湖沼が一体となった広大な内海)にシフトすると、江戸湾(現在の東京湾)に面した千葉は小弓城の原氏のテリトリーとなったのです。
そのため、原胤隆は子の範覚を座主として送り込んだと考えられます。妙見宮としても、遠い本佐倉の千葉氏より近くの小弓を本拠とする原氏の庇護を受ける方が、何かと好都合だったのでしょう。
事実、天文13年(1544)には原胤清が、元亀2年(1571)には原胤栄(たねよし)が神官の地位を認めています(「千葉神社文書」『千葉県の歴史 資料編 中世3(県内文書2)』)。胤清は範覚の兄弟に当たります。
このように小弓の原氏の強い影響下にあったことも、妙見宮が本佐倉に移らずに千葉に残った理由と考えられます。
5 千葉神社(5)
『千学集抜粋』には、天文19年(1550、ただし干支は「辛亥」とあるので、これに従えば翌1551年のこととなります)に妙見宮の遷宮が行われたことが記されています。社殿の建立は天文16年に始まりましたが、数年の歳月を費やして完成し、御神体を新しい社殿に遷す儀式が盛大に行われたのです。
最初に「国守」で「大檀那」の千葉親胤(ちかたね)が馬と太刀を奉納しました。馬を引いたのは馬場胤平、太刀を持ったのは原胤安でした。二番目に原胤清が馬と太刀を奉納しました。馬を引いたのは原胤行、太刀を持ったのは牛尾(うしのお)胤道です。三番目には牛尾胤貞が馬と太刀を奉納しました。馬の役は原胤次、太刀持ちは斎藤清家でした。まず下総の権力者トップスリーが、武士のシンボルである馬と太刀を神前に捧げたのです。
その次に、千葉氏の一族である「御一家」、親胤の近臣である「御近習侍衆」、領国内の武士たちである「国中諸侍衆」の順で、馬と太刀の奉納が行われました。
千葉氏の当主で「千葉介(ちばのすけ)」を称する親胤が、最初に守護神・軍神である妙見へ奉納するのは当然です。しかし、千葉一族である「御一家」より先に、原胤清とその嫡子の牛尾胤貞が奉納していることが注目されます。
なお、胤貞はこの時に「牛尾」を称していますが、牛尾(多古町)は原氏にゆかりの深い土地で、原氏は出身地ともいうべき千田庄(ちだのしょう、多古町)に大きな勢力を持ち、一族の牛尾氏もいました。このため、胤清は自分の嫡男に牛尾を名乗らせたのでしょう。胤貞はこの後、臼井氏を追って臼井城(佐倉市)を手に入れ、さらに原氏を発展させます。
千葉氏の権力をアピールする絶好の機会であった遷宮でしたが、実際は戦国期の下総国が千葉氏と原氏の連立によって支配されていたことを示す場となったのです。しかも、千葉宗家は親胤一人でしたが、原氏は当主の胤清と嫡男胤貞の二人が馬・太刀を奉納し、主君の親胤より存在感を示しています。このことからも、千葉妙見宮と原氏との結び付きがうかがわれます。
ちなみに、黒田基樹氏はこの記事を詳しく分析し、戦国時代の千葉氏の権力のあり方を明らかにしています(「戦国期千葉氏権力の政治構造」『千葉県の歴史』13号、2007年)。
妙見宮(千葉神社)に伝わった古記録である『千学集抜粋』には様々なことが記されていますが、特に「ハレ」の場である儀式の記事には、権力のあり方や社会の様子がよく反映されています。その丹念な読み込みによって中世を明らかにすることができるのです。
6 宝幢院
千葉神社の北側、院内1丁目にある真言宗寺院です。千葉妙見宮と一体となっていた北斗山金剛授寺(近世には妙見寺)には、「六院六坊」などと呼ばれた子院(しいん)が付属し、その僧侶たちは、大祢宜(おおねぎ)たち神官とともに妙見宮・金剛授寺に出仕していました。円満山宝幢院(ほうどういん)はただ一つ現存する子院ですが、現在は独立した寺院となっています。
『千学集抜粋』によると、千葉常重の子で金剛授寺三世の宥覚(ゆうかく)が保延3年(1137)に開きました。当寺について『千学集抜粋』には次のように記されています。
「先代ハ、住寺(持)・供分菩薩所法東院といふ院家に、位牌を立おき、夏中経、二記の彼岸経をハ、六人参て読給ふ、盆の棚をも此院家に結ひて、住持供分まゐりて、水を手向け、代々を吊(弔か)申也、住持の居所には位牌を立すして、彼院家に立て申也、」
文中の「法東院」とは宝幢院のことです。長い引用になりましたが、これを読んでいただくと、宝幢院が座主(ざす)や僧侶の位牌所であったことがよくわかります。前にも述べたように、金剛授寺の住持(住職)である座主は僧侶でした。しかし、亡くなった座主の供養は金剛授寺では行わず、宝幢院に位牌を置き、盂蘭盆(うらぼん)の法要や読経を行っていたのです。近世には座主や僧侶だけでなく、妙見寺の寺領に住む門前百姓の回向(えこう)も行っていました。境内には、今も歴代座主や僧侶の墓碑である五輪塔や卵塔などが残されています。
現代の私たちは、お寺と言えば墓があり、葬式や先祖の供養を行うというイメージを持ちますが、中世や近世にはもっぱら祈願を行い、死者の供養をしない寺院もありました。金剛授寺(妙見寺)もそのような寺院でした。他にも、檀林と呼ばれる寺院は檀家がないところも多く、僧侶を養成し勉学を深めるための学問所でした。
7 大内氏の妙見信仰(1)
千葉に住む私たちにとって、千葉氏と言えば妙見、妙見と言えば千葉氏というように、千葉氏と妙見は切っても切れない関係にあります。しかし、妙見を篤く信仰した武士は千葉氏だけではありません。中国地方の雄として知られる戦国大名の大内氏も篤く妙見を信仰していました。
少々脱線しますが、妙見をまつる千葉神社とその子院であった宝幢院の次に、大内氏の妙見信仰について紹介したいと思います。
大内氏は周防国(山口県)の多々良氏(たたらし)の一門で、同国吉敷郡大内村(山口市大内)を名字の地とします。大内氏は、有力な在庁官人として国司の二等官である「介(すけ)」となり、「大内介(おおうちのすけ)」を称しました。この「地名+介」の名乗り方は、「千葉介(ちばのすけ)」を称した千葉氏とまったく同じパターンです。国府には京から赴任した国司のほかに、現地の有力者も役人として勤めていました。彼らを在庁官人と言いますが、千葉氏は下総国の、大内氏は周防国の介でした。
大内氏は、大内村にあった興隆寺(天台宗)の氷上山妙見社に祀られた北辰妙見菩薩を「氏神」として信仰し、延命祈願から農耕のための請雨(雨乞い)、戦の勝利まで、領国支配の安定を祈っていたのです。
大内政弘の幼名(元服前の名前)は「亀童丸」です。その嫡子の義興、さらに義隆も「亀童丸」で、三代にわたり同じ幼名を称しました。これにより一族の中で、惣領家の正当性を示す意図があったと考えられています。
ちなみに、この「亀童丸」は千葉頼胤の幼名「亀若丸」と大変よく似ています。妙見は霊亀(玄武)に乗る童子の姿で表されます。大内氏も千葉氏も、嫡子に氏神である妙見の加護を願い、その正当性を示すため、妙見にちなむ「亀」を用いた幼名を付けたのです。
このほかにも千葉氏と大内氏との共通性がありますので、次回も紹介していきます。なお、大内氏の妙見信仰については、平瀬直樹氏『大内氏の領国支配と宗教』(塙書房、2017年)などを参照しました。
8 大内氏の妙見信仰(2)
千葉氏が「桓武平氏」に属することは言うまでもありません。桓武天皇の皇子葛原親王の孫である高望王が「平」の姓を賜り、桓武平氏の祖となりました。千葉氏はその子孫で、平良文(たいらのよしぶみ)の流れなので良文流平氏と言われます。
桓武天皇の母は高野新笠(たかののにいかさ、790年没)です。新笠の父は和乙継(やまとのおとつぐ)で、和氏は百済(くだら)の武寧王の子孫とされています。つまり、桓武平氏は、その祖である桓武天皇の時から百済系渡来人と深い縁がありました。そして、桓武平氏が武士として発展する過程で、武芸に不可欠な馬などに関する技術を持った渡来系の人々の信仰である妙見を取り入れたと考えられています。
ところで、大内氏は百済の聖明王の第三王子である琳聖太子が祖であると主張しました。その背後には朝鮮との貿易を有利に進めたいという思惑もあったと考えられます。その真偽はともかく、百済とのゆかりは妙見信仰を持つうえで大きな意味があったはずです。百済との関係も、桓武平氏と共通するものがあります。
さらに、大内氏は妙見が琳聖太子を守護するために周防国に下降したという先祖伝説を作り上げ、妙見と大内氏とを結び付けます。こうして妙見信仰を領国支配のイデオロギーとしていくことも、政治的な危機に際して、妙見に加護された惣領のもとに一族が強固に団結したというストーリーを作った千葉氏とまったく同じです。このように、千葉氏と大内氏はともに妙見を篤く信仰し、いくつもの共通点を持っていました。
また、秩父夜祭りで有名な秩父神社もかつては「秩父妙見宮」と呼ばれ、妙見をまつっています。秩父氏も良文流平氏で、妙見信仰が関東や甲信越の牧が多かった地帯に広がっていることもよく知られています。
北陸の名族である富樫氏も北斗七星と北極星を信仰し、家紋は北斗七星と北極星を表す八曜紋です。室町期の成春の幼名は「亀童丸」でした。富樫氏は加賀国(石川県)の「介」を世襲したので、「富樫介」(とがしのすけ)と称しました。これも「地名+介」のパターンで、千葉氏と同じです。
妙見信仰を千葉県内、千葉氏との関係だけで考えるのではなく、全国的、さらには東アジア的な広い視野で考えることが大切であると思っています。
9 大日寺跡(現在の通町公園)(1)
「千葉家累代の墓塔」と伝えられる五輪塔群(千葉市指定文化財)で知られる阿毘廬山密乗院大日寺(あびらさんみつじょういんだいにちじ、真言宗)は、かつて千葉神社の南側に隣接する通町公園の場所にありました。昭和20年(1945)の空襲で焼失し、戦後、稲毛区轟町へ移転し、戦災復興の都市計画により跡地は公園となりました。
轟町の大日寺には、千葉常兼から胤直・胤将までのものとされる五輪塔のほか、層塔もみられます。現在も残る部材を数えると、五輪塔は100基以上あったと考えられます。その中でも高さ約250cmを測る安山岩製の五輪塔(1号塔)は、律宗様式の本格的な大型塔で、鎌倉時代後期から南北朝時代の優れた石造物です。
大日寺の石造物については、当館の委託により早川正司氏が調査を行いました。その成果は当館の『研究紀要』26号(2020年)に発表されています。
金沢称名寺(横浜市金沢区)に残る聖教(しょうぎょう、僧侶の修学や宗教活動に用いられた仏教の典籍類)には「下州千葉之庄大日堂」などとみえ、大日寺の前身とも考えられます(『千葉県史料 中世篇 県外文書』1966年などを参照)。大日堂では称名寺長老の剱阿(けんあ)が聖教を書写するなど、関東における律宗の中心的な寺院であった称名寺と深い結びつきがあったことが明らかになっています。
中世・近世の千葉は、現在の東京湾(当時は「内海」などと呼ばれていました)に面した湊町でした。称名寺や千葉の僧侶たちは、船で東京湾を往来しました。だからこそ、本格的な律宗様式の五輪塔が千葉に作られたのです。下総国内に多くあった称名寺領の年貢も、千葉から船で送られたことでしょう。
船で称名寺のある金沢に着き、朝比奈峠を越せばすぐに鎌倉です。千葉氏もこのルートで鎌倉の幕府と行き来していたはずです。称名寺との密接な関係は、盛んな水運とそれをもとにした鎌倉と千葉の結びつきを物語っています。
なお、弘化2年(1845)に書かれた大日寺の縁起によれば、創建時には「覆溺の患い」を除くことを祈ったとされます(和田茂右衛門『社寺よりみた千葉の歴史』1984年)。「覆溺」とは船が転覆し乗っていた人が溺れることです。このことも千葉のまちが水運によって栄えていたことを示しているように思えます。
10 大日寺跡(現在の通町公園)(2)
縁起にみる律宗との関係
『鎌倉大草紙』は、室町時代の関東について記した軍記物として高い史料価値を持っていますが、大日寺について次のような記述があります。(『改訂房総叢書』第5輯、1959年所収)。
・大日寺は千葉頼胤が鎌倉極楽寺の良観を開山として小金の馬橋(松戸市)に建立した千葉氏の菩提寺で、貞胤の時に千葉へ移った。
・康正元年(1455)、胤直たち千葉宗家が多古城・島城(多古町)で馬加康胤・原胤房に滅ぼされた際、胤直ら遺骨が大日寺へ送られ、石造の五輪塔が建てられた。
良観とは、西大寺流律宗(真言律宗)の僧侶として有名な忍性(にんしょう)の号です。忍性は鎌倉の極楽寺や三村山清凉院極楽寺(茨城県つくば市)を拠点として律宗を広めました。大日寺が忍性によって開かれたと伝えられていることは、大日寺が律宗寺院であったことを意味します。
宝治合戦(1247)の後、北条氏の勢力拡大とともに房総に律宗が広がりますが、そのような流れの中で大日寺も律宗系の寺院となったのでしょう。北条氏を後ろ盾とした律宗と禅宗(臨済禅)は、当時最先端の宗派でした。
前回述べたように、金沢称名寺と大日寺は深い結びつきを持っていました。称名寺が極楽寺・清凉寺とともに関東における律宗の拠点だったことをふまえれば、忍性が大日寺を開いたという伝承は無視できません。
現在、大日寺に残る大型の五輪塔は「本格的な律宗様式」の石塔ですが、律宗寺院であった大日寺にこのような優れた石造物があるのも当然といえましょう。ちなみに律宗様式の五輪塔には銘文がありませんが、大日寺の五輪塔のほとんどに銘文が見られないのも律宗の様式にのっとっているからかもしれません。
なお、弘化2年(1845)の大日寺縁起によれば、「仁生菩薩」が天平宝字元年(757)に当寺を建立したと伝えられていますが、この仁生は忍性のことでしょう。律宗は古代寺院を復興することが多く、新しく寺院を開いた場合も古代からあった寺院であると主張しました。この縁起にも、そのような律宗の特徴がよく表れています。
11 大日寺跡(現在の通町公園)(3)
昭和38年(1963)3月、通町公園の整備工事を行っていたところ、地下約1m 20cm から梵鐘が出土しました。その場所は、和田茂右衛門氏によれば、戦災で焼失した大日寺本堂の向拝(ごはい)の下付近にあたるそうです(『社寺よりみた千葉の歴史』1984年)。
銅で鋳造されたこの梵鐘は、千葉市指定文化財(工芸品)に指定され、当館に収蔵されています。高さ1m15cm、口径66cmで、次のような銘文が刻まれています(『千葉県史料 金石文篇 一』1975年)。
(梵字)アビラウンケン
諸行無常 是生滅法
生滅々已 寂滅為楽
下総国相馬郡安楽寺推鐘
大勧進沙門栄金
大檀那尼 覚妙
大工神屋 行家
康永三年甲申十一月一日
梵字(サンスクリット)で書かれていますが、「アビラウンケン」とは地水火風空を象徴する真言(しんごん)です。「諸行無常 是生滅法 生滅々已 寂滅為楽」とは『涅槃経』(ねはんぎょう)の有名な一節です。
この銘文によって、下総国相馬郡安楽寺の梵鐘で、康永3年(1344年)に勧進僧の栄金、大檀那の尼覚妙によって造られたことがわかります。神屋行家は鋳物師の棟梁です。
安楽寺は、現在も龍ケ崎市川原代町(かわらしろまち)にある天台宗の寺院で、JR常磐線龍ケ崎市駅(今年の3月に佐貫駅から改称)の近くに位置します。
安楽寺には文和2年(1353年)、「天台堅者賢海法印」が住持であった際に「大勧進沙門栄金」が造った鰐口(わにぐち)が遺されています(茨城県指定文化財)。この栄金は梵鐘の銘文にある栄金と同一人物ですが、ほぼ同時期に同じ人物が造ったもののうち、なぜ梵鐘だけが千葉に運ばれ、大日寺の地下に埋められたのか、ミステリーとしか言いようがありません。しかも、大日寺にはこのような梵鐘があったという記録はまったくありません。
しかし、突然出土した670年も前の梵鐘は、都市化のため破壊され尽したと思われてきた中世の千葉のまちが、足元に眠っている可能性を示しています。かつてこの場所に大日寺があった時は、千葉神社と大日寺が甍を並べ、壮観だったことでしょう。千葉市では2026年の「千葉開府900年」を目指して、通町公園を中世を感じられるスポットとして整備する計画が進んでいます。
12 来迎寺跡(現在の道場北1丁目)(1)
智東山聖聚院来迎寺(ちとうさんしょうじゅういんらいこうじ)は、中世には時宗の寺院でした。近世には浄土宗に属し、天正18年(1590)に徳川家康から朱印地10石を寄進されました。かつては千葉神社の北東約300メートルに位置する中央区道場北1丁目に広い境内がありましたが、昭和20年(1945)の戦災で焼失し、戦後、大日寺とともに稲毛区轟町へ移転しました。その跡地は住宅地となっています。
寺伝によれば、建治2年(1276)に千葉貞胤が一遍を開山として建立し、「来光寺」と称したとされます。一遍智真は時宗の開祖で、全国各地を巡り踊念仏を通して布教し、遊行上人(ゆぎょうしょうにん)と呼ばれました。
時宗では寺を「道場」と称しました。道場といえば、現代の私たちは柔道や剣道などの武道を行う場所をイメージしますが、時宗では地名を冠して寺を呼びました。例えば、藤沢道場とは清浄光寺(神奈川県藤沢市)、当麻道場とは無量光寺(神奈川県相模原市南区)、芝崎道場は日輪寺(東京都台東区)のことです。中央区道場北・道場南という町名は「千葉道場」、すなわち来迎寺があったことに由来します。
来迎寺本尊の木造阿弥陀如来立像(市指定文化財・彫刻)は13世紀後半の美しい仏像で、創建時以来の本尊と考えられています(『千葉市の仏像』1992年)。
今も境内には、千葉氏胤(語阿弥陀仏)、氏胤の夫人と伝えられる円勝禅尼、千葉満胤(弥阿弥陀仏)、吉原見阿、光阿弥、母妙仏、某禅定門の7基の石造五輪塔(市指定文化財・建造物)が並んでいます。これらのうち、円勝禅尼、千葉満胤、某禅定門以外の4基は、いずれも応永32年(1425)2月15日という同じ年月日が刻まれています。旧暦の2月15日は彼岸に当たるので、氏胤とそのゆかりの人たちの追善供養のため同時に建立されたものと考えられます。室町期に制作されたことが明らかな比較的大型の五輪塔がまとまって残り、千葉氏関係の文化財として貴重です。
なお、来迎寺の石造物については、大日寺等とともに早川正司氏が調査を行いました。その成果は当館の『研究紀要』26号(2020年)に発表されています。
13 来迎寺跡(現在の道場北1丁目)(2)
今回は、来迎寺に五輪塔のある千葉氏胤について紹介します。
氏胤の曾祖父頼胤には、宗胤・胤宗の二人の男子がいましたが、長男の宗胤はモンゴル襲来(元寇)に備えるため、九州にあった所領の肥前国小城郡(佐賀県)に留まりました。これに対して弟の胤宗は下総を支配したため、千葉氏は肥前千葉氏と下総千葉氏に分裂したのです。
さらにこの対立に南北朝の内乱がリンクし、一族の争いは激化しました。肥前千葉氏は北朝に属したのに対し、下総千葉氏は南朝に属したのです。ところが、氏胤の父貞胤は北朝方に降伏しました。足利尊氏は貞胤に本国の下総を安堵しただけでなく、伊賀(三重県)・遠江(静岡県)の守護にも任じ、当初は南朝方でありながら足利政権に一定程度重く用いられました。室町時代の千葉氏の発展は、貞胤によってもたらされたといえましょう。
氏胤も尊氏に仕え、父と同じく下総・伊賀の守護となり、さらに下総に隣接する上総の守護職も手中にしました。鎌倉時代の宝治合戦(1247年)で上総千葉氏が滅亡して以来、上総での千葉氏の勢力は著しく低下しましたが、氏胤が守護となったことは、千葉氏が上総へ勢力を伸ばすうえで大きな意味がありました。なお、貞胤・氏胤父子は基本的には京都にいたようです。
氏胤は歌人でもありました。『新千載和歌集』(1359年)は、足利尊氏の意向を受けた北朝の後光厳天皇の命で編纂された18番目の勅撰和歌集です。その第11巻「恋歌1」に、忍ぶ恋の悲しさを詠んだ氏胤の和歌が載せられています。
題しらず 平 氏胤
人しれずいつしかおつる涙河わたるとなしに袖ぬらすらん(1084)
古代・中世では、天皇の命で作られた勅撰集に自分の歌が載ること、つまり勅撰歌人となることはこの上ない名誉とされました。千葉氏の一族で勅撰歌人となったのは、「歌の家」として知られる東氏(とうし)以外には氏胤だけです。
氏胤が勅撰歌人となったのは、血統の上では嫡流の肥前千葉氏に対して、庶流であった下総千葉氏の地位が、足利氏の治める当時の社会で正当な権力であることが認められたことを意味しています。氏胤は下総千葉氏の地位を確立したという点で大きな功績がありました。
氏胤は貞治4年(1365)9月13日に没しました(『本土寺過去帳』、『千学集抜粋』)。来迎寺の氏胤塔の銘文には応永32年(1425)2月15日とありますので、31回忌を迎えた年の彼岸に建立されたのかもしれません。
14 来迎寺跡(現在の道場北1丁目)(3)
千葉氏胤と仏教との関わりで忘れてはならないのが、その子であった酉誉聖聡(ゆうよしょうそう)です。浄土宗の大本山で、徳川将軍家の菩提寺となった増上寺(東京都港区)を開いたことで知られています。幼名は徳千代丸といいましたが、僧籍に入って真言密教を学び、後に浄土宗の高僧聖冏(しょうげい)の弟子になりました。浄土宗は徳川家康の帰依を受けましたが、当寺は家康の命で時宗から浄土宗に改められたと伝えられています。ちなみに、市内の大巌寺(中央区)も徳川家の保護を受け、檀林として繁栄しました。
氏胤には、酉誉と嫡子満胤の他に千田宗胤、馬場重胤、原胤高といった子たちがいました。重胤の曾孫が、馬加千葉氏(まくわりちばし)を継承し、本佐倉城(酒々井町・佐倉市)を築き、千葉から本拠を移したとされる輔胤です。胤高は戦国時代に小弓城(中央区)や臼井城(佐倉市)を拠点に、千葉氏に匹敵する地域権力に成長を遂げた原氏の祖です。氏胤の子どもたちは、仏教、政治の両面で後世に大きな影響を与えていくことになります。
ところで、前にも述べたように、当寺は時宗(時衆)の「千葉道場」でした。氏胤の父貞胤が時宗を取り入れたのです。『千学集抜粋』には、貞胤について「此御代より時宗にならせられ」と記されています。孫満胤の法号は「徳阿弥陀仏」で、以後の千葉氏当主は漢字1文字+阿弥陀仏という時宗式の法号を持つようになりました。例えば、千葉昌胤は法阿弥陀仏、親胤(ちかたね)は眼阿弥陀仏です。戦国時代の千葉氏の菩提寺で、千葉氏歴代の石塔が残る海隣寺(佐倉市)も時宗です。
当麻山無量光寺(神奈川県相模原市南区)は、清浄光寺(神奈川県藤沢市)と並ぶ時宗の大本山ですが、千葉昌胤は同寺27代住職の智光に帰依しました。昌胤は智光の訪問を受けて面会できたことを「満足至極に候」と喜んでいます(「千葉昌胤書状」『千葉県の歴史 資料編 中世4(県外文書1)』2003年)。
来迎寺は千葉氏の保護を受けて寺勢も盛んでした。無量光寺の歴代住職をみると、第5代慈光(康永3年・1344没)から28代良元(天文20年・1551没)までの23代のうち、15人が当寺から就任しています(『当麻山の歴史』1974年)。当寺が時宗教団の中で大変有力な存在であったことがうかがわれます。
15 来迎寺跡(現在の道場北1丁目)(4)
前にも述べたように、千葉妙見宮(現在の千葉神社)と来迎寺は近い位置にありました。妙見宮は真言宗の金剛授寺と一体化していましたが、時宗(時衆)は妙見宮にも勢力を伸ばしていったようです。『千学集抜粋』には、金剛授寺の住職がいなくなったとしても「時宗なと申立る事叶ふまし」とあって、時宗に対する強い反発がみられます。しかし、千葉氏を檀那とした時宗が、軍神・氏神として深く千葉氏と結びついていた妙見宮に入り込んでいくのは当然ともいえましょう。
真名本系の『曾我物語』には、曾我十郎の恋人であった大磯の虎御前が、兄弟の母を訪ねたあと、非業の最期を遂げた兄弟の骨を首に掛け、鎮魂のために諸国の霊場を巡拝したことがみえます。虎御前は善光寺(長野県長野市)から碓井峠を越えて関東に入り、板鼻宿(群馬県安中市)、二荒山神社(栃木県宇都宮市)、中禅寺(同日光市)などを経て千葉妙見宮へ参詣します。そして浅草寺(東京都台東区)、慈光山(埼玉県ときがわ町)などを経由して曾我(神奈川県小田原市)へ帰りました(梶原正昭他『新日本古典文学全集53 曾我物語』2002年)。一遍が開いた板鼻宿の聞名寺が善光寺参詣の拠点であったように、虎御前は時宗の遊行廻国のコースをたどっています。この虎御前の行動は「念仏聖」そのものであり、『曾我物語』の成立に時宗教団が深く関わっていたことが明らかになっています(角川源義「貴重古典叢刊3 妙本寺本曾我物語」1969年)。
金井清光氏は「全国各街道の時衆道場は遊行僧ばかりでなく、御師・山伏・行商人など、種々雑多な旅人が休息したり宿泊したりする。当然、時衆道場には諸国の珍談奇聞や世間話などの情報が集中する。住職は居ながらにして諸国の説話や情報を仕入れることができ、それをまた遊行者に語って聞かせる。遊行者は時衆道場で聞いた話を、行く先々に語り伝えてゆく。つまり街道上の時衆道場は、在地の念仏信仰の中心であると同時に、説話など語り物文芸の集散所でもあった。」と述べています(『時衆の美術と文芸-遊行聖の世界』1995年)。
「千葉道場」(来迎寺)もそのような場であり、千葉妙見宮が真名本『曾我物語』に登場することは、時宗のネットワークの中にあったことを意味します。『千学集抜粋』などに記された様々な説話の中には、時宗によってもたらされたものもあることでしょう。『千学集抜粋』には、千葉胤宗が千葉庄内に7体の阿弥陀を建立したという記事がありますが、北斗七星を神格化した妙見との関連がうかがえます。妙見信仰と時宗などの浄土信仰との習合を示していると考えられます。
千葉には、本町に本円寺、本敬寺といった日蓮宗寺院があり、時宗だった来迎寺、律宗系寺院であった大日寺もありました。金剛授寺に加えて、これらの宗派の寺院が集まっていたことは、中世の千葉が都市的な場として繁栄していたことを示しています。
16 光明寺(中央区中央4丁目)
真言宗の寺院で、近世には妙見寺(中世には妙見宮・金剛授寺、現在の千葉神社)の末寺でした。本尊は木造不動明王立像です。頭部と首の内側に記された墨書銘によると、文明2年(1470)2月に千葉寺に住む河野修理某によって彩色され、同年4月に千葉寺の大覚坊涼順の志によって造立されたことがわかります。昭和20年(1945)の空襲によって体部・光背・台座が焼失し、頭部のみが残されたことは大変惜しまれますが、リアルな肉付きと迫力ある憤怒の面相は15世紀の関東地方の彫刻の中で屈指の正統的・本格的な作例として高く評価されています(千葉市教育委員会『千葉市の仏像』1992年)。
「下総国千葉郷北斗山妙見寺縁起」には、千葉常重が妙見宮の南方に虚空蔵堂を営み「月処山光明寺」と号したとみえます(千葉市立郷土博物館『妙見信仰調査報告書』1992年)。『千葉大系図』には、大治元年(1126)に常重が本拠地を千葉へ移した際に「月処山光明寺、本尊不動明王」を建立したと記されています(『改訂房総叢書 第五輯』1959年)。また、戦時中に金属献納のため失われた、元禄4年(1691)に鋳造された梵鐘の銘文は、金剛授寺の住持であった栄慶が記したものですが、一条天皇の勅願によって妙見堂と同じ所に造営されたとありました。その後、衰えたこともあったようですが、永禄9年(1566)に千葉勝胤の子で金剛授寺十三世常覚が再興したと伝えられています(和田茂右衛門『社寺よりみた千葉の歴史』1984年)。明治以降は独立した寺院となりました。このように、妙見宮と密接な結び付きを持ち、常重が千葉のまちを開いた時から今に続く寺院として重要です。
当寺はかつてQiball(きぼーる)前の大通りの下り車線から北側、現在の中央3丁目にあり、虚空蔵堂と地蔵堂が東に面して建っていました。当寺の境内にあった蓮の茂る池が花街として知られた「蓮池」の由来とされます。
ところが、本町交差点から京成千葉中央駅を結ぶ大通り(市道京成千葉中央駅線)の拡幅のため、大通り南側、現在Qiballのある場所に移りました。さらにQiball建設のため、吾妻橋を渡る通りに面した現在地に移りました。このように寺地は度々変わりましたが、今も「千葉の不動尊」として人々の変わらぬ信仰を集めています。
17 宗胤寺跡(中央区中央4丁目)
千葉県庁から都川に架かる羽衣橋を過ぎ、スクランブル交差点を渡ると左側に県庁立体駐車場があります。その敷地が宗胤寺のあったところです。交差点に面して「明治天皇行在所旧蹟」の大きな石碑が建っています。明治15年(1582)に明治天皇が千葉へ行幸されたことを記念した碑で、陸軍大将一戸兵衛の書です。
当寺は、曹洞宗の寺院で山号は本光山、御本尊は十一面観音です。寺伝によると千葉宗胤が父頼胤や一族家臣のために建立し、境内に「伝千葉宗胤五輪塔」(千葉市指定文化財)がありました。その傍には「御廟の松」と呼ばれた古い松の木があったそうです。昭和20年(1945)の千葉空襲で堂宇を焼失し、戦後、千葉競輪場に隣接する中央区弁天町の現在地へ移転しました。宗胤の五輪塔もここへ移されています。この石塔は、空風輪は後世に補われたものですが、火輪・水輪・地輪にはそれぞれ梵字が刻まれ、15世紀中葉頃のものと考えられています。
当寺を開いたとされる千葉宗胤は、肥前千葉氏の祖となった人物です。宗胤の父胤頼は鎌倉幕府の命令で、モンゴル襲来に備えて九州に滞在していました。常胤以来、肥前国小城郡(佐賀県小城市)は千葉氏の領地であったからです。そして、頼胤は文永の役(1274)で受けた疵のため、建治元年(1275)に没してしまいました。頼胤には嫡子宗胤と二男胤宗の二人の男子がいましたが、兄の宗胤は引き続き小城に残り、弟胤宗が下総の支配を担当することになりました。宗胤の子孫は肥前千葉氏となり、胤宗の子孫は下総千葉氏となりますが、モンゴル襲来は千葉氏の分裂を招いたのです。そして、南北朝の内乱に肥前千葉氏と下総千葉氏との対立がリンクし、下総国内も深刻な戦乱状態に陥ることになります。
宗胤は大隅国(鹿児島県東部)の守護となり、同国の御家人たちを率いて異国警固番役を務めるとともに小城郡の支配も進めて行きました。宗胤は禅宗に帰依し、円通寺(佐賀県小城市、臨済宗)へ常胤以来代々の菩提を弔うために寺領を寄進しています。永仁2年(1294)に宗胤は九州で没しましたが、肥前千葉氏は戦国期にかけて勢力を伸ばしていきます(千葉氏研究プロジェクト(代表宮島敬一)編『中世小城の歴史・文化と肥前千葉氏』佐賀大学地域学歴史文化研究センター、2009)。
その後、肥前千葉氏は内紛を起こし、一族は近世には鍋島氏の家臣として存続していきます。明治維新の際に活躍して司法卿となり、佐賀の乱で首領となって敗死した江藤新平も肥前千葉氏に仕えた家の子孫とされています。
千葉氏の名字の地である千葉に、血統の上では嫡流であった肥前千葉氏の祖である宗胤ゆかりの寺院が今も残ることは大変重要なことです。また、当寺はかつて都川に面した場所にありましたが、千葉氏と水運との関わりという点でも注目されます。
18 御殿跡(中央区中央4丁目)
千葉銀座通りを挟んで宗胤寺跡(県庁立体駐車場)の反対側に、千葉地方裁判所等があります。その敷地が「御殿跡」と呼ばれた場所です。現在は大きなビルが建っていますが、一辺約100メートルの方形の区画であり、宗胤寺跡と同じく南側は都川に面しています。それ以外の周囲は堀の跡と考えられる水田と土塁に囲まれていました(簗瀬裕一「中世の千葉-千葉堀内の景観について-」『千葉いまむかし』11号、2000年)。
この場所が徳川家康の滞在した「千葉御殿」の跡です。家康は鷹狩りのため何度も下総や上総を訪れました。水戸黄門として知られる徳川光圀は、延宝2年(1674)4月27日に千葉へ来ましたが、その紀行文「甲寅紀行」(『改訂房総叢書』第4輯、1959年)には次のように記されています。
千葉の町を出づる所の左の方に、古城あり。伊野花と云ふ。(中略)右の方に松の森あり。「東照宮御旅館の跡なり」と云ふ。
光圀は佐倉街道(現在の国道51号線)を通って千葉の町に入り、妙見寺(現千葉神社)と来迎寺(道場北にあった)について記しています。その次にこの記述があるので、本町通り・市場町通りを経て寒川へ行き、房総往還を通って上総・安房へ向かったと考えられます。市場町通り、今の県庁あたりから見ると、左に亥鼻山、右に「御殿跡」が位置するので、光圀の記載内容と一致します。光圀は家康(東照宮)の孫ですから、祖父の滞在した御殿の跡にひときわ関心を持ち、正確に記録したのでしょう。
千葉市内にあった徳川家康の御殿としては、土塁・空堀等の遺構が良好に残る「千葉御茶屋御殿」(市指定文化財、若葉区御殿町)が有名です。しかし、これとは別に「千葉御殿」が設けられていたのです。近世初期の姿を伝える絵図「下総一国之図」(船橋市西図書館蔵)でも、川(都川)に面した御殿と御成街道に面した御殿の二つが明確に描き分けられています。市内には徳川将軍家の二つの御殿があったのです(簗瀬裕一「千葉におけるもう一つの御殿跡-千葉御殿と千葉御茶屋御殿-」『千葉いまむかし』18号、2005年)。
ところで、この「御殿跡」について和田茂右衛門氏は「御殿跡の御殿が、千葉氏の屋敷跡ではないかと考えると、亥鼻山上に城を築き忠常はこの屋敷に住まい、一朝有事の際には、山上に家族郎党の者どもと籠って敵と戦ったのではないでしょうか。」と述べています(『社寺よりみた千葉の歴史』1984年)。忠常についてはともかく、「御殿跡」が千葉氏の館の跡ではないかと推定されたことは注目されます。
千葉氏の館の位置は不明ですが、「御殿跡」はその候補地の一つです。ちなみに、光圀は「甲寅紀行」で「妙見寺の東に、千葉屋敷あり。」と記しているので、「御殿跡」とは別の場所と考えていたようです。しかし、千葉氏の館は中心市街地(現中央・院内付近)の微高地上のどこかにあったと考えられます。
19 堀内(中央区中央・院内・本町付近)
平安時代末期から室町時代に千葉氏の館がどこにあったのか、つまり千葉氏がどこで日常生活を送っていたのかというのは、千葉の中世史を考える上で極めて大きな問題です。しかし、結論から申せば、現時点では千葉氏の居館があった場所を示す中世の史料は残されておらず、不明としか言えません。前回紹介した「御殿跡」もその有力な候補地の一つですが、断定できる史料はありません。
しかし、『千学集抜粋』には、治承4年(1180)に平家方の藤原親政が攻め寄せた際に「千葉の館」に残っていた千葉成胤が妙見の加護を受けて奮戦したことがみえます。また、『源平闘諍録』では、この「千葉館」を「重代相伝ノ堀内(ほりのうち)」とも言っています。
『千学集抜粋』には「屋形の堀内に妙見おはせしときは」「屋形様御堀内に妙見のおハせし時ハ」といった記載がみられます。この「屋形」「屋形様」とは、もちろん千葉氏当主のことです。「堀内」はその居館で、その中に妙見が祀られていました。つまり、「千葉の館」と「屋形の堀内」「屋形様御堀内」は同じものであることがわかります。
また、同書は金剛授寺(妙見宮、現在の千葉神社)について「下総国千葉庄池田堀内北斗山金剛授寺」と記しています。さらに千葉の守護神の一つである「堀内牛頭天王」は、佐倉街道(現在の国道51号線)に面した八坂神社(本町1丁目)に比定されています(簗瀬裕一「中世の千葉-千葉堀内の景観について-」『千葉いまむかし』11号、2000年)。「金沢文庫文書」にみえる「堀内光明院」は現在の神明町にありました(和田茂右衛門『社寺よりみた千葉の歴史』1984年)。
このような例をみると、簗瀬氏が前掲論文で明らかにしているように、「堀内」は千葉氏の居館そのものを指す場合(狭義の「堀内」)と、居館を含む千葉氏の本拠地である千葉のまちを示す場合(広義の「堀内」)の二通りの意味で使われていることがわかります。つまり、「堀内」は前者の外に後者が広がるという二重の円のような構造だったのです。しかし、後者の広義の場合でも「堀内」は千葉神社のある院内、八坂神社のある本町、光明院のあった神明町にわたる範囲、すなわち現在の千葉の中心市街地に当たることが明らかになります。当然ながら狭義の「堀内」は広義の「堀内」の内部にあったはずですから千葉氏の居館も千葉の中心市街地のどこかにあったことが判明します。
大日寺跡である通町公園の地下から南北朝時代の梵鐘が出土したことを以前書きましたが、
中心市街地のどこかの地下に千葉氏の居館が眠っているはずです。
なお、千葉の「堀内」は「千葉庄堀籠郷」とも呼ばれていました(「中山法華経寺文書」)。
20 【番外編】鎌倉に住んでいた千葉氏(神奈川県鎌倉市)
千葉氏の全盛期と言える鎌倉時代、千葉氏は主に鎌倉に住み幕府に出仕していたようです。
「六条八幡宮造営注文写」(国立歴史民俗博物館蔵、『千葉県の歴史 資料編 中世5(県外文書2・記録典籍)』2005年)には、建治元年(1275)の御家人のリストがあります。これをみると、鎌倉幕府の御家人は「鎌倉中」、「在京」、「諸国」という三種類に分けられていたことがわかります。
そして、千葉氏嫡流家や相馬・武石・大須賀・国分・東といった「千葉六党(ちばりくとう)」と言われる庶子家、遠山方・白井・木内氏は「鎌倉中」として記載されているのです。「下総国」の御家人として記載されているのではありません。
これについて「「鎌倉中」として格付けされた御家人は鎌倉に館をもち、交代で御所内の諸番役を勤めていたのであり、いわば彼らの本籍が「鎌倉中」であった」とされています。「在京」は京都にいる御家人、「諸国」は各国にいる御家人で、国別にまとめて書き上げられています(海老名尚・福田豊彦『田中穣氏旧蔵典籍古文書』「六条八幡宮造営注文について」(『国立歴史民俗博物館研究報告』第45集、1992年)。
言うまでもなく千葉氏は下総国千葉庄を本拠地とする有力御家人ですが、幕府は千葉常胤の直系子孫に当たる一族を「鎌倉中」、つまり鎌倉に住む御家人として位置付けていたのです。
これに対して、臼井氏や常胤の弟である胤光に始まる椎名氏は、「下総国」の御家人として記されています。常胤より前に分かれた一族は、たとえ常胤の弟であっても「諸国」の御家人として位置付けられたのです。
千葉氏は草深い下総で質実剛健な生活を送っていたのではなく、華やかな中世都市鎌倉で過ごすことの多い、都市的な武士であったことがわかります。もちろん、本拠地千葉に帰ることもありましたが、多くは鎌倉にいて幕府に出仕したり、『吾妻鑑』にみえるように儀式に参列したり、将軍の外出に随兵として供奉したりしていました。
鎌倉での千葉氏の屋敷をみると、成胤・胤綱の家は「甘縄」にありました(『吾妻鑑』)。相馬師常の屋敷は現在の扇ガ谷付近にあり、鎌倉駅西口に近い千葉地遺跡は千葉氏の屋敷跡と伝えられているので、千葉一族の屋敷は鎌倉の西側にまとまっていたようです。なお、常胤・胤正は「弁谷殿(べんがやつどの)」と呼ばれているので、東側の材木座付近にも屋敷があったようです。また、妙隆寺(鎌倉市小町、日蓮宗)は千葉胤貞の屋敷を寺院としたものです。
意外なことですが、千葉氏は鎌倉時代にはあまり千葉で暮らしていなかったようです。このことも千葉氏の館の記憶や伝承が早く失われた理由の一つかもしれません。
21 結城(中央区寒川・港町・神明町・新宿町付近)
前々回、治承4年(1180)に平家方の藤原親政が攻め寄せた際に、「千葉館」に残っていた千葉成胤が妙見の加護を受けて奮戦したことに触れました。『源平闘諍録』には、一千余騎の軍兵を率いた親政は赤旗を差して白馬に乗り、「匝瑳北条之内山ノ館」(匝瑳市内山)から「白井ノ馬渡ノ橋」(佐倉市馬渡)で鹿島川を渡り、「千葉結城」へ攻め寄せましたが、親政軍が「結城浜」に現れたことを聞いた成胤は、わずか7騎で立ち向かったとみえます。
また、『千学集抜粋』では、祖父常胤たちに遅れて源頼朝を迎えるため上総へ向かった成胤は、「曽加野」(蘇我付近)から引き返して「結城・渋河」で親政軍と戦ったとされています。
ところで、この合戦の舞台となった「結城」は、現在の行政上の地名としては残されていません。以前から千葉にお住いの方であれば御存じかもしれませんが、今では耳にすることはほとんどありません。わずかに残る痕跡を拾ってみましょう。
JR本千葉駅の改札を出て寒川方面に行くと、港町に「結城幼稚園」がありました。その近くには「結城山満蔵寺」(曹洞宗)がありましたが、現在では別院であった星久喜町に移っています。『千学集抜粋』には「結城は今の寒川なり」とみえます。
また、安政5年(1858)の『成田名所図会』(『成田参詣記』、有峰書店、1973年)には、次のように記されています。
寒川村は天正以前までは結城と称せし地にて、此地方の埜(の)を今も結城埜と称し、結城山満蔵寺と云寺もあり。新田は向寒川(むかふさむかは)と云所なり。此地に結城明神と称する社あり。
この「結城明神」は、寒川から大橋を渡った「向寒川」に鎮座する神明神社(神明町)のことでしょう。その別当寺が光明院でした。また、白幡神社(新宿1丁目)は「結城稲荷」と称していましたが、頼朝が白旗を奉納したという伝承から明治時代になって社号を改めたそうです(和田茂右衛門『社寺よりみた千葉の歴史』1984年)。今も境内には「正一位結城稲荷大明神」の祠があります。また、新宿2丁目には「結城」を冠したビルもみられます。
これらをふまえると「結城」の範囲は、現在の千葉市中心市街地の南側、都川が東京湾に注ぐ河口の寒川・港町から、対岸の神明町、新宿、新田付近にわたったことがわかります。かつての東京湾に面した地域です。
野口実氏は、この地で行われた千葉氏と藤原親政との合戦を「坂東における有力な平家方の一角が崩れた」戦いで、「千葉氏の歴史の中で画期的な大事件」であり、「その意義は鎌倉政権樹立の中で、極めて大きいものがある」と高く評価しています(『坂東武士団と鎌倉』戎光祥出版、2013年)。
千葉氏の飛躍のきっかけとなった結城浜合戦の古戦場であることを伝える貴重な歴史的地名が消え去ろうとしていることは、誠に寂しいものがあります。
22 本円寺・本敬寺(中央区本町1丁目)
中世・近世の千葉のメインストリートは、千葉妙見宮(現在の千葉神社)から都川に架かる大和橋までの「本町通り」、これに続いて大和橋から寒川方面に至る「市場町通り」でした。現在も自動車の往来が絶えない大通りですが、実際に歩いてみると、本町通りは微高地のなかで一番高い位置を、あたかも背骨のように走っていることがわかります。
その本町通りの東側に、本円寺と本敬寺(ほんぎょうじ)という二つの日蓮宗寺院があります。さらに、近くにはかつて正妙寺(しょうみょうじ)という日蓮宗のお寺もありましたが、明治29年(1896)に本敬寺と合併し、廃寺となったそうです(和田茂右衛門『社寺よりみた千葉の歴史』千葉市教育委員会、1984年)。
本円寺は、日蓮宗のなかでも日什を祖とする妙満寺派(顕本法華宗ともいいます)のお寺です。千葉一族の円城寺胤久が日什の弟子の日義に帰依し、日什を開山として康暦元年(1379)に開いたとも、日什によって創建された寺を日喜が永徳2年(1382)に中興開山したとも伝えられています(前掲『社寺よりみた千葉の歴史』)。湯浅治久氏が「東国の日蓮宗」(網野善彦・石井進編『中世の風景を読む 第二巻 都市鎌倉と坂東の海に暮らす』新人物往来社、1994年)で紹介しているように、『門徒古事』という記録には日義が守護千葉介(満胤か)の祈祷所に出向いた際の記事があります。これによると、千葉介が日什の教えを聞きたがったので、これを妨げるため千葉の諸宗の僧侶たちが自分の寺に千葉介を招いて日什に会わせないようにし、千葉近郷の仏像の鼻を欠き落として日蓮宗の仕業と称したといいます(『日蓮宗宗学全書 顕本法華宗部 旧称妙満寺派(第一)』1921年)。
これにより、本円寺からさほど遠くない場所(千葉のどこか)に千葉氏の守護所があったこと、日蓮宗が千葉に進出して千葉氏にも接近していたこと、それに他の宗派の僧侶たちが反発していたことがわかります。
本敬寺は、日蓮宗の古刹として有名な藻原寺(茂原市)の末寺で、藻原寺の十世をつとめた日伝が明応元年(1492)に開いたと伝えられます。また、正妙寺は中山法華経寺の末寺で、日高が正和元年(1312)に開いたと伝えられます。
このように千葉まちの東側、本町に日蓮宗の三つの門流の寺院が集まっていたことは注目されます。京都の町衆たちが日蓮宗の信者となり、比叡山延暦寺と対立して天文法華の乱(1536年)を引き起こしたように、日蓮宗は都市の商工業者に強く支持されました。中世の開創を伝える日蓮宗寺院が集まっていることは、千葉が都市的な発展を遂げ、商工業者が本町付近に多くいたことを示していると考えられます。
なお、千葉神社には土気城(緑区)の酒井胤治・康治父子が永禄7年(1564)に出した「酒井胤治・康治連署制札」が残ります(『千葉県の歴史 資料編 中世3(県内文書2)』2001年)。酒井氏は俗に「上総七里法華」といわれるように妙満寺派(顕本法華宗)の日蓮宗信仰を持っていました。第二次国府台合戦の後に出された制札ですが、酒井氏が千葉に影響を及ぼしていたことを示す史料でもあります。
23 中世の千葉まちの範囲(1)
中世の千葉のまちの範囲はどこからどこまでだったのでしょうか。『千学集抜粋』には、大治元年(1126)、千葉常重が千葉のまちを立てたときの記述として「曽場鷹大明神より御達保稲荷の宮の前まて七里の間御宿也」とあります。
これによると、北東側、常陸(茨城県)や佐倉の方から千葉へ通じる街道(現在の国道51号線、古代の東海道、近世の南年貢道)でいえば、車坂の上にあった曽場鷹大明神(そばたかだいみょうじん、若葉区貝塚町)までが千葉でした。また、南側、市原方面から千葉へ通じる街道(現在の国道16号線の旧道、近世の房総往還)でいえば、海に面した御達保稲荷(ごたっぽいなり、中央区稲荷町)までが千葉でした。曽場鷹大明神から御達保稲荷までが宿(しゅく)、つまり武士、商人や職人、宗教者といった人々が集住するまちだったことがわかります。
それでは、このほかの方角はどうだったのでしょうか。まず、北側です。佐倉から四街道を経て千葉へ通じる街道(近世の北年貢道)でいえば、高品(若葉区)を過ぎると千葉でした。旧道脇には幕末の文久3年(1863)に建てられた「高品の常夜塔」が残り、ここが千葉の出入り口だったことを今に伝えています。高品城は、戦国時代の千葉氏当主の嫡男が本佐倉城(酒々井町・佐倉市)から来て、千葉妙見宮(千葉神社)で元服の式を行う際の拠点として重要な役割を担っていました(拙稿「戦国期千葉氏の元服」『中世東国の政治構造 中世東国論 上』2007年)。
次に北西側、八千代や穴川方面から千葉へ通じる街道(現在の国道16号線)でいえば、作草部(稲毛区)からは千葉の外とされていたようです。原豊前の家来である石出氏が妙見宮の神領に乱入して狼藉を働きましたが、『千学集抜粋』には罪人を処罰したときのこととして、次のような記事があります。
「…本人を縄うちて出させける、さくさ辺のおりとにて、千葉ヘハ入すして、山崎民部少輔に仰せ、頭をきりて…」
これによれば、千葉の内には入れずに「さくさ辺」、つまり作草部で処刑しています。なお、「おりと」という地名は作草部に残っていません。ちなみに、モノレール作草部駅の近くには、享和元年(1801)に建てられた「縄しばり塔」と呼ばれる、道標を兼ねた百万遍塔があります。その右側面には「千葉町へ二十町」と刻まれています(和田茂右衛門『社寺よりみた千葉の歴史』1984年)。江戸時代の人々にも、この辺りが千葉の入り口と意識されていたのでしょう。
以上をまとめると、作草部、高品、曽場鷹大明神、御達保稲荷を結ぶラインの内側が千葉のまちだったと考えられます。
なお、東側の土気往還・東金街道(病院坂を経て現在の大網街道につながる)については不明です。次回は西側について考えたいと思います。
24 中世の千葉まちの範囲(2)
久々のコラムとなりましたことをお詫びいたします。さて、前回は中世の千葉のまちの範囲について、北側は高品、北東側は曽場鷹大明神(貝塚町)、北西側は作草部、南側については御達保稲荷(稲荷町)の内側としました。東側は不明ですが、千葉寺はもちろん千葉の内です。その東、仁戸名(かつては「にへな」と読んでいました)は別の村でしたので、千葉寺と仁戸名の間に境があったと考えられます。
残るは西側です。もっとも東京湾に沿って船橋を経て江戸へ至る街道(近世には「房総往還」、通称「千葉街道」、現在の国道14号線)は、波打ち際を通るため天候に影響され、安定した交通路ではなかったようです。
さて、菅原孝標女の『更級日記』の都への旅立ちを記した部分に「その夜は、くろとの浜といふ所にとまる。かたつ方はひろ山なる所の、砂子はるばると白きに、松原しげりて」とあることは有名です。
ところで、戦国時代の永正11年(1514)に本佐倉城(酒々井町・佐倉市)の城下で、衲叟馴窓(のうそうじゅんそう)が編んだ『雲玉和歌集』(『新編国歌大観 第八巻 私家集編4.』)に、「くろとの浜」を詠んだ次のような歌と記述がみえます。
|
下総千葉の浦を よみ人しらず |
黒戸の浜がどこに当たるのかについては、黒砂(千葉市稲毛区)、畔戸(木更津市)の二説があります。しかし、明確に「下総千葉の浦」とあるので、黒砂であることが明らかです。松林と遠浅の浜の様子を描いた『更級日記』の記述も黒砂に相応しいと思われます。
二首のうち、後者の衲叟の歌にある「さばへ(五月蠅)」とは陰暦の五月に群がり騒ぐ蠅で、稲に付く害虫や、祟りをなす恐ろしい霊魂(御霊)といわれています。また、「さばえなす」は「騒ぐ」「荒ぶる」などにかかる枕詞で、「さばえなす神」とは「陰暦五月頃の蠅のように煩わしくいとわしい邪神・悪神。疫神。疫病神」とされます(『日本国語大辞典』)。「あしき人」の心によって黒くなった世の中と黒戸の浜の白波を対比した歌です。
この歌の注に「みそぎは此神をはらふなり」とありますが、この記述は黒戸の浜で穢れを払うみそぎが行われていたことを示すのでしょう。みそぎは穢れを外に追い出し、入り込まないようにするため、外界との境で行われます。このように考えると黒戸の浜が、中世の千葉のまちとの境界にあったことがわかります。つまり、西側については東京湾に沿った黒戸の浜、つまり黒砂までが千葉のまちだったと考えられます。なお、拙稿「『雲玉和歌集』と上総国」(『中世房総』10号)も参照していただければ幸いです。
25 大和橋と市場町
今回から、大和橋を渡って都川の左岸にある「千葉氏ゆかりの地」を紹介します。
第22回「本円寺・本敬寺」でも述べたように、中世・近世の千葉のメインストリートは、千葉妙見宮(現在の千葉神社)から寒川の湊に至る通りでした。このうち都川に架かる大和橋までを「本町通り」、これに続いて大和橋から寒川方面を「市場町通り」と呼んでいます。つまり中世・近世の千葉のまちは、都川の右岸(東側)と左岸(西側)の二つの地域に大きく分かれ、大和橋が両地域をつないでいたのです。
ちなみに都川の左岸にある千葉県庁の所在地は、千葉市中央区市場町1-1です。『千学集抜粋』には「曽場鷹大明神より御達保稲荷の宮の前まて七里の間御宿也」とあり、さらに「橋より向、御達保まては宿人屋敷也、これによつて河向を市場と申なり」とあります。大和橋から千葉のまちの南側の境界である御達保(五田保、ごたっぽ)の稲荷神社(中央区稲荷町)の間には「宿人屋敷」があり、そのため都川の対岸を「市場」と言うと説明しています。
この「宿人」(シュクニンと読むのでしょう)とは、「市」が立つ場所に住み、そこが湊である寒川に隣接することを考えれば、商人、職人や漁業者、水運業者たちと考えられます。
小島道裕氏は戦国期城下町について、「大名と主従制結合を持つ人間によって作られた空間」である「広い意味での給人居住域」と「非主従制的な空間」である「市町」との両者によって構成されるとしています(「戦国期城下町の構造」『戦国・織豊期の都市と地域』青史出版、2005年)。
第19回「堀内」で述べたように、都川右岸の堀内(ほりのうち)は千葉氏の居館や家臣たちの屋敷、妙見宮などの千葉氏と関係の深い社寺があり、千葉氏の権力の中枢とも言うべき場でした。これに対して都川の対岸が市場と呼ばれることは、小島氏の提唱した「二元的」なあり方によって理解できます。斎藤慎一氏が指摘するように、千葉は川を挟んで位置する堀内と市場という「異質な空間」によって成り立つ「二元的な構成」を持つまちだったと考えられます(「戦国期城下町成立の前提」『歴史評論』572号、1997年)。
しかし、「堀内」と「市場」は対立するものではありません。『千葉妙見大縁起絵巻』に描かれているとおり、中世以来、千葉妙見の祭礼では神輿とともに千葉から出る「千葉舟」と寒川から出る「結城舟」がまちを巡行しました。本館ホームページのコラム「千葉の例大祭~ハレの日と信仰(No. 1)」(白井千万子研究員)にあるように、戦前まで寒川は市場町にある千葉神社の「御仮屋(おかりや)」まで来た千葉神社の神輿を引き受け、海に入る「御浜下り(おはまおり)」を行い、再び「御仮屋」で神輿を千葉へ引き渡しました。妙見の祭礼は千葉と寒川が一体となって行われ、「堀内」である千葉と寒川をつなぐのが大和橋と「市場」であったのです。
なお、「大和橋」という名称ですが、『千学集抜粋』には単に「橋」とあり、江戸時代には「大橋」と呼ばれていました(和田茂右衛門『社寺よりみた千葉の歴史』千葉市教育委員会、1984年)。明治24年(1891)の『千葉繁昌記』には「大和橋」がみえます。
26 羽衣の松
千葉県庁の一画、県議会議会棟の前に位置する羽衣公園に「羽衣の松」があります。この場所には、明治44年(1911)に完成し、ルネッサンス式の偉容を誇った旧県庁舎が建っていましたが、昭和37年(1963)に新庁舎(現中庁舎)が落成すると解体されました。
現在の松は昭和60年(1985)に、千葉県の人口が500万人を突破したことを記念して植え直されたものです。かつて、今の位置より東に池を中心とした「千葉公園」があり、その中に「羽衣の松」と呼ばれた古木がありました。下総の国学者宮負定雄の『下総名勝図絵』(弘化3年・1846のはしがきあり。川名登編、国書刊行会、1990年)には「田の中にあり。昔の松は枯れてなし。今ある松其の世継松なり。昔、天女降りて羽衣を此の松が枝に掛け、此の所の池にて水を浴みし所なりといひ伝ふ」とみえます。
千葉の「羽衣伝説」は様々なバリエーションがあるのですが、その代表である『妙見実録千集記』(『改訂房総叢書』第2輯、1959年)には次のように記されています。
千葉介常将。此の代に至って、天人降りて夫婦に成り給へり。子細は千葉の湯之花の城下に、池田の池とて清浄の池あり。此の池に蓮の花千葉に咲けり。貴賤上下して見物す。或夜人寝静まりし夜半過に、天人天下り、傍らの松の枝に羽衣を懸置き、池の辺へ立寄りて、千葉の蓮花を詠覧し給ふ。夫より湯の花の、城へ影向成りて、大将常将と嫁娶し給ひ、程無く懐胎有りて、翌年の夏の頃、恙無く男子産生し給ふ。是を常長と号す。
さらに、この話に感じ入った帝の「千葉(せんよう)の蓮花によって千葉を名乗れ」との叡慮によって千葉介を称したと続きます。「常長 天人の御子也」とあるように、羽衣伝説が千葉氏と結び付けられていることが大きな特徴となっています。千葉の支配者である千葉氏が「聖なる一族」であると主張するために、このような話が作られたのでしょう。この説話は「右天人は、妙見大菩薩の御変化也」と結ばれています。天女は千葉氏が氏神・武神として崇敬する妙見の変化(へんげ)、化身だったという種明かしです。
県庁の中庁舎の下を抜けて千葉地方裁判所の方へ渡る、都川に架けられた橋は「羽衣橋」です。オフィス街でロマン溢れる伝説に思いを馳せるのも楽しいことではないでしょうか。
なお、この伝説の舞台が、千葉氏の権力の中枢とも言うべき「堀内(ほりのうち)」ではなく、都川対岸の「市場」であることが気になります。「市」では商品や金銭がやり取りされますが、それは外部との出入りを意味します。ですから網野善彦氏が述べているように、「市」は「神々と関わる聖域」「冥界との境」でもあったのです(「市の立つ場」『増補 無縁・公界・楽-日本中世の自由と平和-』平凡社、1987年)。
都川に面し、寒川湊に隣接する「市場」にあった池に天女が現れたのは当然かもしれません。根拠は無いのですが、「羽衣の松」は天女だけでなく「市神」の依り代だったのかもしれないなどと想像をたくましくしています。
27 お茶の水 (1)
本町から大和橋を渡り、左折すると右手、猪鼻公園の入り口に「お茶の水」があります。傍らにある石碑には、次のように記されています(常用漢字に直し、句読点を付しました)。
治承の昔、千葉常胤卿源頼朝公を居城亥鼻山に迎へし時、此の水を以て茶を侑む。公深く之を賞味せりと伝ふ。爾来お茶の水と称し、星霜八百年、清水滾々として今に渇せず。
千葉市域にも少なからず伝えられる「頼朝伝説」の一つとして広く知られています。碑文には「滾々(こんこん)として今に渇せず」とありますが、残念ながら水が枯れて久しく、わずかにかつての雰囲気を偲ぶことができるのみです。
なお、「茶を侑(すすむ)む」とあることについて、常胤や頼朝の時代には茶はなかったという方がいます。教科書に載る栄西の『喫茶養生記』(建保2年・1214の成立)の印象が強いためでしょうか。しかし、古く奈良時代から喫茶は行われ、平清盛による日宋貿易によって茶ももたらされました。しかし、薬としての効能が求められたのであり、「茶の湯」が始まったのは室町時代で、毎日茶を飲むようになったのは江戸時代以降です。
ところで、このお茶の水については頼朝伝説ではない話も伝わっています。「水戸黄門」として有名な徳川光圀は、延宝2年(1674)に水戸から房総を経て鎌倉を訪れる旅をしました。この年の干支が庚寅(かのえとら)だったので、その記録は『庚寅紀行(こういんきこう)』と呼ばれます。これはもちろん漫遊ではなく、史料探訪のための真面目な旅でした。
光圀は神崎、成田、酒々井を通り、4月27日に千葉へ来ました。千葉のことを記した文のうち「千葉屋敷」の部分は本コラム第18回「御殿跡」で触れましたが、光圀はお茶の水について次のように記しています。
千葉の町を出づる所の左の方に、古城あり。伊野花と云ふ。(中略)古城の山根に水あり。「東照宮御茶の水」と、云ひ伝ふ。(『改訂房総叢書』第4輯、1959年)
これによれば、頼朝ではなく東照宮、つまり徳川家康のお茶の水だというのです。光圀が来たのは、家康が没したのは元和2年(1616)ですから、光圀が千葉へ来たのはそれから60年も経っていません。まして光圀は家康の孫ですから、無責任なことを書くとも思えません。千葉御殿を訪れた家康がこの湧き水を賞味したこともあったのでしょう。
いつの世でも湧き水は大切なものであり、聖人や偉人と結び付けられました。弘法大師が杖を刺したところ水が湧き出たという伝説は広く分布します。お茶の水もそういった文脈で考えるべきでしょう。
28 お茶の水 (2)・井花(いのはな)
前回、お茶の水について頼朝伝説と家康伝承を紹介しました。今回は『千葉大系図』(『改訂房総叢書』第5輯、1959年所収)にみえる、千葉氏に関する言い伝えを紹介します。平忠頼(忠常の父)について次のように記されています。
|
延長八年庚寅六月十八日、下総国千葉郡千葉郷に誕生するなり。此の所に忽ち水湧き出づ。此の水を以て生湯と為す。後世、湯花水と号す。(読み下し文とし、句読点を付した。) |
これも有名人にまつわる湧水伝説ですが、忠頼の産湯として千葉氏と結び付けています。「湯花」は「ゆのはな」と読むのでしょう。
ところで、貴重な中世資料として知られる『本土寺過去帳』(『千葉県史料中世篇 本土寺過去帳』1982年)の二三日のところには、次のような記事がみえます。
|
永正三丙子八月 原蔵人丞殿法名朗寿 東六郎殿 千葉井花ニテ打死、諸人證仏果 |
永正3年の干支は丙寅で、「丙子」は永正13年に当たります。『千学集抜粋』(『妙見信仰調査報告書(二)』千葉市立郷土博物館、1993年)には次のように記されています。
|
一条院薄墨の御証文は、範覚の世に井鼻を持たれし時、永正十三丙子八月二十三日、三上但馬守、二千余騎にて打落す、此時薄墨の御証文は宝器ともみな失にける |
これによって『本土寺過去帳』の「永正三丙子」は「十」が脱字したことがわかります。永正13年(1516)8月23日に「井花・井鼻」で大きな合戦があり、原氏や東(とう)氏といった千葉氏の家臣や一族が討ち死にしたことが判明します。
ちなみに攻め寄せた三上氏は、近江(滋賀県)の佐々木氏の一族で、上総に勢力を有していました。また、「井鼻」に立て籠もった範覚は金剛授寺(千葉妙見宮)の座主です。
以上のとおり「湯花」「井花」「井鼻」はいずれも「いのはな」と読み、亥鼻・猪鼻のことです。当館のある亥鼻・猪鼻の語源については、イノシシの鼻のような地形だからとか、亥の方角(北北西)に突き出した地形だからと言われます。しかし、中世の史料である『本土寺過去帳』に「井花」あることから、井戸のある、イノシシの鼻のように北北西へ台地が突き出した場所と考えるべきでしょう。もちろん、この井戸はお茶の水のことです。
湧水や井戸は生命や産業にとってなくてはならないものであり、信仰の対象となりました。お茶の水には祠の中に安置された不動尊や寛保3年(1743)の不動尊をはじめ、地蔵などの石造物がいくつも並んでいます。お茶の水は、ここから南約200メートルにある智光院(真言宗)が支配していました。
29 七天王塚(1)
お茶の水から「病院坂」を登り、千葉大学亥鼻キャンパスの正門を過ぎると、バス停「千葉大薬学部前」とバス停「中央博物館」の間の右側に、大木の生えた塚が二つあることに気づきます。説明板があるので、七天王塚であることがすぐにわかります。
因みに、このバス通りは近世の「東金街道・土気往還」で、現在の国道126号や県道20号千葉大網線(大網街道)が開通する前は、千葉と東上総を結ぶ重要な道でした。しかし、近代になって亥鼻の台地上に現在の千葉大学医学部附属病院ができると、街道の入り口に当たる坂は「病院坂」と呼ばれるようになりました。
七天王塚は、その名のとおり7基の塚からなります。残りの5基は千葉大学亥鼻キャンパスの中に点在し、タブノキ、クスノキ、エノキ、マツなど、鬱蒼とした木々が生えています。
これらの塚の上には、いずれも石碑が置かれています。その年号をみると、もっとも古いものは安永2年(1773)です。もっとも新しい花崗岩製のものは昭和53年(1978)とされます(大谷克己『千葉の牛頭天王』千葉市教育委員会、1982)。これらには「堀内牛天王」「牛頭天王」「七天皇」七天王」といった神の名前が刻まれています。これによって七天王塚に牛頭天王が祀られていることがわかります。
牛頭天王は牛の頭に人の体を持った神で、素戔嗚尊(スサノオノミコト)と同一視されています。仏教では祇園精舎の守護神とされました。京都東山の祇園にある八坂神社の祭神は素戔嗚尊です。
荒ぶる神として知られる素戔嗚尊は、疫病を退散させる神として人々の信仰を集めました。山鉾巡行で有名な、京都の夏を彩る八坂神社の祇園祭は、かつて「祇園御霊会(ぎおんごりょうえ)」と呼ばれ、疫病が流行した時に矛をまつり、疫神や悪霊を送ったことに始まるとされます。気温の高い夏は伝染病が流行りますが、昔の人はこれを鎮めるため、素戔嗚尊、つまり牛頭天王に祈ったのです。
新型コロナウイルスが猛威をふるうなか、にわかに疫病を退治する妖怪「アマビエ」が脚光を浴びています。しかし、疫病退散の大先輩は牛頭天王です。荒ぶる神であるだけに、そのパワーも極めて強力です。最強の疫病退散の神といえましょう。
そのような牛頭天王が、七天王塚という「東金街道・土気往還」を挟むようにして点在する塚群にまつられているということは、やはり街道、陸上交通を意識したものでしょう。牛頭天王、つまり八坂神社は都市的な場や交通の要地にまつられることが多くあります。東上総方面から来ると、七天王塚を過ぎて「病院坂」(もちろん近世以前にはそのような名前は付いていませんでしたが)を下れば、そこは千葉のまちです。
なお、明治44年(1911)の『千葉街案内』には「七生松(ななをひのまつ)」として紹介され、七天王塚という名前ではありません。しかし、ともに「七」という数に意味があると考えられます。
七天王塚は、お茶の水と同じく智光院が支配していました。
30 七天王塚(2)
様々な伝説に彩られた七天王塚については、大別すると次のようにいくつもの説がありますので、紹介していきます。
- 千学集抜粋』にみえる、千葉の守護神「堀内牛頭天王」である。
- 7つの塚の配置が北斗七星のかたちと一致しており、千葉氏の妙見信仰を示している。
- 平将門の影武者7人の墓である。
- 猪鼻城の大手の土塁が残存したもの。
- 閻魔王をはじめとする七王を祀ったもので、昔の十王堂の名残りである。
- 古墳群である。
このうち1.~4.が千葉氏との関係を伝えています。まず、1.について考えを述べます。
確かに『千学集抜粋』(『千学集抄』)には千葉の守護神の一つとして「堀内牛頭天王」が記されています。以前は猪鼻城が鎌倉時代の千葉氏の居城だったと思われていました。このため、「堀内」は猪鼻城(千葉城)であり、その守護神として亥鼻城の近くに七天王塚が配置されたと考えられてきたのです。
ところが、当コラム第19回「堀内(ほりのうち)」で述べたように、千葉氏の本拠地である「堀内」は、都川の右岸、現在の中央区院内・中央・本町を中心とする地域でした。したがって、亥鼻の台地上にある七天王塚が「堀内牛頭天王」ではあり得ません。「堀内牛頭天王」は簗瀬裕一氏が指摘したように、現在も本町1丁目にある八坂神社の可能性が高いと考えられます(「中世の千葉」『千葉いまむかし』13号、2000年)。千葉まちの道路交通の基点とも言うべき通町交差点に近く、佐倉・香取へ通ずる街道(現国道51号線)に面する八坂神社は、交通の要衝である都市的な場に祀られる牛頭天王にふさわしい場所です。
前回、旧東金街道・土気往還に面して千葉まちの入り口に牛頭天王が祀られたのは、重要な交通路を意識したのではないかと述べました。そのとおりだと考えますが、『千学集抜粋』にみえる「堀内牛頭天王」ではないことは留意すべきです。
なお、塚にある安永2年(1773)の石碑に「堀内牛天王」とありますが、既に江戸時代後期には猪鼻城が鎌倉時代の千葉氏の城であると思われていたため、当時の人たちも『千学集抜粋』の「堀内牛頭天王」を七天王塚と考えたのでしょう。
次に2.・3.で重要な役割を果たす「七」という数に関して述べます。広く知られるように、千葉氏が信仰した妙見は北の方角を示す北斗七星、もしくは北極星が神格化された神です。そのため妙見信仰では、「七」は特別な意味を持つ聖なる数とされます。千葉妙見宮(現千葉神社)の祭礼が七日間行われるのも、その一例でしょう。北斗七星のかたちに配置されたと言われる7基の塚が、妙見信仰を通じて千葉氏と結びついたのは当然といえるでしょう。
明治期には「七生松(ななをひのまつ)」(古川国三郎編纂『千葉街案内』1911)、大正期には「七つ塚」と呼ばれていましたが(藤澤衛彦編著『日本伝説叢書 下総の巻』1919)、やはり「七」が冠されています。「七」に特別な意味が込められていたことがわかります。
31 七天王塚(3)
今回は、3.の「平将門の影武者7人の墓」説について述べます。
千葉氏は将門と祖を同じくする坂東の桓武平氏であり、千葉常胤の二男師常(もろつね)に始まる相馬氏は、将門の子孫と称しました。相馬氏が移住した福島県浜通り地方で今も行われ、勇壮な戦国絵巻として有名な「相馬野馬追」(国重要無形文化財)が、将門が牧の野馬を敵に見立てて追ったことに由来すると伝えられるのも、千葉一族と将門との深い結びつきを示しています。
千葉氏は、東国の自立を目指したといわれ、志半ばで倒れた将門に対して強い同族意識を持っていました。例えば、治承4年(1180)の結城浜合戦で有力な平家方の藤原親政と戦った千葉常胤の孫の成胤は、「平親王将門には十代の末葉(ばつよう)、千葉の小太郎成胤、生年(しょうねん)十七歳に罷(まか)り成る。」と名乗りを上げたとされます(鎌倉時代末期に成立していた『源平闘諍録(げんぺいとうじょうろく)』による)。千葉氏は将門の子孫と称することもあったようです。
将門にはそっくりな影武者が7人いましたが、将門を裏切った小宰相(桔梗御前とも言われます)という女性が見分け方を教えたため討ち取られたという伝説があります。ここでも聖なる数「七」が大きく関係します。妙見信仰を通じて千葉氏と将門が結び付けられていたと言えるでしょう。
ところで、将門は坂東の英雄であるとともに非業の死を遂げた「怨霊」でもありました。大手町(東京都千代田区)の「首塚」に代表されるように、将門の怨霊は強い力を持ち、祟るとされてきました。前々回に述べましたが、七天王塚に祀られる牛頭天王も「荒ぶる神」でした。怨霊として「祟る」将門、「荒ぶる神」牛頭天王、強い力を持ち畏怖される神どうしとして、両者が次第に結びついていったのも当然と考えられます。
こうして「七天王塚の祟り」がまことしやかに語られることになったのでしょう。実際に訪れてみると、鬱蒼とした木々が生えて日が陰る塚の雰囲気も、不吉な気分を募らせます。医学部・薬学部・看護学部などのある千葉大学亥鼻地区では、工事の際に塚の上に生えていたクスノキの枝を払い落としてしまったため、事故が発生したり関係者に良からぬことが起きたりしたと語られています(大谷克己『千葉の牛頭天王』千葉市教育委員会、1982年)。5号塚にある牛頭天王の石碑には昭和53年(1978)の年号と某大手ゼネコンの社名が刻まれています。
これらの話についてはコメントできませんが、「祟り」によって塚や塚に生える樹木、つまり貴重な史跡や自然が残されてきたと言えるかもしれません。七天王塚は昭和34年(1959)に千葉市指定文化財(史跡)として指定されています。
32 七天王塚(4)
今回は、6.の古墳群説、4.の「猪鼻城大手の土塁」残存説について述べます。
千葉大学亥鼻キャンパス内で、医薬系総合研究棟を建設するため平成14年(2002)の第1次調査~平成22年(2010)の第5次調査まで、千葉大学によって発掘調査が行われました。その成果は『千葉市中央区亥鼻城跡 千葉大学医薬系総合研究棟建設に伴う発掘調査報告書』(千葉大学亥鼻地区埋蔵文化財調査委員会・千葉大学文学部考古学研究室、2011年。以下『報告書』といいます)によって詳しく知ることができます。
医学部本館の東側、七天王塚の4号塚・5号塚・6号塚・7号塚に囲まれた場所を調査したところ、全長約28メートル、前方部約6メートル、後円部約22メートルを図る前方後円墳の1号墳と、やはり前方後円墳と考えられ2号墳が発掘されました。1号墳は前方部が小さくて後円部が大きい、「帆立貝式」といわれるタイプの古墳です。後円部の南側には軟質砂岩の切石を積んだ横穴式石室があり、埋葬された人物の歯も出土しています。検出された遺物から7世紀初頭に築かれたことがわかりました。また2号墳も7世紀前半に築かれたものです。さらに5号塚の周囲にも古墳時代の土坑がありました。
このような発掘調査の成果から、『報告書』は「七天王塚に囲まれる位置で前方後円墳が検出されており、それ以外にも、一番盛土が少ない七天王塚5号塚の周辺からも土壙墓と考えられる土坑が2基検出されていることからみて七天王塚は古墳の残存である可能性が極めて高い」と結論付けています。
これに従うと、自動的に「猪鼻城大手の土塁」残存説は成り立たなくなります。現状からみても七天王塚はそれぞれ独立した塚であり、かつて連続した土塁であったようには認められません。また、城郭の土塁であれば、これに伴って堀があるのが普通ですが、その痕跡もみられません。
最後に、5.の十王堂の名残り説について述べます。藤澤衛彦編著『日本伝説叢書 下総の巻』(日本伝説叢書刊行会、1919)には「七天皇」として「七天皇は、勿論、七王で、閻魔王を首(はじ)めとして、七王を祀れるもので、昔の十王堂(秦広王・楚江記・宋帝王・五官王・閻羅王・下城王・泰山王・都市王・平等王・転輪王を祀る。[筆者注 十尊の名は当該書のまま])の名残りである。そのうち七王を祀れる例は、伊豆(田方郡田中村大字御門六角堂に之を祀る。)などにもある(「伊豆の巻参照。」)が、この思想と、十三仏を祀る思想(例諸国に多い。)とが混じ、此塚も基礎をなしたものと思はれる」とあります。
十王は道教や仏教で亡者の審判を行うとされる十尊です。七天皇塚に十王が祀られており、仏教の十三仏の影響を述べる説は、この他にみることができません。しかし、はるか古代に古墳群があり、6号塚には墓塔もしくは供養塔である戦国期の小型五輪塔の空風輪部が3つあり、いずれ述べるように亥鼻の台地上が中世以降も葬送の地であったことを考え合わせると、十王の伝説が生じたのも一理あるように思えます。
33 智光院(中央区市場町)
お茶の水から亥鼻山の裾を南へ200メートルほど進むと、左手に智光院の立派な山門とお堂が見えます。郷土博物館のある亥鼻公園へ登る石畳の左側です。
当寺は、正式には「小河山 青蓮寺 智光院」と称する真言宗豊山派の寺院で、寺伝によると康正2年(1456)に千葉(馬加)康胤によって開かれたとされます。御本尊の木像不動明王立像はその頃の作で、貞享5年(1688)に妙見寺(現在の千葉神社)の僧栄慶が修理した旨の墨書が残り、当寺が近世には妙見寺と深いかかわりを持っていたことがわかります(『千葉市の仏像』千葉市教育委員会、1992)。境内には月星紋や九曜紋がみられ、千葉氏ゆかりのお寺であることが実感されます。
康胤は千葉満胤の二男で、馬加(まくわり、現在の花見川区幕張)に住み、千葉一族のなかで長老的な存在でした。享徳の乱が勃発すると、円城寺氏ら直臣層に支えられた千葉胤直たち千葉本宗家が管領上杉氏側に属したのに対し、康胤は庶子家の原胤房らとともに古河公方足利成氏に属しました。康正元年(1455)、胤房が千葉城を攻め落とし、敗走した胤直らが多古城・島城(多古町)に籠城すると、康胤・胤持父子は胤房とともに胤直らを攻めて自害させ、千葉本宗家は滅亡したのです。
公方成氏は、このような康胤の「忠節」を高く評価し、千葉氏を継承させました。康胤に始まる千葉氏を「馬加千葉氏」といいます。成氏は上杉方の地盤を切り崩すため、安房には里見氏、上総には武田氏を送り込みました。ところが、下総では外部勢力の侵攻ではなく、千葉氏内部の勢力交代によって上杉方から足利方の勢力圏になったのです。このことは中世の東国社会における千葉氏の存在の大きさを感じさせます。しかし、康胤は康正2年(1456)11月に上総八幡(市原市)の合戦で討死しました。八幡の無量寺(浄土宗)には、康胤・胤持父子の墓と伝えられる中世の五輪塔があります。
なお、智光院には銅造如来形立像(14世紀前半)、銅造菩薩形立像(鎌倉時代後期、善光寺式阿弥陀三尊像の脇侍)といった、創建年代よりも古い仏像が伝来しています(前掲『千葉市の仏像』)。智光院の前身となった寺院が既に存在していた可能性が考えられます。
智光院は猪鼻城跡の直下にあるため、この場所に千葉氏の居館があったのではないかという説があります。千葉本宗家を滅ぼした康胤が、千葉氏の菩提を弔うために館の跡に寺を建立したという考えはとても魅力的です。鎌倉幕府を滅ぼした足利尊氏が、北条氏の霊を弔うため執権屋敷の跡に宝戒寺(鎌倉市)を建立したという例もあります。
しかし、繰り返しになりますが、千葉氏の本拠である「堀内(ほりのうち)」は都川の対岸で、智光院が「市場」にあること、猪鼻城が戦国時代の城郭であること、智光院の地は千葉氏のような有力な守護クラスが居館を構えるには狭いことを考えると、千葉氏の館は他の場所に求めるべきと考えます。
智光院はお茶の水の不動や七天王塚を支配していました。本堂の裏側には「お茶の水清水不動尊」が遷座されています。
34 胤重寺(中央区市場町)
智光院の南、亥鼻公園へ登る石畳の道の右側が胤重寺(いんじゅうじ)です。光明山胤重寺と称する浄土宗の寺院で、寺伝によれば、開山の雲巌上人は武石胤重(たけしたねしげ)の子孫で、胤重の菩提を弔うため永禄元年(1558)に開いたとされます(『千葉県浄土宗寺院誌』千葉県浄土宗寺院誌刊行委員会、1982年)。雲巌上人は、浄土宗二祖で「鎮西上人」と呼ばれる聖光房弁長(しょうこうぼうべんちょう、1162~1238)の法脈を汲むとされます。
胤重は、千葉常胤の三男で「千葉六党」の一人として知られる武石三郎胤盛の子で、武石次郎を称しました(「神代本千葉系図」『改訂房総叢書』第5輯、1959年)。武石は現在の花見川区武石町で、今も真蔵院や武石神社などの武石氏ゆかりの史跡が残ります。胤盛は父常胤から千葉氏の本領である千葉庄(ちばのしょう)の西部に位置する武石周辺を分け与えられ、名字としたのです。
ところで、鎌倉末には成立していた、『平家物語』の異本である『源平闘諍録』(げんぺいとうじょうろく)には、千葉成胤が平家方の藤原親正を迎え撃った「結城浜合戦」の際に、成胤に続いた武士として「多部田の四郎胤信・国分の五郎胤通・千葉の六郎胤頼・堺の平次常秀・武石の次郎胤重」たちがみえます(福田豊彦・服部幸造全注釈『源平闘諍録(下)』講談社、2000年)。胤信は大須賀氏の祖、胤通は国分氏の祖、胤頼は東(とう)氏の祖で、いずれも常胤の子です。しかし、武石氏は胤信・胤通・胤頼の兄弟である胤盛ではなく、その子の胤重が参加していることが気になります。胤盛は父常胤とともに源頼朝の傍に従うなど、何らかの事情があって合戦に加わらなかったのかもしれません。しかし、胤重は若い時から武石氏の軍事行動を代表するような立場にあったとも考えられます。
松島の五大堂の鐘(嘉禄3年・1227)に「日(亘)理郡地頭武石二郎胤重」とあり、胤重が早くから陸奥国亘理郡(宮城県)へ進出していたことがわかります(岡田清一「陸奥の武石・亘理氏について」『千葉氏関係資料調査報告書2. 東北千葉氏と九州千葉氏の動向(亘理氏及び仙台千葉氏)』千葉市立郷土博物館、1997年)。ちなみに、東北へ移住した武石氏が亘理氏を称し、さらに近世には伊達氏の一門に列せられて涌谷伊達氏となったことはよく知られています。当寺が武石氏の祖である胤盛ではなく、胤重の供養のため建立されたとされることは、胤重が一族の中で重要な存在であったためかもしれません。
当寺の御本尊は木造阿弥陀如来立像です。この他に13世紀中ごろの銅造千手観音菩薩坐像、本来は懸仏(かけぼとけ、壁面に懸ける仏像)であった銅造薬師如来坐像が残されていますが、この二体は「円城寺」に安置されていたものです(『千葉市の仏像』千葉市教育委員会、1992年)。円城寺は佐倉市城(じょう)にあり、千葉氏の重臣として知られる円城寺氏と関係のある寺とも言われます。
本堂には月星紋がみられ、千葉氏の由緒を持つお寺であることがわかります。また、境内には、供えてある塩でなでるとイボが取れるといわれる「塩地蔵」、柔術の戸塚揚心流の祖である戸塚彦介英俊と子の英美の墓(千葉県指定史跡)があります。
35 高徳寺(中央区亥鼻2丁目)(1)
胤重寺からさらに南へ進み、県立中央図書館を過ぎ、信号のある交差点を渡ると、左手に石柱の門があります。龍興山高徳寺、曹洞宗の寺院です。
寺伝によれば、原四郎胤高が北朝年号の貞治4年(1365、南朝年号では正平20年)に建てたとされます。胤高は千葉氏胤の子で、戦国時代に生実城(中央区)・臼井城(佐倉市)を拠点にして千葉氏に匹敵する地域権力に成長を遂げた原氏の祖に当たります。享徳の乱で千葉城を攻め、馬加(まくわり)康胤とともに本宗家を多古城・島城(多古町)で滅ぼしたことで知られる原胤房は、胤高の孫です。
また、近世の『千葉伝考記』には大日寺旧記を引用するかたちで、「氏胤の建立にて」とあります(『改訂房総叢書』1959)。いずれにせよ、当寺は南北朝時代に建立されたと考えられます。なお、宝徳元年(1499)に宗徳寺の機然正哲和尚が中興開山となったとも伝えられています。宗徳寺は生実の柏崎にありましたが、後に臼井へ移った曹洞宗の寺院で、原氏の菩提寺です。このことからも、当寺が原氏と深い結び付きを持っていたことがわかります。
御本尊はゆったりとしたお姿をした木造地蔵菩薩半跏像で、南北朝時代の作です。仏像の専門家も「創建時に遡り得る本尊像が伝わることは歴史的にも注目されよう。」と高く評価しています。左足を踏み下げて座っていますが、このような姿の地蔵を「延命地蔵」といいます。(『千葉市の仏像』千葉市教育委員会、1992)。
ところで、本寺の門を入るとすぐ左手に閻魔堂があります。その中に木造閻魔王座像が安置されています。座っていますが、像の高さは約168cmに及び、閻魔大王にふさわしく玉眼の入った目をカッと見開き、口を開いて一喝しているようで、たいへん迫力があります。いうまでもなく、閻魔は死後、人間の罪業を裁く十王の中心です。頭部内側には墨書による銘文があり、これによって明応4年(1495)に造立されたことが判明します。
その左側には木造奪衣婆坐像があります。奪衣婆は三途の川のほとりで、亡者から着衣を剥ぎ取る鬼婆で、その名にふさわしく恐ろしい形相です。この像にも墨書銘があり、天文12年(1543)に作られたことがわかります。戦国時代の閻魔王像と奪衣婆像があわせて残されていることは大変貴重です。さらに、閻魔と奪衣婆の上の壁面にある棚には、江戸時代の寛文9年(1669)に作られた、50cmほどの小振りな十王像がずらりと並んでいます(前掲『千葉市の仏像』)。
次回は、御本尊が地蔵菩薩であることに加え、当寺に閻魔をはじめとする十王や奪衣婆という冥界の者たちが揃っていることの意味を考えたいと思います。
36 高徳寺(中央区亥鼻2丁目)(2)
前回申し上げたように、当寺の御本尊は南北朝時代の木造地蔵菩薩半跏像で、明応4年(1495)に造立された木造閻魔王座像、天文12年(1543)の木造奪衣婆坐像という、中世の仏像が3体も残されており、大変素晴らしいことです。また、江戸時代の十王像も揃っています。
地蔵菩薩は、よく知られているように地獄へ堕ちた衆生の苦しみを救う仏として信仰を集めました。多くは僧の姿とされ、地獄・餓鬼・修羅などの六道をめぐりながら衆生を救済するとされましたが、特に地獄での責め苦から救ってくれる仏と考えられてきました。
人間は死ぬと七日ごとに十王の裁きを受けるとされます。初七日の秦広王から始まり、初江王、宋帝王、五官王、閻魔王、変成王と続き、四十九日の泰山王という順番です。これで決まらない場合は、百ケ日に平等王、一周忌に都市王、三回忌に五道転輪王の裁きがあります。これら十王の中でもっとも有名なのが、生前の善悪の振る舞いを映し出す「浄玻璃鏡(じょうはりのかがみ)」を持つ閻魔王です。閻魔王の本地仏は地蔵菩薩とされました。
死後、最初に出会う奪衣婆は、三途の川のほとりで盗みをした者の指を折り、亡者の衣服を剥ぎ取り、懸衣翁という老爺の鬼が衣領樹という大樹にかけます。その重さには生前の行いが現れるとされます。さらに、奪衣婆は閻魔王の妻であるという説まで生じました。
このように亥鼻山(亥鼻台地)を背にした当寺に、冥界を代表する地蔵菩薩・閻魔王・奪衣婆が安置されることは、亥鼻山周辺が来世、冥界と関係の深い土地であったことを示す痕跡ではないかと考えられます。
詳細は後日、猪鼻城のところで述べたいと思いますが、戦国時代になって城郭が築かれる前、亥鼻台地は宗教的な空間、聖なる場であり、葬送の地でもあったと考えられます。七天王塚を紹介した際には、古墳があったこと、十王を祀った塚という伝承にも触れました。
石井進氏は「歴史の生き証人「柏槇(びゃくしん)」 建長寺」で、鎌倉の建長寺(臨済宗)について次のように述べています。
むかし北条時頼が執権の時、斉田(さいた)左衛門という武士が無実の罪で地獄谷で処刑されようとしたが、日頃あつく信仰している地蔵像が身代わりに立ったおかげで一命を助かった、その小像が心平寺の本尊の胎内に移され、さらに建長寺建立の際、仏殿本尊の頭部に納められたと伝えられている。刑場であり、葬送の谷であった地獄谷の名ごりが、地蔵菩薩への信仰として今も建長寺のなかに生きつづけているのもまことに理由あることであろう。(『風土と歴史をあるく もうひとつの鎌倉 歴史の風景』そしえて、1983)
亥鼻山と高徳寺との関係は、これにかなり似ていることがわかります。高徳寺に残る、冥界のトリオともいうべき地蔵菩薩・閻魔王・奪衣婆たちは「千葉氏の本拠である千葉城」とは異なる亥鼻山のイメージを示してくれます。
37 東禅寺(中央区亥鼻2丁目)(1)
高徳寺の石の門を出て左手に行くと、道が二股に分かれます。左の方へ50メートルほど進み、三叉路をさらに左に折れ約30メートル行くと、また三叉路があります。右手には県立千葉高校の正門へ登る坂道が見えますが、左側の谷津(小支谷のことを南関東では「谷津(やつ)」とか「谷戸(やと)」、「谷(さく)」といいます)の中の道を進みます。亥鼻山の南側の裾を回り込むように200メートルほど行くと、右側に亥鼻保育園、左側にお寺があります。
ここが曹洞宗の金剛山東禅寺です。本堂の棟には月星紋が輝き、千葉氏ゆかりの寺院であることがわかります。寺伝によれば、千葉貞胤が円中規公を開山として嘉禄2年(1327)に建立したとされています。当初は臨済宗で、夢窓礎石の像がありました。
保育園に隣接して墓地があり、かつては道の両側、保育園などを含む谷津のなか全体を境内としていたことがわかります。この谷を「東禅寺作(さく)」と呼んでいたそうです。「作」は「谷」の当て字でしょう。江戸時代の終わり、海防のため佐倉藩が亥鼻山に藩士を駐屯させた際には、この谷津の中で鉄砲の調練を行ったといいます(和田茂右衛門『社寺よりみた千葉の歴史』千葉市教育委員会、1984)。弾が外に出る可能性が少ないためでしょう。
当寺の御本尊は木造薬師如来坐像で、『千葉市の仏像』(千葉市教育委員会、1992)では「鎌倉時代前期の慶派の作風に連なる」としています。穏やかな中にも力強い表情をした、美しくも堂々とした仏像で、同書は「市内はもとより県内の中世彫刻の中でも抜群の作行を示し、(中略)鎌倉時代の彫刻史上に重要な作例に挙げられる」と絶賛しています。個人的な感想ですが、千葉市美術館の特別展「房総の神と仏」(平成11年・1999)で初めて拝見した際に、大いに感銘を受けたことが思い出されます。
ちなみに、慶派とは康慶・運慶父子に始まる仏師の一派としてあまりに有名ですが、鎌倉時代の慶派の優れた作品が当寺に残されていることは、その造立の後ろ盾となった千葉氏が大きな力を有しており、鎌倉時代の千葉が高い文化水準を持っていたことを意味します。
なお、かつて当寺には元徳3年(1331)の梵鐘がありました。その銘文は中世の千葉のまちの姿を考える上で極めて重要なものですが、その内容の考察については後に譲ることとして、今回は「円覚首座比丘奇英為之銘曰」という一節がみえることだけを紹介しておきます(『千葉縣史料 金石文篇一』千葉県、1975)。
これによって円覚寺首座の比丘(びく、僧侶)が銘文を書いたことがわかります。鎌倉の円覚寺は北条時宗が無学祖元を開山として建立した臨済宗の大本山で、当寺が臨済宗であったことが裏付けられます。しかし、後に原氏の菩提寺である宗徳寺(曹洞宗、現在は佐倉市臼井台)の末寺となり、その二世の機然正哲和尚が中興開山となったため、曹洞宗に改められたと考えられます。前に紹介した高徳寺も機然正哲が中興し、宗徳寺の末寺となっていますから、戦国時代には亥鼻を含む千葉一帯が原氏の強い影響下にあったことがうかがえます。
コラム:中世の城跡をめぐる
遠山成一(郷土博物館研究員)
当コラムでは、最近ひそかなブームともいえる中世城郭を、それも千葉市内を中心に取り上げ、解説したいと思います。城歩きするときに、より有意義な散策が可能になれば幸いです。
なお、城歩きは季節的には晩秋から早春までが最適です。これ以外の季節は、害虫、害獣がいたり、草の繁茂などで遺構が見づらいこともあるので、おすすめできません。また、滑落で思わぬケガをしかねません。できるだけ複数で行かれることをおすすめします。
城跡が私有地の場合は、所有者の方の許可を得てから入るようにしてください。
- 中野城跡
- 大久保城跡
- 平山城跡 ~千葉宗家が一時本拠とした城~
- 東常縁余話 ~和歌を贈って城を取り戻した東常縁~
- 多部田城跡
- 大椎城跡
- 浜野城跡〔生実藩蔵屋敷〕 その1 その2
- 高品城跡 その1 その2
- 千葉六党の城 大須賀氏
- 千葉六党の城 国分氏の城
- 千葉六党の城 東氏の城
- 千葉六党の城 相馬氏の守谷城 その1 その2
- 立堀城跡
- 猪鼻城跡
- 城山城跡
- 生実城跡 その1 その2
- 南小弓城跡 その1 その2
- 土気城跡 その1 その2 その3 その4
- 千葉六党の城 海上氏の本拠中島城 その1 その2
- 廿五里城跡
- 南屋敷遺跡
- 千葉六党の城 東氏の城 その2
- 千葉市内の城館関連小字名
- 大井戸館跡
- 鹿島川流域の城 総論
- 大篠塚城跡
- 馬渡馬場館跡
- 太田要害城跡
1 中野城跡(千葉市若葉区中野町)
中野城跡は、国道126号線で東金方面に向かう途中、中野バス停の手前左手に大きく「本城寺中野城跡」の看板があり、すぐに入口がわかります。国道から坂を下り、また上っていくと顕本法華宗長秀山本城寺の境内に入ります。中野城跡は、この本城寺を含む一帯が城域となっています。城域からやや離れて、南から東に鹿島川が蛇行して北流しています。城跡は台地上に築かれ、西から南西にかけては、鹿島川へ流れ込む小さな谷が天然の空堀として機能しています。
城跡は四方を空堀で囲まれていたと思われますが、台地続きの南東側は北東隅部を除くと土塁がわずかに残るだけで、空堀は埋められたのか、確認することができません。しかし、こちらに大手があったと思われます。これに比べ、北東から北西部は土塁と空堀がよく残ります。また国道から境内に向かう上り坂の右手には、斜面に二重の土塁がよく残っていて、一番の見どころと言えましょう。縄張構造からみて、戦国時代まで使用されていたと考えられます。
歴史的にみると、本城跡は房総酒井氏の祖とされる酒井定隆が、最初に入った城と一般には言われています。近世初頭に著された『土気城双廃記』によれば、 定隆は「上総と下総の境に中野村と云う所に住居成され(現代語訳)」とされています。この「中野村…住居」ということから、中野にある城、中野城が定隆の拠った城とされたものと考えられます。
しかし、両総国境の中野村は、千葉市緑区中野町だけでなく、市原市中野もこれに該当します。市原市中野は、土気に水源をもち千葉市中央区浜野で東京湾に注ぐ村田川(上総下総の国境となる)の中流域左岸に位置しています。日泰開基の本行寺があり、酒井氏ともゆかりの深い浜野と、土気の中間に位置しています。土気城にやがて進出する酒井氏が一時拠点を置いたのは、市原の「中野村」と考えることも十分可能だと思われます。
本城寺縁起(『千葉縣千葉郡誌』所収)によると、土気城に移った定隆により日泰を開山として延徳元年(1489)に本城寺が開基されたといいます。つまり城としての機能は、この時点で終わったということになります。しかし、縄張構造的には前述のように、少なくとも戦国時代まで使用されていたと考えられます。また、地理的にみて鹿島川の水源地に程近い土気城にとって、本城跡は鹿島川沿いに侵入してくる敵を迎え撃つ格好の位置にあります。ですので、本城跡は土気城の重要な支城(境目の城)の一つと言えるでしょう。
実際、永禄8年(1565)に北条氏政の軍勢が土気城を攻めた時、臼井原氏率いる一団が戦っていますが、こうした北方からの敵を抑える役割を果たしていたものと思われます。
このように考えますと、本城跡が城としての役割を終えたのは、少なくとも本城寺が開基された延徳元年よりも後へ下るのではないでしょうか。ともあれ中野城は、土気酒井氏にとって重要な支城であり、ここに日泰ゆかりの本城寺が建立されたのもうなずけます。
なお、下の鳥観図は余湖浩一氏のウェブページ「余湖くんのお城のページ」より、お借りいたしました。

2 大久保城跡(千葉市花見川区浪花町)
JR総武線の新検見川駅を過ぎ幕張方面に向かうと、間もなく花見川の鉄橋を渡ります。山側の車窓からは、左の川岸に張り付いて、ぽつんと取り残されたこんもりとした小山が見えるはずです。これが唯一遺された大久保城の遺構です。城域の主要部は、戦後まもなく花見川の流路を直線に付け替えた時に、台地ごと消滅してしまいました。さらに遺された城域も宅地化によって大きく改変されてしまいました。そこには大学の寮がありますが、台地縁辺には腰曲輪も残るそうです。この大久保城跡の西側の道路は旧河道跡に造られており、窪んでいるのがわかります。ここを境に本城跡側は浪花町、西側は幕張と住居表示が分かれます。
大久保城跡の中心部のあった台地南麓からは旧花見川の河口に近く、また検見川神社(八坂社)が鎮座しています。神社の前には、街道に沿って本宿・上宿・中宿・下宿の街並みが広がります。16世紀初頭の永正2年に連歌師宗長が小弓の原胤隆のもとを訪ねた帰路、浦風が激しく検見川の宿に泊まることになりました(『東路のつと』)。中世の段階に、房総往還に該当する道沿いに宿場町が形成されていたことがわかります。
なお、『更級日記』の作者菅原孝標女(すがわらのたかすえのむすめ)が歩いたはずの上総国府と下総国府とを結ぶ古代官道は、検見川神社のすぐ北に字「大道」があるので、海際の房州往還より高い台地上を通っていたと思われます。
また、旧花見川河口は湊としても機能していたと思われます。というわけで、検見川の宿は、宿場町、鳥居前町、湊町という複合的な機能をもった町として賑わったことでしょう。
それでは、大久保城跡はどのような機能を持った城だったのでしょうか。残念ながら、本城跡はほぼ消滅した関係で、縄張構造がまったくわからず、中世のどの段階に使用されたのか不明です。また、どのような主体が城に拠ったのかもよくわかりません。城と宿とは、やや距離が離れているので、城と城下集落という関係とは言い切れないと思われます。
ただ、これより上流は、千葉六党の武石氏の名字の地武石となります。武石氏といえば鎌倉時代初期に東北へ移住した一族は有名ですが、下総に残った一族もおり、これとの関連が推測されます。つまり、江戸内海(東京湾)への出口を確保すると同時に陸路(房総往還)を抑える、という役割を持った城だったのではないでしょうか。
なお、本コラムを書くにあたって「千葉市の遺跡を歩く会」のウェブページ「花見川水系の歴史的景観」を参照しました。
3 平山城跡(千葉市緑区平山町) ~千葉宗家が一時本拠とした城~
千葉市で平山町といえば、享徳の乱によって千葉宗家は佐倉千葉氏の祖である輔胤・孝胤(のりたね)系に替わり、本拠が千葉市中心街からいったん「平山」に移ったことが知られています(『千学集抜粋』)。平山町には輔胤から勝胤までの三代が居住した平山城跡があります。同城跡は都川支川の上流、亥鼻からは直線距離にして約8km奥へ入った地点にあります。同川に向かって南西に突出した半島状の台地に、城跡は位置しています。城域はおおよそ300m×170mと大規模で、部分的ではありますが、土塁もよく残っています。現状では、妙見社の建つ先端の曲輪以外は民家が建ち並んでいて、残念ながら詳しく見学することはできません。しかし、先端部の腰曲輪や城跡の縁辺部は遺構もよく残っていて、見応えがあります。
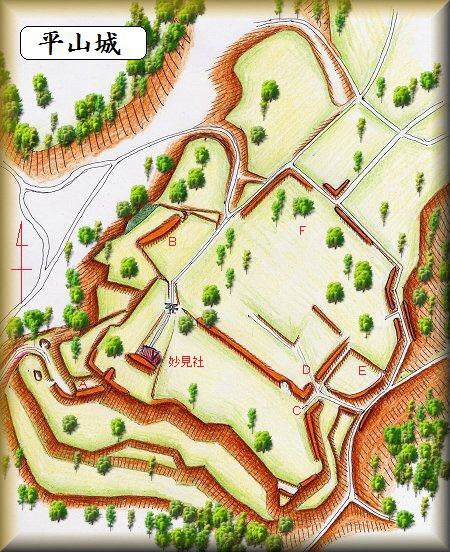
さて、この城で注目したいのは城本体よりも、やや離れて存在する字「しく」、つまり宿の部分です。宿といえば街道の宿場町のほか、城の城下集落として従来とらえられてきました。しかし、房総の宿という小字70例を調べたところ、街道とは無縁に形成された城下集落としての宿は、唯一この平山城の宿地区だけでした。他は街道に形成されたものか、城の直下の街道沿いに町場の宿を囲い込みながら形成されたものがほとんどです。これら街道に沿って展開する宿は、いわゆる短冊型地割という、間口が狭く奥行きが深い形状をとります。しかし、平山の宿は、方形の区画の中にブロック状の地割があるという、房総では極めて珍しい形状をとっています(『千葉市図誌 上』)。その理由は、この宿の形成された歴史的背景にあります。
15世紀半ばの享徳の乱によって、鎌倉公方足利成氏と対立する関東管領上杉方についた千葉胤直・宣胤父子は、馬加康胤・原胤房らによって千葉城を追われ、ついには千田庄多古で滅亡を遂げます。胤直・宣胤に代わって千葉宗家を襲った馬加康胤も、京都将軍家が上杉氏を助けるため遣わした東常縁によって討たれました。その結果、岩橋(酒々井町上岩橋・下岩橋)に本拠をもつ馬場氏系の輔胤の系統が千葉宗家を継ぐことになります。この輔胤が平山に入るのです。平山城と輔胤の家臣団が居住する宿は、この時に取り立てられたと思われます。
平山城は一時的な築城ではなく、縄張からみても本格的な城といえましょう。また、家臣団の居住地である宿をともなっています。
ところで、なぜ千葉の中心街から奥まった所に築城したのは、海からの直接の攻撃を避けたためと思われます。とはいえ、佐倉千葉氏と緊密な関係にあった小弓原氏の本拠小弓城とは、さほど離れてはいません。しかも、小弓と旧東金街道(松ヶ丘町から仁戸名・川戸町・大宮台・平山町を経て、川井町で国道126号線に合流する)とを結ぶ道から、平山城へ至るわけです。陸上交通からみても小弓にも亥鼻へも通じていました。
千葉宗家が平山・長峰を去り、文明年間に本佐倉城へ本格的に移転すると、地理的にも海岸部から奥まった位置を占める平山城は、その役割を終えたようです。城下の宿からは家臣団が消え、その後住む者もいなくなったと思われます。現状の「しく」は山林と化しています。とても人家が立ち並んだとは想像もつきません。
文中の鳥瞰図は、余湖浩一さんのウェブページ「余湖くんのお城のベージ」よりお借りしました。
4 東常縁余話 ~和歌を贈って城を取り戻した東常縁~
前回の平山城で登場した東常縁(とうのつねより)に関する有名なエピソードを、今回ご紹介したいと思います。以下は、『鎌倉大草紙』という戦国時代には成立をみたと考えられる古記録に記された話です。
享徳の乱に端を発した千葉家の内紛により、康正元年(1455)八月、宗家の千葉胤直父子が馬加康胤・原胤房らに滅ぼされました。京都の将軍足利義政は近臣である常縁に対し、馬加康胤を退治し、武蔵へ逃れた実胤(胤直弟の賢胤の遺児)を千葉に連れ戻すよう命をくだしました。美濃の山田庄(岐阜県郡上市大和町)を本拠にしていた常縁は、祖先の故郷下総国へ下り、両総を転戦します。ついには康胤を討ち取りますが、武蔵の実胤を連れ戻すまでには至りません。美濃より同行した配下の浜春利を東金城に配し、自らは故地東庄へ戻りました。
常縁が下向して十年余りが経った1467年、京では応仁の乱が勃発します。西軍の山名方に属していた斎藤妙椿は、東軍勢を駆逐し美濃一国を平定しました。斎藤家は守護土岐氏の守護代を務める家柄で、妙椿は甥にあたる守護代斎藤利藤の後見役として権勢をふるっていました。この過程で、美濃東氏の本拠篠脇城(しのわきじょう:郡上市大和町)も妙椿に奪われてしまったのです。
承久年間に美濃山田庄を東素暹(胤氏)が得ると、その子行氏に伝領され、代々美濃東氏として発展していきました。常縁は、足利将軍の命で下総に下向している間に、二百年以上持ちこたえてきた故地を奪われてしまいました。悲嘆にくれた常縁は、父の命日に心情を和歌に託しました。
あるかうちに かかる世をしも見たりけり 人の昔もなほも恋しき
これを見た浜春利は、兄康慶に書状を送り、この歌を書き添えました。康慶もこの歌に感じ入り、諸所で披露しているうちに、妙椿にも知られるところとなります。歌人であった妙椿は、常縁に和歌を贈ってくれたら篠脇城を返す旨、伝えさせました。これを聞いた常縁は、十首の歌を詠むと春利を介して妙椿に贈りました。
堀川や 清き流れを隔て来て 住み難き世を 嘆くはかりそ
このほか九首を受けた妙椿は、常縁へ返歌を贈ります。
言の葉に 君の心はみつくきの 行く末とをくへ 跡は違わじ
こうして、将軍の許しを得て下総を離れた常縁は、本拠の篠脇城を妙椿より受け取ることができたのです。これが『鎌倉大草紙』に載る有名な話です。もちろん、単に和歌に通じた両者が心を通わせて実現した、という理由だけでかたづけられないでしょう。背景には、応仁の乱という複雑な政治力学があったと思われます。
ところで、篠脇城のある郡上市大和町は、国指定名勝の東氏館跡庭園や明建(妙見)神社、さらには古今伝授の里フィールドミュージアムがあり、見どころの多い町です。訪れてみて驚いたのは、明建神社の前の集落を歩いていた時です。家々の表札を見ると、なんと東総地区に多い千葉県ゆかりの姓がずらりと並んでいました。山麓の森の中に厳かに建つ神社と、八百年前から連綿と続くこの集落の歴史を思うと、不思議な感動を覚えたものです。
また、篠脇城跡は山頂の主郭の周りをぐるりと畝状竪堀(うねじょうたてぼり)が取り巻く、千葉県では目にすることのできない遺構があります。畝状竪堀とは、城の斜面に垂直な竪堀を連続して掘りこむものです。ちょうど斜面が畑の畝のようになります。敵が斜面を横に移動するのを妨げ、堀底を上ってくる敵を上から射撃しやすくするために造られると考えられています。篠脇城の場合は、山頂の曲輪の周囲をぐるりと連続して畝状竪堀が廻ります。筆者が訪れたのは、ちょうど有名な郡上の盆踊りが行われている最中でしたので、残念ながら草に埋もれた畝状竪堀は見ることができませんでした。登山道の途中で、マムシの子どもを見てしまったものですから、草を踏み分ける勇気がなかったのです。
5 多部田城跡(千葉市若葉区多部田町)
国道126号線(東金街道)を東金方面に進み、大草町の千城台入口の交差点を過ぎてしばらく行くと、千葉市平和公園入口に至ります。ここを右折し、都川を渡るとすぐにまた右折します。バス停「平和公園いずみ台ローズタウン入口」を過ぎるとすぐに現れるY字路を右方面に進み、千葉へ戻るようにします。すると細い道の両側に、間口が比較的狭く奥行の長い家並が続きます。ここが宿地区です。しばらく行くと正面に小高い森があり、道はここにぶつかり左折します。多部田城跡は、この小高い森の中とその手前宿地区の南方にかけてとなります。
千葉常胤が鎌倉幕府創設に貢献し、大須賀郷(保)を新恩給与されると、四男胤信がここに入部します。多部田の地は胤信が初めに名のった名字で、宗家が大須賀へ移った後も胤信の次男胤秀一族が残り、「多辺田」を称しています。
|
多部田城跡概念図 外山信司氏作図 |
さて城跡は、切通で大きく東西二つの部分に分かれます。西側(千葉市街地寄り)が主たる曲輪としてよいでしょう。ここには妙見社の小さな祠が祀られており、成田市域の大須賀氏の城と共通するところです。なお、この城で注意しなければならないのは、第二次世界大戦中の軍部による地形改変です。聞き取りによってわかるだけでも、東側曲輪の妙見社裏の中途半端な掘り込みと、西側曲輪の東西方向に延びる二本の掘り込みは、旧日本軍が防空壕やその他の目的のために掘ったと言われています。妙見社裏の土橋は、東側字「松崎」の畑へ行くために盛り土して土橋状の通路にしたものだそうです。このように、一見すると高度な築城術かと誤解されかねない遺構は、どうやら後世の改変になるものと思われます。
しかし、西側曲輪の南側の堀は規模も大きく戦国時代後半まで使用されていたと思われます。それでは、戦国時代まで使用されていた理由は何でしょうか。そのカギは宿地区にあります。前述のように、ここの宿地区は間口が狭く、奥行きが長いという典型的な短冊型地割をしています。これは街道の宿(宿場町)によく見受けられる形です。つまり、城跡に隣接する一見城下集落としてみえる宿も、城が築かれる前に街道の宿として成立をみていたと考えられるのです。
それは、多部田地区は仁戸名方面からの道が通過しており、この街道の宿として発展したものと考えられるからです。具体的には、仁戸名から城の腰城跡を左に見ながら支川都川を渡り、突き当たる長峰地区で東へ折れます。千城小学校を経て途中太田町・坂月町方面に北上せずにさらに東へ進み、北大宮台から大宮台への進入道路を横断して進むと、小支谷を渡り多部田城跡の東西に分ける切通に至ります。現在水田となるこの小支谷の字を「馬渡」といいます。馬渡地名は川の渡河点につけられ、各地に残ります。よく知られるところでは、国道51号線が鹿島川を渡る千葉寄りの佐倉市馬渡地区で、これは古代末期には地名として確認できます。
多部田からは、都川左岸に沿って上り、旧東金街道に至る道や、高根町から北上して下泉町から佐倉方面に行く道などが想定されます。多部田の宿のさらに東方には字「豊前屋敷」「陣場」があります。豊前屋敷は重臣クラスの屋敷地であったと思われ、もともと街道の宿であった宿地区が城下集落として取り込まれ、さらに東方に城下集落が拡大したものと考えられます。
このように考えると、街道沿いに成立した宿とこれを取り込んだ多部田氏の屋敷(館)が基本にあり、その後、街道を抑える関所的な役割を果たす城郭が構えられ戦国期に至った、と考えられないでしょうか。また、秀吉による小田原合戦時に房総の小田原方の城々が攻め落とされていますが、この時、多部田城も攻撃を受け落城したという伝承が残っているそうです。これが事実を伝えるものとすれば、戦国最末期まで本城は使われていたことになります。ちなみに多部田氏の名は、多部田城と直接関係するかどうかわかりませんが、多辺田与太郎なる人物が天正2年(1574)9月の「千葉氏黒印状」(松本昌之家文書)に記載されています。
この記事を書くにあたり、ウェブページ「千葉市の遺跡を歩く」から「多部田の歴史を歩く 2」を参照させていただきました。また、概念図は外山信司氏作成図(『千葉県所在中近世城館跡詳細分布調査報告書1.』から)を使用させていただきました。
6 大椎城跡(千葉市緑区大椎町) ~土気城の南西の守りを担う~
JR土気駅南口は1980年代に大型宅地開発をうけ、広大な農地や山林はあすみが丘の街並みに姿を変えています。大椎城跡はあすみが丘東地区の南西部に隣接する、東西400m、南北100mほどの昔の面影を残す独立丘状の台地に占地しています。
城は東西に細長い台地を南北に掘り切った四つの郭からなる、「直線連郭」の形態をとります。台地の先端にあたる西端部の郭が主郭(近世城郭でいう本丸に相当)で、2郭・3郭・4郭と並びます。東側の台地部と4郭とは、自然の沢を利用した馬の背状の土橋でつながります。
四つの郭はそれぞれ空堀で区画されますが、2郭と3郭、3郭と4郭の間の堀は「折り」(*1)とよばれる技法が使われています。主郭・2郭・3郭のそれぞれ東端には土塁が築かれています。しかし、2郭・3郭・4郭のそれぞれ西端には土塁は築かれていません。つまり優位な郭に相対する端(大椎城の場合は西端)には、土塁を築かないのです。なぜならば、敵が4郭→3郭→2郭と攻め進む時に、西端部に土塁が築かれていたとすると、敵にとって恰好の身を隠す場所を提供してしまうことになるからです。
主郭と2郭のそれぞれ東端の土塁には折りの技法が用いられ、隣接する土塁の開口部となった虎口(出入り口)に横矢(*2)がかかるように工夫されています。
城跡南麓には、台地裾部を数段のテラス状に整形した集落が展開しています。この中には「ねごや」、「ね」という屋号をもつお宅があります。ねごやとは根小屋とか根古谷などと書き、中世城郭の城下集落に相当する区画を指します。家臣や城主の居住空間となっていましたが、「小屋」ということで、あくまでも仮の住まいと考えられます。これに対し、日当たりの悪い北麓は自然のままに残されていたようです。
ところで大椎といえば、大治元年(1126) 千葉氏が常重の代に千葉市へ移住する前まで、本拠としていたとされる(『千学集抜粋』)地です。しかし、この大椎城は形態から見る限り、常重の頃のものとすることは到底できません。戦国時代も後期の、つまり土気酒井氏関連の城とみるのが妥当なところでしょう。実際、本城周辺には、宅地開発で消滅してしまったいくつかの城があったことがわかっています。後台城跡・御堂前城跡(大椎町)、大谷城跡(あすみが丘)です。大谷城跡はつくりかけの城と評価されています。これらの城は大椎城とともに、村田川沿いに侵入する敵に対する防御を担っていたと思われます。
この記事を書くにあたり、簗瀬裕一氏執筆の『千葉市の戦国時代城館跡』(千葉市立郷土博物館 2009年)および小高春雄氏『山武の城』(私家版 2006年)を参考にさせていただきました。また城の図面は、『千葉市の戦国時代城館跡』掲載の図(簗瀬裕一氏作図)をお借りしました。なお、城内に入るには南側の私有地である人家を抜けるのは避け、東側のあすみが丘東地区から土橋を渡る方法をとっていただきたいと思います。
(*1) 折り…「折ひずみ」とも言い、堀や土塁をわざと屈曲させて築くことをさす。堀底を進む敵は前方を見通せないことや、進行速度がおくれてしまう心理的負担を負うことになる。また、城内からは、敵の正面と側面を同時に攻撃しやすい利点が生ずる。
(*2) 横矢…「横矢をかける」という使い方をする。敵の側面を攻撃すること。例えば盾などで正面や左側面を守る(右ききは盾を左手でもつ関係で)ことができても、右側面は守ることができない。土塁に折りを入れて城に向かって攻めてくる敵の右側面を攻撃しやすくなる。これを横矢とか横矢をかける、という。
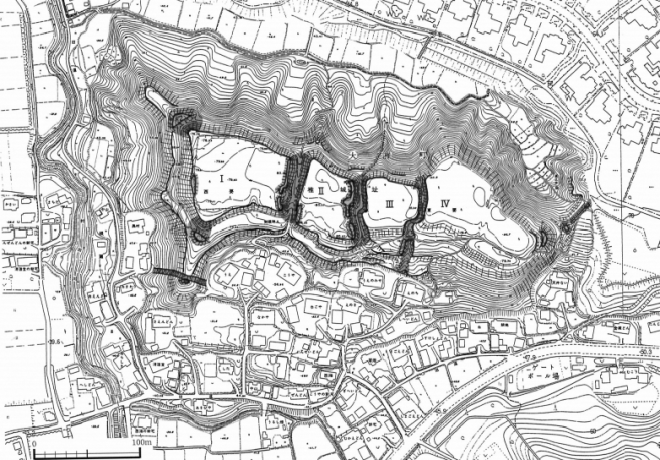
7 浜野城跡〔生実藩蔵屋敷〕その一 (千葉市中央区浜野町)
JR内房線浜野駅で下車し、千葉市街地方向へ向かって歩くと、十分足らずで顕本法華宗如意山本行寺が見えてきます。この一帯に、あまり知られていませんが中世の城がありました。生実藩蔵屋敷跡として一般に知られる浜野城跡です。残念ながら、現状では城の痕跡はまったくと言ってよいほど残っておりません。しかし宝暦5年(1755)の古絵図には、本行寺の西側は「城ノ内」とされており、城であったと、かつては認識されていたのです。
浜野は中世には「浜」とか「浜村」と呼ばれていました。塩田川(現浜野川)の河口を利用した湊は、東京湾の水上交通の拠点の一つとして大変重要な役割を果たしていました。この湊を管理する施設が、浜野城です。近世の生実藩の年貢米を江戸に運ぶための施設である生実藩蔵屋敷は、戦国期以来の浜野城を利用していると考えられます。
浜野の湊は、原氏の本拠小弓城の外港と位置付けられます。しかしながら、永禄から元亀年間にかけて、北上を試みる里見氏の前に、小弓城は落城を余儀なくされ里見氏の占領をうけました。元亀2年(1571)8月、小弓城の奪回をはかるべく北条氏は下総へ進攻しました。佐倉の千葉胤富も配下の東下総の軍勢に動員をかけていることが文書からわかります(「元亀二年ヵ八月廿八日付千葉胤富書状」『原文書』)。いったんは里見氏より城を奪い返したものの、再び奪いかえされています。
その後、原氏は小弓城を取り戻したようです。そして天正2年閏11月、三次にわたる攻撃の末、関宿城をついに手に入れた北条氏政は、いよいよ里見氏との対決に全力を注ぐことになりました。まずは里見方に下っていた東上総の土気・東金の両酒井氏を攻めます。天正3年8月16日、北条氏繁は「当口着陣早々御吏僧誠以喜悦候(当地に着陣したところ、早々とお使いの僧をよこしていただき、うれしく思います)」と本行寺に宛てて書状を認めています(「北条氏繁書状」『本行寺文書』)。ここで「当口」とは具体的には明らかにはできませんが、浜野に近い湊のある場所ではないかと思われます。というのも、玉縄(鎌倉市)衆を率いる氏繁は水軍の将であり、東京湾を船でやってきたと考えられるからです。氏繁は「明後日本納近所可為計□(略ヵ)間(あさってには本納城の近所を攻撃するつもりなので)」と書中で述べており、土気酒井氏方の本納城(茂原市)周辺を攻撃するとしています。
本納へは「当口」を発って茂原街道の潤井戸まで至れば、東国吉さらに金剛地(ともに市原市)を経て移動することが可能です。最終的に北条方による東上総攻略は成功し、猛攻をうけた土気・東金酒井氏は天正4年の段階では北条方に属することになりました。そして天正5年には北条氏と里見氏の和睦がなり、房総の地で両者がぶつかることはなくなりました。
浜野は、このように東上総方面(茂原市や長南町)、また安房方面にも陸上交通が伸びており、まさに水陸交通の要衝というべき地です。この地に築かれた浜野 城は「海城」ともいうべき性格をもっていました。浜野城の主郭は、本行寺の北西にあたる「御蔵」の部分で、その東側に三日月形に隣り合う曲輪が絵図では「城ノ内」と記されています。「城ノ内」の東側には堀が巡っていたようで、堀の北側からは塩田川の水を引き込んでおり(「浜野城想定復元図」『千葉市の戦国時代城館跡』)、舟の出入りが可能であったと考えられています。生実藩の蔵屋敷は、御蔵に入った年貢米を直接舟で東京湾に運びこむことができたはずです。
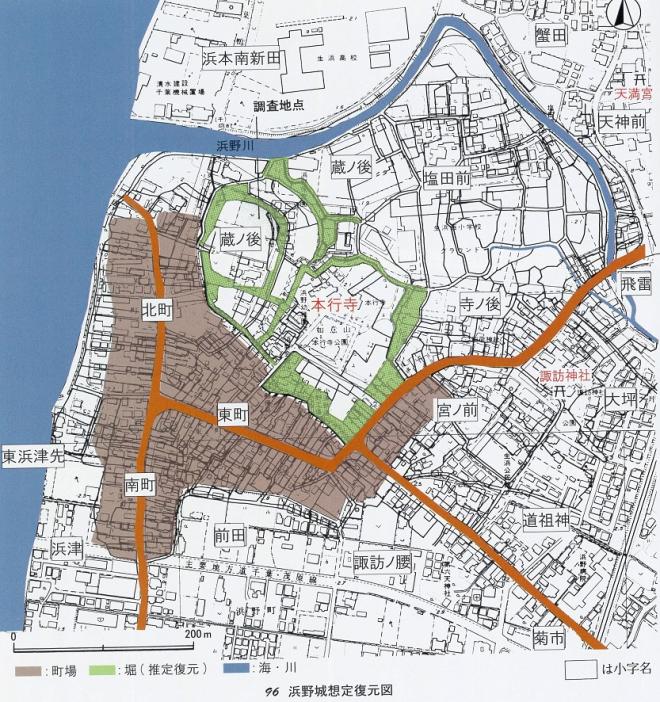
次回「浜野城跡 その二」では、浜野と関係の深い酒井氏(とくに東金酒井氏)との関わりを中心にみていきたいと思います。なお、記述にあたっては前掲『千葉市の戦国時代城館跡』を参考にいたしました。
8 浜野城跡〔生実藩蔵屋敷〕その二 (千葉市中央区浜野町)
浜野城跡の一画を占める如意山本行寺は、開基日泰上人の房総布教の根本寺院です。日什門流の品川妙蓮寺住僧であった日泰は、房総への教線拡大のため渡海して浜村(千葉市中央区浜野)に行き、一廃寺を再興したとされます。これが本行寺であり、時に文明元年(1468)のこととされます。
妙蓮寺と本行寺とを兼帯していた日泰は、品川から浜村へ渡る便船で酒井定隆と出会ったとされます(『土気古城再興伝来記』)。定隆と目される土気・東金酒井氏の祖清伝は、開基日泰ともに文明13年の鎌倉本興寺本堂建立の大檀那として記載されています(「本興寺棟札銘」)。清伝=酒井定隆としてよければ、文明年間初めに、日泰と定隆の間に交流があったことは認めてよいと思われます。
本行寺の位置する浜(浜野)と酒井氏の関係は、戦国時代末まで続きます。それは本行寺も同様で、東金酒井氏の本拠東金にある本漸寺住職は、本行寺と兼帯していたこともあります。
「本行寺文書」にある「遠山氏ヵ副状断簡」には、北条氏が本行寺に与えた禁制を「土気へも東金へも写彼文、袋ニ拙者書状ヲ指添進候、」と奏者である遠山氏と思われる人物が指示しています。この禁制は、元亀二年(一五七一)九月二日付で、里見氏に奪われた生実城の奪回を目指し、北条勢が生実近辺に進攻してきた時に、発給されたものと考えられています。本行寺と東金・土気の酒井氏領域の寺院との密接なつながりがうかがえます。
また、東金酒井氏の家臣鵜沢家に伝わった「鵜沢文書」(原本は行方不明、東京大学史料編纂所に謄写本あり)には、浜と東金酒井氏との密接なつながりを示す文書がいくつかあります。羽柴秀吉による小田原攻めを控えた天正17年(1589)頃のことですが、北条氏の配下にあった東金酒井氏の当主政辰(まさとき)は小田原城にいて、留守を預かる東金城の鵜沢氏らに宛て、何通かの書状を認めています。
年貢の徴収のことと兵糧のことが主な内容ですが、「はまにて与三兵へこしらへ候兵糧」と書かれているものがあります。浜野で米を集め、兵糧として小田原へ送ったのです。ところが、北条氏の定めた枡(榛原枡)で量らなかったため、北条氏に提出する兵糧(大途兵糧)としては枡目違いとなってしまいました。
さらに、伝馬を「はまへ出し候へく候」と指示もしています。東金で集めた兵糧米を浜野へ送ったり、あるいは湊町である当地に集められた米を買い求めた可能性もありますが、東金酒井氏にとって浜野湊は重要な場所であったことがわかります。
ところで東金と浜野は、旧東金街道を使って直接結ばれています。東金から現国道126号線を進み、若葉区高根町宮田の交差点を左折(県道66号線生実方面)します。途中、平山町で大宮町方面に右折(旧東金街道)せず、直進して鎌取町を経て北生実城にぶつかります。
土気からは浜野へは、大網街道を千葉方面に進み、緑区鎌取町で高根町宮田からの道(県道66号線)と交差するところを左折すると、同じく北生実城へ達します。
このように土気・東金酒井氏にとって、外房と内湾を隔てた武相方面とを結ぶ重要な湊でした。そのため浜野城は水堀で浜野川(塩田川)につながり、直接、内湾に荷だしできる港湾機能も持っていたと考えられます。なお、昭和58年(1983)と平成20年(2008)に発掘を受けており(未報告)、生実城と同時期に使用されていたことがわかっています。
記述にあたっては、同じく『千葉市の戦国時代城館跡』を参考にしました。
9 高品城跡 その一 (千葉市若葉区高品町)
国道51号線を、千葉市中央区本町1丁目の広小路から佐倉方面に向かうと、若葉区貝塚町の千葉刑務所脇から四街道方面に左折する道があります(明治40年に千葉監獄が寒川より移転してくる以前は、貝塚町の大六天社で道が分岐していました)。江戸時代には「北年貢道」と呼ばれた、佐倉藩が千葉港へ年貢を陸送した道でした。この道は中世まで遡る、戦国時代の千葉氏の本拠本佐倉城と千葉とを結ぶ重要な道の一つでした。
現在の道でいうと、高品城は、椿森陸橋方面から京葉道路をまたぎ都賀方面に向かう道路と、千葉刑務所方面から来た道とが交差する地点から見て、正面やや左手(北西方向)奥のマンションの建つ辺りに存在していました。
マンション建設のため、平成6年(1994)と7年に主郭周辺の発掘調査が行われ、15世紀から近世初頭までの遺物と空堀・地下式坑・建物址・墓などが検出されました。これによって、15世紀代には建物と墓域として利用されたこと、城として取り立てられた16世紀代には造り替えをともなう二期があったことがわかっています。
高品は中世には高篠と呼ばれており、15世紀初頭には高篠地名が記録に残ります(『香取造営料足納帳』)。戦国期の15世紀後半には千葉氏は本佐倉(酒々井町本佐倉)に本拠を移します。本佐倉城です。
しかし、宗家の嫡男の元服は、最後の当主邦胤の時まで代々千葉の妙見社で行われました(『千学集抜粋』)。永正2年(1506)に元服した昌胤の記録をみてみましょう。本佐倉城から大勢の警固の供を連れ千葉に向かい、千葉の町の出入り口となる高篠で、昌胤(この時点ではまだ幼名ですが)はお供の者たちと待機します。
妙見社への使者原孫七は高篠を発ち、社前において元服にあたり実名を一字くじで選びます。千葉氏は通字を胤としていますので、胤の前につける一字を三通の中から選ぶわけです。くじを引いた後、孫七は高篠で待つ昌胤の元へ戻ります。そして警固の衆を引き連れ、元服式をあげるため妙見社へと昌胤は向かいます。
この時、千葉のまちの八幡社・麻利支天天神・御達報稲荷・瀧蔵権現に礼銭を納めに、安藤豊前守が遣わされます。高品城主安藤勘解由の先祖にあたる人物と思われます。
永正2年の千葉昌胤の元服と弘治元年(1555)の親胤の元服は、礼銭の使者を安藤豊前守が務めていますが、50年ほどの開きがあり、同じ受領名を名のる親子か祖父と孫と考えられます。

高品城跡の主郭直下、城内に等覚寺がありますが、こちらの薬師如来坐像には胎内銘があり、貴重な情報を伝えてくれています。元亀2年(1571)7月2日の日付で城主と思われる大檀那安藤勘解由ほか親族3名、無姓の者20数名が記されています。これら「高篠念仏衆」として結縁する無姓の人びとは、高篠郷に住んでいた民衆と思われます。左衛門・右衛門・兵衛など官途名を名のる者6名のほかは、名前のみで記されています。これら全員を有力名主層とみて、安藤氏の被官とする考えもあります。官途名をもつ6名はそう考えてもよいと思います。しかし、残りの無姓の人びとは、戦国後期に力を蓄えた作人層とみることはできないでしょうか。被官とできるかどうかは「高篠念仏衆」と記されていることから宗教的結合とみられ、直接結びつけることは慎重に考えたいと思います。
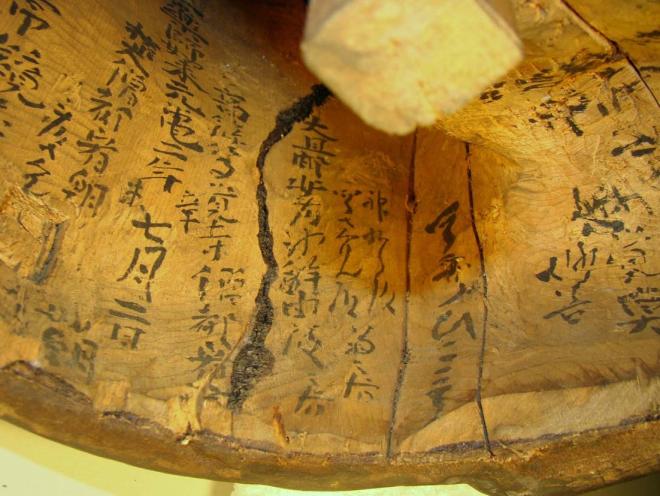
以上、外山信司氏「下総高品城と陸上交通」(『千葉城郭研究』第4号 1996年)および『千葉市の戦国城館跡』(千葉市立郷土博物館 2009年)を全面的に参考にしました。文中の写真はいずれも当館蔵のものを使用しました。
次回は、交通からみた高品城、および高品城の発掘の成果について述べたいと思います。
10 高品城跡 その二 (千葉市若葉区高品町)
千葉氏は、大治元年(1206)大椎より千葉に移って以来(『千学集抜粋』)、千葉の町を本拠にしていました。ところが、15世紀半ば享徳の乱がおこると、宗家を襲った馬加氏は、上杉氏を支援する京都将軍家の派遣した東常縁によって、討伐をうけます。そのため水陸交通の要衝である千葉は、攻撃を受けやすいことから、内陸部の平山(緑区平山町)に本拠を移しました[本コラムの三 平山城]。
さらに、長峰(若葉区大宮町)を経て「佐倉」(酒々井町本佐倉・佐倉市大佐倉)に本佐倉城を築き、天正18年(1590)まで本拠とします。高品の地は、本佐倉城と千葉常重以来の本拠地である千葉とを結ぶ街道の一つである、近世でいう「北年貢道」が貫いています。前回みたように、高品城はこの街道を押さえる役割を果たしていました。
千葉の町から、現国道51号線で佐倉方面に向かい、道場坂下交差点から大六天社の北側を巻く道が本来の北年貢道で、明治年間に千葉監獄(現千葉刑務所)が貝塚町に移転した際、この道は無くなりました。現在は、千葉刑務所先の交差点を左折します。すると高品の集落に入り、都賀方面に道は延びます。
北年貢道は中世に遡ることは確実で、千葉市―四街道市―佐倉市―酒々井町を結んでいました。経路を詳しくみてみましょう。高品からは原町入口の交差点で、近道ですが急坂の「夫婦坂」のある道と、平坦ですがやや遠回りとなる道とが、分かれます。二つの道は、若松町の御成街道手前で合流して、四街道方面にまっすぐ伸びています。
四街道の語源といわれる四街道交差点を過ぎると、戦前の軍隊施設により途中道は無くなっていますが、四街道市役所脇を経て、物井、亀崎を通り、佐倉市羽鳥で鹿島川を渡り、寺崎に入ります。
中世の道は、佐倉市六崎から皿田橋で高崎川を渡り、野狐台(やっこだい)町、大蛇(おおじゃ)町、上代(かみだい)を経て長熊にて、佐倉市八木から来た古東海道香取路(地元の方は成田道と呼びます)と合流します。
本佐倉城と千葉の町を結ぶ街道は、北年貢道に相当するもののほか、古東海道香取路(佐倉市神門から千葉方面は南年貢道となる)や、鹿島川を佐倉市大篠塚で渡り、四街道市山梨を経て千葉市若葉区若松町で古東海道香取路と合流する道など複数本考えられます。
高品城は、北年貢道の千葉の町の玄関口ともいえる位置づけができます。『千学集抜粋』では、本佐倉城にいた千葉氏の嫡子が元服を迎える時、高品の地でお供の者たちといったん待機し、その後、妙見社に向かうとされます。このことから、戦国期の千葉氏は、元服にあたりこの北年貢道に相当する街道を通って千葉へ来ていたといえいます。逆に言えば、待機する場所としての城郭のあった高品を通る道が選ばれたといえるでしょう。現国道51号線に該当する南年貢道(古東海道香取路)では、千葉の町の境界にそのような場所は存在していません。
次に発掘の成果を簡潔に述べてみましょう。主郭のほか多くの曲輪面や、折りをともなう空堀、城に先行して存在していた地下式坑などが検出されました。遺物としては、常滑焼大甕(15世紀前半)、白磁皿(16世紀)、白磁碗(14世紀)、青磁皿(15世紀)、天目茶碗、かわらけ、すり鉢(15~16世紀)、内耳土器(16世紀)などです。
|
|
|
写真 主郭と空堀 |
常滑焼大甕 |
出土遺物の検討により、15世紀半ばから近世初頭まで使用されたことがわかりました。前回触れたように15世紀初頭の記録の載る『香取造営料足納帳』には、「高篠」(高品の古名)の地名が記されています。「平新左衛門」と「原越前入道」の両名が、それぞれ四町八反前後を領有していたことが記されています。15世紀半ばの地下式坑を伴う建物址や墓は、これらに関わる名主(みょうしゅ)などの屋敷であった可能性が高いと思われます。
その後16世紀になり、高品城が取立てられたようです。これは『千学集抜粋』の千葉氏の元服に関する記事に合致します。さらにもう一度、城の造り替えが行われたこともわかりましたが、高度な縄張から戦国末期、さらに言えば元亀2年(1571)の千葉邦胤の元服に関わる修築と考える説もあります。
元亀2年といえば、等覚寺の薬師如来坐像の胎内銘に載る城主安藤氏が思いだされます。この年の元服は、小弓城を占拠した里見氏のため、佐倉妙見宮(本佐倉城内)で行わざるをえませんでした。これは、逆に考えれば、小弓を攻撃する里見氏の脅威によって、最前線たる高品城を強化したことにつながるとも考えられましょう。
今回も、簗瀬裕一氏の編著になる『千葉市の戦国城館跡』および外山信司氏の「下総高品城と陸上交通」(『千葉城郭研究』4号)を参考にさせていただきました。文中の写真は当館蔵のものを使用しました。
11 千葉六党の城 大須賀氏
今回は千葉氏の城から離れますが、千葉六党の城と題しまして大須賀氏の城をとりあげてみます。ところで大須賀氏とはどんな一族でしょうか。
大須賀氏は、千葉常胤四男の多辺田四郎胤信から出る一族です。常胤が源頼朝に従って鎌倉幕府創設に多大な貢献を果たすと、新恩給与を受けて下総各地に子息たちを分派させました。その一人が大須賀保に入部した四男の胤信です。当初、胤信は名のりを多辺田としており、千葉市若葉区多部田町周辺を領有していました。
大須賀保には、もともと上総氏一族である大須賀氏(前期大須賀氏)が領主としておりましたが、上総広常が頼朝に誅殺され所領を没収されたため、胤信が新しい領主として入ることになったと考えられます。
そして胤信は大須賀を名のることになりました(後期大須賀氏;一般に大須賀氏という場合こちらを指します)。前期大須賀氏もまったく滅亡してしまったわけでなく、小規模な土地を領有する武士としてしばらくは存続したことが史料からうかがえます。
胤信の子孫は、旧下総町名古屋周辺にも勢力を伸ばし、やがて助崎大須賀氏(助崎氏)と呼ばれる一族と、旧大栄町松子を本拠とする本宗家とに分かれていきます。
松子城跡(成田市松子)
今回は、松子に拠った本宗家の本城である松子城をご紹介いたします。とは言っても、残念なことに成田空港建設にともなう1970年頃の土取りによって、ほとんど跡かたもない状態となっています。唯一、横堀の痕跡がかすかに残る「稲荷馬場」と呼ばれる区画が本城の北側に隣接して残ります。
幸いなことに実測図が残されており(図参照)、なんとか破壊前の状況を読み取ることができます。消滅した本体は、北から南に向かい「城ノ内」、「用害」、「後詰」の字名をもつ三つの郭から成り立っていました。いわゆる直線連郭の城といえます。城ノ内と用害の間は直線状空堀で分けられていましたが、「用害」と「後詰」の間は、発掘により屈曲した堀が発見されました。この堀の壁面には橋脚と思われる柱穴跡が見つかっており、木橋をかけて用害と後詰を結んでいたことがわかります。
後詰は西方斜面下に枡形空間(出入り口に附属して設ける小空間)を持ち、後詰に上る虎口(出入り口)があることから、中心的な郭(主郭)とは考えにくいと思われます。城ノ内と後詰に挟まれた独立的な郭である用害が主郭とみてよいでしょう。
周辺の字名から、城の出入り口を表す「戸張」、家臣団などの居住する「根古屋」が確認できます。さらに城の南東700mには「内宿」地名が残り、こちらも家臣団が居住していた城下集落と考えられます。
松子城跡と国道51線をはさんだ南側台地には馬洗城跡があり(こちらも公共施設建設により消滅)、香取方面へ向かう旧道が裾を巻いており、街道を監視する役割を果たしていました。
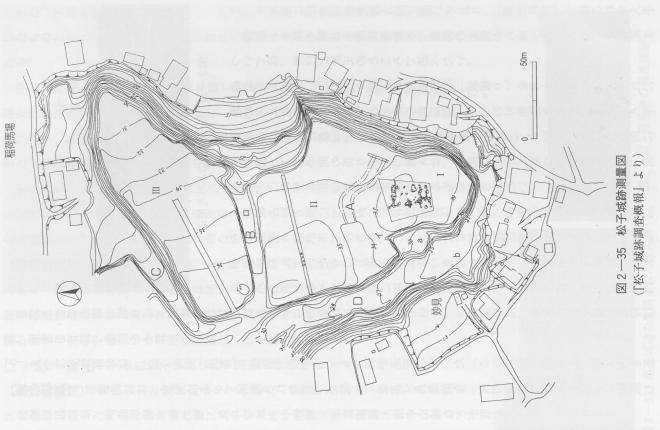 |
| 図 松子城跡実測図(『松子城跡調査概報』より) |
松子城跡の周りには馬洗城のほかにも多くの城跡が配置され、それらは支城として機能していたと思われます。伊能塙城跡・奈土城跡・久井崎城跡・中野城跡・津富良(つぶら)城跡・清水山城跡です。このうち、久井崎城跡は土取りによって、すでに消滅していますが、他は今もなお遺構をとどめています。
こうしてみると、松子城は戦国期には独立した勢力となっていた大須賀氏の本城として、城としての構造、城下集落、支城群とも申し分ない規模を持っていたといえるでしょう。
実測図は『大栄町史 通史編 中世補遺』よりお借りしました。図の左が北方向となります。
12 千葉六党の城 国分氏の城
今回は、国分氏の城をとりあげます。治承4年(1180)9月に安房国へ逃れてきた頼朝一行を助けた千葉常胤とその子たちの中で、当時から千葉以外の名字を名のっていたのは三男武石胤盛、四男多辺田胤信と五男の国分胤通の三人でした。
武石は現在の市内花見川区武石町、多辺田は同じく若葉区多部田町を指します。国分氏は、下総国府に近い国分寺が置かれた国分(市川市国分)を名字に名のっていました。頼朝を助け鎌倉幕府創設に貢献した常胤は、上総広常の遺領をはじめ奥州、九州などに新恩給与を受けました。子息たちは両総をはじめ、全国各地に分派していきました。国分氏は奥州のほか香取神領(香取市)に所領を得、戦国末期まで香取地域で勢力を保っていきます。
ここでは、戦国後期の国分氏の本城であった大崎城(矢作城)を紹介したいと思います。
国分氏の城 大崎城
大崎城は、戦国後期から末期にかけて、国分氏の本城として使われていました。利根川に注ぐ香西川の中流域、北方へ突き出した標高20~30mほどの舌状台地を、長軸で約700m使った大規模な城です。特に、南端部白幡神社周辺の複雑な折りの入った堀切に代表される、南側からの脅威に対する防御施設が目をひきます。それというのも、城の北方は当時沼沢地が広がっていたと思われ、台地続きの南方から攻めるしかなかったからです。
現在、1.郭の中央を両総用水路が縦断しており、遺構は大きく改変されている可能性があります。しかし、1.郭と2.郭とを分ける二重堀切や、3.郭の南に向いた大土塁など見どころは豊富です(縄張図参照)。
2002年から03年にかけて、1.郭の北東部などが発掘調査され、台地裾部の土留め遺構や、低湿地を埋め立てた生活面などが検出されました(写真)。

ところで大崎城は、天正3年(1577)に上総小田喜(夷隅郡大多喜町)の正木憲時の軍勢によって、1月と4月の二度にわたって攻め立てられます。この時、城の西方約1kmの大竜寺の住持大虫和尚が本城に避難しており、その時の様子が『大虫和尚語録』に記されています。それによれば、大虫は城の一段低い平場に避難しており、上の曲輪から子犬が投げ捨てられたため、その犬に名前をつけ飼ったということです。また、4月の攻防戦では城に詰めていた成毛新九郎ら70余名が討ち死にしたことが記され、戦国時代の厳しい現実が伝わります(外山信司「下総矢作城(大崎城)と大虫和尚」『城郭と中世の東国』2005年)。
小田喜正木氏による大崎城攻めは、どのように行われたのでしょうか。永禄3年(1560)の正木氏による香取侵攻は、舟を使って小見川の富田台に「打ち上げ」(大祢宜実隆置文)『香取大祢宜家文書』)たことと、当時の香取内海に面した「相根塚」に城を構えてあしかけ七年ほど香取占領を続けたことから、水運を使ったことは確かでしょう。
 |
| 大崎城跡縄張図(浅井達也氏作成) |
正木憲時による天正年間の香取侵攻は、千田庄多古から栗山川沿いに北上し、伊地山(香取市)、福田(同)、本矢作(同)を経て、大崎城の南方に達したのではないでしょうか(鈴木沙織「東禅寺から香取の海へ」『青山史学』31号)。千田庄中村の北中六所神社には、元亀3年(1572)に兵火にかかって焼けたという記録があり、同年12月、千田庄中村の峯妙興寺に正木憲時の奉じた里見氏禁制が出されていて、千田庄まで正木氏が出張ったことがわかります。
また、多古と香取市府馬を結ぶ街道の途中にあたる多古町東松崎の能満寺は、勝浦城主正木時通(日運)の開基とされます。また、能満寺は松崎城の一画にあり、同族正木憲時が松崎城に入った可能性も考えられます。つまり、香取方面への行軍の中継基地となったのではないでしょうか。
最後に、大崎城にいた国分氏がさらに新城を築いたとされる、岩ケ崎城について簡単に触れておきます。
利根川に面した岩ケ崎城跡は、稲敷市方面から見るとひときわ目立つ独立丘にあります。国分氏が築いてほどなく、小田原合戦で国分氏は滅びます。徳川家康の関東入部にともない天正18年(1590)、鳥居元忠が矢作藩四万石で同城に入ったとされます。しかし、慶長5年(1600)の関ケ原合戦の前哨戦伏見城の戦いで、元忠らは討死を遂げます。戦後、矢作藩を継いだ元忠の嫡男忠政は岩城平(磐城と改名)十万石に加増され転封されました。それにより、岩ケ崎城は廃城になりました。
近世の古文書によれば、国分氏は「天正十年之比同郡岩ヶ崎へ新城ヲ築」(「下総国香取郡矢作領佐原村古来ヨリ覚書」『佐原市史 資料編 別編一 部冊帳 前巻』)いたとされます。その理由として「大崎之城地分内狭要害悪鋪候ニ付」(同前)としています。つまり、大崎城は狭く要害性に劣るので、新たに岩ケ崎に城を築いたということです。
大崎城の城地はけっして狭いとは思いませんが、確かに城下集落をおく余地に乏しいと言えます。それに比べ岩ケ崎は香取内海に面し、「海夫注文」に載る岩ケ崎津もあって水運の拠点の一つで、国分氏が領域を経営するにはより発展性があったのでしょう。
国分氏が本拠を大崎城から岩ケ崎城へ移したのは、ここに大きな要因があると考えられます。
文中の縄張図は、浅井達也氏の図面(千葉城郭研究会編『図説房総の城郭』所収)をお借りしました。また、写真は2013年1月の香取郡市文化財センター主催現地見学会の際、筆者が撮影したものです。
13 千葉六党の城 東氏の城
千葉常胤の伯父にあたる海上常衡(上総氏系海上氏)が領有していた三崎庄(海上庄:現在の銚子市・旭市の一部)は、常衡の孫片岡常晴が佐竹義政に与した疑いで召し上げられ、千葉常胤に与えられました。そして、六男胤頼が橘庄(東庄:現在の東庄町)とともに領有するところになりました。胤頼は東氏を名のり、六党の一つ東氏が成立しました。
東氏からは、海上庄に基盤を置く海上氏(千葉氏系海上氏)が分派しました。一方、東氏惣領は承久の乱後、山田庄(岐阜県郡上市)の新補地頭*として入部し、以後、美濃東氏として続いていきます。シリーズ「4 東常縁余話」でとりあげた室町幕府奉公衆の東常縁はこの美濃東氏になります。
海上氏が海上庄を基盤に戦国末期まで領域支配を行えたのに対し、下総に残った東氏は、室町期に鎌倉府奉公衆としての活動はあるものの、戦国期ともなると目立った動きはありません。
 |
| 須賀山城跡遠景(東方向より) |
東氏の城 須賀山城跡
さて、今回取りあげる須賀山城は、香取市(旧小見川町)と東庄町の市境に位置します。12世紀末に東胤頼が築いたとされています。須賀山城の東麓には、東氏ゆかりの東福寺が、西麓には芳泰寺(東胤頼供養塔と伝わる近世の石塔あり)があって、本城が東氏と関連深いことは確かでしょう。しかし、現在見ることのできる遺構は戦国後期のものと言ってよく、台地続きに築かれた森山城とそん色ない造りをしています。両城の主郭どうしは、直線距離にして約1.3kmも離れており、この間は遺構がほとんどみられない平坦な台地でつながっています。須賀山城と森山城は同時代に使われていたとみてよいと思います。
それを裏づけるのが「原文書」(当館蔵)です。年未詳九月六日付「千葉胤富書状」には、森山城将である海上中務少輔と石毛大和守宛に胤富は「其地新繰輪江野平外記木村大膳亮可罷移候」と命じています。つまり、森山城の新しく造った繰輪(曲輪)に野平・木村両名を移らせなさい、と胤富は指示しているのです。
同じく年未詳九月二十三日付「千葉胤富判物」には、海上蔵人と石毛大和守に宛てて舟曳の割当を命じた内容が記されています。それには、須賀山城の曲輪である「西くるわ衆」・「大ろくてんくるわ衆」が載っています(外山信司「原文書に見る森山城」『千葉城郭研究』2号)。
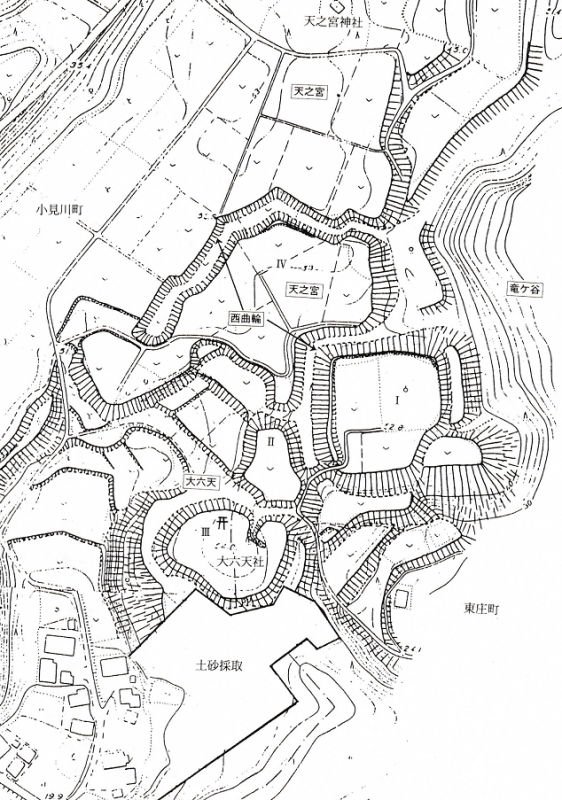 |
| 須賀山城跡概念図(外山信司氏作成) |
ところで、千葉氏の当主胤富は、以前、海上氏に養子として入り、森山城に在城していたことがありました。胤富が千葉氏の当主として呼び戻された後、森山城に城主は置かずに、城将が数名置かれていました。
胤富が宛先とした海上中務少輔と海上蔵人は、城将としての時代差があり、永禄8年(1565)に当たる「乙丑」の干支のある文書に中務少輔が宛てられています。同年と想定される文書にも同じく宛先としてあることから、中務少輔が森山城に在城していたのは、永禄年代(1558~1570)半ばと考えられます。
この頃、胤富が新しく森山城の曲輪を造らせた要因といえば、何と言っても永禄3年(1560)~9年(1566)にかけての里見氏の香取侵攻でしょう。つまり、須賀山城は、この時点で大改造をうけ、現在見ることのできる構造となったと考えられます(前掲外山論文)。
里見氏の香取侵攻は、永禄9年でいったんは収まりますが、天正3年(1575)には、香取市の国分氏の本城大崎城(矢作城)が攻められています。このように、里見氏の脅威は永禄年間以降も続いたわけです。さらに、国分氏による千葉氏への反乱(天正9年以前)や常陸南部の争乱があり、新たな須賀山城の曲輪には、「小門衆」・「西くるわ衆」・「大ろくてんくるわ衆」などとよばれる兵力が詰めていたと考えられます。
面白いことに、森山城の主郭を出たところに馬出**があり、須賀山城の主郭も同様に馬出状の曲輪(縄張図ではローマ数字で2と表記)があり、両城の共通性が感じられます。関東における馬出の分布と小田原北条氏との関係性が指摘されています。小田原北条氏の後ろ盾を得た森山原氏が城将として頭一つ抜け出すとともに、小田原北条氏の支配力が増したことが、両城に馬出が設けられた原因とされます(前掲外山論文)。
 |
| 2郭(馬出曲輪)より主郭虎口をみる |
また、Wikipediaでは、須賀山城の主郭を天之宮神社周辺としています(標柱もたっています)が、この場所は城外で、遺構はこれよりも南側に少し離れたところに展開しています。注意が必要です。
執筆にあたっては、外山信司氏の「原文書に見る森山城」(石橋一展編著『下総千葉氏』戎光祥出版 2015年;初出前掲)を参考にさせていただきました。縄張図も同論文より借用しました。本文中の写真は筆者撮影によるものです。
新補地頭…しんぽじとう。承久の乱後、多くの東国御家人が西国を中心に地頭職を得て入部した。支配をめぐって現地の農民らとの間で紛争が増え、そのため、幕府は新補率法という法を定めた。新規に入部した地頭にこれを適用(新補地頭)させた。これに対し、頼朝以来の従来の地頭を本補地頭とよぶ。
馬出…うまだし。城郭の出入り口(虎口:こぐち)の前面に設けられた、防御力を増すための空間。多くの場合、城郭本体とは堀で隔てられ、土橋や木橋で接続することによって、万一馬出を敵に乗っ取られても守りきれる工夫がされている。城外に面した側には、土塁が築かれることが多い。形状によって、角馬出と丸馬出などと呼び分けられる。県内の事例としては、他に本佐倉城の向根古谷郭(酒々井町)や土気城(千葉氏緑区)、津辺城(山武市)などが知られる。
14 千葉六党の城 相馬氏の守谷城 その一
今回は、千葉市だけでなく千葉県からも離れて、茨城県守谷市の守谷城を取り上げます。なぜ茨城県なのかは、以下の文章をお読みいただきたいと思います。
千葉常胤の二男師常は、相馬氏を名のったことで知られていますが、岡田清一氏により、相馬氏を称したのは文治2年(1186)6月以降、文治5年(1189)8月以前であるとされます(『相馬氏の成立と展開』戎光祥出版)。相馬の名のりは、相馬御厨(現在の我孫子市・柏市・野田市の一部と茨城県取手市、守谷市の一部)によるものですが、治承寿永の内乱の初期までは、故あって上総氏の一族常晴が相馬氏を名のっていました。
上総広常の誅殺によって、相馬御厨の支配権は常胤に戻り、二男師常が継承して「そうまの二郎」と呼ばれるようになりました。師常の屋敷の有力な候補地として、現在は消滅してしまった羽黒前遺跡(我孫子市新木)があげられています。発掘により、古墳時代から近世までの複合遺跡ということが判明しましたが、なかでも13~15世紀と目される方形居館跡が検出されました。古代の相馬郡家の正倉(倉庫)群に比定される日秀西遺跡(ひびりにしいせき)の東方1kmに位置します。羽黒前遺跡は郡家関連施設として使われ、中世の段階では千葉氏の居館として使われた可能性が高いと考えられています(以上、前掲岡田書)。
 |
|
小高城跡遠景(福島県南相馬市小高) 2006年3月撮影 同城に拠った相馬氏は、建武3年(1336)5月、南朝方に攻められ落城するも、後に奪い返した。その後、慶長11年(1606)に至るまで相馬氏の本拠となった。 |
奥州合戦の恩賞として、東海道大将軍を務めた常胤は奥州に新恩給与をうけ、二男師常は行方郡(南相馬市)を譲与されました。さらに、師常の子息義胤の代に高城保(宮城県松島町)を新恩給与されています。その後、相馬氏は奥州へ移った相馬氏と下総に残った相馬氏の二流に分かれます。
奥州相馬氏は、南北朝期に尊氏に従い北朝方として、南朝勢力の強かった奥州で小高城を落とされ、滅亡の危機に瀕しました。しかし、なんとか命脈を永らえ戦国大名、そして近世大名相馬中村藩6万石として続いていきました。
 |
|
小高城跡に祀られる小高神社(祭神天御中主命=妙見) 撮影日 同前 |
一方、下総相馬氏は史料が少なく、戦国後期に至るまでの動向があまり明確とは言えません。『本土寺過去帳』には、享徳の乱の最中、康正2年(1456)正月の「市河合戦」で「相馬盛屋殿妙盛」が討死にしたと記録されています。盛屋とは守谷(茨城県守谷市)のことで、この頃の相馬氏はおそらく守谷城に拠っていたと思われます。市川合戦に至る経緯は以下の通りです。
前年の康正元年(1455)8月に多古・島合戦(香取郡多古町)で滅びた千葉宗家胤直父子と行動をともにしていた胤直弟の賢胤は、ひと月後の9月に島の栗山川下流にあたる小堤(小堤城か:横芝光町)で自害しています。この時、子息実胤、自胤(よりたね)兄弟はここを抜け出し、市川城まで逃れます。翌2年正月、足利成氏は簗田氏・南氏らに命じ、市川城を攻めさせました。市川合戦では相馬氏のほか、胤直方であった曽谷氏・円城寺氏・武石氏も亡くなっています。こうしたことから、下総に残った相馬氏は上杉方であった胤直についていたとみられ、享徳の乱においては逼塞を余儀なくされたものと思われます。
また『本土寺過去帳』には、文亀3年(1503)8月に「相馬守谷殿」が没しているとされ、守谷には引き続き相馬氏が拠っていたとわかります。しかし、古河(茨城県古河市)に近い地理的環境から、古河公方の家臣化していったようです。大永5年(1525)と目される古河公方足利高基書状には「相守因幡守」と書かれており、相馬守谷氏が高基に「無二励忠信(無二に忠信を励)」んでいるとされます。永禄年間に入ると、関宿城に拠っていた古河公方足利義氏の重臣簗田氏の配下に組み込まれます。そして小田原北条氏(以下北条氏)と簗田氏の抗争に巻き込まれ、簗田氏から守谷城を明け渡すよう迫られました。
そして公方義氏の御座所として北条氏も入り整備をしますが、北条氏と簗田氏の和議が破れ、最終的には義氏の移座は実現しませんでした。現在みることのできる守谷城は、構造的に北条氏の手が入ったものとみてよいでしょう。
15 千葉六党の城 相馬氏の守谷城 その二
それでは、守谷城の縄張構造を見ていきましょう。地理的には、城跡は小貝川の右岸に接する旧守谷沼に突き出した舌状台地に位置します。周囲を沼沢地に囲まれた要害の地といえます。
また、近世大名の菅沼氏が相馬氏の滅亡後、一万石で入部しており、台地続きの守谷小学校の敷地となっている部分まで広く使っていました。今でも、小学校付近には土塁の残欠が見られます。もっとも、この部分は、公方義氏の御座所として永禄年間に整備されていた可能性もあります。
台地部分からは木橋で渡ったと思われますが、一番近い曲輪は馬出状の曲輪(「御馬屋台))で、城外に向かって土塁が築かれ、虎口部分に枡形*を持っています。この御馬屋台から主郭(「平台」;ひらのだい)に渡るために、さらに木橋が使われていたと思われます。主郭の虎口にも枡形が設けられ、厳重な防御が施されています。
現状では主郭の北側、南西側(馬出曲輪側)、南東側一部に土塁が回っていますが、本来は全周していたものと思われます。北側には台地下の船着き場へ降りるための道があります。
主郭は平成7年(1995)に発掘調査が行われ、倉庫とみられる建物跡9棟のほか、多くの遺物が見つかっています。守谷市中央公民館の郷土資料展示コーナーに、一部が出品されています。
主郭と北東方向に堀を挟んで隣接する馬出へは、土橋でつながります。この馬出は細長い独特の形をしています。おそらく北条氏の手によって、平台の北東側に土橋を残して堀を掘り、この形状に造り出されたと思われます。馬出の北側部分には、平台方向から土橋を渡る者に対して、横矢がかかる工夫がされています。このことは、この馬出より北に、優位な曲輪があることを意味しています。実際、沼に近い先端の曲輪を「一の曲輪(本丸)」とする図面も存在します。確かに守谷城跡のように、半島状の地形(舌状台地)に曲輪をいくつか造る場合、先端の曲輪が一番優位(主郭)であることが一般的です。
しかし、実見した限りでは、平台が主郭として相応しいと思っています。その理由は、平台の防御が先端の曲輪よりも勝っていること、また、平台の方が、10m以上標高が高いことです。先端の曲輪は、いざという時の舟での脱出も想定した、詰の曲輪的な役割を果たしていたのではないでしょうか。
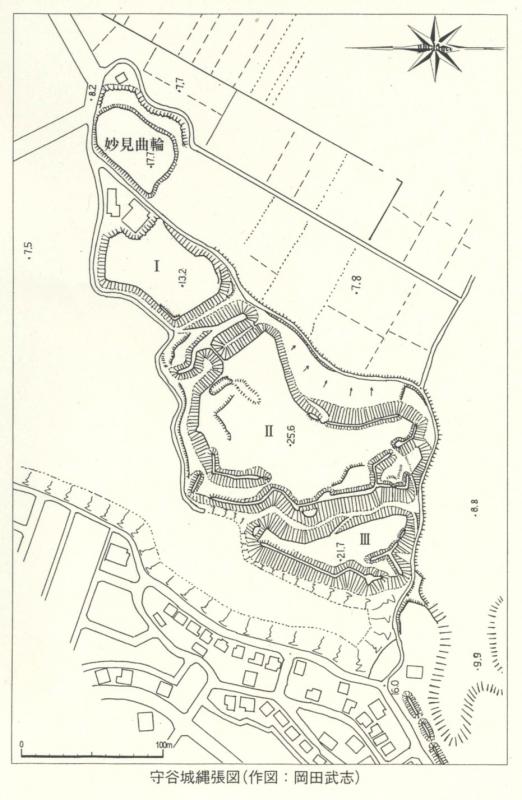
前回も触れたように、永禄年間になると北条氏と古河公方家臣の関宿城主簗田氏の対立のなかで、古河公方足利義氏の御座所として、相馬氏の守谷城が望まれることになりました。実際、北条氏の家臣が守谷城に入り、手が加わりました。縄張構造のうえでも、北条氏の関与が伺えます。しかし、簗田氏と北条氏の和議が破れてしまったため、守谷城はそのまま相馬氏が居続けたわけです。
こうして、元はと言えば千葉常胤の二男師常にルーツを有する相馬氏は、関東足利氏の奉公衆(直臣)として戦国の世の終焉を迎えました。また義氏も古河公方としての実質的な力は、北条氏によって奪われてしまい、氏姫という娘だけを残しました。
天正18年(1590)、北条氏が滅び、関東には徳川氏が江戸に入ります。秀吉は、側室にした島子(小弓公方足利義明の孫)の願いを入れ、島子の弟足利国朝と氏姫を結婚させ、名門足利氏の血統を残そうとしました。そして栃木県の喜連川(さくら市)に四千石を与えました。ところが国朝は文禄の役に従軍途中、病死してしまい、安房にいた弟頼氏が氏姫と再婚することになりました。
二人の間にできた義親以降、代々喜連川氏を名のり、四千石(のち五千石)ながら大名扱いされる特殊な家柄として、明治まで続きました。明治を迎えると、足利氏に戻し、現在も家として存続しています。
喜連川には相馬氏の墓石もあり、おそらく古河公方家臣としてこの地にやってきた相馬氏一族がいたものとみられます。
ちなみに江戸時代の文化14年(1817)、国学者の高田與清(ともきよ)という人物が、江戸を出て常陸南部から千葉方面に旅をした紀行文『相馬日記』を著しています。その中で、地元の人に守谷城を案内してもらった時の、大変興味深い記述がありますので、長文ですが最後にご紹介いたしましょう(出典:奈良女子大学学術情報センター所蔵資料電子画像集「相馬日記巻三」)。
まづ相馬小次郎師胤が城跡ありて今にから壕升形などのさまむかしのままに残れり。師胤ハ千葉介常胤が三郎子にて。その裔のひつぎ応仁年中までここの城主也といへり。後元和といふ年のころ土岐氏の君こゝにすまれしが、上野国沼田城へうつられてより此城遂にすたれぬとぞ。畠の中道を東へ廿町あまりゆけバ大壕曳橋などいふ所あり。平の臺といふところハいとたかき岡にて。こゝぞ将門がすみし所なる。まためくるめくばかりの深きほりきをわたりて 八幡廓にうつる。将門がいつきまつりし妙見・八幡とまうすがこゝに鎮座しを。今はこもり山の西林寺にうつしまゐらせたり。
今から二百年ほど前の守谷城の様子が、現地を見たことのある人であれば、手に取るようにわかる記述になっています。
縄張図は岡田武志氏の「守谷城縄張図」(茨城城郭研究会編『改訂版 図説茨城の城郭』)をお借りしました。また、「相馬日記」翻刻にあたっては外山信司氏のご助力をいただきました。
枡形…城の出入り口(虎口)などに設けられた、土塁などで区切られた小空間をいう。直接、敵を城内に入れることなく、枡形空間に留めることで城内からの攻撃を有効にできる。城内に造ったものを内枡形、虎口の外に造ったものを外枡形という。
 |
|
左手が御馬屋打台、右手が平の台(主郭) 両者を木橋で渡したか |
 |
| 平の台と馬出の間の堀切 「めくるめくほりき(り)」と表現された堀か |
16 立堀城跡(千葉市緑区平山町)
立堀城跡は、外房有料道路の出入り口近く、支川都川右岸の丘陵上に位置します。千葉市斎場のすぐ南側となります。
本城跡は、本コラムの3回目で紹介した平山城の支城と言われています。しかし、平山城の西方約900mに位置してはいますが、平山城とは水系が異なっています。立堀城よりも下流で支川都川と合流する、同川のさらに支流が平山城のある水系です。ですから、平山城への侵入路を抑えるという役割は薄いと思われます。
それでは本城跡の存在理由は、いったい何でしょうか。それは街道を抑えることにあると考えます。と言いますのは、本城跡は現在も県道66号線浜野四街道長沼線が、外房有料道路と交差する辺を睨む格好の位置にあるからです。
この県道66号線の一部(生実―千葉市若葉区中田町区間)は、おそらく中世まで遡れることは間違いないと考えます。先ほど述べた交差点を南へ上ると、大網街道(県道20号線千葉大網線)と交差します。土気・大網の東上総方面に抜けることができ、これは東京湾側と九十九里側とを最短で結ぶ重要な街道です。この交差点を「野田十字路」(バス停名は「野田十文字」)と言います。野田十文字の名称は古く、戦国時代まで遡る可能性があります。
野田十字路を浜野方面に進むと、生実城跡の大手に至ります。生実城跡の発掘により、この道が大手口と重なっていることから、中世に遡る道であることは間違いありません。それどころか、古代の官道と関係の深い「大道」の小字が大手口の鎌取寄り一帯に残ることから、古代の道の可能性も考えられます。
永正15年(1518)に下総高柳(埼玉県久喜市)から足利義明が「総州御進発」し、その後生実城に入部し小弓御所様(いわゆる「小弓公方」)と呼ばれるようになります。そして、兄の古河公方足利高基と関東足利氏の正嫡をかけた争いに発展していきます。高基側についていた本佐倉城の千葉氏は義明と対立しますが、千葉氏方の弥富原氏(佐倉市岩富)の朗典(実名不詳)は生実城を攻めるため、天文4年(1535)4月20日「小弓野田合戦」で「小弓ニテ」討死しました(『教蔵寺過去帳』、なお『本土寺過去帳』では6月20日)。第一次国府台合戦で義明が敗死する三年ほど前の出来事です。
弥富原氏はどのような経路で生実へ行こうとしたのでしょうか。立堀城跡との関係もあるので、些末な説明になりますが、みていきたいと思います。まず弥富原氏の居城岩富城のある佐倉市岩富から、鹿島川沿いに南下します。千葉市若葉区中田町で支流平川が鹿島川に合流するところから、今度は平川沿いに南下します。千葉市内へ流れこむ都川と平川とが一番接近する地点(分水帯)-千葉市若葉区中田町の宮田交差点付近-から、分水帯を越えて県道66号線浜野四街道長沼線に入ります。これは旧東金街道で、間もなく都川を渡った後、若葉区川井町・佐和町を通過し、旧東金街道から別れ生実方面に進みます。そのまま進み平山町の台地を下って、支川都川を渡り、再び台地を上がると野田十文字に達します。旧東金街道方面から来てこの台地を下る道を、ちょうど見下ろす位置に立堀城跡が造られているのです。構造面からみても、崖際の南側土塁に物見台状の張り出しが造られており、道の監視をしやすくしています。
 |
| 縄張図 簗瀬裕一氏作成(『千葉市の戦国時代城館跡』より) |
このように考えると、本城跡が使用された時代として、第一に永正15年から天文7年(1538)にかけての足利義明と千葉氏・原氏の対立していた頃が、浮かびあがります。実際、『本土寺過去帳』によりますと、弥富原氏の孫九郎郎久は永正14年(1517)5月15日に「ヤトミニテ」討死しています。岩富の地元の寺院の過去帳では、「坂戸押合ニテ」永正16年(1519)6月15日に討死したと記されています(『教蔵寺過去帳』、『長福寺過去帳』)。「坂戸押合」とは、岩富城の鹿島川をはさんだ対岸で、先に述べた生実城から野田十文字を経て、平山町の台地を上って旧東金街道から、平川沿いに岩富に向かう道を進むと坂戸に至ります。つまり、小弓公方勢が本佐倉城の千葉氏を攻撃するためには、岩富城の対岸の坂戸を通過せねばならないのです。朗久の討死した年は、義明が総州へ入った永正15年の後と考えるべきで、地名・年紀とも地元資料の方の蓋然性は高いと考えます。
第二に、里見氏が生実城を攻めるようになる16世紀中ごろ以降、生実と本佐倉・臼井方面とを結ぶ、この街道の重要性が増した時点があげられると思います。実際、原氏は生実城を里見氏に度々攻撃され、臼井に本拠を移しています。ちなみに生実-四街道-臼井-印西を結ぶ街道沿いには、立堀城のように土塁に突起部を持つ小型城郭が点在します。そして、県内でこうした城郭が十数例ある中で、ほとんどは陸上交通と関係していることがわかります(拙稿「戦国後期の陸上交通と城郭」『城郭と中世の東国』千葉城郭研究会編 高志書院 2005年)。
以上のように、平山城の支城として評価されてきた立堀城は、むしろ平山城の使われていた15世紀後半より後に、戦国後期まで交通路を抑える城として存在した可能性を考えてみました。
縄張図は、当館『千葉市の戦国時代城館跡』2009年 所収の簗瀬裕一氏作成のものをお借りしました。また、岩富原氏に関する記述は、外山信司・遠山成一「岩富原氏の研究」(石橋一展編著『下総千葉氏』戎光祥出版 2015年;初出1986年)を参照しました。
17 猪鼻城跡(千葉市中央区亥鼻)
今、大河ドラマで千葉県内に知られるようになった千葉常胤ですが、いったいどこに住んでいたのでしょうか。千葉氏の屋敷は『吾妻鏡』によりますと、「常胤が門前に至りて案内するのところ、幾程を経ず、客亭に招請す。(中略)常胤、門客等を相率して、御迎へのために参向すべきの由、これを申す。」と記されています。つまり、常胤の屋敷には門や客亭があり、さらに幾人かの食客(門客)を置くだけの広さがあった、と考えられます。そして、常胤が千葉にいたことは、同じく「盛長(安達)、千葉より帰参して申して云はく」(治承4年9月9日条)と書かれていることから確かといえます。
それでは、千葉のどこにいたのでしょうか。これまで当館の建つ亥鼻の高台(いわゆる千葉城)に常胤の屋敷があったと、一般には流布されてきました。しかし、ここ三十年くらい前から、千葉氏の屋敷は沖積低地(現在の千葉市の中心街、千葉市中央区)のどこかにあったと考えられるようになってきました。
その有力候補地の一つが、千葉地方裁判所のある一画です(簗瀬裕一「千葉城跡概説―千葉氏居城の基礎的考察―」『千葉いまむかし』11号 1998年;のちに石橋一展編著『下総千葉氏』2015年 戎光祥出版 に再録)。
平安時代末から鎌倉時代初期にかけての武士の屋敷は、沖積低地や丘陵の端を掘りこんで造りだした平場に構えられることが多かったのです。
「千葉城」という文言が初めて登場するのは、建武2年(1335)の千田胤貞・相馬親胤による千葉攻めの時で(「吉良貞家披露状写」『相馬文書』)、別の文書によると同じ攻撃対象を「千葉楯」と記しています(「相馬松鶴丸著到軍忠状写」『相馬文書』)。この「千葉城(千葉楯)」とは、どこにあったのでしょうか。
南北朝初期の合戦では、「要害」、「城」、「館」、「楯」の用語が文書中に多く現れます。城・館・楯とは、おそらく低地の屋敷を城構えにした程度、つまり楯を置いたりして防御を強めたものだったと思われます。この頃、文書に「堀内構城郭」とか「屋形構城郭」などと登場します。堀内(ほりのうち)あるいは屋形とよばれた屋敷地を城郭構えにしたことを意味します。南北朝の内乱期に合戦が恒常化するなかで、屋敷を城構えにする、あるいは天険の地に籠って城と称するようになったのです。千葉市街地では、天険の地と呼べる所はありませんので、屋敷を城構えにしたのかもしれません。
千葉城における千田胤貞・相馬親胤連合軍と千葉貞胤の戦いは、足利尊氏の上洛があり、北朝方の胤貞らはこれについていったため、結局、決着がつかず中途で終わってしまいました。
この後、千葉城が歴史の舞台に上ってくるのは、享徳の乱のはじめの頃です。享徳4年(1455)3月、千葉宗家の胤直を、叔父馬加康胤と原胤房らが千葉城に襲って、千田庄(多古町)に逃亡させたことでした。この時の千葉城がどこを指すのか、大変悩ましい問題です。
といいますのは、最近の研究では15世紀後半頃から、武士は城を恒常的に維持するようになったとされます(齋藤慎一「武士の本拠」『中世の城と考古学』石井進・萩原三雄編 新人物往来社 1991年)。馬加康胤が襲った千葉城は、亥鼻(猪鼻)の高台に築かれた城であったのでしょうか。結論から言うと、そうではなく、南北朝期にあった千葉城合戦で使われたような、低地にある屋敷を城構えしたものであったと思われます。
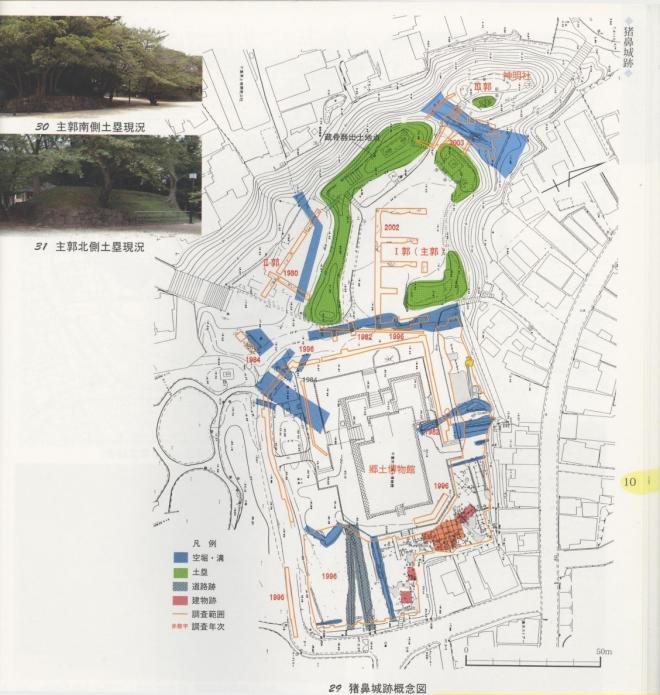 |
その理由として、過去に行われた猪鼻城の発掘(1980年度より六次)から、1.主郭にあたる場所(当館の北西部、土塁に囲まれた区画)からは建物址が検出されていない、2.当館の建物の東側の一段低い部分(現駐車場)からは14世紀から15世紀中頃の建物址(礎石建物も)が検出されたが、城に関わるものか不明、3.千葉氏の宗家に相応しい陶磁器類の出土が少ないことなどがあげられています(『千葉市の戦国時代城館跡』千葉市立郷土博物館、前掲「千葉城概説」)。猪鼻城が歴史の舞台に登場するのは、永正年間(1504~21)になってからです。『千学集抜粋』によれば、永正13年(1516)に妙見座主範覚が「井鼻」を取り立てた、とあります。北斗山金剛授寺尊光院の首席僧侶である範覚は、原胤隆の子息でした。この年の8月23日、三上但馬守が二千騎で押し寄せて、亥鼻城を落とした、とされます。この時の戦闘で、弥富原氏の朗寿、東六郎ほかが討死しています(『本土寺過去帳』廿三日条)。
三上氏は近江佐々木氏の一族で、南北朝期に佐々木氏が上総国守護になった時から、上総に入ってきた可能性があります。三上氏は、当時、真里谷武田氏や原氏・千葉氏と対立していました。真里谷武田氏は、真名城(茂原市真名)を本城とした三上氏を追い落とすために、永正14年(1517)、伊勢宗瑞(北条早雲)の力を借りて真名城を落城させました。
このように戦国時代に入ると、本佐倉へ本拠を移した千葉氏に代わって、小弓の原氏が猪鼻城を取り立てたと思われます。しかし、直後の永正14年には、原氏の小弓城は真里谷武田氏によっておとされてしまいます。その後、小弓城には古河公方足利政氏の子にして足利高基の弟である足利義明が入り、小弓御所様(小弓公方)と呼ばれ房総の多くの武将を膝下においていました。そして高基とその跡を継いだ晴氏と対立を続けます。
しかし、その義明も天文7年(1538)に国府台合戦で敗死し、小弓城は再び原氏が入部することになります。亥鼻城も再び原氏の持ち城になったものと考えられます。
猪鼻城は、陸上交通の観点からみると、東上総への道(東金街道そして土気街道)が膝下を通っています。東金酒井氏と土気酒井氏の本拠へと通ずる道です。原氏は時に敵対することもありましたが、酒井氏とは密な関係にありました。
また、江戸と房州をむすぶ街道(近世の房州往還)も千葉の街中を通っており、陸上交通を抑えるには好都合でした。
一方、鎌倉時代には武総内海(東京湾)の要津の一つであった千葉湊と、そこに注ぐ都川も猪鼻城の間近にあり、水運にも恵まれていました。なお、戦国時代後期ともなると、蘇我や浜野の方が港湾としては多く利用されていたようです。
最後に、鎌倉時代から室町時代にかけての千葉氏の本拠となった屋敷はどこにあったのでしょうか。残念ながら、発掘に拠らないとはっきりとしたことはいえません。市街地化の進んだ街中ですが、もしかしたら千葉氏の屋敷の遺構が破壊されずに、どこかに眠っているかもしれません。なお、この点に関しては、本年3月に当館より刊行されました『千葉いまむかし』所収の、西野雅人氏の「都川河口砂州の発掘調査について」において、氏により貴重な提言がなされています。この提言が生かされ、近い将来、発掘により千葉氏の屋敷が姿を現してくれることを願ってやみません。
文中の概念図は、『千葉市の戦国時代城館跡』の簗瀬裕一氏によるものを使用させていただきました。
18 城山城跡(千葉市若葉区大宮町)
市内大宮町にある城山城は、小字名の「城山」からつけられたと思われますが、城山を固有地名として城名にするのは、少し抵抗があります。せめて大字名を入れて「○○城山城跡」ならばわかるのですが。ある市では、大字が「城」のため、そこにある城跡を「城城跡」と呼びならわしている例があります。閑話休題。
さて、大宮町にある城山城跡は、千葉東金有料道路が城跡の北東面すぐ脇を通っていて、反対方向の南西側は支川都川が造りだした低地に面しています。川を挟んだ向かい側には、仁戸名坂上で土気往還から分かれた旧東金街道が通り、この道は支川都川を城山城跡の南東200mほどのところで渡り、大宮町の台地上へと上っていきます。この立地こそが城山城の取立てられた理由と考えられます。
城跡の有料道路をはさんだ東方200mほどの所には、古くは北斗山金剛授寺と称した栄福寺があります。この山号寺号は、千葉神社の前身北斗山金剛授寺と全く同一です。栄福寺には、享禄元年(1528)に詞書が、天文19年(1550)に絵と詞書の二巻の絵巻物として成立した、『紙本著色千葉妙見大縁起絵巻』(非公開)が伝来しています。また、天正4年に臼井城内の妙見堂に納めるため、原胤栄の願いにより制作された「木造妙見菩薩立像」(非公開)と、同2年、原胤栄により臼井城内の妙見堂に吊るすために作られた「金透彫六角釣灯籠」が、同寺に所蔵されてきました。
享徳の乱の初期に、千葉宗家が千田庄で滅び、馬加系千葉氏が宗家を襲った時に、平山城(千葉市緑区平山町)に本拠を構え、のちに長峰(栄福寺とその北西域一帯)に移ったとされます(『千学集抜粋』)。さらに文明年間に、本佐倉城を築いて本拠を移します。この城山城跡が、この時の千葉氏の本拠に取り立てられた長峰の城でしょうか。私は、その可能性は低いと考えます。理由として、まず本城の縄張構造があげられます。
城山城は平山城と比べても平坦面が狭く、千葉氏が一時的とはいえ本城としたとは思えません。さらに特徴的なことに、支川都川を見下ろす櫓台状の高まりが、城の南西端に設けられている点です。これは明らかに旧東金街道を監視するため、と考えられます。縄張面からは、本城の役割は街道監視にあると言えます。強いて言うならば、東金酒井氏と原氏が敵対関係にあった時期に、原氏が抱えていた城ではなかろうかと考えます。ここを突破されると、原氏のいた亥鼻城に攻め込まれてしまうからです。あるいは、里見勢が小弓をなんどか攻略しており、里見軍の本佐倉城への侵攻を食い止める役割を負っていたかもしれません。
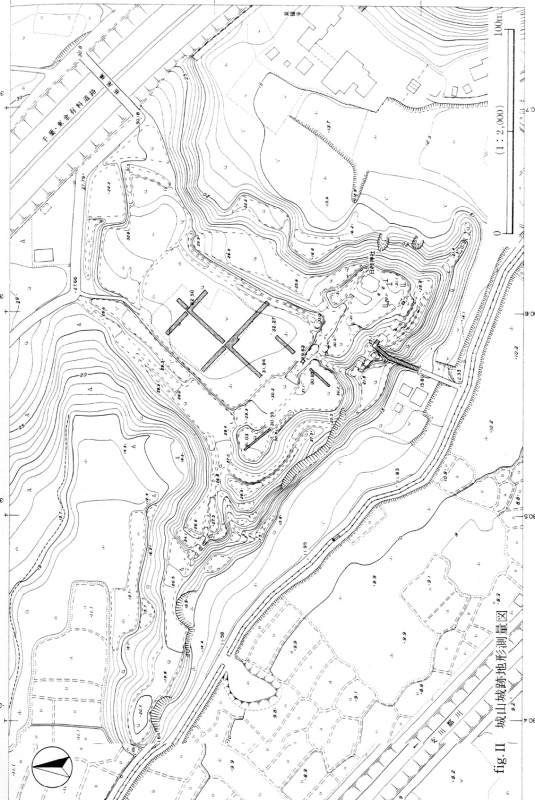
有料道路をはさんだ北には「宿」地名があり、これをもって城下集落ととらえる考えもあるでしょう。しかし、この宿は栄福寺に向かう街道にともなうもので、城下集落とみることには、私は否定的な考えを持っています。
この街道は旧東金街道から分かれ、栄福寺門前から直角に折れて旧長峰の中心部を経て、加曾利の国道126号線(東金街道)に合流します。宿は長峰の中心部からやや離れた栄福寺寄りに位置しているので、門前の宿と考えることができるかもしれません。同様な例は、多古町南玉造の蓮華寺の門前宿と大網白里市小西の正法寺前の宿があります。
また、少し古くなりますが、15世紀初頭には原氏が長峰に所領を持っていたことが記録されており(「香取造営料足納帳」)、長峰と原氏のつながりが窺えます。
城山城跡は、このように原氏と関連の深い栄福寺と長峰にあることから、戦国時代後期に、原氏の抱えた城であったと考えられます。
測量図は『千葉県中近世城館跡研究調査報告書 第9集 城山城跡・東金城跡』(千葉県教育振興財団文化財センター 1989年)掲載のものを使用させていただきました。
19 生実城跡(千葉市中央区生実町) その1
当館では、本年10月18日から12月11日まで、特別展「我、関東の将軍にならん ―小弓公方足利義明と戦国期の千葉氏―」を開催いたします。そこでは、義明のいた小弓城について触れますので、今回は生実地区の城跡をとりあげたいと思います。
生実地区には、ふたつの「おゆみ城」があることはよく知られています。千葉市中央区生実町にある生実城(北生実城)と、同区南生実町にある南小弓城の二か城です。両者は、ほぼ南北に1.3kmほど離れて存在しています。もっとも北生実城の方は、ほとんど遺構を残しておらず、生実神社境内地にわずかに堀跡と土塁の痕跡を見るにすぎません。
両城の関係は、21世紀を迎える頃までは、南小弓城が古く北生実城の方が新しい城とされてきました。というのは、次のような通説があったからです。それは永正14年(1517)に真里谷武田氏と足利義明が南小弓城を攻め落とし、城主原氏を追い出して、義明が代わりに入部して小弓公方となった、というものでした。そして、天文7年(1538)の第一次国府台合戦で義明が敗死し、原氏が生実に戻ると、原氏は新たに北生実城を築きあげたとされました。しかし、後述のように、その後の研究の進展と北生実城跡の発掘により、これらは否定されることになります。
ここでは生実城(北生実城)を紹介しましょう。残念なことに、主郭を含む主要部分は1970年代初期に団地造成により、破壊されてしまいました。実測図は残りましたが、発掘は行われませんでした。今となっては痛恨の極みです。その後、幸か不幸か、北生実城の一画を計画道路が貫通することになり、1988年から1996年にかけて5次にわたる発掘調査が行われました(『千葉市生実城跡』千葉市教育委員会他 2002年)。筆者も、発掘現場を見学させてもらったことがありました。この発掘により、遺構や遺物が明らかにされ、新しい事実が判明したのです。
すなわち、北生実城からは天文7年以前の遺物が多く発見され、天文年間以前より城として使われていたことです。そして、義明と関連すると思われる享禄4年(1531)銘の庚申待武蔵板碑が井戸の足場として転用されていることがわかり、義明のいた小弓城とは、この北生実城であるとされたのです。さらに、文献面での調査により、簗瀬裕一氏は中村国香著『金ケさく紀行』の一節(「重俊院の僧の語りしは『寺を去ること東へ数歩にして、小弓御所義明の舘趾あり』」)を見出し、義明がいたのは北生実城主郭近辺であることを補強されたのです。
 |
| 写真は生実神社脇の堀跡と土塁 2020年撮影 |
こうして、現在では北生実城こそが小弓公方義明にいた城である、と変わりました。そうなると、南小弓城はいつ造られたのだろうか、という問題になります。これは、残念ながら即答はできません。やはり発掘により確認するしかありません。
ただ言えることは、戦国時代後期に里見氏の攻勢が強まり、生実地区が里見勢によって占拠されることがありました。南小弓城は、村田川をはさんで里見氏勢力下にあった西上総方面と直接対峙しています。南小弓城の役割は、一つには里見氏の侵攻に対する防御にあったと思われます。
さて、北生実城は近世に入っても森川藩陣屋が一画に置かれ、明治に至るまで使用されてきました。発掘でも近世の遺物が多く出土しています。また大手跡(発掘により一部判明)では県内でも稀な丸馬出が検出されたほか、8.郭東端では畝堀が用いられていることがわかりました。これらは、戦国末期から近世初めの遺構かと思われます。
では、北生実城はいつから使われ始めたのでしょうか。その始期は、原越後入道道喜(胤房)が文明3年(1471)9月9日に「小弓館ニテ打死」しており(『本土寺過去帳』)、遺物面からもこの頃が北生実城の始まりとして整合性があるとされます(ただし、それ以前の遺物もある程度出土しているそうです)。
20 生実城跡(千葉市中央区生実町) その2
永正6年(1509)10月に、連歌師の柴屋軒宗長は原宮内少輔胤隆の小弓館を訪れ、千葉の街で妙見宮の祭礼や300頭の早馬を楽しんでいます(『東路のつと』)。彼は胤隆の館で連歌を興行し、館からみる絶景について記述しています。この胤隆の館こそ北生実城ではないかとされます。
それから10年もたたない永正14年(1517)10月には、真里谷武田氏の侵攻で小弓城(北生実城)は落とされ、城主原二郎が討たれたとされます(『快元僧都記』)。胤隆は天文5年(1536)まで生存しています(『本土寺過去帳』)ので、原二郎は別の人物を指すものと思われます。
そして翌永正15年7月に「雪下殿様(義明)総州御進発」(「不動寿丸書状」『鑁阿寺文書』)となりました。つまり、義明が高柳(埼玉県久喜市)から総州(上総・下総)へ移ったのは永正15年のことで、永正14年の小弓城攻めには、義明は参加していなかったことがわかりました。
ところで、この義明の「総州御進発」が、即、義明の北生実城入部を意味するものかは、悩ましいものがあります。というのも、市原市八幡宿に「小弓に入る前に、義明は八幡御所を構えていた」という伝承があるからです。年代的には矛盾しますが、義明は初め飯香岡八幡宮の別当寺霊応寺に入り、その後、八幡に御所を構え、小弓原氏を滅ぼしてから小弓城に移り、小弓公方となったというものです。
飯香岡八幡宮には、義明と兄高基のために家臣が奉納した六百巻の「大般若波羅密多経」も残されており、また伝八幡御所や伝義明夫妻の墓もあって、なんらかの義明とのつながりを物語るように思います。小弓城に入る前に、八幡にいた可能性、もしくは小弓と八幡の両所にいた可能性も考えてみてもよいのではないでしょうか。
北生実城は、主郭(字本城)の北側に字ネコヤがあります。ネコヤ、すなわち根小屋は、16世紀初頭の永正年間には当時の文書史料に登場しています。城の根(台地や山の麓)に造られた家臣団の小屋を指します。東日本に偏って地名が残り、一種の方言と考えられています。千葉県は根小屋地名(屋号も含む)が管見の限り64か所あり、全国でもっとも多く残ります。
生実池の北東にあたる花輪町・赤井町方面から流れ込む小河川の造った低地より、一段高い段丘面(千葉面;標高7mほど)に根小屋が形成され、標高17mほどの台地上に主郭など城本体が展開していました。現在は、主郭部は大きく削平され宅地と公園になって、まったく往時の面影はありません。
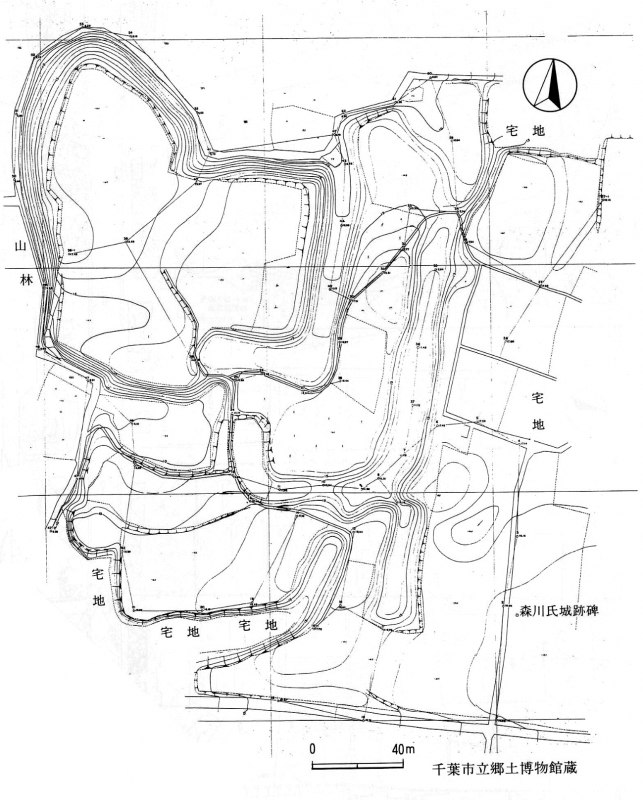
以下、生実城跡概念図にもとづいて縄張構造をみると、主郭から2.郭へは馬出状の小曲輪を経て土橋で接続された可能性が指摘されています。さら2.郭から3.郭へも、通称妙見山の馬出を経て土橋でつながっています。3.郭から通称天神山の曲輪(4.郭)も土橋で渡り、5.郭自体が馬出状となっていて6.郭となる字旧邸(近世の森川藩陣屋跡)へと続きます。このように馬出を連続させる技法は、県内ではあまり類例をみないものといえます。もっともこれは戦国末期の姿であって、義明の小弓御所の時代のものとはいえませんが、里見氏と対峙していた戦国末期に、高度に発達した構造をみせています。それでも、里見氏によって落城させられています。
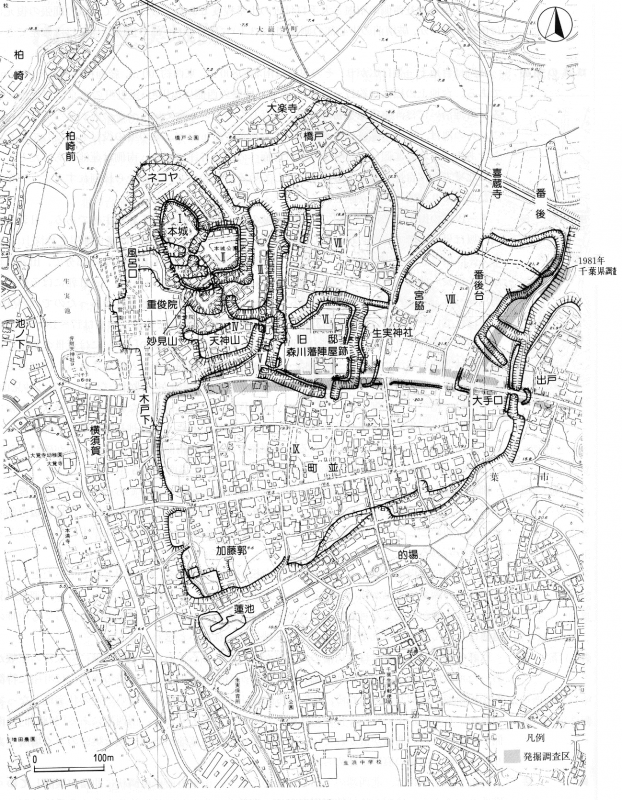
最後に、発掘で明らかになった戦国時代の残酷な現実について、記しておきましょう。それは、生実神社のすぐ南側地区の発掘により、地下式坑(地面に竪穴を掘りさらに横へ掘り進めて直方体空間を作ったもの)で二体の人骨が発見されたことです。二体とも老女で、年齢の割には歯の減り具合は少なく、高貴な身分であったと推測されています。この二体の頭骨には、刀による漸創があり、ほぼ即死であったとされます。非戦闘員である老女が、このような凄惨な死に方をしたというのは、落城による混乱のなかで起きたものと考えられます。
北生実城は、永正14年(1517)10月に真里谷武田氏により城主原氏の時に落城したほか、天文7年(1538)10月、第一次国府台合戦で義明が敗死した後の落城、さらに元亀元年(1570)に里見氏による落城が記録されています。これらのどの時期にあたるかは何とも言えません。よく落城にともない、城内にいた足弱、こどもまでなで斬りにしたという話を聞きますが、身近なところで戦国の凄惨な現実を見せつけられた気がしました。
生実城跡実測図、生実城跡概念図ともに『千葉県の歴史 資料編 中世1(考古資料)』千葉県 2009年 から借用しました。
21 南小弓城跡(千葉市中央区南生実町) その1
戦国時代後半になると生実地域は、真里谷武田氏領を侵食して上総に勢力を伸ばした安房里見氏が、下総を窺うようになりました。弘治元年(1555)10月、里見氏配下の正木時茂が千葉に侵攻し「宿中に放火」したとされます(『千学集抜粋』)。また永禄3年(1560)12月には、同じく時茂は小弓城の原胤貞と戦っています(「太田資正宛長尾景虎書状」『上杉文書』)。
永禄12年(1569)2月には、里見勢は松戸・市川まで出張り、帰路臼井筋の郷村に放火したうえで、椎津(市原市)へ着いた、と千葉胤富は書状に記しています(「豊前山城守宛千葉胤富書状」『間宮家文書』)。これは臼井―船橋―(海路)―椎津という経路を通ったと考えられ、東京湾の要津の一つ椎津湊(椎津城)は里見方が押さえていことを意味しています。
その翌年、元亀元年6月2日の日付で、胤富は上総大台(芝山町)城主井田平三郎に宛てて、次のように急を知らせています。長文になりますが、意訳してみます(元亀元年6月2日付井田平三郎宛「千葉胤富書状」〔井田文書〕)。
「このたび里見勢が久保田(袖ケ浦市)に、城を築こうとしている。完成すれば下総の西筋は里見勢の思い通りになってしまうので、完成する前に対策を講ずるべきであったが、遅々として進まなかった。ようやく一両日のうちに行動に移せるとのこと、いたしかたない。それなのに、里見勢はまた生実近辺に付城を築くための準備をしているので、久保田の普請が完成しだい、翌日には生実の普請に取り掛かるであろう。もしそうなったら、久保田一か所でも下総は手詰まりなのに、いわんや両城が完成してしまったら、西筋どころか下総の過半を里見方が手に入れる目前となってしまう。普請が未完成の内に、すぐに乗り込んで決着をつけるべきである。昨日、(生実城主の)原胤栄が牛尾胤仲を使者として申し上げたが、北条氏政にも加勢を望んだところである。久保田と生実(の付城)の両方が出来てしまうようであれば、いかんともしがたい。急ぎ行動に移すべき時は、まさに今なので、この5日には、軍勢を引き連れて当地近辺に必ず着陣するように。(後略)」
「付城」…敵の城を攻めるために、敵城近辺に攻撃拠点として築く城のこと。陣城、向城ともいう。
この「当地」を久保田・生実のどちらととるか判断が難しいですが、生実城主の胤栄が牛尾胤仲を使者にたてて氏政に申し述べていることから考えると、生実とみるべきかもしれません。実際は、この年の8月21日に、原氏の拠る小弓城(北生実城と南小弓城の両城と考えられます)は北条氏の加勢を得られず里見氏によって落とされてしまいました。そのため、原氏は臼井へ本拠を移すことになります。ここで問題となるのは、里見氏が「生実近辺」に「地利を見立て」たという、その場所です。
上総方面から里見勢が進軍すると、村田川を渡って椎名崎町周辺の台地上が候補の一つになろうかと思われます。この時、南小弓城がその前面に立ちはだかることになります。以前は、北生実城跡に比べ古い形態と考えられていた南小弓城跡は、今では、折の入った堀・土塁などの縄張構造からみても決して古くはなく、戦国後期の構造と考えられています。時期的には、この頃、本城があってもおかしくないわけです。
この南小弓城跡と大百池(おおどいけ)をはさんだ緑区おゆみ野中央2丁目に「大百池公園」があります。ここは「城の台」と呼ばれています。おゆみ野の開発にともない、公園造成のための事前発掘が行われました。その結果、柵列などは検出されましたが、ほとんど遺物はなく、土塁や虎口の遺構が確認されました。このことから、恒常的には使用されなかった中世城郭遺構という判断が下っています(『千葉東南部ニュータウン34-千葉市城ノ台遺跡-』千葉県教育振興財団 2006年)。
胤富の井田氏に宛てた文書でいう「生実近辺ニ敵地形見掛候」の「生実近辺」とは、すでに先学の指摘にもありますが、この城ノ台のことではないでしょうか。南小弓城跡とは大百池をはさんだ200mの至近距離ですので、疑問をもつ方もいらっしゃるようですが、胤富の他の文書には「てきまちかにとり出いたし候」(年月日不詳「平川後室宛千葉胤富書状写」〔豊前氏古文書抄〕)とあります。これを「敵、真近に砦いたし候」と読むことができれば、「とり出」を城ノ台ととれるのではないでしょうか。発掘の結果も、遺物もほとんどなく、柵列、腰曲輪、台地基部側の土塁と虎口など、付城の特徴を示していると思います。
このように、南小弓城は戦国後期に北上する里見氏勢力に対し、北生実城とセットで、最前線の城として機能していたことがうかがえます。
さて、この後、南小弓城と北生実城はどうなっていくのでしょうか。つづきは「南小弓城跡 その三」で述べたいと思います。
以下に掲げる南小弓城跡の縄張図は、『千葉市の戦国時代城館跡』(千葉市立郷土博物館 2009年)掲載のものを使用しました。「城ノ台」は図の右端中央部にわずかに顔をのぞかせています。
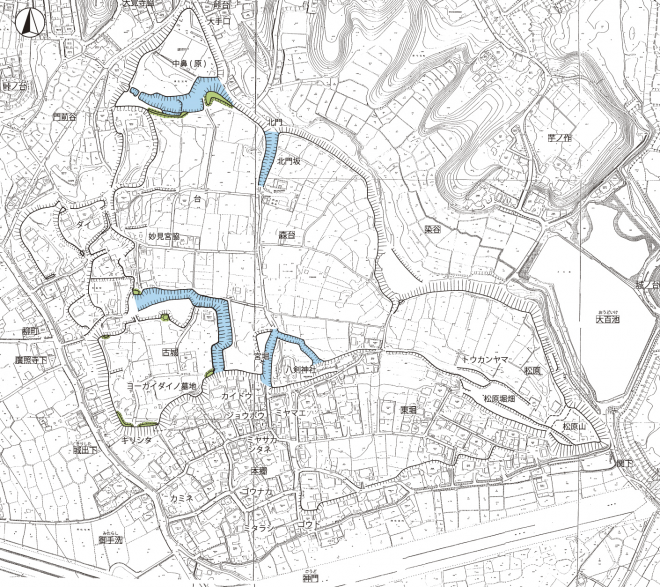
22 南小弓城跡(千葉市中央区南生実町) その2
南小弓城と北生実城ともに、里見氏によって落されてから一年余り後、元亀2年(1571)9月2日付で浜村(中央区浜野町)の本行寺に宛てて、北条家の禁制が出されています。つまり、両城の奪還のために北条氏政が直々に出馬したとみられます。これには千葉胤富も配下の森山衆(香取市岡飯田の森山城を中心とした家臣団)を動員するなど(元亀2年ヵ8月28日付「千葉胤富書状」〔原文書〕)、総力をあげて対応しています。その結果、一時、原氏は生実城を取り戻したようですが、間もなく北条氏が引き上げると、再び里見氏の手に落ちた模様です(元亀2年ヵ9月8日付里見義頼宛「里見正五義堯書状」〔延命寺文書〕ほか)。「敵退散、我々満足同前可思食候」と述べています。
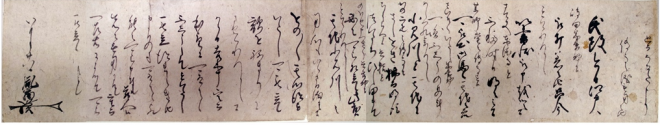 |
| 写真は「千葉胤富書状」(当館蔵) これによると、胤富は「氏政が今日(元亀2年8月28日)に江戸城へ着いたと、今書状が届いた。すぐに出馬するので、明後日の一日には全員引き払って菱田(芝山町)まで出てくるように…」と、森山衆に命令しています。 |
同年9月17日には市川の「府中六所宮」に宛てて里見家制札(須和田神社文書)が出されており、生実を拠点に、胤富の心配していた通り下総「西筋」まで里見の軍勢が席巻しています。また、『先学集抜粋』によれば、「一、元亀二年辛未十一月望、佐倉妙見宮にて邦胤御元服なされける、是ハ房州里見義弘小弓にありて、佐倉と御戦かりけるゆゑ、千葉へはまゐり給ハさる也、」とあり、この年の年末近くまでは里見氏の勢力が小弓・千葉周辺を支配していたようです。
こうした小弓をめぐる千葉氏・原氏と里見氏の抗争は、天正5年(1577)に里見義弘が北条氏政に屈服し和睦するまで続いたと思われます。一方、東上総から東下総方面では、元亀3年(1572)12月に正木憲時が里見氏の意向を奉じて、千田庄の峯妙興寺(多古町南中)に禁制を発給しています。また、天正3年(1575)正月と4月、小田喜正木憲時は千田庄を通過する経路を使い、国分氏の本拠矢作城(大崎城:香取市大崎)を攻撃しています。
しかし、天正2年閏10月に、北条氏政はようやく簗田氏の関宿城を落とすと、翌年より上総の里見氏勢力に猛攻撃をしかけます。そのため天正4年中には、里見氏の配下にいた土気・東金両酒井氏は北条方に下りました。翌5年には、前述のように里見義弘が北条氏政に屈服することになります。
これで、ようやく小弓の原氏による支配が回復されることになりました。以上、みてきたように、小弓地域は千葉氏・原氏と里見氏の取りあいが長い間続きました。南小弓城は、こうした背景のなかで造られていったものと思われます。
では、なぜ小弓がこれほどまでの取りあいとなったのでしょうか。これは足利義明が小弓に御所を設け、「小弓上様」などと呼ばれたことと同じ理由によると思われます。一言でいうと「小弓は水陸交通の要衝にあった」ということです。生実城の外港ともいうべき浜野の湊があり、浜野城が置かれていました。同時にこの地は、後の房総往還とよばれる内房沿岸の街道が通り、浜野―茂原を結ぶ茂原街道、浜野―小弓を経て東上総(土気・東金)へ至る大網街道・東金街道、さらには東金街道から分かれて佐倉・臼井方面に向かう道などのある、陸上交通では扇の要的な位置を占めています。
このように小弓地域は、政治的・軍事的にも経済的にも重要な地点といえます。ここに二つの大きな城が造られたのも、こうした地理的・歴史的背景があったからと考えられます。
いよいよ来る10月18日の火曜日から、本館令和4年度特別展「我、関東の将軍にならん-小弓公方足利義明と戦国期の千葉氏-」(入館料無料)が始まります。小弓公方足利義明と北生実城跡・南小弓城跡の関係をはじめ、小弓・浜野地区に関する展示もありますので、ぜひご観覧くださいませ。図録も販売いたします。
皆様のお越しをお待ち申しております。
23 土気城跡 (千葉市緑区土気町) その1
千葉市の東端、緑区土気町には、今も遺構をよく遺す土気城跡があります。主郭部にはかつての日本航空の研修所の建物が建ち、今は高齢者施設となっています。そのため、主郭部には無断で立ち入ることができません。しかし、施設外部には堀や土塁などよく遺っており、一見の価値があります。
土気城は、酒井氏によって15世紀後半に取立てられたとされます。酒井氏は、酒井定隆が初代で土気城に入り、妙満寺派日蓮宗(現顕本法華宗)を領内に広め、いわゆる「上総七里法華」を実現させたとされます。そして、のちに東金へも分派し、戦国時代を通じて東金酒井氏は土気酒井氏とともに、東上総の国衆として、北条氏と里見氏の間で離反を繰り返しました。
しかし、近年、酒井氏に関する研究も進んで、従来の説が覆されつつあります。まず、定隆という人物ですが、従来から指摘されるように一次史料には実名は残っていません。ただ、「清伝」という法号の人物が文明年間(1469~1486)には実在しており、80年ほど後の土気酒井氏や東金酒井氏から祖先として明確に位置づけられています。清伝が定隆であった可能性も考えられます。
文明13年(1481)に鎌倉本興寺(鎌倉市大町)本堂建立にあたり、日泰上人とともに大檀那となった酒井清伝ですが、永禄2年(1559)同寺本堂の再興に、東金酒井氏らとともに私財を投入した土気酒井氏の胤治は「故清伝之裔(こせいでんのすえ)」と自称しています。また、東金酒井氏の胤敏も書状の中で「曽祖為始清伝入道(そうそせいでんにゅうどうをはじめとなす)」と記しています。
このように、土気・東金両酒井氏ともに清伝の末裔を称していますが、清伝の出自に関しては諸説あって定まっていません。
さて、その清伝は『本土寺過去帳』によれば、没年月不詳で「山辺にて」死去していると記録されており、実際に土気城に拠っていたのか、他の史料にもなく不明です。「山辺」とは、土気城北麓の金谷郷、南麓の南玉、池田・大竹・餅木が近世の山辺村となっており、台地上の土気城に対して、麓にあたる周辺地域が「山辺」としてよいでしょう。
確実なところでは、清伝の子隆賢は永正17年(1520)4月21日、「土気にて」没しており、この人物は16世紀初頭に土気城に拠っていたと考えられます。また、出土遺物を検討した簗瀬裕一氏によれば、瀬戸美濃焼編年では15世紀後半(1460~1480年)から出土するようになるので、長享年間(1487~88)の土気城再興説も「全く事実無根でもなさそうで、ある程度史実を反映している可能性を否定できない」とされます。
また、「新発見の医書『江春記抜書』と田代三喜」という演題で、2011年に日本医史学会で発表がありました。ここで清伝に関して、興味深いことが紹介されました(『日本医史学会雑誌』2011年)。これによりますと、有名な室町・戦国期の医師で「医聖」と広く称された人物、田代三喜との交流が伺える事実が示されました。というのは、三喜の兄にあたる周林蔵主は鎌倉建長寺塔頭三代目江春庵とされ、この人物から清伝は『江春記抜書』という医書を借りたことが明らかにされました。
この中で、木香丸(もっこうがん)という腹痛に用いられる漢方薬の処方の箇所に、「清伝、虫起ル時可用」と記されているとのことです。鎌倉に田代一族が居住していた頃、周林、三喜とも建長寺の僧であったとされます(『今大路家記抄』)。清伝と田代一族は宗派こそは違え、交流があったことがわかります。
以上のことから、清伝という人物が文明年間に鎌倉を拠点として活動しており、この人物こそが、その後東上総に入部し、土気酒井氏の祖(定隆か)となった考えられること、そして同氏2代目とされる隆賢(実名不明)は15世紀末頃より土気城に拠っていた可能性が高いと思われます。
今回参考にさせていただいた文献は次の通りです。
小高春雄『山武の城』私家版 2006年
簗瀬裕一執筆『千葉市の戦国時代城館跡』千葉市立郷土博物館 2009年
遠藤次郎・鈴木達彦「新発見の医書『江春記抜書』と田代三喜」『日本医史学会雑誌』2011年 日本医史学会
滝川恒昭「房総酒井氏に関する基礎的考察」(佐藤博信編『中世房総と東国社会』岩田書院2012年
今回は土気城主酒井氏について述べましたが、次回は、土気城の構造について考えてみたいと思います。
24 土気城跡 (千葉市緑区土気町) その2
土気城の構造を見るうえで注意しなければならないのは、今見ることのできる土気城跡は、城として使われた最後の段階の姿であることです。もちろん、これに加え、後世の改変が加わります。このことは中世城郭一般にあてはまりますが、とくに土気城の場合、造り変えられている部分が遺構として明確に残っており、稀有な例と言えます。
城を造り変える場合、堀幅を広げたり、曲輪を増設したりする例が多いのですが、堀を拡幅する場合、古い堀を掘り広げることが多く、古堀の痕跡は発掘によらないと明らかになりません。しかし、土気城の場合は古い堀を壊さず、新しく掘った堀と並べています(第2郭と第3郭の間)。両者は規模も違い、新しい堀には高い土塁もあり、一見して時代差がわかります。
 |
| 写真 土気城跡第2郭の土塁と古堀の痕跡(土塁の向こう側竹林の部分) |
また、土気城は造り替えにともない、第3郭を増設し、さらに「井戸沢」から南へ屏風のような折りの入った大規模な空堀を入れ、第3郭には出入り口に馬出曲輪(字あらいとはり)を設けました。ちなみに「とはり」は戸張のことで、当時の書状によく表われる用語です。出入り口に設けられた木戸のような施設(もしくはその場所自体を指す)を意味します。
ところで、この造り替えはいつ行われたのでしょうか。これだけの大規模な改変は、羽柴秀吉の関東来襲の風聞のたった天正13年頃から、北条氏領国の主な城で一斉に行われており、土気城の場合もこの時期が考えられます(遠山執筆分「土気城」『千葉県歴史の道調査報告書 御成街道 附土気往還・東金街道』千葉県教育委員会 1989年)。
これから取り上げる文書史料は、永禄8年(1565)2月に、当時里見氏に従属していた土気酒井氏が、北条氏政の軍勢に土気城を攻められた時のものです。この時、城主の酒井胤治は、同盟する里見氏の援軍もなく、北条氏の攻撃を受け、それも長引くことが予想されるので、越後(新潟県)の上杉輝虎(のちの謙信)に一刻も早い関東出兵を請う書状を送りました(永禄8年2月18日付河田長親宛「酒井胤治書状」早稲田大学図書館所蔵文書)。
北条勢の主力は、臼井原氏と東金酒井氏の軍勢でした。土気酒井氏と同族の東金酒井氏は、土気城を攻め、多くの犠牲者を出しています。胤治と東金酒井氏当主の胤敏は、又従兄弟の関係となります。戦国時代のみならず武士の世界では、兄弟同士でも戦い殺しあうことも珍しいことではありません。ましてや、というところでしょうか。
さて、胤治書状を読むと、戦闘の状況がよくわかります。これをみると、城をめぐる攻防は出入り口(近世の軍学でいう「虎口(こぐち)」)で行われたことがわかります。当時の文書には「戸張」とか「木戸」という文言が登場しますが、これにあたります。本書状には戦闘のあった場所として、「宿城」、「金谷口」、「善生寺口」の三か所が登場します。
土気城は麓からの比高が60から70mほどあり、麓から攻めるのに急崖をよじ登って攻めるわけにはいきません。登城路を攻め上るしかなかったのです。一方、台地続きは平坦続きで攻められやすいので、空堀と土塁で厳重に防御しました。それでも、城内へ通ずる通路は確保しなければなりません。この通路に沿って、家臣や商工業者の住まう城下集落(宿)が造られていきます。
城攻めを行う時、敵はまっさきにこの宿に攻めこみ、焼き払うことを行いました。こうして宿や城下町を壊された城のことを、当時は「生城(はだかじろ)」、「裸城」などと言い、落城寸前の状態を指しています。そのために守る側は宿や城下町を堀や土塁などで囲み、敵の攻撃から守ろうとしました。宿を防御したものは「宿城」と称し、この書状にも「宿城」での合戦があったことが記されています。大手口に通ずる登城路の城に隣接して宿が造られ、これが永禄年間には宿城に発展していたことがわかります。
現在残る遺構をみると、字「あらいとはり」の区域が堀と切岸により三角形の馬出曲輪に形成されています(近年、手前の堀は埋められてしまいました)。これは前述のように、天正後期の改造になるものと考えられます。永禄8年の段階では、この「あらいとはり」から土気城第3郭にかけての部分に宿城が造られていたと、筆者は考えています(根拠は前掲『歴史の道報告書』に詳述してあります)。
次に、書状に載る「金谷口」とは具体的にどのあたりを指すのか、考えてみたいと思います。「金谷」とは、土気城跡の北方の小中川の最上流となる金谷郷を指します。文字通り谷津の最奥部となる上金谷の集落から、土気城へと上る切通状となる登城路があり、主郭直近に通じています。ここを突破されると、落城間近と言ってもよいでしょう。この登城路をクラン坂と呼んでいます。「暗み坂」の転訛とも言われています。この金谷口では、東金酒井氏配下の「河嶋新左衛門尉・市藤弥八郎・宮田・早野以下宗者共百余人」が討ち取られるという大激戦となっています。百余人をそのまま信じるかどうかはさておき、かなりの激しい戦いとなっています。切通しとなる上り坂が延々と続き、切通しの上から射撃されたら、ここを突破するのはかなり困難だと想像できます。
 |
| 写真 金谷口の坂 |
長くなりましたので、この続きは次回の「その3」で述べたいと思います。
25 土気城跡 (千葉市緑区土気町) その3
さて、永禄8年の北条氏による土気城攻めでは、宿城・金谷口・善生寺口の三か所で激戦があったと胤治書状には記されていました。宿城と金谷口は、ほぼ場所を特定できましたが、善生寺口に関しては、比定地は二つの考えがあり、どちらとも決め難いものがあります。
ひとつは、小高春雄氏によって比定されている第3郭と馬出曲輪(字あらいとはり)の南麓となる、大網白里市南玉(みなみたま)の辺りとする考えです。顕本法華宗善勝寺のある台地の東麓にあたります。南玉集落の西方にある南玉池のさらに西奥部が、腰曲輪をともなう遺構もあり、この辺りを考えています(小高春雄『山武の城』私家版)。
ちなみに善勝寺は、土気城跡主郭の西に「善生寺曲輪」とよばれる一画(現高齢者施設が建つ)があり、もともとこの地に善勝寺の前身にあたる寺院があったものと考えられます。永禄8年の段階では、現在地に移転されており、東麓が「善生寺口」と呼ばれてもおかしくはないでしょう。ただし、この一帯は、旧房総東線の時代に国鉄線路が敷かれたため、改変されてしまい、旧状を復元する(とくに台地上までどのような経路で行くか)うえで困難さをともないます。
 |
| 縄張図(『千葉市の戦国時代城館跡』より) 永禄期はこの図とは異なる様相を示す |
もう一つの考え方として、善勝寺の西麓周辺を「善生寺口」にあてるものです。縄張図(『千葉市の戦国時代城館跡』より)を描いた簗瀬裕一氏は、この考えをとるようです。筆者も、以下に述べる理由で、こちらの考え方をとります。
善勝寺のある台地(善勝寺台地とします)は、南を頂点とする三角形状をしており、その南端は急崖となっています。台地上南端には、善勝寺砦跡とよばれる小さな城郭遺構があります。大網の市街地より土気・誉田方面に向かう県道(県道20号千葉大網線)を、ちょうど見下ろす位置になります。この県道は、善勝寺台地の南麓から東南東方向(大網の市街地方向)に延びる細尾根に造られていますが、土気城が機能していた頃から存在していたと考えられます。
また、善勝寺台地西麓の県道に突き当たるように、大椎・小食土町方面からの旧道(旧土気往還)が交わっています。これは千葉方面より土気市街地を経ずに、バイパスして大網に向かう道で、沿道には古代・中世の住居址や古墳群など遺跡が連なり、古代からの道と考えてよいものです。ただ、今はあすみが丘の団地となってしまい、旧道は拡幅されたりして古道を追うのは厳しい状況です。しかし、土気往還と思われる道路遺構が、発掘によって遺跡群の中から検出されています。このように、大網市街地からの道と千葉からの旧土気往還が交わるのが、善勝寺台地西麓ですので、この辺りが善生寺口の比定地候補の一つとできると考えます。
酒井胤治書状には、善生寺口で「十余人打候」と記されていますが、小高説を採るならば、金谷口を攻めた東金酒井氏の一団から分かれた軍勢が、南玉へ回ったと考えることができます。また、善勝寺西麓説を採るならば、宿城を攻めた臼井原氏に率いる軍勢の一部が、こちらへ回って攻めたと考えることができます。残念ながら、善生口で討ち取られた面々の名前が書かれていないので、どちらをとるか断定することはできません。
このように、酒井胤治書状は、当時の土気城の構造が垣間見える貴重な文書といえます。なお、胤治の書状をうけた謙信は2月24日には越山し、厩橋城(前橋市)に入ったこともあり、北条軍は退去したようで、土気酒井氏は攻撃に耐え抜いたようです。これも、堅い守りの土気城だったからこそでしょう。この後、土気酒井氏と東金酒井氏は、北条方につくことになりましたが、里見氏の攻勢の前に、元亀2年(1571)末には北条方から里見方にまた従属することになります。こうしたなか、土気城はさらなる北条方の攻撃を受けることになります。これは次回「その4」で述べたいと思います。
26 土気城跡 (千葉市緑区土気町) その4
前回までは、永禄8年2月の北条氏政による土気城攻めについて、詳しくみてきました。土気城に関わる攻防戦は、実は最低でももう二回はあったと考えられます。一つは年未詳6月22日付の「村上民部大輔宛足利義氏書状」(『秋葉文書』)に記された土気城攻め、もう一つは、直接土気城が攻撃されたかは不明ですが、土気領を攻撃された天正3年の北条氏による東上総攻撃です。今回は、これまでいつ行われたのか明確にはなってこなかった(元亀年間から天正初期とされていた)前者について、みていきたいと思います。
 |
| 金谷よりみた土気城跡(中央の小高いところが主郭周辺) |
年未詳6月22日付の村上民部大輔宛の古河公方足利義氏書状では、「向土気及行」、「酒井左衛門次郎者六十人討取」ったことを、村上民部大輔は義氏より賞せられています。「向土気及行」は「土気に向かいて行(てだて)におよび」と読み、土気城を攻撃したことを意味しています。
ところで、村上民部大輔とは何者でしょうか。村上氏といえば、武田信玄との激闘で知られる信濃の村上義清が有名です。村上民部大輔も祖先は信濃村上氏の出身と考えられ、戦国後期に八千代市の米本城主であった村上氏です。民部大輔を称するのは、村上綱清という人物で、高野山の「西門院文書」には民部大輔綱清の署名・花押が据えられた書状があり、戦国後期に実在したことがわかります。この綱清は文書の上からは永禄年間(1558~1569)まで活動していたことがわかります。そして、天正3年(1575)には、子息助三郎胤遠(たねとお)が文書に表れ始めるので、元亀から天正初期(1570~1574)に綱清から助三郎に代替わりがあったと考えられています。
さて、綱清が土気城を攻めたのはいつのことでしょうか。義氏の書状にはヒントになることが書かれています。それは、義氏のいた古河城を、敵対する小山氏が攻めたという記述です。義氏が古河城へ入城できたのは、永禄12年(1569)以降ですので、土気城攻めは元亀から天正初期(それも胤遠との代替わり前と考えられる天正2年まで)と考えることができます。
ところで、土気酒井氏は里見氏と千葉氏・北条氏との間で、情勢に応じて離反を繰り返す複雑な動きをとります。永禄8年2月に北条氏に攻められた後、北条方に従属し、同10年頃里見氏に本納城を攻められる事態がおこりました(「小田原編年録」)。その後、永禄12年まで北条方についていることが確認されていますが、里見氏の攻勢の前に、元亀2年(1571)12月には里見方についたことが史料からわかります(「宍倉文書」)。このことから、北条氏に土気城が攻められる事態となったのは、元亀3年6月以降のことと考えられます。
以上のことから、綱清の土気城攻めは、元亀3年(1572)から天正2年(1574)の間と限定されました。先の小山氏による古河城攻めに関しては、天正2年に関宿城が北条氏に攻められており、近接する古河城を攻める余裕が小山氏にはないと思われることから、元亀3年か天正元年(1573)のどちらかと、さらに絞れることになります。
それでは、どちらでしょうか。当時の里見氏と千葉氏との攻防の面からみると、元亀元年8月に里見氏によって小弓原氏の本拠小弓城が陥落します。そのため、小弓原氏はもう一つの本拠臼井城へ移らざるをえませんでした。米本城は、位置的にみて臼井城の西方の守りの要ともいえる城です。村上氏は、元亀2年から3年にかけて東京湾岸を席巻する里見氏に対し、臼井城を守るべく米本城において対処に追われていたものと考えられます。いまだ小弓城の回復もままならなかったはずの元亀3年6月に、村上氏が土気城を攻める余裕はなかったものと推測できます。
こうしてみると、村上氏が土気城を攻めたのは、天正元年(1573)6月のこととできます。そして、これが村上綱清の消息のわかる最後の史料となります。天正3年には、確実に子息助三郎胤遠は土気を含む東上総に進攻しています。また、前年の天正2年にも北関東に出張っていると思われる書状もあり、どうやら天正元年を境に、綱清と助三郎父子の当主の交替があったようです。その意味では、「酒井左衛門次郎者六十人討取」り、古河公方足利義氏から賞された土気城攻めは、綱清人生最後の活躍の場だったかもしれません。
参考文献
『八千代市の歴史 通史編』「第三編中世 第四章戦国時代 第四節米本城主村上氏について」(遠山成一執筆分)八千代市 2008年3月
外山信司「米本城主村上綱清と上総―清宮秀堅『下総旧事』を手がかりに―」『千葉県の文書館』第27号 2021年3月
遠山成一「もう一つの土気城合戦」『歴史研究』戎光祥出版 2023年3月
27 千葉六党の城 海上氏の本拠中島城 その1
鎌倉時代初期に千葉常胤の六男胤頼が、東庄・三崎庄を得て東氏を名のり、その孫にあたる胤行の弟胤方が三崎庄を領有して海上氏と称することになりました(常胤系海上氏)。その後、室町期には、海上氏は鎌倉公方(のち古河公方)の奉公衆として活動しています。この海上氏の本拠の城が中島城(銚子市中島町)です。
中島城は、利根川の川湊である野尻・高田津に近く、また九十九里平野北端となる旭市(旧飯岡町)方面からの道を睨む、水陸交通の要衝を占めています。旧飯岡町は中世の塩業が行われていたことが文書からもわかっており(「原文書」『千葉市立郷土博物館所蔵原文書』)、この道を通って、塩荷が野尻津より「塩船」で内陸へと運ばれていました。また、道の途中の銚子市猿田町には交通に関る神猿田彦命(さるたひこのみこと)を祀る猿田(さるだ)神社もあり、この道の重要性がわかります。
 |
|
写真 高田町方面(利根川方面)からみた中島城跡 |
また当城の周辺には海上堀内妙見社(堀内神社)をはじめ、海上氏ゆかりの寺社がいくつか点在しています。海上堀内妙見社は、中島城跡の東方200mほどの所に位置し、明応9年と天文10年の造営に関る棟札写が残り(「宮内家文書」『戦国遺文 房総編』第2巻)、海上氏の当主が大檀那を務めていることがわかります。また、棟札に記載される家臣に加世(加瀬)・宮内・島田・大那木・平岩・飯岡・石毛の諸氏がみえ、家臣団構成がある程度判明しています。これらの名字は、現在も銚子市近辺に多くみられます。
中嶋城跡の南方200mほどの岡野台町にある、等覚寺に祀られる仏像3体のうち「木造薬師如来立像」2体は、明治初期の廃仏毀釈によって廃寺となった引摂寺(いんじょうじ)にあったものが引き取られたものとされています。2体とも鎌倉期のものとされ、千葉県の指定有形文化財となっていますが、とくに1体は、「運慶の作風に学んだ慶派仏師の作品」(千葉県教育委員会ウェブページ)と考えられています。
また等覚寺からは、建長4年(1252)銘のある金銅経筒が出土しました。ここには「施主平胤方」と記されており、海上氏の祖となった海上胤方が亡くなった母親の供養のため、写経し埋納したものと判明しました。また、当城の南約4kmにある常世田山常燈寺(じょうとうじ)にある木造薬師如来坐像(国重要文化財)の修理を、仁治4年(1243)に平胤方・藤原女の夫妻が他の人たちとお金を出し合って行っていることが、修理銘からわかっています。このように初代海上氏(常胤系)の時代からの遺蹟が残る当城一帯は、まさに海上氏の本拠地と呼ぶにふさわしいといえるでしょう。
以上のことは、既に半世紀前に、旧県史(『千葉縣史料』各篇)に携われた小笠原長和氏によって、詳細に解明されています。
現在、残る中島城の遺構は戦国後期の様相を示しますが、中世前期の海上氏の本拠となる屋敷は、現中島城跡の一画か、あるいは周辺の他の場所に設けられていたものと考えられます。高森良昌氏の「海上氏の墳塋と菩提寺考」(『研究紀要』第2号 千葉市立郷土博物館 1996年)では、「この場所(引摂寺-引用者)は海上氏の居館址と考えられている」とされ、等覚寺の東方に隣接した区画にあったとしています。
その引摂寺跡の北に隣接する堀内妙見社には、「堀内」(堀の内)の名称が遺ることからも、小笠原氏も指摘しますが、古い時代の武士の屋敷地がこの一帯にあったと考えることができるかと思います。
 |
| 県指定有形文化財「金銅経筒(建長四年在銘)」 千葉県教育委員会ウェブページより |
中嶋城の構造等については、次回に述べたいと思います。参考文献も最後に掲載します。
28 千葉六党の城 海上氏の本拠中島城 その2
中島城は戦国後期の形態を残す城郭で、東西500m、南北400mという県内でも有数の大規模城郭です。標高40m弱の台地上に、幅7~8mほどの空堀(現状は埋められて畑となる)で、大きく四つの曲輪から成り立っています。また、主郭東麓の腰曲輪にあたる部分には水堀と思われる窪みもあり、これは県内の城郭では珍しい部類に入ります。
 |
| 写真 主郭(畑地の部分)にある「史跡 中島城跡」の石碑と堀跡(画面右の藪) |
城跡の南には、銚子市四日市場町に河口をもつ高田川が流れています。同じく北および東側には逆川が流れ、両川が自然の水堀の役割を果たしています。また、城の北東側は、往時は後背湿地(バックマーシュ)が広がっていたと思われ、なかなかの要害地形です。城域東端が主郭となっており、当時の香取内海に向かって眺望が開けています。
その主郭の台地麓に通称「大手口」があり、これより高田川に沿って、東南東方向へ一直線に道が伸びますが、ここ一帯は通称「宿」と呼ばれています(井上哲朗「中島城跡」『千葉県の歴史 資料編 中世1(考古資料)』千葉県 1998年)。現在、短冊地割(耕地整理の結果)となる水田が道の南側に見られます。明治時代の迅速測図をみると、現状とあまり変わらない直線道路が伸びておりますが、古い公図では短冊地割にはなっていませんでした。
水田の中央近くに牛頭天王(ごずてんのう)を祀った小さな祠があります。これは迅速測図で、神社の地図記号で確認できます。この辺り一帯は、昭和21年(1946)の空中写真をみると既に耕地整理が済んでしまっていて、旧状は追えません(戦前の早い段階で行われたためか、古い公図には直線道路の北側にあたる字関上だけ地割図が残っていませんでした)。
ところで牛頭天王は素戔嗚尊(すさのおのみこと)と同一とされ、牛頭天王社は明治の神仏分離令によって素戔嗚尊を祀る八坂神社に強制的に変えさせられました。また牛頭天王は、釈迦の生誕地である祇園精舎の守護神とされ、八坂神社の祭礼が祇園祭(明治以前の祇園御霊会)と呼ばれるのもその関係からです。
祇園祭は、都市の祭礼として悪疫退散(ですから疫病の流行する夏にお祭りをします)を願うものです。中島城の「宿」に牛頭天王が祀られているのも、城下の商工業者たちの住んでいた城下集落(いわゆる「都市的な場)の名残と思われます。宿のすぐ裏(南側)には高田川が流れ、香取内海から入り込んだ舟が荷を搬出入していた可能性が考えられます。
 |
| 写真 通称「宿」地区の牛頭天王社 |
次の史料は、直接中島城の「宿」ではありませんが、宿の裏の高田川を通り、中島城直下の根小屋集落へ荷を運んでいたことが想定されるものです。
正木時定ヵ判物写 (宮内家文書) 『戦国遺文 房総編』第二巻
須賀筋(旭市付近)より下しほ荷之事
一月之中十五日、舟木・野尻之宿ニ可下、後日於城取之上者、根小屋へ可引之者也、
仍如件、
永禄三年極月十四日 (花押)
野尻宿商人中
永禄3年(1560)10月、里見氏(主力は正木氏)は香取領に侵攻し、この後同9年まで占領を続けました。この文書は、一宮正木氏の正木時定と思われる人物が、野尻宿の商人らに宛てたものです。飯岡方面より運ばれた「しほ荷(塩荷)」について、月の内半分の15日間は舟木と野尻の宿へ塩荷をおろし、後日、城でこれを取る際は根小屋へ引き上げるよう指示したものと考えられます。
ここでいう根小屋をもつ「城」とは、舟木と野尻宿に近接する中島城のことを指すものでしょう。中島城膝下と言ってもよい舟木・野尻両宿は、香取内海(現在の利根川)に面して位置します。中嶋城に現在根小屋地名は残されていませんが、これに該当しそうな集落は、東麓・南麓そして西麓にみられます。ここでは高田川に面した、中島城南麓の集落が史料にある「根小屋」に該当すると思われます。舟木・野尻宿から塩荷を直接陸送し、城へ運ぶことも考えられますが、両者間を隔てる後背湿地を結ぶ道が確保されていたか疑問です。それよりも舟を使えば高田川河口から遡上し、根小屋直下の船着き場まで運ぶことが可能です。なお、現状の高田川は流れが急で、しかも、川底の岩盤が削れて凹凸が激しい箇所もあり、水量が少ないと航行が難しいと思われます。この点、水量の問題や船曳のことなども考える必要がありそうです。
ところで、この文書を発給した正木氏は一宮正木氏と考えられており(『戦国遺文 房総編』第二巻)、海上氏からみれば明らかに侵略者です。その正木氏が野尻宿の商人らに命じ、海上氏の本拠である中島城へ塩荷を運ばせることができたのは、不思議な感じがします。この時点で海上氏は本拠から撤退し、正木氏が中島城を占拠していたのではないかとのことです(滝川恒昭氏のご教示による)。塩荷などの輸送を担い広域に活動する「流通商人」である宮内氏は、それぞれの商圏における領主との関係を維持していたわけですから、敵も味方もないわけです。
この文書を現在に伝えた宮内氏は、塩の生産地である旧飯岡町の三川に給地を持っており、香取内海より奥深く遡上した関宿方面まで商圏にしていたことがわかっています(関宿城主簗田持助の発給した文書が宮内家文書として伝わる)。ちなみに銚子市の高田町や中島城の周りには、非常に多くの宮内姓が今もいらっしゃいます。
里見氏(正木氏)が香取侵略したのも、滝川氏が指摘するように香取内海の富の掌握にあったことが、この文書から理解できます。
なお、城跡周辺の公図閲覧にあたり、銚子市役所都市整備課土木室の職員の皆様にお世話になりました。記して感謝申しあげます。
参考文献 文中であげた他
小笠原長和「下総三崎荘と海上千葉氏」『中世房総の政治と文化』吉川弘文館 1985年(初出1969年)
井上哲朗『千葉県中近世城跡研究調査報告書11 中島城跡・鹿渡城郭』千葉県教育振興財団文化財センター 1991年
滝川恒昭「戦国期房総における流通商人の存在形態」『中世東国の地域権力と社会』千葉歴史学会編 岩田書院 1996年
『本佐倉城跡史跡指定20周年記念事業講演 敵を阻む城、にぎわう城下』(滝川恒昭氏執筆分「千葉氏と里見氏の香取侵攻」)2018年 酒々井町・佐倉市
29 廿五里城跡(千葉市若葉区東寺山町)
廿五里(つうへいじ)城跡は、千葉都市モノレールで都賀駅から動物公園駅方面へ向かう途中、みつわ台駅の手前、向かって右方向直下に見える城です。市内ご在住の方には、かつての殿山ガーデンのあった所、と言ったらわかりやすいかと思います。残念なことに近年、モノレール線路側の台地が大きく削りとられて宅地化され、景観がすっかり変わってしまいました。
城本体はかつて殿山ガーデンとして使われており、施設内に城郭遺構らしきものも見られました(千葉市の遺跡を歩く会ウェブページ「みつわ台周辺-2 廿五里南・北貝塚と廿五里城跡」の空撮写真は1974年当時の空中写真が載っています)。
 |
| 写真 廿五里城跡(画面左側が大きく削平された部分) 2017年2月 |
本城跡は東寺山町の町域北東端にあたり、字二十五里(小字名はこの字です)に位置します。この城を示すと思われる「寺山在番」、「寺山在城」と記載される史料が存在します。「秋山仙一家文書」中の永禄3年ヵ10月24日付大須賀薩摩丸宛「千葉胤富書状」です。これは永禄3年に、小田喜正木氏が里見氏の命により、香取へ侵攻した時のものと考えられています(『大栄町史 通史編 上巻 原始中世編』2000年)。胤富は、「寺山在番」から本拠地へ戻ったばかりの大須賀薩摩丸に対し、小見川の富田台(現香取市富田)へ上陸した房州衆に対処するよう求めています。この寺山とは廿五里城を指すと考えてよいでしょう(外山信司「下総高品城と陸上交通」『千葉城郭研究』第4号 1996年)。
この文書には「寺山在城之陣労」と記され、薩摩丸が寺山の城(廿五里城)に在番していたことがわかります。この背景には次のような出来事が関係します。永禄3年(1560)5月に、北条氏が陣城を築いて久留里城の里見氏を攻めたため、里見氏は越後の上杉謙信(当時は長尾景虎を名のる)に救援を求めました。これにより、謙信は初の関東進出(越山)を果たします。その報を聞いた北条氏は、直ちに久留里城の包囲陣を解き、謙信の軍勢に備え移動しました。
その年の10月、正木氏による香取侵攻が始まります。一方、東京湾岸の西上総・西下総でも里見氏の北上の脅威があったようです。廿五里城に詰めていた薩摩丸は、千葉と佐倉を結ぶ街道を押さえる高品城(当「研究員の部屋」コラム9・10で紹介済)の後方支援のため在城していたと思われます。
その脅威もいったんは薄らいだのか、薩摩丸は在番を解かれて本拠地へ帰りました。しかし、ほどなく正木氏の富田台上陸があったため、胤富から帰陣して間もなくですまないが、と富田台近辺への速やかな着陣を求められています。
ところで、東寺山町は古くからの中心地である字本郷の北に宮海道が、南には浜道がそれぞれ小字名として残ります。この両字名は廿五里城の交通網に関るものとしてとらえられてきましたが、明治期の迅速測図を読んでみると、宮海道は、むしろ西寺山(現若葉区源町)の中心地字本郷と東寺山の字本郷を結ぶ役割が大きかったと考えられます。また、浜道は東寺山の本郷より南へ下り、支谷を渡って高品城の北端(春日神社のすぐ南側)の堀切道を経由して千葉の街(湊)に行く、文字通りの浜道だったと考えられます。ですので、廿五里城の役割は、外山氏も指摘するように、あくまでも千葉と佐倉(本佐倉)を結ぶ「北年貢道」を押さえるためのもので、同じ役割を果たしていた高品城の後方支援の城としての性格が強いと思われます。
本城はモノレール建設に先立ち、発掘調査が行われました。以下、『千葉県の歴史』掲載の笹生衛氏の見解に従って記述します。台地縁辺部より、板碑や五輪塔・宝篋印塔をともなっていたと思われる墓域が広がっていたことが確認できました。板碑は25個体分出土しましたが、1基のみ「建武元(1334)年十月日」の紀年銘がありました。石塔は「15世紀を中心として年代が推定できる」とされます。
また、本城の西に隣接する地区(現高齢者施設)からは、発掘により和鏡が発掘されています(報告書未刊、『千葉市制100周年記念 千葉市内出土考古資料優品展』千葉市教育振興財団 2021年11月)。こちらまで墓域が広がっていたことが想定されます。
つまり、廿五里城のある台地は、「14世紀前半に板碑をともなう墓域が成立し、15世紀を通じて板碑・石塔をともなう土坑墓・火葬墓が営まれ」、16世紀後半にはこれらを撤去して城が築かれたと推定されます。ちょうど16世紀後半になると、里見氏(正木氏)の下総侵攻が始まり、想定される本城の果たした役割から考えると、築城の時期は合致すると思われます。
このように史料にも登場する中世城郭が、施設である程度壊されていたとはいえ、十分な調査もなく(ほぼ)消滅してしまったのは、残念なことと言わざるを得ません。なお、本稿執筆にあたっては、参考文献等、外山信司氏のご教示を得たところが大きかったことを書き添えます。
参考文献 文中に掲げた他
笹生衛「廿五里城跡」『千葉県の歴史 資料編 中世1(考古資料)』千葉県 1998年
『絵に見る図で読む 千葉市図誌 下巻』千葉市 1993年
30 南屋敷遺跡(千葉市若葉区源町)
今回ご紹介する南屋敷遺跡は、文字通り中世の城ではなく、これまでの呼び方では「館跡(かんせき:やかたあと)とされる分類に入るものです。ただし、1980年代より「館(やかた)」という言い方に対し疑義が出されています。私たちが持っている武士の居住空間は、いわゆる「方形館跡」という、土塁と堀で囲まれた正方形や長方形の区画をイメージします。しかし、これは、あくまでも戦国時代にはいってからの、防御性を高めた頃のものと近年認識されています(ただし、土塁をもった館も、発掘によって鎌倉時代から少数ですが存在したこともわかっています)。そのため、近年になって中世前期の武士の居住地を、「館」に代わり「屋敷」と呼ぶことが提唱されています(あまり定着しているとは言えないようですが)。
南屋敷遺跡は、堀と低い土塁をともなう長軸45m、短軸38mの小規模な「屋敷」跡です。特徴的なことに、周辺部より屋敷内部が低くなっており、「堀込式屋敷」と呼ばれています。当遺跡を発掘調査した簗瀬裕一氏のネーミングとのことです。同様なタイプとして、池の尻館跡(四街道市)、井野城跡・臼井屋敷跡(佐倉市)、埴谷周路館跡(山武市)、東中山台遺跡群(36)地点(船橋市)などが知られています。下の表は、管見の限りで類例を集めた堀込式屋敷の一覧表です。
| 遺跡名 | 所在地 | 外 寸 | 使用年代 |
| 南屋敷遺跡 | 千葉市若葉区 | 東西45m×南北38m | 15C代~16C前半 |
| 池の尻館跡 | 四街道市 | 南北52m×東西約29m | 15C後半~16C初 |
| 井野城跡 | 佐倉市 | 複郭 | 15C~16C |
| 臼井屋敷跡 | 佐倉市 | 長軸35m×短軸27m | 15C後半~ |
| 埴谷周路館跡 | 山武市 | 南北55m×東西40m※ | 14C後半~15C後 |
| 東中山台遺跡群(36)地点 | 船橋市 | 南北50m×東西30m? | 15C後半~16C末 |
※土塁内側の寸法 ここにあげた他、墨古沢遺跡(酒々井町)、米本城跡c地点(八千代市)が堀込屋敷跡にあたることを、道上文氏よりご教示いただきました。
南屋敷遺跡の土塁の内側平坦面は、土塁の頂部より2mほど掘り下げられていて、防御性に乏しくなっています。内部は主郭と二つに分かれた副郭があり、発掘により主郭から主屋(3期にわたり建て替えられています)が検出されています。また、南北に分かれた副郭からは、それぞれ軸線を主屋に合わせた小規模建物が見つかっています。
出土遺物としては瀬戸窯、瀬戸美濃窯、カワラケ、瓦質内耳土鍋、砥石などがあり、貿易陶磁は1点のみです。このことから、屋敷の主は上層農民(土豪層)と考えられています。つまり、村落の指導者クラスの屋敷ではないかということです。この点において、池の尻館跡(貿易陶磁も7点)・埴谷周路館跡(同2点)で、同じような傾向を示します。
また、成立年代も埴谷周路館跡を除くと、大半が15世紀台か15世紀後半です。15世紀といえば、政治史的にみると、15C半ばの1455年から享徳の乱が勃発し、両総各地で戦乱がおこります。城郭史学からは、恒常的に城郭が維持されるようになるのは15世紀後半からとされています。こうした政治状況が屋敷の主たちにどのような影響を与えたのか、戦国史研究においても大きなテーマといえるでしょう。残念ながら、これに即答はできませんが、ネゴヤとの関連が大きいと、筆者は考えています。
あえて見通しを述べさせてもらいますが、ネゴヤの史料上の初見は、管見の限りでは「喜連川文書案」の「道哲足利義明書状案」です。この文書は、昨年開催した「我、関東の将軍にならん-小弓公方足利義明と戦国期の千葉氏-」でも展示したものです。この中で、「敵城近辺、田井・横山・小沢要害、根小屋以下悉被打散…」とあり、この書状は大永元年(1521)に比定できますので(当「研究員の部屋」の小弓公方関係を参照)、16世紀初頭にはネゴヤが形成されていたと考えてもよいと思われます。
つまり、堀込屋敷が廃れていくのと並行して、根小屋が各地に形成されていくということです。ただし、市村高男氏はネゴヤの「小屋」に注目され、あくまでも仮の小屋であることを強調されています。すなわち、ネゴヤの住民たち(家臣たち)は本拠を持っていて、あくまでも職住接近したネゴヤは仮の住まいである、という意味です。堀込屋敷とネゴヤの関係をみていくと、家臣団のネゴヤへの集住(定住)が進んでいく、と考えてもよいのではと思います。まだまだ深く検証する必要がありそうです。
参考資料
『千葉県の歴史 資料編 中世1(考古資料)』1998年
市村高男「中世東国の宿の風景」『中世の風景を読む 第二巻 鎌倉と坂東の海で暮らす』(網野善彦・石井進編 新人物往来社 1994年)
その他、各遺跡調査報告書
31 千葉六党の城 東氏の城 その2
六党の城シリーズ13「東氏の城」で須賀山城を取り上げましたが、最近、新たな知見を得たので、再度書き足したいと思います。というのは、須賀山城が東に面する桁沼川は、水運で重要な役割を果たしていたのではないか、という論文に接したことがきっかけとなりました。鈴木哲雄氏の「海上千葉氏の領国支配-網代・製塩・「郷中開」-」(『都留文科大学大学院紀要』第27号、2023年3月)です。
研究員の部屋(遠山)27・28で紹介した「海上氏の城中島城 その1・その2」では、九十九里平野北端の須賀郷(旭市飯岡)で生産された塩を、台地を越えて高田・野尻津(銚子市)に運び、舟で上流へ運んだ旨を書きました。しかし鈴木論文では、もう一つの経路の可能性を指摘しています。それは、須賀郷より椿海へ直接出て、舟で北上し、椿海の北端からさらに奥まった東庄町青馬まで運びます。ここの地峡部で、積み荷を桁沼川(利根川に注ぐ)側に引き上げて(もしくは、舟を引き上げて)、同川を下って笹川津に着きます。ここから香取内海を行ったとする考えです。
鈴木氏は、青山宏夫「干拓依然の潟湖とその機能 椿海と下総の水上交通試論」(『国立歴史民俗博物館研究紀要』第118集、2004年)を参照しながら、この経路を須賀郷からの「塩舟」が航行した一つのそれと考えておられます。けだし、卓見と考えます。と言いますのは、氏が同論文の注で記しているように、「千葉胤冨判物」(「原文書」)にある「地摺役」を、「船引」「船越」するためのものと考えておられるからです。筆者は、十数年前に「原文書」の研究会で3年間学びましたが、この地摺役というものが何であるのか、当時理解できていませんでした。鈴木氏が想定されたように、舟を綱で引き上げて、分水嶺(帯)を越したということで、地を摺るための労役が地摺役だったのでしょう。
先日、東庄町青馬の字船引の現地を訪れましたが、東庄町立東庄中学校のすぐ西隣にあたる同地は、地峡部の幅は数十m(道路と住宅地一軒分ほど)ほどです。しかも、青山論文に指摘されていますが、青馬と反対側の同町窪野谷の谷頭にも舟引の小字が残ります。おそらく実際に斜面部を、舟が引き上げられたのではないでしょうか。こうして、中世当時は存在していたとされる桁沼に塩舟が入り込み、笹川の津へと運行されたと思われます。津は桁沼川河口部に近い場所に比定されています。
ちなみに、桁沼は、往時は香取内海に口を開いていたわけではありません。現在の桁沼川の最下流部の川幅とほぼ変わらないものと思われます。というのも、町場や古い寺社(八坂神社も存在する)があることから、これらの乗る砂州によって桁沼は塞がれており、桁沼川の下流部にあたる流路によって香取内海とつながっていたと考えます。
中世、おそらく戦国時代末頃までは、桁沼の地名通り大きな沼が笹川の街の背後に存在したと考えられます。そして、椿海からの舟が台地を越して、桁沼に入り込んできました。積み荷の主なものは塩です。
こうしてみると、須賀山城の存在意義として、この水運を掌握するものであったと考えることができます。そして実際、須賀山城の東には真言宗西福院という寺院が、田んぼのなかに存在します。
 |
| 上写真:西福院(東庄町笹川)遠景 下写真:同土塁状遺構 |
 |
往時は西福院近辺まで湖水が打ち寄せていたと思われます。規模は、100m×長辺100・短辺60mほどの多角方形です。西福院の敷地周囲には土塁が残り、小字南城(みなみしろ)とつけられていることからも、中世城郭の跡を寺院化したものではないかと考えられています。
つまり、流通経路を抑える役割を果たしていたのが、西福院の前身の城郭だったのではなでしょうか(仮称:西福院城跡)。
また、南北朝期14世紀後半の「海夫注文」(「旧香取大祢宜家文書」)には、笹川の津の知行主として「東六郎」(六郎は惣領が称する仮名)が記載されており、この笹川一帯は東氏の本拠地であったとわかります。西福院の敷地がもともと方一町(約100m四方)であったとすれば、東氏の屋敷地であったことも当然考えてよいと思います。須賀山城は、いざという時に立て籠もる城だった可能性があります。もちろん現在の形とはまったく異なるものだったはずです。
ところで、永禄3年(1560)から同9年(1568)まで、里見氏(主力は正木氏)が香取侵攻をした際に、軍記物ではありますが、「府馬左衛門・東六郎」が正木氏に与同した、とされています(『東国戦記』)。府馬氏に関しては、拙稿「里見氏の香取侵攻の経路に関する一考察-交通史の観点から-」(『里見氏研究』創刊号 2022年3月)にて、その蓋然性が高いことを述べましたが、東六郎に関しては、なぜ名前があがったのかも考えが及びませんでした。しかし今回、もう一つの「塩の道」を考えた時、東氏が正木氏に与同した蓋然性は高いと思うようになりました。二次史料とはいえ、何らかの史実を反映している可能性があります。すなわち、以下のような理由によります。
東氏の支族である海上氏は、後に千葉氏を継ぐことになる胤冨が一時養嗣子として入っていたこともあって、当地域一帯の流通をおさえ権力を握っていました。それに対し、本家筋にあたる東氏(六郎は、東氏祖の胤頼から代々惣領が名のる仮名)は海上氏の後塵を拝していたと思われます。こうしたなか、正木氏の侵略により、海上氏は正木氏に敵対して中島城を奪われるなど、一時逼塞を余儀なくされていたようです。
これに対し、東氏惣領家は富の源泉として重要な塩の流通経路を、正木氏と結び既述の椿海‐桁沼ルートに重点を移すことで、東総地域の支配権を一挙に挽回しようとしたのではないでしょうか。笹川の津をめぐる東氏と森山城代海上氏の確執も想定されます。
正木氏の香取支配は数年間続きましたが、最終的には永禄9年には撤退していきました。冒頭の胤冨判物で、椿海‐桁沼ルートが塩舟の経路として指定されているということは、おそらく東氏の掌握していた同ルートを、当地域の支配を回復した胤冨があらたに獲得し、高田・野尻ルートとともに掌握したことを意味すると考えます。
ちなみに、外山信司氏のご教示によれば、天正13年(1585)-この年に邦胤は家臣により暗殺されます‐に、東氏は東大社の大般若経を千葉邦胤らとともに奉納しています。このことからみて、東氏は正木氏の撤退で完全に勢力を失ったわけではないようです。ただし、東氏の須賀山城は、「原文書」にみられるように、永禄9年以降、森山城と一体化して胤冨に掌握されるようになっていきました。天正17年(1589)の北条氏による「森山表穀留」(米穀の流通を強制的に止めること)とは、実際には笹川の津(森山表)で行われたと考えるべきでしょう。千葉邦胤の死後、千葉氏領国が北条氏の支配下に入った天正末期には、森山城・須賀山城は、北条領国の一支城化していたといえます。
参考文献は、文中に記した通りです。また、西福院については平野剛氏のご教示をいただきました。現地見学には、東庄町教育委員会教育課のご協力をいただいたことを付記します。
32 千葉市内の城館関連小字名
前々回(5月24日)ご紹介した若葉区源町(旧西寺山地区)の南屋敷遺跡は、15世紀代の土豪クラスの屋敷跡と考えられています。実は市内には、まだいくつかの土豪もしくは名主(みょうしゅ:作人らの農民に名田を貸出し、賃料をとるだけで自らは耕作をしない上層農民)の屋敷に関連すると考えられる小字が散在しています。
例えば、殿山・殿台・殿内といった領主層の屋敷の存在を表す小字は、殿山は若葉区原町・貝塚町、花見川区畑町に、殿台は大字として若葉区殿台町に、殿内は若葉区中野町、殿内海道は若葉区源町にそれぞれ存在します。これらの小字に隣接して前畑・前田・門田といった、領主の直営地(佃や御正作:みしょうさく)を意味する地名があります。若葉区谷当町には堀ノ内と門田、同区川井町には竹ノ内(館ノ内か)と前畑という組み合わせもあります。
例えば大字となりますが若葉区殿台町に、小字で前畑・松葉(的場の転訛)があり、行政区的には稲毛区萩台町に属す前田が、台地上の前畑の麓付近に展開しています。
南屋敷遺跡には殿台堀込の小字が残り、前畑の小字が近接します。同遺跡はたまたま近年まで開発されず、遺構が残っていましたが、他の例ではほとんど遺構は残っていません。これをどう考えるかです。早いうちに、市街地化や耕作によって破壊されたと考えるのか、または初めから土塁や堀といった構造をしていなかったのかです。
近年の研究成果によれば、東国における中世前期の武士の屋敷は堀や土塁をともなうものはあまりなかった、と考えられています。土塁や水堀で囲まれた「館」のイメージは、実は戦国時代になってからのものです。そうであれば、武士よりも階級的には下となる土豪や上層農民の屋敷も、土塁や堀をもっていなかったと考えた方がよいでしょう。
15世紀代に、「堀込式屋敷」と名付けられた南屋敷遺跡のような特徴的遺構をもつ屋敷が、下総中心(8例中7例)に出現します。生活面が地表面より2メートル近く掘り下げられているのが特徴ですが、もう一つ台地先端や縁辺部ではなく、台地基部か、やや奥まったところに占地するという特徴をあげることができます。戦国期になると、防御しやすい舌状台地先端部を取り込む占地になります。その点、土豪層の屋敷は、防御性というものをさほど重視していなかったせいでしょう。
なお、南屋敷の存在する小字「殿台堀込」とは、示唆的な字名です。すなわち殿台だけでなく「堀込」と続くのは、地表面から掘りこんでいる特徴に因むものと考えられます。
また、先述の若葉区殿台町の前畑・松葉、前田(稲毛区萩台町)の小字群ですが、中山法華経寺文書「日蓮聖教紙背文書」中の「寺山郷百姓橘重光訴状」に登場する論人(被告)寺山殿を彷彿とさせます。寺山殿の本拠地は、寺山の地(若葉区東寺山町・源町・みつわ台)のどこかにあったと思われますが、殿台は、寺山殿同様千葉氏を支えていた地域の小領主層の屋敷地ではなかったかと考えます。周辺の若葉区原町、貝塚町に見られる殿のつく小字は、こうした領主層の屋敷地であった可能性が高いと思われます。
一方、「百姓橘重光」は下人を抱えており、名主級の有姓の農民(文字通り百姓:ひゃくせい)だったと思われますが、こうした名主層は鎌倉時代、どのような屋敷に住まっていたのでしょうか。おそらく、本郷の小字地名の残る村落中心部に、塊村(かいそん)状に屋敷を構えていたのではないかと思います。
※塊村…とくに計画もなく、街路に依存することもなく、不規則に家屋が集合して塊状の平面形を示す集村をいう。〔日本大百科全書〕
遺構は見られずとも、地名から中世村落の復元に迫るやり方は有効だと思われます。ただ、残念なことに、千葉市では住宅地などの開発が進んでおり、かつての景観が損なわれていて、旧状を復元するのが困難です。せめて小字や通称地名などの聞取りによる保全が重要になると考えます。今回も『絵にみる図で読む 千葉市図誌』下巻(千葉市、1993年)を参考にしました。
33 大井戸館跡
千葉市若葉区大井戸町は、土気に源を発し印旛沼に注ぎ込む、鹿島川中流域の沖積低地に形成された集落です。この集落の一画に、38m×27mほどの小規模な方形館跡が存在します。なぜか同館跡は、平成の初期に行われた千葉県の城館跡悉皆調査(千葉県所在中近世城館跡詳細分布調査)では城館跡として掲載されていません。
しかし、筆者は外山信司氏と同行して、1980年代半ばに現地を踏査していました。また、後に知ったのですが、『さらしな風土記』(更科風土記研究会 1999年)には「大井戸館跡」として載せられています。
今回、同館跡をぜひこのコラムに掲載して、日の目を見させてあげたいと考え、本シリーズ(市内の城)の最後をこの大井戸館跡の記述で飾りたいと思います。なお、直近の現地踏査および写真は、外山研究員の手を煩わせました。
まず大井戸館跡の立地環境ですが、冒頭触れましたように土気に水源をもつ鹿島川中流域の左岸、標高20m弱の舌状に北東方向へ延びた段丘面に大井戸の集落があります。その中央西端にある大宮神社の北側に、同館跡は位置します。
 |
| 写真 西方向から大井戸館跡をみる(写真撮影 外山信司氏 2023年6月) |
|
|
| 写真 大井戸館跡西側土塁と空堀(撮影 外山信司氏 2023年6月) |
当地域は、中世前期の段階では白井荘に属していました。応永13年(1406)段階では、大井戸の下流1.2㎞ほどにある谷当(千葉市若葉区谷当町)は、円城寺近江入道が領有していました(「香取造営料足納帳」)。また、鹿島川支流弥富川流域にある、同じく白井荘に属する根古谷城(八街市根古谷)も城主円城寺氏の伝承を持っています。
大井戸館跡もこのような訳で、円城寺氏に関る領主の屋敷が元になった可能性があります。
しかし、遺構をみると、同館跡西側、すなわち金親町(千葉市若葉区)方面から注ぐ鹿島川支流に面した側に、小規模ながら堀と土塁を持っています。このことから、同館は戦国期の土豪のものであったと考えられます。
なお、谷当町には今は土取りで消滅した谷当城跡があったほか、鹿島川に面して堀の内、西に隣接して門田の小字があります。堀の内地名が必ずしも屋敷地を意味するものではありませんが、この門田は、まさに屋敷に隣接する領主の直営田(佃、御正作)であったのでしょう。ただ、前述の15世紀初頭に見られる円城寺近江入道との関係は、今一つ不明です。
ところで交通史的観点から大井戸をみると、小弓から千葉市若葉区中田町を経て、鹿島川支流の平川沿いに遡る「佐倉古道」(ルートは複数あるようです)が、大井戸集落の北側を通っています。また、金親町(若葉区)の金光院方面からの道も、同集落から支谷を隔てた西を通って谷当町方面に延びています。これらの道は、幹線とは言えないまでも、本佐倉城から四方へ延びる支線の一つと位置付けられると考えます。
このことは歴史的にみると、とくに小弓公方足利義明の存在した16世紀前半の永正~天文年間に、この経路が意味を持ってくることになると思います。『本土寺過去帳』には、永正14年(1517)5月に、「ヤトミ」(弥富:佐倉市岩富)で弥富原氏の朗久が討死しているとされます。岩富所在の寺院の過去帳では、永正16年6月に「坂戸押合」(佐倉市坂戸)にて朗久は討死したとあります。
永正14年10月には、真里谷武田氏は伊勢宗瑞の軍勢の助力を得て、三上氏を「三上城」(真名城:茂原市真名)から没落させています。そして、二日後には真里谷武田氏は小弓城を落として、小弓の原氏は小金(松戸市)へ逃れています。弥富原氏の朗久の討死を、『本土寺過去帳』の永正14年5月ととるならば、前年8月に三上氏が猪鼻城(千葉市中央区)を攻めた事件に関連して、三上氏による本佐倉城攻撃にともなう前哨戦であった可能性が考えられます。
茂原市真名から北上し、いくつかのルートはあろうかと思われますが、鹿島川(あるいは平川)水系に出て、大井戸を経て弥富方面に行くことは十分考えられます。もちろん大井戸館跡に拠って敵の軍勢と戦うには、同館は小規模(38m×27m)すぎるので戦略上の意味はあまりないと思われます。こうしたことから大井戸館跡は、平時は弥富原氏家臣層となるような大井戸集落の土豪の持ち城として、水陸交通の監視等に使われていたのかもしれません。
34 鹿島川流域の城 総論
千葉市内の城の紹介は、前回の大井戸館跡をもってひとまず終了となりました。続いて新シリーズとして「鹿島川流域の城」を始めたいと思います。今回は、総論としてなぜ鹿島川の城をとりあげるのか、説明したいと思います。
鹿島川は土気(千葉市緑区)に源流を発し、ほぼ北に向かって下り印旛沼に注ぐ、全長32㎞弱の一級河川です。中世において、中流域には白井荘が、下流の高崎川との合流点付近には印東荘が成立していました。戦国期に入ると、千葉市内より佐倉(中世の佐倉は酒々井町本佐倉・佐倉市大佐倉周辺)に千葉氏は本拠を移します。それが本佐倉城です。これ以降の千葉氏を、とくに佐倉千葉氏と呼ぶことがあります。
佐倉千葉氏にとって鹿島川は、長大な天然の堀の役割を果たすことになります。今でこそ鹿島川の流路に沿った美田が眺望できますが、近代に入るまでは、鹿島川の流れは蛇行を繰り返し、氾濫原が広がっていました。ですから、最大七、八百メートル幅の谷底(こくてい)平野を渡るためには、どの場所でも、というわけにはいかず、古来より一定の場所に限られてきました。
例えば、古代の古東海道と同じような経路をたどったと思われる近世成田街道は、佐倉市馬渡で鹿島川を渡っていました。このことは、平安末期、源頼朝の挙兵に従った千葉氏を討伐しようと、匝瑳北条(現匝瑳市)より千田親雅が兵を引き連れ、千葉氏の本拠を襲う経路にも登場します。この時の経路は、『源平闘諍録』(『平家物語』の異本)によれば、以下の引用の通りです。
平家の方人千田の判官代藤原の親正、(中略)匝瑳の北条の内山の館より、右兵衛佐(源頼朝)の方へ向はんと欲す。(中略)一千余騎の軍兵を相ひ具して、武射の横路を越え、白井の馬渡の端を渡つて、千葉の結城へ罷り向ひけり。
現在の匝瑳市内山の館を出た親正は、台地際の道(現在の国道126号線より台地寄りか)を南下したと考えられます。山武市富田(旧成東町富田)から台地上に上がり(「武射の横路」)、境川を渡って山武市埴谷を経て、佐倉市岩富から同馬渡に向かい、馬渡で鹿島川を渡ったものと思われます。馬渡からは、親正はほぼ国道51号線に沿うような古東海道以来の古道を千葉市内に向かい、結城浜(現在の千葉市中央区神明町・新宿周辺)で迎え撃った千葉成胤と合戦をすることになります。
このように平安末期には、古代の古東海道の重要な渡河点としての馬渡が確認されます。ですので、国道51号線の旧道沿いに展開する馬渡の集落(宿)は、少なくとも中世前期には成立をしていたものと考えます。
このほかにも、鹿島川の渡河点はいくつか考えられますが、これらにはほとんどと言ってよいほど、中世城館が組み合わさっています。こうした城館跡は、佐倉千葉氏の領域の出入り口を防衛するなど、それぞれ存在理由を持っていると考えます。本シリーズでは、これらの城館跡を、主に同氏との関係から探ってみたいと思います。
 |
| 写真 下流からみた馬渡(向って右が千葉方面:左が成田方面) |
佐倉千葉氏の成立した戦国期において、この鹿島川が焦点となったことは幾度かありました。まずは、16世紀初頭の「篠塚の陣」の時です。古河公方足利政氏・高氏(後の高基)父子が、千葉孝胤を討伐するため、古河を出て篠塚(佐倉市大篠塚・小篠塚周辺)に足かけ三年もの間、陣を敷いていたというものです。
次に焦点となったのは、小弓公方足利義明の時期です。永正18年(1521)6月ころ、安房の里見氏が義明の命によって、本佐倉城周辺を攻撃し、和良比堀込城(四街道市和良比)に帰還したと考えられています。この頃は、臼井氏も小弓方に付くことになり、鹿島川を挟んで古河公方足利高基方の佐倉千葉氏と小弓公方足利義明方の臼井氏との緊張状態が続いたものと思われます。大永2年(1522)8月、当時義明方の小西原氏家臣が「佐倉ニテ」討死したと『本土寺過去帳』に記録されており、本佐倉城周辺で合戦があったことを知る唯一の資料となっています。
小弓公方滅亡後は、安房の里見氏が下総まで攻め込むことが何度かあり、臼井周辺が里見氏の攻撃を受けたこともありました。こんどは里見氏の北上の危険性が高まってきました。
しかし、里見氏に鹿島川を越えて攻められたことは、少なくとも資料上では確認できないのでなかったものと思われます。
以上のように、鹿島川は戦国期佐倉千葉氏にとって、本拠本佐倉城の重要な防衛線であったことがわかります。それでは、同川両岸に並ぶ城館跡について、本シリーズで逐次紹介していきたいと思います。
35 大篠塚城跡 (佐倉市大篠塚)
鹿島川は馬渡を過ぎてから西北西方向に流れを変えますが、同川右岸の台地が西に向かって、猪の鼻のように突き出していて、川の流れはこれを取り巻くように西北西から北東へと、ほぼ90度変えます。
大篠塚城跡は、この真西に突き出した台地の南面の、ちょうど台地がほぼ直角になった角地に占地しています。崖面に向かい緩やかに傾斜した角地を削平し、城の居住面である平坦面を造り出したため、背後の台地続きから城内を見おろせるような構造となっています。これを防ぐため、背後の台地続きに空堀を入れ、さらに城内部を見透かされないように高土塁を造成しています。城内から土塁頂部までの高さは、5mほどを測る大土塁となっています。
この城は南面する鹿島川の谷底平野と、対岸とを結ぶ渡河点(四街道市山梨字東向井と大篠塚)を睨むように立地しています。ちなみに、対岸にあたる四街道市山梨字には、東向井城跡があり、渡河点両岸にそれぞれ城が築かれていることになります。もちろん、本城の役割はこれだけではなく、鹿島川を遡上する河川交通を監視する役目を負っていたことは十分想定できます。なお鹿島川の河川交通については、別項にて詳しく分析する予定です。
 |
| 写真 南東方向よりみた大篠塚城跡(中央やや右寄り) |
さて、本城の造られた時期はいつ頃に求められるでしょうか。そこで重要だと考えられるのが、佐倉市石川の追分(岩富・東金方面と山梨・千葉方面の分岐点)より西南西方面(山梨・千葉方面)に分かれた道です。残念ながら、石川追分より大篠塚に延びるこの道は、東関東自動車道の建設によってほぼ消滅してしまいました。しかし、明治時代に作成された「迅速測図」におれば、石川からの道は本城を巻くようにして、鹿島川を渡って四街道市山梨に向かっています。現在も大篠塚から対岸四街道市に渡る道は、ほぼ明治時代の迅速測図に記載された道を踏襲しています。
本城は、構造的にみて背後からの攻撃には弱いといわざるをえません。背後からの攻撃はあまり想定しておらず、鹿島川とその渡河点を睨んだ構造といえます。とすると、その役割を発揮できた時期として、まずは篠塚陣をあげることができます。
篠塚陣とは、ようやく近年になって、その存在が実証できたという歴史的出来事です。それまでは『千学集抜粋』に記載されるのみで、事実を証明する確固たる史料がなく(傍証は可能であっても)、その存在が今一つ明確にできませんでした。ところが「篠塚陣」という文言の記載された文書が発見されたことで、実在が証明されました(滝川恒昭「戦国前期の房総里見氏に関する考察-新出足利政氏書状の紹介と検討を通じて-」『鎌倉』119号 2015年)。
それは足利政氏・高基(当時は高氏を名のる)父子が、本佐倉城に拠る千葉孝胤(のりたね)を討伐するため、佐倉市小篠塚・大篠塚一帯に陣をとり、文亀2年(1502)から永正元年(1504)までのあしかけ三年(ただし途中で古河へ帰った時期もあるとされる)にわたって在陣したものです。長い期間、篠塚に在陣したものですから、政氏は大勢の家臣を引き連れており、行政府として篠塚の地が機能していたことが想定されます。
こうしたなかで、大篠塚城はどのような役割を果たしていたのでしょうか。前述したように、構造的にみて本城は台地続きからの攻撃に弱いといえます。もし本佐倉から孝胤の軍勢が攻めてくるとしたら、台地続き方面からでしょうから、本城の高土塁はこうした事態を想定して盛られていると思われます。もっとも千葉氏にとって、古河公方はこの時点で半世紀にわたって仕えてきた主君ゆえ、積極的な攻撃をしかけたかどうかは疑問ですが。
あとは、政氏側に仕えていた臼井氏一族が守備する鹿島川左岸(西側)の城とともに、河川交通および渡河点を監視する役目を負っていたと思われます。というのも、常総内海(香取の海)から武相内海(東京湾)へ水運を使い物資を運ぶには、印旛沼に入り、鹿島川をさかのぼって現在の国道51号線近くにある荷揚げ場(馬渡馬場館跡の位置)へあげ、陸路千葉湊へ運搬するのが早い方法と思われるからです。さもなければ、関宿近くまで舟で運び、太日川(現在のほぼ江戸川に相当する中世段階の川)を下って武相内海へ出る方法が考えられますが、遠回りになります。政氏陣営に印旛沼から鹿島川に入り、陸路千葉へ運ぶ経路を抑えられてしまうと、この関宿経由の方法をとらざるを得ません。
浜宿湊を外港とし、領域経済に大きくていたと想定される千葉氏にとって、香取内海から印旛沼(当時は印旛浦と呼ばれる)に入る舟が減ることは、経済的に大きなマイナスになったはずです。大篠塚城が鹿島川水運を抑えるということは、単に軍事面だけでなく、経済面でも意味があったと考えられます。
次に、歴史的に本城が機能を発揮したと思われるのが、篠塚陣より20年ほどたった永正18年(大永元)の小弓公方足利義明(道哲)による本佐倉城攻めという事件が起きた時になります。こちらについては、「研究員の部屋(遠山)特別展 その7道哲が本佐倉城を攻めさせたのは事実か」に書きましたので、詳しくはご覧いただければと存じます。四街道市和良比の和良比堀込城が登場する文書があり、本佐倉城(酒々井町・佐倉市)の近辺を攻めた里見上野入道が和良比堀込城に帰陣したという内容です。四街道から陸路で本佐倉城を攻めるには、鹿島川を渡河しなければなりません。その一つの候補が大篠塚城と東向井城との間の道だったと思われます。
このように、小規模な城郭にも、以上みてきたような歴史的背景が想定できます。大規模であったり、高度な縄張構造を持つ城郭にばかり目がいきがちですが、何の変哲もないような小さな城館にも、存在理由(レーゾンデートル)があるものです。こうした城たちの無言の「声」を聞き逃さないようにしたいものです。
36 馬渡馬場館跡
鹿島川左岸の佐倉市馬渡には、二か所館跡が残ります。国道51号線をはさんで、北側の馬渡集落にある馬渡館跡と、南側の馬渡馬場館跡です。後者は馬渡字馬場にある真言宗千蔵寺の境内となっています。短軸30m、長軸50mほどの小規模な館跡ですが、西と北には土塁と堀をともなっています(空中写真では、現在通路となる南側にも空堀が認められる)。
馬渡館跡の方は集落の中にある、北側に河岸段丘面をもつ武士の屋敷と評価できると思います。一方、馬渡馬場館跡の方は馬渡本村からは少々離れており、別の役割があろうかと推測されます。渡河点を守るという考え方もあるようですが、ここでは字馬場に注目してみ
ましょう。
 |
| 写真 国土地理院空中写真(MKT617-C3-21)1961年9月28日撮影 写真中の黄色矢印先端部が馬渡馬場館跡の位置。画面左中央下辺より、斜め右上に向かう道路が国道51号線の旧道にあたる道。 |
馬場という地名には、いくつかの意味があると考えます。一つには、武士の屋敷の近くに設けられる馬の調練場、他にも神社の神事で流鏑馬を行う場所につく場合があります。また物資の積み下ろしをする場所にもつけられる場合があります。
馬場館跡のある現国道51号線の南側一帯は、字名を馬場といいます。ここでは、鹿島川水運で運ばれた荷を、馬などに積み替えて国道51号線とほぼ同じ経路で千葉まで運んだと考えられます。実際に鎌倉時代には、現在の東庄町から旭市北部にかけて存在した称名寺領荘園上代郷(かじろごう)の年貢を、香取内海水運を使い印旛沼(中世当時は印旛浦と呼ばれ入り江だった)から鹿島川に入って、馬渡馬場まで舟を使い運んできたものと考えられています。
室町時代に入ると、称名寺領荘園も実質的に消滅してしまいますが、香取内海からの物資や東京湾方面からの物資が、最短経路であるこの経路で行き来していたものと思われます。その意味で、戦国期の造作になると思われる本館跡も、物流の拠点を防衛する意味を持たされていたのかもしれません。もちろん渡河点を防衛する機能もあったでしょうが。
実はこうした物流の拠点につく馬場地名は、県内でいくつかの例があります。馬場地名に関して、いずれ別稿で述べたいと考えています。
37 太田要害城跡(佐倉市太田)
太田要害城は、高崎川との合流点より直線距離で約2.7㎞上流の、鹿島川右岸の台地縁辺に位置しています。川を挟んだ400mほど対岸に、四街道市亀崎地区の突出した段丘面があり、最も両岸が狭まった地点となります。15世紀初頭の千葉氏被官の中小領主層の所領分布およびその面積などの載る『香取造営料足納帳』によれば、当城跡の周辺には「大和田」と「亀崎」の地名が存在しています。大和田は太田の古名とされ、亀崎は対岸の四街道市亀崎と考えられます。なお、匝瑳市にも亀崎地名があり、『納帳』に載っていても不思議ではありませんが、大和田と亀崎がセットで載るのは、鹿島川の重要な渡河点となる地を千葉氏被官が所領として有していたことを意味するものだと考えます。
太田要害城の「要害」は、天険の地を表すことから、そこに籠って戦うという意味で城を意味するようになりました。なお、正しい小字は用替(ようがえ:要害の転訛)です。南北朝時代に入ると、地名+要害で文書史料に頻出するようになります。本城跡は史料には登場しませんので、いつ頃築城されたかは不明です。しかし、交通史の面から考えると、佐倉市内を通過する「下総道」は、初期の頃、現在の国立歴史民俗博物館の台地下の鹿島橋の位置を渡れずに、南に迂回して太田と亀崎、もしくは大篠塚と四街道市山梨字東向井を渡っていた、と考えられています(高橋健一「戦国時代佐倉の鹿島宿」『旧国中世重要論文集成 下総国』戎光祥出版、2019年、初出1992年による)。
この下総道は、戦国後期には香取市下飯田(旧小見川町)の森山城と江戸城を結ぶ道として史料に現れます(小笠原長和「徳川家への献上柑子」『中世房総の政治と文化』吉川弘文館、1984年、初出1960年、および遠山成一「戦国後期下総における陸上交通について」同前『旧国中世重要論文集成』、初出1994年)。下飯田からは府馬(香取市)-鏑木(旭市)-大寺(匝瑳市)-多古(多古町)-佐倉(酒々井町本佐倉)-臼井(佐倉市)-大和田(八千代市)-船橋(船橋市)-八幡(同前)-市川-松戸-葛西(東京都葛飾区)-浅草(同)、そして江戸城へとつないでいます。安土桃山時代から江戸時代初期、柑子ミカンを江戸城の家康の元へ献上するために使われていた経路です。この経路は中世前期から存在したと思いますが、初期の下総道の臼井・佐倉間は、現在の国道296号線のように佐倉市角来と同田町間の現鹿島橋の所在地を渡河したのではなく、南へ迂回し太田と亀崎を渡っていたものと私は考えます。その理由は、鹿島川下流を渡河することが、初期の頃は後背湿地の広がりによって困難であったからと考えるからです。しかし、戦国時代後期になると、近世佐倉城跡と重複する位置にあった鹿島城跡の存在から、最短距離で臼井と本佐倉城を結ぶ経路である角来と田町の間が渡河できるようになったのではないでしょうか
私が、下総道は初期に太田・亀崎間を渡河していたと考えるのは、本城跡の北東に「宿」そして「馬場」地名が残ることも一つの理由です。古来より、ある程度の大きい川の岸辺には自然発生的に宿場が形成されるとされます(新城常三『鎌倉時代の交通』吉川弘文館、1995年)。馬渡の宿がまさにその例です。太田の宿もそのようなものであり、いわゆる城下集落として扱われる宿とは、性格が異なるものです。
さて、太田要害城跡の構造は、台地が鹿島川方向に突出した部分を利用し、台地とは土塁と空堀で区画した単郭の城です。前項の大篠塚城跡が緩傾斜地の先端を利用したため、城郭の背後が城の平面より高くなってしまったのとは異なり、本城跡はほぼ同一面で崖面近くまで等高線が伸びており、堀と土塁で十分防御できます。しかし、単郭の構造からは、領域支配ではなく、渡河点および河川交通の監視としての役割が窺えます。
また台地と城域を分ける土塁と堀の北端は台地側に櫓台状に突出しており、城郭用語でいう「折(おり)」となっています。これは敵の攻撃に対して、敵の側面(とくに楯をもつ左側ではなく、防御が難しい右側面)を狙う-これを「横矢をかける」といいます-目的で設けられるものです。こうした折をもつ城郭は、戦国時代になると多く見られるようになります。
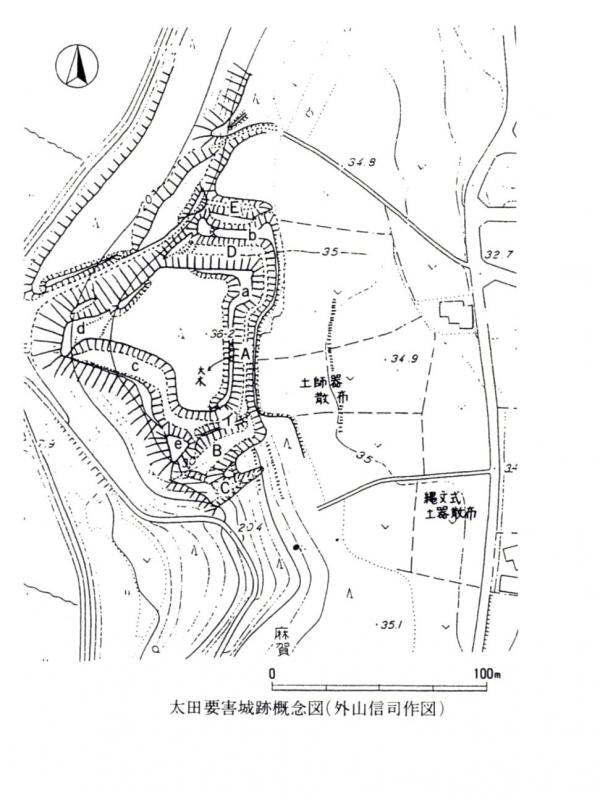 |
| 図は『千葉県所在中近世城館跡詳細分布調査報告書Ⅰ-旧下総地域-』より |
前々項(35 大篠塚城跡)でも述べましたが、1500年代の前半に、小弓公方足利義明が成立し、まもなく古河公方陣営にいた臼井氏が義明側に帰属してしまいます。臼井氏は、古河公方足利高基側についていた本佐倉城の千葉氏とは、敵対関係になったわけです。まさに鹿島川流域を境に両陣営が睨みあうことになりました。この状況下、里見上野入道による「敵城(本佐倉城と見なされる)近辺」の攻撃があったわけです。この時期には、既に本城は築かれており、機能していたと思われます。
戦国後期には、里見氏の北上によって千葉氏領国が脅かされるようになると、本佐倉城を本拠とする千葉氏にとって、鹿島川流域は重要な防衛ラインになりました。しかし、実際に鹿島川流域まで攻め込まれたという史料は残っていませんので、里見氏と千葉氏との当該地域での衝突はなかったものと思われます。
こうしてみると、本城跡は戦国時代後期まで存在意義はあったものと考えられます。
概念図は、外山信司氏の図(『千葉県中近世城館跡詳細分布調査報告Ⅰ 旧下総国地域』千葉県 1995年)をお借りしました。
令和5年度特別展「関東の30年戦争『享徳の乱』と千葉氏-宗家の交代・本拠の変遷、そして戦国の世の胎動-」あ・ら・か・る・と
その1 平山城跡補遺
先に平山城については、遠山の研究員の部屋「中世の城跡をめぐる」の№3で取り上げました。今回特別展「関東の30年戦争「享徳の乱」と千葉氏」開催にあたり、平山城跡を本格的に踏査できましたので、その成果を述べたいと思います。
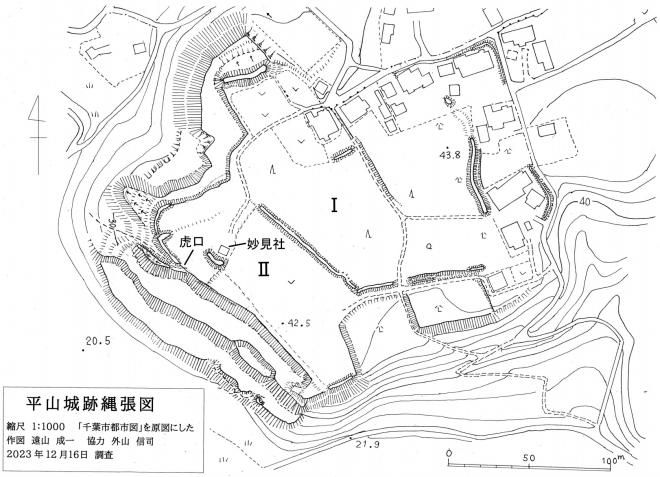
一番の疑問点であったのは、台地基部を隔絶する堀・土塁がなかったのか、という点でした。これまでは民家の密集地を抜けて山林に入るわけにいかなかったので、これを確認することができなかったのです。しかし、今回は当館の調査として、ご地元の方の許可をいただいて、内部まで調べることができました。その結果、台地を隔絶する土塁と堀跡一部を確認することができました。これにより、平山城の疑問点が解決しました。しっかりとした堀と土塁で、台地続きに侵入する敵を防ぐことが可能です。折の入った堀と土塁は完存しているわけではないのですが、ほぼ復元することができます。
しかしながら、全体的な縄張構造をみると16世紀の初頭の様相を示しており、文明年間に本佐倉城へ移転した千葉宗家は、その後、本城を常設的に使うことがなかったであろうことを裏づけます。例えば現在みることのできる堀幅は、上幅で4~5mほどで、民家建設による改変は考えられますが、戦国後期の城にともなうものとは思えません。
本城は、『千学集抜粋』の次の記述から、馬加康胤によって築かれたと考えられています。
(前略)康胤御子胤持、輔胤、孝胤、勝胤まて以上五世ハ、平山におはしけれハ、平山より御参詣ありて、(後略)
康胤は、康正元年(1454)11月に馬加城を落とされて千葉へ逃げ込み、さらに千葉を追われて平山に入ります。しかし、康正2年10月には東常縁によって市原八幡で討ち取られています。ですから、平山にいたのは一年にも満たない期間となります。ですので、康胤が築いたとしても今見ることのできる平山城とは異なった、簡素な構造ではなかったかと推測されます。
本格的に築城したのは、「岩橋殿」と呼ばれ、「岩橋(酒々井町)へ御上り也」と記された輔胤ではないかと考えます。そして、彼の連れてきた家臣団は、新しく造られた「宿」地区に居住したと考えます。前にも述べましたが、平山の宿は、県内の他例の中では、きわめて異例な地割をとっています。県内70例ある宿地名(屋号等も含む)のうち、ほとんどが道路に垂直に短冊地割(間口が狭く奥行きが長い敷地)をとるのに対し、平山の場合は道には関係なくブロック状が不規則に並ぶ形をとります。管見の限りでは、70例のうち唯一です。
文明16年(1484)頃、孝胤は本佐倉城を築きます。その後、まったく平山城が使われなかったかどうかは不明です。しかし、立堀城跡(緑区平山町)の存在から、戦国後期には平山城の存在価値は失われたものと推測できます〔立堀城跡については「中世の城跡をめぐる」№16をご覧ください〕。すなわち、小弓から旧東金街道に合流して佐倉方面を結ぶ、戦国期の古道を抑える格好の位置にある立堀城に比べ、この道から500mほど奥へ入った平山城の存在価値は小さいと言えるでしょう。縄張構造的にも、単郭ではありますが、立堀城の方が技巧的と言えます。
とくに、永禄から元亀年間にかけて、里見氏(正木氏が主体)の攻勢が続き、小弓の城(北生実城と南生実城の両方か)が里見勢に落とされたこともありました。小弓から佐倉方面に攻め込むことが、この街道を使えば可能です。本格的な里見勢の佐倉方面への進撃があると仮定すると、単郭の立堀城跡ではそれを食い止めるのは不可能かと思います。こうした事態が起これば、平山城にも兵力が詰められた可能性も考えられます。しかし、そうした事態に備えて平山城に手を入れた形跡も見当たらないので、そこまでは里見勢も動かなったのでしょう。
最後に、本城跡の探索は、くれぐれも地元の方からの許可をいただいたうえでお願いします。
(遠山成一)
その2 円城寺氏について1
享徳の乱で原氏と戦い敗れ、下総を追われて武蔵へ逃れた円城寺氏は、戦国後期になると千葉氏の家臣として下総へ復帰します。円城寺氏は系図上では日胤の跡を継いだことになっています。今回(2/16~3/3)展示させていただいた「圓城寺系図」(展示資料2-1-12)では、円城寺を名のる最初の人物は図書允貞政(ずしょのじょう さだまさ)となっています。
貞政は「円城寺氏を継いで千葉介の家臣第四に列する、下総国八木城に居城し、武功あり」と同系図には記されています。そして系図上では、貞政は千葉常胤の代にいたとされますが、同時代史料で円城寺氏が確認されるのは、早くとも鎌倉時代の終わり頃です。横浜市の「金沢称名寺文書」に、千田荘東禅寺(多古町寺作)の長老湛睿(たんえい)書状として「又土橋寺事、千葉介、図書左衛門、御寺方へも遣状候」とあり、この図書左衛門が後ほど触れます円城寺氏です。時代的には、ほぼ鎌倉時代末から南北朝初期と人物と考えられます。
ところで、貞政の貞は千葉貞胤の偏諱(主君の実名の一字をもらい受けること)と考えられます。実際、「田所家文書」(『千葉県の歴史 資料編 中世2』)には、円城寺図書右衛門入道に宛てた千葉貞胤書状案があります。これは建武政権が建武元年(1334)8月に発した徳政令の内容を、在京していた貞胤が下総にいる図書右衛門入道に知らせて、この法を守るように伝えたものです。この円城寺図書右衛門入道こそが系図に載る円城寺貞政その人だと考えます。
そして、同じく「田所家文書」には「九 徳政令につき香取文書具書案」の続きに、沙弥蓮一奉書案」が載ります。これは同年九月三日付で沙弥蓮一が香取政所の留守所へ「自下総守殿御状」、つまり前出の千葉胤貞書状案(の内容)を香取社家へ披露しなさい、としています。沙弥とは在家のまま髪を落とし仏道修行している人のことをいいますので、蓮一は図書右衛門入道を指すと考えられます。そして書き止めの文言は「仰せにより執達件の如し」となっており、この文書は上位者(下総守兼下総守護ヵ千葉貞胤)の意を奉じて、下位者(香取政所留守所)へ宛てたものとできます。つまり、蓮一(円城寺図書右衛門入道)は守護代的な地位にいることがわかります。こうしてみると、円城寺貞政が貞胤の偏諱を受けていることに納得できると思います。
ところで、ややこしいことに先ほどあげた者の他、少し下った時代の人物で「図書左衛門」の官途名を名のる円城寺氏も存在するのです。それは円城寺図書左衛門源胤朝という人物です。胤朝は、永和2年(1376)2月15日付の多古町妙光寺の日蓮坐像胎内銘に大檀那として記載されます。また、数年前の応安5年2月日付で中山本妙寺(後の中山法華経寺)の日祐に宛てて、千田義胤の意をうけた奉書を出しています。こちらも「図書左衛門尉源胤朝」の署名で「仰せに依り件の如し」としています(「中山法華経寺文書」『千葉県の歴史 資料編 中世2(県内文書1)』)。前述の湛睿書状に出てくる図書左衛門と同じ官途名を名のるので、胤朝の先祖にあたる、多古に所領をもつ円城寺氏と考えてよいと思います。
 |
|
写真 島城跡遠景(栗山川・借当川合流点「並木のふけ」より) 現香取郡多古町島。 画面左に位置する「妙光(現正覚寺)ニテ」千葉胤直は自害した。(撮影 遠山成一) |
このように南北朝後期の千田荘には、「源姓」を名のる円城寺氏がいたことになります。本来、常胤の子日胤の後裔を標ぼうするならば平姓のはずです。実際、今回の展示でも「芝山観音教寺宝塔銅造棟札(複製)」および「竜腹寺宝塔銅造棟札(拓本)」に、円城寺肥前守平胤定が記載されています(展示資料1-2-3および1-2-5)。
また、他例では明徳元年(1390)10月15日付で円城寺ひやうへ三郎源満政が、香取社の社家である録司代家で文書などが盗まれたことを報告する披露状(「旧録司代家文書」『千葉縣史料 諸家文書』)を発給しています。さらに15世紀初頭の応永年間に作成された「香取造営料足納帳」(展示資料2-1-2)には、「円城寺源へ(兵)」、「円城寺源内左衛門」がいて、源姓の可能性があります。
ところで、平姓と源姓の円城寺氏がいるということは、どういうことでしょうか。先の円城寺図書左衛門源胤朝は、日蓮坐像胎内銘に大檀那である胤朝本人と並び「平氏女図書母」が記されています。つまり、胤朝の場合は、円城寺氏である母と源姓を名のる父をもつのではないかと考えます。他例も同様か、縁戚関係などで円城寺を名のったと思われます。先にあげた「香取造営料足納帳」には千葉荘・印東荘・千田荘・白井荘などに円城寺氏一族が散在しています。つまり、円城寺氏という一族は、日本史でいう、南北朝時代に血縁的一揆集団から地縁的一揆集団へと変化していくという流れを、まさに体現している一族ではないでしょうか。もともと、系図上でも千葉氏庶家から分かれた白井氏・鏑木氏一族に、円城寺氏の出自が求められます。この点、ライバルであり、円城寺氏が滅ぼされることになる原氏は、千葉氏胤の子で惣領満胤の弟にあたる胤高から出ており、対照的です。
次の「円城寺氏について その二」では、享徳の乱の起きる頃までに見られる円城寺氏について考えてみたいと思います。
(遠山成一)
【参考文献】
外山信司・遠山成一「岩富原氏について」(石橋一展編著『中世関東武士の研究17 下総千葉氏』戎光祥出版、2015年(初出『房総史学』26号、千葉県高等学校教育研究会歴史部会、1986年)
遠山成一「室町前期における下総千葉氏権力構造についての一考察-「香取造営料足納帳」の分析を中心に-」(前掲石橋『下総千葉氏』所収、初出『千葉史学』16号、千葉歴史学会、1990年)
遠山成一「円城寺氏について」(中世房総史研究会編『中世房総の権力と社会』髙科書店、1991年)
その3 円城寺氏について2
ここでは、享徳の乱前夜に出された円城寺氏に関ると考えられる二通の文書を紹介いたします。
まず一点目ですが、「香取旧大禰宜家文書」のなかに、姓未詳「前下野守胤仲」の土地打ち渡し状があります。日付は享徳3年(1454)6月13日付けで、以下のような内容です。
下総国香取神領の小野・織幡両村の事について、(主君の)病気治癒祈願として今月9日に出した寄附状の内容のとおり、土地を大禰宜胤房代官にお渡ししました。(病気治癒の)御祈禱については先例のとおり、処理してください。
この前下野守直仲は、私にとっては長い間謎の人物となっていました。ところが、ある研究会の席上、石橋一展氏から円城寺氏ではないかと思われる、という報告をいただき、即座に合点がいきました。
まず享徳3年6月13日の日づけですが、享徳の乱の始まる同年12月27日の半年ほど前となります。そして、主君の歓楽(病気)といえば、千葉胤将の亡くなるのが同年6月23日(『本土寺過去帳』)です。これが胤将に関るものだとすれば、打ち渡し状は亡くなる10日前に出されたことになります。
そして、前下野守の受領名は、今回展示した円城寺文書の「足利成氏書状」の宛所が円城寺下野守であり、なおかつ『本土寺過去帳』十二日条に千葉宣胤とともに亡くなった「圓城寺下野妙城」と同一です。つまり、前下野守直仲とは、この円城寺下野守のこととして間違いないでしょう。実名の直仲も、千葉胤直の偏諱とすることができます。
このことから見えてくるのは、円城寺下野守直仲は、胤直の偏諱を得て腹心でしたが、胤直が家督を胤将に譲ってからは、胤将に仕えたということです。そして胤将が享徳3年(1454)6月に亡くなると、再び胤直(この頃は入道しており常瑞を名のる)に仕えました。
前述「足利成氏書状」の内容は、上総国二宮荘(茂原市北西部)長尾郷に関して円城寺下野守が「申上旨」に対し、成氏は長棟(上杉憲実)が参上してから話し合い、(成氏の)安堵状(御判)を出すようにする、というものです。
長尾郷に関し「申上」げた内容とは、長尾郷の領有を求めたと考えられます。この書状の発給年は未詳ですが、宝徳年間と考えられています。宝徳年間には、既に千葉胤将が家督を継いでおり、胤将は足利成氏の忠実な配下として活躍しています。そして、円城寺下野守は胤将の守護代的立場で、成氏に「申上」げたものと考えられます。
胤将は文安3年(1446)4月に、上総国坂田(現横芝光町坂田)の霊通寺に宛てて紛失状(「千葉胤将紛失状」神保誠家文書)を発給していることから、上総国の守護職を持っていたと考えられています。ちなみに、文安3年は胤直から胤将に代替わりしたとされています。
こうしてみると、円城寺下野守直仲は、下総国守護で上総国も兼任していた胤将の守護代的立場にあったと考えることができるのではないでしょうか。
もう一点円城寺氏と思われる書状は、これもまた石橋一展氏からのご教示によりますが、宝徳2年(1450)10月27日付、姓未詳源壱岐守直貞寄進状です。本状は本妙寺(後の中山法華経寺)に宛てて、風早荘平賀(松戸市)の年貢のうち毎年二結(二貫文)を本妙寺に寄進することを約したものです。
源直貞を円城寺氏と考える理由は、(一)実名の「直」は胤直の偏諱の可能性があること、(二)源姓円城寺氏の存在が明らかであり、なおかつ千田氏に仕えていた円城寺図書左衛門源胤朝が中山法華経寺日祐に対し、八幡荘谷中郷(市川市中山・若宮・高石神)を千田義胤の命を奉じて安堵していること、があげられます。さらに(三)直貞の受領名壱岐守は、前述『本土寺過去帳』十二日の条に、円城寺下野妙城とともに壱岐守が記載されていて、これは直貞本人を指すと考えられるからです。
源姓円城寺氏が、東葛飾地域の八幡荘・風早荘に所領を有していた可能性があり、この点において小金周辺に地盤のあった原氏と競合関係にあったのではないでしょうか。これが享徳の乱において、原氏と円城寺氏が衝突した一つの原因となっていると思われます。
(遠山成一)
【参考文献】
石橋一展「千葉胤将の家督継承と死去」(『室町遺文』月報5 関東編第5巻、東京堂出版、 二〇二二年)
その4 多古城と島城
康正(こうしょう)元年(1455)8月12日と15日の両日、千葉を追われ千田荘多古に逃げていた千葉胤直・宣胤(のぶたね)父子は、多古城と島城でそれぞれ自害しました。『鎌倉大草紙』によれば、12日には宣胤が多古城で、15日には胤直は島城を追われ、土橋如来堂(多古町寺作)でそれぞれ自害したとされます。土橋如来堂とは多古町寺作の土橋山東禅寺の一堂とされ、東禅寺にある五輪塔は「伝千葉胤直墓」として町指定史跡になっています。
ところが、事実はそうではなかったことが、川戸彰氏によって明らかにされました。氏は『本土寺過去帳』15日条にある胤直の記事から、胤直の自害した「妙光ニテ御腹被召」の文言を手がかりに、「妙光」が島の本覚山妙光寺であることをつきとめました。つまり、島から栗山川を使って上流の多古町寺作にある東禅寺に逃げたわけでなく、島城に西に隣接する現正覚寺(写真1参照)で自害した、ということです。
島妙光寺は、茂原市の藻原寺(そうげんじ)(旧妙光寺)の日向(にこう)門流の僧が南北朝期に開基したものです。ところが同寺は明治41年(1908)に長崎県に移転しており、その跡地には成等山正覚寺が建立されています。邪教として幕府より厳しい弾圧を受けた妙光寺は、不受不施派から受布施派に転向せざるを得ませんでした。ところが、明治時代となって不受不施の教義が許されると、潜伏していた不受不施派の信者たちは、受不施に転向した妙光寺を受け入れなかったため、長崎県へ移転していったとのことです。
一方、宣胤は『鎌倉大草紙』によれば、「城外のむさといふ所の阿弥陀堂」で自害したとされます。「城外のむさ」とは『多古町史』には「ゐさ」(居射)の誤伝の可能性を指摘しています。多古町多古の小字で居射があり、多古城から出てここにあった阿弥陀堂で自害したと思われます。
『本土寺過去帳』12日条には、「五郎殿十三歳 千葉介宣胤法名妙宣」と記載されますが、
死亡した場所は書かれていません。ただ、一緒に列記される人物として「常陸大充殿妙充 同子息」とあり、常陸大掾(だいじょう)父子が死亡していることが目を引きます。これは上杉方として、胤直父子らの援軍に駆け付けたものの、島城で討死したか自害したものと思われますが、逆に胤直らを攻めて討死したという考えも出されています。
同じく「圓城寺下野妙城 同壹岐守妙宣 同日向守妙向」とあり、円城寺氏が三名並べられています。前回の研究員の部屋「その3 円城寺氏について2」で書いたように、円城寺下野守直仲と円城寺壱岐守直貞のこととして間違いないと思われます。
ちなみに嘉吉2年(1442)に千葉胤直・胤賢兄弟が大檀那となり造立した、芝山観音教寺(山武郡芝山町)および印西龍腹寺(印西市竜腹寺)の宝塔棟札に載る円城寺肥前守平胤定は、記載されていません。代替りで一線から退いたか、享徳康正の変の起こる以前に死去していたかと思われます。
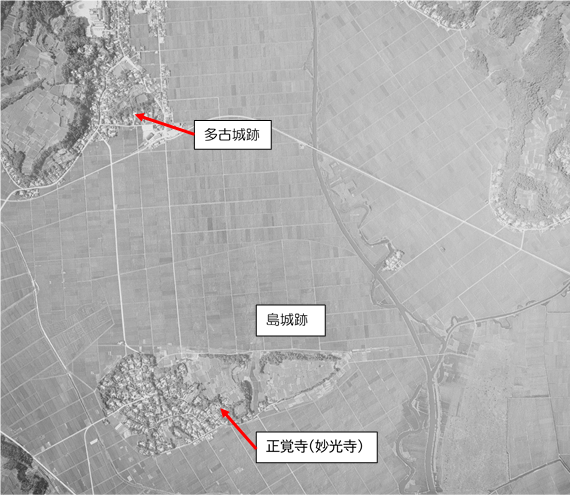 |
|
〔写真1〕 国土地理院空中写真 1963年7月27日撮影 |
ところで、『鎌倉大草紙』の記述から、従来、享徳康正の変が勃発したのは享徳4年(1455)3月のこととされていました。しかし、最近の長塚孝氏らの研究により、享徳4年7月のこと(直後に康正元年に改元)とするのが正しいと考えられるようになりました。確かに、3月から滅びる8月まで5か月近くかかっており、疑問を感じることがありました。
7月に千田荘に逃げたとすれば、わずかひと月足らずで多古城・島城は陥落したことになります。これは城郭の縄張をみれば、得心がいくところです。とくに多古城に関しては、現在は多古町の切通地区の台地縁辺部にわずかに空堀が残るだけとなっていて、縄張構造が不明でした。しかし、戦後間もなく撮られた空中写真では、台地から東へ突き出した部分に、はっきりと曲輪の存在が認められます(上記写真2)。
 |
| 〔写真2〕 多古城跡 国土地理院空中写真 1948年9月26日撮影 台地先端より台地続きまで、3から4郭構造だったと思われる。台地縁辺部には逆コの字形の堀切が、畑地となって現存する。 |
台地先端の東端の曲輪が主郭(近世城郭でいう本丸部分)にあたると思いますが、城郭として小規模であることがわかります。この縄張構造をみれば、5ヵ月も持ちこたえることは困難であったと思われます。
今回の特別展では、残念ながらこれまでの説で展示しましたが、今後は享徳康正の変の勃発に関して、享徳4年3月説から同7月説に変更せねばなりません。
(遠山成一)
【参考文献】
川戸彰「千葉介胤直と妙光寺」『中世房総』第10号、中世房総史研究所、1998年(後に石橋一展編著『下総千葉氏』戎光祥出版社、2015年、に再録)
令和4年度特別展「我、関東の将軍にならん-小弓公方足利義明と戦国期の千葉氏-」あ・ら・か・る・と
- その1 「飯香岡八幡宮蔵大般若波羅蜜多経の謎」
- その2 「永正16年の足利高基の椎津城攻撃について」 前編
- その3 「永正16年の足利高基の椎津城攻撃について」 後編
- その4 足利義明の「総州御進発」について
- その5 臼井氏を非難する高基書状二点について
- その6 原基胤とは何者か ~義明に翻弄された生涯~
- その7 道哲が本佐倉城を攻めさせたのは事実か
- その8 小弓野田合戦の伝承と史実
その1「飯香岡八幡宮蔵大般若波羅蜜多経の謎」
この18日、火曜日より、標記特別展が始まりました。これまで足利義明をメインテーマとした展示は皆無であったといってよいでしょう。義明が御所を構えた小弓(中央区生実町)のある千葉市で、本展を開催できることは大変喜ばしいことであり、同時に責任をひしひしと感じます。
先学の研究成果に大きく拠りながら、謎の多い義明の実態解明に努めたつもりですが、いろいろ壁に突き当たりました。本コラムでは、図録や展示キャプションでは触れえなかった疑問点や、また紙数の都合で十分な説明ができなかったところなどを「アラカルト」的に取り上げてみたいと思います。
第1回目は、本展の序章でご紹介する市原市八幡に所在する飯香岡八幡宮の所蔵する「大般若波羅蜜多経(だいはんにゃはらみたきょう)」を取り上げます。
大般若波羅蜜多経(以下、大般若経といいます)が神社に所蔵されていると聞いて不思議に思われた方もいらっしゃるかもしれません。明治時代になるまでは神仏習合の考えのもと、日本人は神と仏を同じものと捉えていました。本地垂迹説といって、本来の仏様(「本地」)が日本に出現した時に、かり(権)の姿(権に現れるで「権現」)である神様の姿をとったとする考え方です。ですから、天照大神の本地は大日如来、同じく素戔嗚(すさのお)は牛頭天王(薬師如来)、八幡神は阿弥陀如来、妙見のそれは十一面観音(あるいは薬師如来)などと考えられていました。
というわけで、お寺と神社が一緒にあっても不思議ではありません。今でも神社とお寺が近接して建立されているのは、この理由によります。
飯香岡八幡宮も、かつてはすぐ隣に神社と一体化した寺院(若宮寺=別当寺)がありました。それを霊応寺(れいおうじ;りょうおうじ)といいました。境内地は、JR八幡宿駅の構内及び西口ロータリーを中心とする一帯で、駅の東口にあたる地域に墓所(御墓堂遺跡)を構えていました。明治以降の神仏分離により今は廃滅しましたが、毎朝夕、通勤客や通学生徒で賑わう駅は、かつてはお寺と墓地だったのです。
大般若経は「飯香岡八幡宮宝殿」に寄進されたものですが、こうした理由で別当寺の僧侶たちが読経したものと思われます。
さて、この大般若経の巻五百には裏書があり、我々展示担当者の頭を悩ませる文言が記されています。それは「義明征夷将軍御家繁昌、子葉孫枝栄花松椿亀鶴之算、高基大樹将軍両君如シテ羽翼ノ、関東八ケ国掌中、(後略)」というものです。
この文言の何が問題かというと、大般若経が飯香岡八幡宮に奉納されたことから、少なくとも義明が小弓に移座した後のことと考えられます。とすると、義明と高基は対立関係にあるわけで、「両君羽翼の如くして」の文言と状況的に合わないわけです。
次に奉納した人物ですが、保生庵建清という関東足利氏の根本家臣と思われる人物です。「龔而保生庵建清、以懇志需全部六百巻、匣数六十箱、櫃三合、奉寄進」と記されています。「龔」とは「両手でうやうやしくそなえる」(『新版 漢字源』学習研究社)の意味があり、建清が寄進したことがわかります。
我々は建清とこの文言の前に載る「殊者俗名南在名小曾祢(彌)与三郎信直、武運長久、家門富貴、衆人愛敬之為」の小曾禰信直と同一人物と考えましたが、問題となるのはそれでよいのかということです。あるいは、建清と信直は同じ一族(例えば親子)という可能性も捨てきれません。
展示資料の5-4「パネル 佐野為綱・小曾禰胤盛連署書状」(潮田家文書)でわかるように、その後も小曾禰氏は小弓公方の家臣として仕え、義明の死後も子息頼淳の側近としてみえます。
小曾禰氏は、尊氏の側近高師直で知られる高氏一族の支族南氏の庶家にあたります。足利市の南部、渡良瀬川支流矢場川左岸に小曽根町という地名が残り、おそらくここが小曾禰氏の名字の地でしょう。小曾禰氏は、佐野氏同様、雪下殿(鎌倉の鶴岡八幡宮若宮の別当)の奉公人として仕え、義明について小弓に移ったものと考えられます。
そして最大の謎となるのが、次に紹介する文書の解釈です。「喜連川家文書案三」の「足利高基感状写」です。
「今度椎津被立御馬之砌、抽粉骨被走廻之条、感悦候、巨細園田信濃守ニ被仰含候、恐々不宣、 八月廿六日 高基御判 建請首座」
永正16年(1519)8月、足利高基は、前年小弓に入部した弟義明に対し、義明の擁立主体真里谷武田氏の東京湾に面した重要な湊であり、重要な支城椎津城のある椎津(市原市椎津)を攻撃しました。椎津は、小弓から南西に10数kmほどの距離にあります。
この攻撃には、高基の発給した感状などから、常陸の菅谷氏、羽生氏、下総の結城氏らが参加したことがわかります。また他の文書からも下総千葉氏が参陣したことが想定されます。
そして、高基の軍勢の中に「建請首座」がいたという事実です。建清と建請首座は同一人物と考えられます。そうであれば飯香岡八幡宮に大般若経を納めた義明側近が、義明を攻撃した軍勢の中にいたことになります。この矛盾をどう考えたらよいのでしょうか。
この矛盾を解く一つの仮説は、はじめ(永正16年段階)高基方についていた建清(建請)がのちに小弓方につき、それ以降、大般若経を寄進したと考えるものです。このように考えれば、高基と義明双方を立てて「両君比翼の如く」と願った気持ちも理解できます。
以上のように、飯香岡八幡宮に寄進された大般若波羅蜜多経の奥書をめぐっては、小弓公方成立に関わる重大な謎が隠されています。資料の精緻な分析により、思いもよらぬ発見につながる可能性があります。展示にあたり、まだ完全に解明できたわけではありませんが、観覧される皆様方に材料として提示し、一緒に考えていただければ僥倖です。
本文を擱筆するにあたり、貴重な資料の展示を快諾いただいた飯香岡八幡宮宮司平澤政人様、同じく氏子の皆様方にあつく御礼申し上げます 。
その2 「永正16年の足利高基の椎津城攻撃について」 前編
前回「大般若波羅蜜多経の謎」で触れた標記攻撃について、今回はもう少し深く掘り下げてみたいと思います。羽生上総介(はにゅうかずさのすけ)に宛てられた古河公方足利高基の感状写(展示番号3-26パネル「足利高基感状写」)は、国立公文書館所蔵の「常総文書」に記録されたものです。「常総文書」とは、常陸土浦藩の農政学者長島尉信(ながしまやすのぶ)が嘉永3年(1850)に刊行したもので、現在は亡失した中世文書を筆写しており、大変貴重なものとなっています。従来、この羽生氏について『水海道市史』などを除いては、茨城県行方市羽生の羽生氏と考えられてきました。霞ヶ浦の北部東岸に面した羽生を所領とした常陸大掾氏系の羽生氏です。
これに対して、常総市羽生町の羽生氏としたのが『水海道市史 上巻』(1983年)でした。ただし、同市史では感状の発給者を政氏として、年代も永正12年(1515)のこととしています。しかも、父足利政氏と子の高基の不和の中で、政氏が「上総椎津城(市原郡)の高基党、真里谷党を攻撃させ、戦功があったのをみて次の感状(「渡辺新兵衛尉宛高基感状写」[石塚文書]と「羽生上総介宛高基感状写」[常総文書]のこと―引用者)をあたえている」と記述しています。これらは基本的に事実誤認であり、高基と真里谷武田氏が結んだ事実はありませんし、この文書は高基の感状写であることは間違いありません。模写された花押(サイン)は高基のそれで、政氏の花押とは異なっています。
しかしながら、羽生氏を当時は横曽根城(常総市豊岡町乙)にいた羽生氏としたことは卓見といえましょう。羽生氏は元々羽生館(常総市羽生町の現法蔵寺)におり、その後、横曽根城に移ったとされます(前掲『水海道市史』)。横曽根城は羽生館の鬼怒川の下流1kmほど、鬼怒川に面したところに位置しています。
感状写の宛所羽生氏が同所の羽生氏である根拠は、「常総文書」の添書きの記載からです。この文書の伝来について長島は、「岡田郡横曽根村 羽生利右衛門所蔵…」と添書きしており、長島がこの感状を書写した幕末には、原本が横曽根村(現常総市豊岡町乙)の羽生利右衛門のもとにあったのです。以上のことから.永正16年(1519)の椎津城攻めで高基に従ったのは、利右衛門の先祖の羽生氏だったといえましょう。
ところで、この羽生氏ですが、「常総文書」の長島の添書きの続きには「羽生利右衛門所蔵 今渡辺を氏とす」とあります。このことは、以下に述べる理由から、羽生氏は元来の名字は渡辺氏で、当地の羽生町に入部したため羽生氏を名のり、後に(江戸時代以降か)渡辺に復姓したと思います。
渡辺氏といえば、大阪府の淀川河口の渡辺の地(残念なことに地名は無くなってしまいました)を本拠とする水軍の将渡辺党が思い浮かびます。結論から言えば、羽生氏はこの渡辺党につながる一族と考えられます。その理由は、この鬼怒川水系には他にも渡辺氏がおり、水軍を率いて戦闘に参加し、あるいは流通に従事している様子がみてとれるからです。例えば、常総市古間木(ふるまき)の渡辺氏は古間木城に拠って、ちょうど永正年代に政氏方と高基方の対立時に高基方(『水海道市史』では政氏方とする)として働いています。実は、椎津城攻めに関する高基の感状写に、渡辺新兵衛尉あてに出された永正16年の9月3日付のもの(「石塚文書」)があります。しかし、この文書は「なお、検討を要す」とされ、史料としては取り扱いに注意が必要とされています。筆者は、新兵衛尉が古間木渡辺氏かどうかはさておき、なんらかの史実を反映したものと考え、椎津城攻めにおける渡辺氏の従軍を肯定的にとらえています。
このほかにも先学により、小手指(茨城県猿島郡五霞町)や向古河(埼玉県加須市)の「流通商人」の渡辺氏の存在が指摘されています(佐藤博信「古河公方とその周辺-特に小手指と向古河の渡辺氏をめぐって」『千葉県の文書館』第3号 1997年、後に同『江戸湾の中世』第二部第八章「下総渡辺氏の歴史的性格」として再録 思文閣 2000年)。両所は古利根川・渡良瀬川水系に接し、陸路では小手指に奥大道が通るなど、古鬼怒川水系と連絡する要衝といえます。
また、千葉県でも印旛沼沿岸にいた渡辺氏が知られています。まず、佐倉市岩名玉泉寺の金剛力士像吽像の胎内簡札には、明応6年(1497)8月1日の日付で「地頭渡邊厳二良」と記されています(『千葉縣史料 金石文篇二』)。次に旧本埜村(現印西市)竜腹寺の龍腹寺の五重塔(今は亡失)の鋳銅棟札には、塔の建設は嘉吉2年(1442)11月に始まり、辛未年(宝徳3年:1451)に完成したとあり、「渡邊次郎左衛門慰(ママ)源廣豪」の名が、当主千葉胤直と重臣円城寺氏に次いで上位に刻まれています(『同前』)。両者は仮名の二郎(次郎)を同じくすることから、半世紀近くの開きがありますが、同一氏族の関係の可能性を考えてみてもよいでしょう。
佐倉市岩名は、鹿島川が印旛沼に注ぐ河口に面しています。そして、そこから北西2kmほどの印旛沼に面した地に飯野城跡があるのです。同城跡は単郭で沼に面しており、舟入とみられる地形があって、いかにも水軍の城にふさわしいといえます。
嘉吉2年に筆頭家臣円城寺氏に次ぐ位置にいた渡辺氏は、印旛沼水系を抑える水軍の将として重用されたものと考えられます(しかし、千葉氏が本佐倉に本拠を移した文明年間以降、渡辺氏の名は史料上みえなくなります。胤直らとともに享徳の乱で滅亡したのでしょうか)
このように、渡辺氏は水軍の将らしく、関東各地の河川湖沼の沿岸部に拠点を構えたことがみてとれます。鬼怒川沿岸の羽生の地に入部した渡辺氏(羽生氏)も、こうした渡辺党の一員だったと思います。
それでは、以上のことが椎津城攻めとどのように関係してくるのでしょうか。長くなりましたので、続きは次回に述べたいと思います。
その3 「永正16年の足利高基の椎津城攻撃について」 後編
前回ご紹介した永正16年の椎津城攻めに関連して、足利高基が発給した建請首座宛ての感状(喜連川家文書案三)があります。その文言に、「今度椎津被立御馬之砌」とあり、高基自身が出陣したことがわかります。それでは、古河城にいた高基はどのような経路で椎津城を攻めたのでしょうか。
まず高基の動員した軍勢には、他の感状等から菅谷氏(すげのやし:常陸宍倉城主)・結城氏(下総結城城主)・羽生氏、そして千葉氏・原氏・海上氏などがいたことがわかります。高基は、どのような経路で軍勢を率いて椎津城に至ったのでしょうか。
椎津城は、「寺社群と交易場を中心とした湊津の存在が十分想定される」(佐藤博信『江戸湾の中世』第3章「上総椎津中世的展開」 2000年:初出1996年)場に築かれた湊城(海城)というべき城です。椎津城の東300mに位置する、支城の正坊山砦跡の麓には境川が流れ、船着き場と伝承される場所があります。現在埋め立てが進んでいますが、第2次世界大戦直後、境川の河口はJR内房線の線路から200mもないところにありました(国土地理院 1946年2月28日撮影空中写真)。東京湾を行き来した船が、河口から船着き場まで十分に入ってこられる位置と言えましょう。
ところで高基は、船で攻めたのでしょうか。「御馬を立てられ」という感状の書き方から、陸路を想定するべきではないかという考え方もあるでしょう。しかし、これからみるように、海路(水路)を経たと考える方が合理的と思えるふしがあり、すでに先学により、その旨の指摘があります(佐藤博信「小弓公方足利氏の成立と展開」『中世東国政治史論』2006年:初出1992年)。
その経路で考えられるのは、第一に古河の高基は渡良瀬川より水運で、そして陸路を通って関宿へ出ます。そこから船で藺沼水系(現在の利根川)を経て、印旛浦(現在の印旛沼)に入って高基党の本佐倉城の千葉氏のもとに至る経路が考えられます。この経路を使えば、鬼怒川水系を使用できる結城氏や羽生氏、霞ヶ浦沿岸の宍倉城(かすみがうら市宍倉)の菅谷氏も香取内海から印旛浦へ入り、同様に本佐倉城に至ることが可能です。
しかし、問題は、本佐倉からどのような経路を使って椎津城を攻めるかです。ここでまた、二つの考え方があります。一つは、本佐倉より陸路で椎津城を攻めたという考え方。もう一つは、陸路で東京湾の湊津にいったん出て、そこから船で海路椎津城を攻めたとする考え方です。
本佐倉から陸路を直接椎津に向かうには、小弓を通るのが近道であり、それには小弓城にいる義明とぶつかることになり、この経路は考えにくいと思われます。
また本佐倉より大きく東上総へ回り、高基方についていた長南武田氏の領域を通り、山越えして椎津へ出るという経路も考えられますが、あまりにも遠回りとなって現実には考えにくいと思われます。また途中真里谷武田氏の領域を通過するので、椎津まで攻めこむのは困難でしょう。
一方、東京湾の湊津から船で椎津へ向かうのも、高基と敵対する臼井氏が印旛沼西端を抑えているので、東京湾まで出るのが困難と考えられます。
以上のように考えると、高基の軍勢が本佐倉まで来たと考えるのは、成り立ちにくいと思われます。
第二に、水路で古河より椎津へ至る経路を想定してみましょう。香取内海を通る経路は想定しにくいとなると、利根川東遷以前の河川交通で考えてみる必要があります。当時の流路は非常に複雑でわかりにくいのですが、簡潔に述べると、古利根川は直接、現在の東京湾に流れ込んでいましたし、渡良瀬川も太日川(現在の江戸川に近い流路)となって東京湾に注いでいました。現在の利根川は、当時藺沼・鬼怒川・小貝川を集めて香取内海に注いでおり、渡良瀬川・旧利根川水系とは結ばれていないと考えられています。なお、細い水路で両水系は繋がっていたと考える見方もあります。ここでは、前者、つまり両水系は直接繋がっていないと考える立場で、以下話を進めます。
さて、渡良瀬川沿いの古河に本拠をおく足利高基は、渡良瀬川より太日川を経て、直接東京湾に出ることが可能です。香取内海水系の菅谷氏、鬼怒川水系の結城氏・羽生氏らは、香取内海から藺沼を遡上し、陸路で五霞町小手指を経て、渡良瀬川水系へ連絡して、高基同様、東京湾にでることができます。もちろん、小手指で渡良瀬川を下る船の調達が問題となってきますが、小手指には、前回、紹介した佐藤博信氏の取り上げた小手指渡辺氏がいます。
問題は、川船と海船をどう使いわけたかです。渡良瀬川を行き来した船(川船)は、東京湾を航行できたかが問題となります。一般に川底の浅い河川を航行する船は、船底がフラットな高瀬舟のようなものが適しています。それに対し、海を行く船は波風で転覆しないよう、喫水線から船底までを大きくとる必要があります(そのためには船底に重量物を積み安定性を保つことが必要)。果たして、高基の軍船は、渡良瀬川から東京湾を自由に航行できたのでしょうか。現在の川の様子から、中世当時を想像するのは難しいことですが、古河から太日川河口まで東京湾を航行した船で、行き来することは可能だったと、私は考えています。
以上、推測に推測を重ね、迂遠な考証に終始しましたが、永正16年(1519)8月の足利高基による椎津城攻めは、水系を使い軍船で攻めたものと考えました。
なお、河川の水量についても考えねばなりませんが、旧暦の8月(現在では9月)の水量は、四万十川の例ですが、9月の長雨のせいか豊富といえます。関東でもほぼ同様と考えてよいでしょう。
(参考:https://www.jswe.or.jp/publications/jutaku/wsi/pdf/seikasyu-002.pdf(外部サイトへリンク))
その4 足利義明の「総州御進発」について
足利義明が小弓に向かって進発したのは、今でこそ永正15年(1518)7月のことだとされています。しかし、これが定着したのは1990年代後半以降といえるでしょう。それまでは、『快元僧都記』の記事(展示資料2-13 パネル「快元僧都記(群書類従)」)から、永正14年10月15日よりすこし前の時期と考えられてきました。
同書には、「義明は父政氏に勘当され、奥州に下向していた時、上総の武田真里谷三河守入道に招請をうけた。そして、小弓の原氏と戦闘を繰り返しては敗れていた真里谷氏は、義明を大将にして小弓城を攻め落とし、「原次郎と家郎高城越前守父子」を滅亡させた。」とあり、傍書に小弓落城は永正14年10月15日と記されています。この記事が根拠とされ、長らく永正14年の小弓落城と、それ以前の義明下総入部が定説となっていたのです。
しかし、永正14年義明入部説を否定したのが、古河公方研究で知られる佐藤博信氏でした。その根拠となったのが、展示資料3―5「パネル不動寿丸書状(鑁阿寺文書)」の存在です(佐藤博信「雪下殿御座所考」『日本史研究』302号 1987年 の注において、すでに永正15年7月の可能性を示唆されています)。
書状の内容は、鑁阿寺の支院普賢院に宛てて、「雪下殿様(足利義明に比定)が「総州御進発」するので、御祈禱を依頼する(義明の)御書が出されました。この旨を(鑁阿寺へ)お伝えいたしましたので、よくよく御祈禱に励んでいただければ素晴らしいことです。」というものです。
鑁阿寺の支院は12院あり、それぞれ干支に対応して毎年ごとに事務を担当(年行事)する支院が代わりました。佐藤氏は、各支院宛ての多くの文書を検討した結果、普賢院は寅年の担当であるとしました(「鑁阿寺文書覚書」『日本歴史』402号 1982年、後に同氏『中世東国の支配構造』思文閣出版 1989年)。永正15年は戊寅(つちのえとら)の年です。このことから、佐藤氏は「雪下殿様総州御進発」つまり義明の下総国小弓への発向を、永正14年ではなく、同15年7月のこととしました。そして『快元僧都記』の諸本の検討から、群書類従本の記事は後筆の可能性が高いとし、内容の誤謬を指摘したのです(「小弓公方足利氏の成立と展開」『歴史学研究』635号 1992年、後に同『中世東国政治史論』塙書房 2006年 に再録)。
実際、以上のことは展示2-11のパネル「足利道長政氏書状(臼田文書)」で、裏付けられることになります。この書状の日付「閏十月廿八日」は、閏月から永正14年で間違いありません。この当時、子息高基との抗争に敗れ、埼玉県久喜市の館(後の甘棠院)に隠棲し、出家し道長と名のっていた政氏が、山内上杉氏の家臣臼田氏に宛てたものです。
内容をみると、日を追って(政氏の)義明との仲は親しい状態となっており、臼田氏は高柳(義明のこと)に忠節を尽くすべきである、と政氏が指示したものです(佐藤前掲「雪下殿御座所考」、後に前掲『中世東国の支配構造』に再録)。ここで注目すべきは、この時点で政氏は「義明」と呼んでいることです。つまり、永正14年閏10月には、還俗して空然(こうねん)から義明と名のり高柳に在所していることが窺われます。この点、『快元僧都記』では、この前月の10月15日に義明が下総で総大将として小弓城を攻め落としていることになっていますが、まずこれは考えられません。義明は、書中にあるように高柳(久喜市)[展示資料2-5 パネル高柳御所跡]にいることがわかります。
また、先学の指摘(滝川恒昭「小弓公方家臣・上総逸見氏について」『中世房総』6号 1992)に依拠しますが、恒岡源左衛門尉入道に宛てた道長(足利政氏)書状写(「常陸誌料雑記五一」所収)も、義明の総州進発に関し重要な手がかりを与えてくれます。同文書は年欠の「四月廿六日」に出されています。書状の内容には「建芳死去」とあり、内容からみて建芳(扇谷上杉朝良)が亡くなってあまり経たない頃のものと判断できます。建芳の死去は永正15年4月21日の事ですから、直後の同年4月26日に岩槻城主太田氏の家臣である恒岡氏に宛てて出されたものと言えます。太田氏は太田道灌で有名な扇谷上杉氏の家宰(重臣)です。そして道長の「高柳江仰含」との文言から、永正15年4月の段階まで、義明は高柳にいたことが判明したのです。
こうして、佐藤氏の一連の研究と先学の史料発掘により、義明の「総州御進発」の時期は永正15年7月と確定しました。ですから、繰り返しますが、永正14年10月の小弓城攻めには、義明は参加していなかったのです。
ただ、気になる点残っています。「総州」をどう解釈するかです。これを下総国小弓としてよいかです。本展の第6章でも取り上げましたが、市原市五所には義明の八幡御所(展示資料6-13 パネル「伝八幡御所」)があったという伝承があります。この伝承は時系列に誤りであることは明らかですが、まったく無視できないとも思えます。市原市八幡には雪下殿ゆかりの八幡社、飯香岡八幡宮が所在し、義明と高基兄弟の宥和を願った文言の載る大般若波羅蜜多経も同社に納められています(展示資料序-1)。八幡と義明のつながりは、何らかの史実を反映している可能性があるのではないでしょうか。総州=上総といえないだろうか、ということです。
また、下総国を「総州」と呼ぶのかという点も気になるところです。その点は、戦国時代に、下総を指して「総州」と呼んだ例は複数見つかっており、結論から言えば「総州御進発」を下総国小弓への進発ととらえて差し支えないと考えます。
いずれにしても、市原と義明の関係は、今後も研究の余地があるように思えます
(この点については、簗瀬裕一「小弓公方足利義明の御座所と生実・浜野の中世城郭」『千葉城郭研究』第6号 2000年に詳しい)。
その5 臼井氏を非難する高基書状二点について
古河公方足利高基は、義明についた臼井氏を書状の中で猛烈に非難しています。それも時を隔て二度にわたって述べていますので、高基の臼井氏に対する怒りは、かなりのものだったと思われます。
今回の展示には、この2点の文書が揃いました。高基の怒りが吐露された、これらの文書をみていきましょう。
一点目は、展示資料3—28「足利高基書状」(渡辺忠胤氏所蔵文書)です。千葉氏の当主勝胤に宛てて、ここでは「臼井の不忠先代未聞に候」と記されています。今回の展示では、この書状を永正16年の高基の椎津城攻めに関連したものと考えてみました。「十一月廿七日」の日付からみると、八月の攻撃時よりやや間が空きすぎる感はあります。しかし、冒頭の「不思議の子細に就きて」の解釈は、外山研究員によれば、「不思議」とは思いもよらないこと、またはけしからぬこととすべきだそうです。とすれば、「思いもよらない(理性的な思慮の及ばないけしからぬ)事態が生じたので、帰座したところ…」と読めます。
これと「臼井の不忠先代未聞に候」がどう関係するかですが、「臼井の不忠」こそが「不思議の子細」ではなかったか、これが外山氏とともに検討した結論です。そうなると、これが永正16年の椎津城攻めに関わることとしてよければ、以下のような文書解釈が考えられます。
(椎津城を攻めるため、高基自ら出陣したが、)味方とばかり思っていた臼井氏が突然、義明方に寝返った(「不思議の子細」)。そのため、(急遽)高基は軍を引いて古河へ帰還した。その時に、千葉昌胤をはじめ海上氏・原氏等が高基のお供についてくれた。これには大変うれしく感動した。(それに比べ)臼井の不忠は、これまで聞いたことがない、はなはだ驚くべきことだ。
臼井氏は印旛沼の西端、水陸交通の要衝臼井荘一帯を支配していた千葉氏の同族(千葉常胤の父常重の弟常康から始まる一族)です。高基にとってみれば、いわば突然退路を塞がれる事態となった訳です。それゆえ、「令帰座」しめざるを得なくなったと考えられます。
実は、このことはすでに黒田基樹氏が「(前略)臼井氏が千葉氏から離叛して小弓方に応じたことが知られるが、それはまさに高基の帰還の際のことであったとみられる。そのため高基の帰還は、かなり困難な状態に置かれたとみられる。」と書いておられます(「古河・小弓公方両家と千葉氏」『佐倉市史研究』第24号 2011年)。けだし卓見かと思われます。前述の解釈で、黒田氏の想定は裏づけられたのではないでしょうか。
さてもう一点は、展示資料3-31「長南三河守宛足利高基書状」(東京大学史料編纂所所蔵文書)です。こちらは高基自筆の書状で、先学により大永4年(1524)に比定されている、長文のものです。長南三河守とは長南武田氏を指し、同族の真里谷武田氏が義明を擁立した主体であったのに対し、初めから長南武田氏は高基方を貫きました。ここにはいろいろな情報が詰まっており、大変興味深い内容となっています。しかし、とても全文を説明できる力は筆者にはありませんので、臼井氏の裏切りについてのみ、ここでは触れてみます。
高基は、「私の命をなんとか長らえてまでも、彼の仁(臼井氏)の滅亡をみてみたいものだ」とまで書いています。ここまで高基に書かせたのも、前述のような突然の裏切りということもあったと考えますが、元来、臼井氏は忠実な高基方の氏族であったからではないでしょうか。
それは、16世紀初頭の篠塚の陣の頃まで遡ります。篠塚の陣とは、『千学集抜粋』の記事からその存在は知られていたものの、一次史料がないとされ、長い間歴史的事実であったのか不明とされてきました。足利政氏・高基父子が千葉孝胤を討伐するため、篠塚(佐倉市小篠塚・大篠塚周辺)に陣をとり、3年近く居続けたというものです。
近年になって、関連する史料・記録が相次いで指摘され、歴史的事実とほぼ確定しました(和氣俊行・佐藤博信・田中宏志各氏の論考)。そしてついに、「篠塚陣」の文言の載る、足利政氏の里見刑部大輔宛書状(原本)の存在が明らかになりました(滝川恒昭「戦国前期の房総里見氏に関する考察-新出足利政氏書状の紹介と検討を通じて-」『鎌倉』119 2015年)。
陣の置かれた期間は、文亀2年(1502)から永正元年(1504)のあしかけ3か年という説が有力です(和氣俊行「下総国篠塚陣についての基礎的考察」佐藤博信編『中世東国の政治構造』岩田書院 2007年)。この間、篠塚公方府ともいうべき行政府が出現したとされます(佐藤博信「下総篠塚の陣に関する一史料」『戦国史研究』59号 2010年)。そして、3年にわたって、鹿島川右岸(北岸)の篠塚の陣を、対岸の城郭群で支えていたのは臼井氏一族だったのです。千葉氏に味方する勢力が北上して、陣の背後を脅かすことのないよう、臼井氏は後方を固めていたと考えられます。
このように、政氏・高基父子の在陣を3年にもわたり支え、忠節を果たした臼井一族が、椎津城攻めでは不忠(主君に不利益になることを行うこと)をなした。これは高基にとって、とても許せることではなかったのでしょう。そうしたことが、5年後の大永4年(1524)になっても、「露命之ながらへ度も…」の表現につながったのではなでいでしょうか。
ちなみに、臼井氏が滅亡したのは、天文15年(1546)のことでした。高基自身は10年以上前の天文4年に、子の晴氏との抗争に敗れて亡くなっています。臼井氏の滅亡どころか、仇敵の弟義明の討死(天文7年)も見ることはなかったのです。
両史料の展示に快諾いただいた所蔵者・機関の皆様には、篤く御礼申し上げます。
今回、とくに外山研究員との話し合いのなかで、考えがまとまりました。その旨を明記します。
その6 原基胤とは何者か ~義明に翻弄された生涯~
原基胤という人物を知っているという方は、房総戦国史にかなり詳しい方と思われます。原氏は知っているけれど基胤は知らない、という方がほとんどだと思われる、無名に近い人物です。しかし、今回の展示ではこの人物が義明と絡んで、注目に値する動きを見せるのです。
具体的には、展示資料3-32「パネル道哲判物写(井田康博氏所蔵文書)」です。年不詳12月11日に出されたこの文書で、道哲(義明)に「孫二郎(原基胤)は、道哲に対して不忠な態度をとらない旨、数度も誓詞を出して約束したので、油断をしていたところ」と書かれています。もともと小弓城にいて、道哲と対立する高基側についていた原氏です。そのため、道哲方に誓詞を何度も出さなければ信用されなかったのです。
ところが続けて「去る22日の夜に(不忠な)態度を明らかにした」とあり、ついには道哲から離反する姿勢をしめしました。これには道哲も井田氏に対して、小弓公方側についていた椎崎勝住と相談して小弓方であることを明らかにするよう求めています。
原基胤の父胤隆は、永正6年(1509)の連歌師宗長による小弓訪問の際「小弓館」の主でした。しかし、永正14年(1517)10月には、真里谷武田氏らの攻撃 をうけ、小弓城は落ち、「原次郎并家郎高城越前守父子滅亡」(展示資料2-13 パネル『快元僧都記』)という事態が起きます。胤隆は天文5年(1536)7月に布川(茨城県北相馬郡利根町)で亡くなっています(『本土寺過去帳』)ので、この「原次郎」とは胤隆の弟朝胤のこととされています。
小弓原氏の当主となった基胤は、小弓を追われてもともとの原氏の所領であった小金(松戸市)に拠ったとされます。そして大永4年(1524)4月1日までは、確実に高基方についていたことがわかります(展示資料3―31「足利高基書状」)。基胤の「基」は高基の偏諱をうけたものと考えられています。
それでは、「道哲判物写」にみる、基胤による義明からの離反はいつだったのでしょうか。それは、同文書にある道哲の花押(サイン)が重要なヒントを与えてくれます。義明は四度改名をし(愛松王→空然→宗斎→義明→道哲)、花押も生涯五つの形を用いています。佐藤博信氏の分類によれば、この「道哲判物写」に据えられた花押は、最終形の花押Eとわかります。一つ前の花押形Dの終見が天文3年閏正月10日付の道哲書状のものですので、それ以降ということになります。
しかし、基胤は、天文4年(1535)6月20日、小弓公方の軍勢と小弓野田(千葉市緑区おゆみ野・誉田町)で戦い、岩富原氏の朗典らとともに討死をとげています(『本土寺過去帳』)。原氏の本拠小弓城を奪回しようとしてのことと考えられています。
このことから、「道哲判物写」が出された時期は、天文3年12月11日と確定できます。つまり、大永4年4月以降のある時期、基胤は義明方につき、天文3年末頃には義明に反旗を翻したようで、翌4年6月に小弓軍と戦って討死を遂げたということになります。
小弓奪回を果たせず、むなしく討死した原基胤ですが、その3年後、第1次国府台合戦で義明らが敗死すると、原氏は故地小弓の奪回を果たすことになります。その時の原氏の当主は、基胤の弟胤清がついていました。
本文を書くにあたり、黒田基樹氏の「古河・小弓両公方家と千葉氏」(『佐倉市史研究』第24号 2011年)、および佐藤博信編『戦國遺文 古河公方編』(東京堂出版 2006年)を参考にさせていただきました。
その7 道哲が本佐倉城を攻めさせたのは事実か
展示資料3-14「文禄慶長御書案 道哲書状(喜連川文書)」には、道哲(足利義明)が里見上野入道(義通)に命じ、「敵城」を攻めさせたことが記されています。以下、読み下し文で全文を掲げます。
敵城近辺田井・横山・小沢要害・根小屋以下、悉く打ち散じられ、其の地蕨に至り帰陣の由、聞き候、目出たく簡要に候、此のたび関宿へ動(はたら)き、これ成されたく候、走り廻り候はば、いよいよ以て戦功たるべく候、其の東悦のため遣わし候、恐々謹言、
六月十八日 道哲
里見上野入道殿
この文書を最初に取り上げたのは、古河公方研究で知られる佐藤博信氏です(「小弓公方足利氏の成立と展開」『歴史学研究』685号 1992年、後に同『中世東国政治史論』塙書房 2006年 に再録)。佐藤氏は、「敵城」を千葉氏の本拠本佐倉城(酒々井町本佐倉・佐倉市大佐倉)に比定し、帰陣した「蕨」を四街道市和良比の和良比堀込城としたのです。そして、年欠文書を永正17年(1520)のもの、つまり前年の足利高基の椎津城攻めに対する反撃ととらえました。
これに対し、田井以下の地名が佐倉近辺に見当たらないことから、「蕨」は埼玉県蕨市という反論も出ました。そうであれば、「敵城」を本佐倉城とみることはできません。しかし、永正17年段階で、里見氏が埼玉県蕨市に橋頭堡を築くことはできないとする、有力な再反論もあって、敵城を本佐倉城とする佐藤説は定着していると言って過言ではないでしょう。
ただし、田井・横山・小沢の3地名について、依然として比定地が見つからないのが、今後の課題として残ります。
その後、黒田基樹氏は佐藤説を支持しながらも、年代を一年後の永正18年(大永元年)6月18日の可能性があることを示唆しました(「古河・小弓両公方家と千葉氏」『佐倉市史研究』第24号 2011年)。その根拠として挙げたのが、『本土寺過去帳』に載る次の記事です。
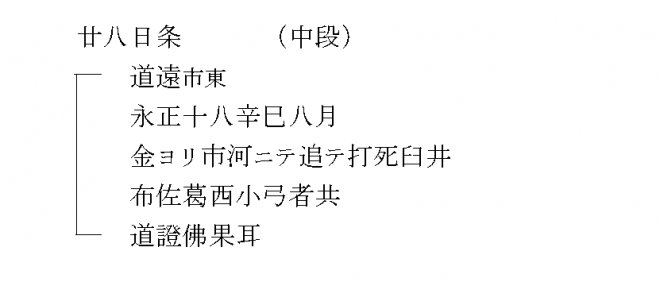
これは、高基方の簗田氏の拠る関宿城(野田市)を攻撃するため、小弓から出張った軍勢が、小金領(松戸市周辺:原氏・高城氏の支配領域)を攻めるも攻めきれず、市川まで押し戻され、そこで討死したというものです(市川合戦)。つまり、先の道哲の書状には「此のたび関宿へ動き、これ成されたく候」とあり、里見義通は関宿を攻めることを命じられています。関宿を攻めるために通過せざるを得ない小金領は、もともと原氏が小弓に来る以前に領有していたとされます。永正14年10月15日に小弓城を追われた原基胤らは、小金城に戻ったと考えられています。その後、小弓城に入った足利義明は道哲と道号を名のるようになりましたが、小金に拠る小弓原氏とは敵対していたのです。永正18年(大永元:1521)8月、道哲の遣わした軍勢には、「市東」(市原市)、「臼井」、「布佐」(布川豊島氏)、「葛西」(葛西城の大石氏)、そして「小弓」(道哲の直属軍)などがいました(前掲黒田論文)。里見氏の軍勢の記述がありませんが、『本土寺過去帳』の性格上、書かれていないだけで、この軍勢に里見氏も含まれていたと思われます。
もし、この道哲の書状が永正18年のことであれば、約二月後に小金城攻撃と市川合戦がおきたとみることができます。もちろん、永正17年に本佐倉城近辺を攻めた後、和良比へ帰陣した義通は、すぐには関宿城攻撃に移らず、翌年に行ったとも考えることは可能ですので、この書状をただちに永正18年と確定することはできません。
しかし、手がかりになりそうなことがあるのです。それは、同記事のすぐ隣りに記された、次の記載事項です。同記事を使った研究の中で、これまでこの点を指摘したものは、管見の限りではありません。
「妙高位タカハシ其(共ヵ)打死」
「臼井、布佐、葛西、小弓者共」が討死した記述のすぐ隣に、この記載がなされています。「妙高位タカハシ」とは誰でしょうか。大網白里市小西を本拠とする小西原氏の重臣に高橋氏がおり、一族は同過去帳にも数多く載せられています。さらに、干支で「壬午」の年の8月に、小西高橋與四郎其ほかが「佐倉ニテ打□(死ヵ)」している記載もあるのです(『本土寺過去帳』廿九日条)。妙高位タカハシとは小西の高橋氏のことでしょう。そして、「壬午」とは大永2年(永正18年8月に大永に改元)にあたります。「佐倉」は、本佐倉城のある酒々井町本佐倉・佐倉市大佐倉を指します。小弓原氏と同族の小西原氏ですが、事情により小弓軍に参加していたものと思われます。
細かい論証は別の機会に譲りたいと思いますが、上述のように大永2年に本佐倉城を攻めた小西原氏の軍勢で討死したものが出ていることを考えると、次のような流れを考えることができます。
すなわち、永正18(大永元)年6月、里見義通は道哲に命じられて本佐倉城近辺を攻撃し、和良比堀込城に帰陣します。その時道哲より関宿攻めの要請をうけて、二か月後には、小金で原氏と戦い、市川まで押し戻されて味方に多くの戦死者を出しました。翌年の大永2年8月に、反撃に出た義明方は、前年(永正18年)に続いて本佐倉城攻めを決行した、とみるわけです。
以上のことから、「その地蕨に至り帰陣」の「蕨」を埼玉県の蕨市に当てることは、かなり難しいことがわかります。この道哲書状が永正17年であれ、18年(大永元)であれ、小金の原氏と敵対したまま、里見氏が長駆、埼玉県の蕨市まで陣を進めるのは考えにくいと思われます。また、義明にとっての最終目標は、高基の拠る古河城です。埼玉県蕨市は、この点から考えても、「其の地蕨に至り帰陣」とは地理的にみて言えないと思われます。
書状の出された年を、永正17年とみるのか18年とみるのか、残念ながら断定するところまではいきませんが、永正18年(大永元)とみる方が、蓋然性は高いといえるでしょう。
蛇足になりますが、小西原氏の本拠である小西城は、戦国後期とみられる縄張構造をもった城跡でしたが、圏央道ができたため、そのほとんどが壊されてしまいました。それでも該当部の全面発掘をうけ報告書が刊行されたことが、せめてもの救いになりました。東金酒井氏と土気酒井氏との領域のはざまに位置する小西原氏でしたが、その動向はさらに精査する必要が感じられます。
その8 小弓野田合戦の伝承と史実
本コラム「その6 原基胤とは何者か」で取り上げた天文4年(1535)6月の小弓野田合戦ですが、野田十文字原合戦として、近世の軍記物や地元の伝承では、以下のような話が三つほど伝わっています。
一つめは、天文7年(1538)10月の第1次国府台合戦で、義明方について敗れた里見勢を追いかけた北条氏の軍勢が、里見勢と野田十文字原で戦ったという話です。二つめは、永禄8年(1565)、土気酒井氏と里見氏との間で、野田十文字原(誉田1丁目から2丁目)で合戦があり、土気酒井氏が勝利したとされます。そして三つめが、天正18年(1590)に、野田十文字原において、原胤栄が徳川家の酒井家次と戦って討死したという話です。
このうち最後の話は、原胤栄は前年の天正17年には死去していますので、明確な誤りです。また、永禄8年の土気酒井氏は、2月に北条氏政の軍勢に土気城を攻められ、激しい戦いを繰り広げています。この時、土気酒井氏は里見方でしたが、里見氏からの援軍はないことを土気城主酒井胤治は嘆いています。ですから、この両者の闘いが同年にあったとは、信じ難いものがあります。
これらの伝承のもとになったのは、天文4年(1535)6月の原基胤らが討死した、史実としての小弓野田合戦であると思われます。同合戦が記録として残るのは、『本土寺過去帳』、『教蔵寺過去帳』(佐倉市岩富町)、『長福寺過去帳』(佐倉市岩富)という日蓮宗寺院の過去帳の記録によります。なお、本土寺の末寺が経蔵寺、長福寺です。というのも、討死した原氏一族は本土寺やその末寺の外護者であったためです。
これらの過去帳は、日牌形式(命日の日づけごとに死者の法名・実名・死亡日時・同場所などが記されたもの)で、自然死でない場合はその記録(「〇〇ニテ打死ニ」など)も載せられることがあります。
小弓野田合戦は、こうして『本土寺過去帳』以下に記録されたのです。
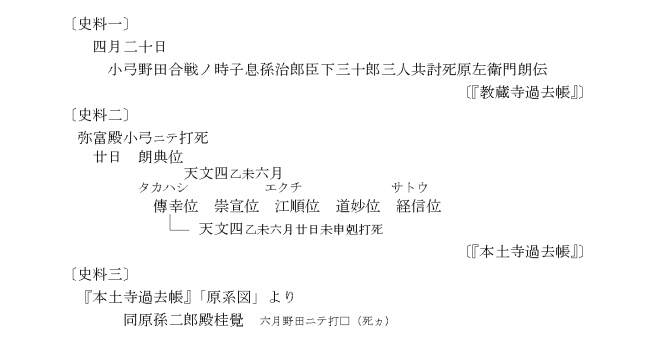
史料三の「原孫治郎殿桂覺」は原基胤のことです。「六月野田ニテ打□(死ヵ)」とは何を表すのかというと、史料一の「小弓野田合戦ノ時子息孫治郎臣下三十郎三人共討死原左衛門朗伝」の「子息孫治郎」が基胤のことで、「小弓野田合戦」で討死したという意味です。「野田」とは、現緑区誉田町の古名で、小弓の東に隣接する地域です。本コラム「その6」でも述べましたが、道哲(足利義明)に従っていた原基胤は離反して、足利高基方に復帰したのが、前年天文3年の11月のことでした。
この小弓野田合戦では、史料二の『本土寺過去帳』廿日条によりますと、「タカハシ」、「エクチ」、「サトウ」ら5人も「天文四乙未六月廿日未申剋打死」したとあります(ただし、経蔵寺の過去帳では死亡日が「四月二十日」となっていて、食い違ってはいます)。「未申剋」とは、今でいう午後1時から同5時の間、という意味です。前週のコラムでも触れましたが、高橋・江口氏は小西原氏(大網白里市小西に本拠をおく原氏一族)の家臣として、同過去帳に何人も記載されています。つまり、この小弓攻めには小弓原氏のみならず、一貫して高基方であった弥富原氏と、これまであまり注目されてはいませんでしたが、小西原氏も参加していたことがわかります。つまり、原氏一族を挙げての戦いであったのです。しかし、小弓原氏・弥冨原氏の当主を含め、原一族とその家臣は討死した者を多く出してしまいました。
小弓原氏は当主基胤が死去したため、弟で牛尾氏を継いでいた胤清が当主の座につきました。その後は、胤清-胤貞-胤栄(たねよし)と続いていきます。
なお、天文4年から3年を経た天文7年(1538)10月、第1次国府台合戦において小弓公方道哲(足利義明)らが討死すると、小弓原氏は20年余りの時を経て、故地小弓を奪回することになります。
小弓浜野・佐倉(弥富)・土気・市原市市東方面にそれぞれ通ずる陸上交通の要地野田でおきた、天文4年の小弓野田合戦の記憶が、冒頭の地元の伝承に形を変えたのではないでしょうか。
この11日の日曜日で特別展も閉幕を迎え、本コラムも今回で最終回となります。まだ書かねばならないこともいくつかありますが、別の機会に譲りたいと思います。最後まで閲覧賜り、ありがとうございました。
「小弓公方足利義明」異聞
その1 名都借要害は名都借城跡のことか
大永7年(1527)11月3日付で、古河公方足利高基は鮎川美濃守にあてて感状(戦功を賞する賞状)を与えています。鮎川氏が名都借要害を攻めて疵を蒙ったことを褒め讃えたものです。翌々年の享禄2年(1529)3月20日には、同じく大永7年の名都借要害攻めで疵を負った鮎河豊後守へ、同様な感状を与えています。美濃守と豊後守は、同族と思われます。
 |
| 写真 名都狩城跡の西側土塁 |
名都借要害とは、流山名都借城跡を指すものと、一般には考えられています。今から10数年前、筆者の属する研究会の合宿で、現地を訪れたことがありました。同城跡には、民家が建っており、家人は御留守であったので敷地内は見学できず、周囲しか見ることができませんでした。北側斜面に横堀はあるものの、台地続きの東側には堀や土塁の痕跡もなく、小規模な館城という印象をもったものです。攻撃を受ければ、たちまち落城しそうなお城なのです。一見した感想は、なぜここの城を攻め、激戦があり、高基が感状を出したのだろうという素朴な疑問でした。
名都借城跡を見学した後、すぐ西に隣接する前ヶ崎城跡へ場所を移して、公園化された同城を見学しました。しっかりした土塁や堀が残り、当時はコンパクトな城と思ったものです。ところが、前ヶ崎城跡は、すでにその頃は第2郭・第3郭とも台地が削られていて、実際の大きさは、南北400m近い規模をもつ大規模城郭でした。筆者たちの見たのは、舌状台地北端に残る主郭部だけだったのです。土地勘がないせいで、残念なことに、この二つの城の関係性には思いが及びませんでした。いずれにしても、小規模な名都借城跡とそこをめぐる合戦とが頭の中で合致せず、頭の片隅に疑問として残ったまま、長い時間が過ぎてしまったのです。
 |
| 写真 前ヶ崎城跡主郭部 |
今回の特別展で、義明(道哲)の動向を探るうち、史料でいう「名都借要害」とは前ヶ崎城のことを指すのではないか、と考えるようになりました。もっとも城関連のネットの記事などには、前ヶ崎城が「名都借要害」のことではないか、とする記述もみられますが、根拠等は示されておらず、不勉強ですが、これを述べた文献にもお目にかかったことがありません。
ここでは、両城について考えてみたいと思います。まず、なぜ名都借要害をめぐって合戦がおきたのか、です。そもそも、高基の感状を得た鮎川氏は、関宿城主簗田氏の家臣です。この合戦は、関宿城主簗田氏が主力となっていると考えてよいでしょう。
では、「名都借要害」に拠っていた主体は誰であったのでしょうか。それは、ずばり義明(道哲)と考えます。
というのも、「展示資料3―16足利高基書状(写真版)」に考えるヒントがあります。この書状には、年紀どころか月日も記されていません。高基が小山政長に宛てて、関宿城へ攻撃をしかけた義明に対し、政長は直ちに参陣して反撃をしたことを賞している内容です。注目したいのは、追って書きに「下口より押返し揺ぎ候」ということを高基が聞き及んだと書いていることです。
よく書状のなかで「〇〇口」と地名で記すことがあります。〇〇への出入り口という意味で、一定の広がりをもつ区域として使われます。しかし、この追って書きの部分では「下口」と、地名ではない特定の場所を示すと思われる書き方をしています。このことから、義明の軍勢は、関宿城の城下町を含む城域まで攻めこんだものと解釈できます。
これに対し、政長は出入り口(下口)の部分で、攻め寄せる義明軍を押し返し、反撃を加えたとされます。残念ながら、日時が書かれていないので、この文書だけではこれ以上のことはわかりません。
しかし、大胆に推理すれば、関宿へ攻め込んだ義明軍に対し、反撃に出た関宿の簗田軍は義明の拠る「名都借要害」(実は前ヶ崎城)に攻め込み、名都借要害合戦が行われたのではないでしょうか。年未詳の史料で、義明の「当地落居不可有程」、「公方様向当地被出御馬候」、「当地御在城」という文言のはいったものが三点あり、「当地」が何処を指すか重要な問題となってきます。ここでの細かい論証は避けますが、大永7年(1527)に、以上述べたような関宿をめぐる大きな動きがあったものと考えます。
なお、国土地理院のウェブページの「空中写真閲覧サービス」で、1961年6月3日国土地理院撮影の前ヶ崎城跡周辺のモノクロ空中写真を見ることができます。
1. 空中写真の検索方法(画面左側) 「空中写真」を選びクリックする
2. 整理番号 MKT613
3. コース番号 C40
4. 写真番号 22
とそれぞれ入れると該当画像1点のみが示されるので、地図上の〇囲みの「1」のマークをクリックすると、モノクロで写真が表示されます。さらに「高解像度」をクリックすると、拡大してもかなりはっきりと見ることができます。拡大縮小は自由にできます。この写真からは、破壊されるまえの北へ延びた舌状台地上の前ヶ崎城跡(堀跡も植生の違いで明瞭にわかる)を見ることができます。すぐ東には名都借城跡も見ることができます。
これをご覧いただければ、当時の高基らが前ヶ崎城(『本土寺過去帳』には前ヶ崎に城があったことが記録されている)を名都借にある要害と間違えても仕方ないと納得いただけるでしょう。それだけ両者は近接し、地元の者でない限り、前ヶ崎と名都借とが混同されやすいものと思われるからです。
その2 里見氏の天文の内乱・武田氏の天文の内乱
小弓公方足利義明を支えた房総の主勢力に、真里谷武田氏と房総里見氏がいます。前者は永正14年(1517)10月15日に小弓城を攻め落とし、原氏や家老高城氏を小弓から駆逐しています。また、後者は「義明様小弓城ニ御移リ、房州里見、常陸鹿島、武州小府佐々木以下、悉ク奉随之」(『快元僧都記』)とあるように、義明の小弓入部からほどなく義明に従ったようです。
両者は天文2年(1533)から同3年にかけて、一族の間でそれぞれ内乱がおこります。先に里見家中で事件がおきました。天文2年7月、稲村城(館山市稲)でおきた当主里見義豊による正木通綱と叔父実堯誅殺についての従来の通説は、滝川恒昭氏によって大きく塗り替えられました(「房総里見氏の歴史過程における『天文の内訌』の位置付け」『千葉城郭研究会』第2号 1992年、後に同氏編著『房総里見氏』戎光祥出版 2014年、に再録)。
父を殺された里見義堯らは真里谷信隆の百首城に逃れ、義豊と敵対する相模国の北条氏を頼りました。やがて、北条氏の援軍を得た義堯方の勢力は義豊勢を追い詰め、義豊は真里谷恕鑑を頼り上総国へ逃れることになります。真里谷武田氏でも父恕鑑と子の信隆が、敵味方に分かれたのです。翌3年4月、恕鑑や小田喜武田朝信の支援をうけた義豊は、安房国へ攻め入りますが、犬掛(南房総市)で義堯軍と戦い敗れ討死しました。
 |
| 写真 南方向(一ノ坪方面)からみた稲村城跡 |
こうして、里見義通・義豊と続いた本宗家は、義堯とその子孫へと交替しました。滝川氏によれば、この時に、義豊系統(前期里見氏)の痕跡は意識的に消されたということです。以後は、勝利した義堯の系統(後期里見氏)が近世初頭まで続いていくことになります。
この里見氏の内乱に、小弓公方足利義明の関った形跡は見当たりません。おそらく、小弓から遠く離れた安房国での出来事であったから、と思われます。
この里見氏の内乱では、真里谷武田氏は親子で義豊方と義堯方とに分かれましたが、この矛盾は天文3年(1534)、今度は真里谷武田氏の内紛となって現れます。恕鑑の跡目をめぐって対立、抗争した武田氏天文の内乱です。この年の7月1日に死去した恕鑑の家督を嫡子信応(のぶまさ)がとるか、庶子信隆(こちらを嫡子とみる説があります)がとるか争われました。既に同年5月10日の段階で、足利義明は信応に対して、上総が意のままになったならば、荘園を一つ与える旨述べています。恕鑑死去の前から、なにやら内部対立の気配が感じられます。
そのわずか十日後、足利義明は「上総衆(信隆ら)」退治のため出陣しています。そして11月20日には、義明は真里谷や椎津城を攻撃して「敵百余人」を討ち取ったとされます。庶子信隆とその支持勢力の籠っていた諸城です。真里谷城に庶子信隆が入っていたとなると、嫡子である信応は本拠となる真里谷城にいられなかったのでしょうか(信隆を嫡子とみれば問題ありません)。小弓公方足利義明を支える最大勢力である真里谷武田氏の内乱は、義明の力で信応方の勝利で終わりました。
しかし、諸矛盾の根本的解決にはならなかったようで、天文6年(1537)5月、再び上総国で内乱が勃発しました。第二次武田氏天文の内乱です。5月14日、信隆は「新地」の城に立て籠もり、信応の追放を義明に訴えました。実は、この「新地」の城についても、真里谷城(木更津市)に近接する天神台城(同前)とみる考え(通説)と、真里谷城を指すという考えの二通りの説が存在しています。本題からはずれますので、詳説はしませんが、末尾に参考文献をあげておきますので、興味がおありの方はご覧ください。以下は、通説に基づいて述べたいと思います。
さて、信隆の訴え=蜂起に対して、義明は天神台城をはじめ、信隆方として蜂起した峰上城(富津市)・百首城(同前)を攻撃しました。義明の命をうけ里見義堯は百首城を、信応は天神台城を攻めました。義明は峰上城を攻めましたが、これは反乱の拠点であったからとされます。信隆方は北条氏に救援を求め、北条氏は「特殊軍事部隊=大藤衆」である大藤金谷斎(おおとう きんこくさい)を天神台城に遣わしました。
ところが、信応方の攻勢の前に天神台城は窮地に陥りました。北条氏綱は、信応・義明方に和睦を申し入れ、その交渉の窓口となったのが、後に駆け込み寺として知られることになる鎌倉の尼寺、東慶寺主渭継尼(いけいに)らでした。彼女は義明の妹とされます。氏綱はこの関係を利用し、和睦を願ったものです。
 |
| 写真 真里谷城跡の主郭 千畳敷 |
そして小弓公方義明の「御免」により、峰上城ほか二か城の籠城勢力の赦免と大藤金谷斎らの帰国も許されました。反乱の主体であった信隆は、峰上城を明け渡して降参しました。信隆は、当時の降参の作法として、鶴岡八幡宮や江の島への参詣という形をとりました。その後は北条氏の庇護のもと武蔵に留まることになりました。
このように、里見氏と真里谷武田氏の天文年間のそれぞれの内乱は、違った形で終結しましたが、とくに真里谷武田氏の場合、天文6年に内乱が再燃したことが小弓公方足利義明の運命に大きな影響を与えることになりました。天文7年の第1次国府台合戦における義明の敗死です。国府台合戦については、別の機会に譲りたいと思います。
【参考文献】 文中に示したほか
『千葉県の歴史 通史編 中世』千葉県 2007年 第三編第一章第五節「小弓公方と房総の諸氏」(佐藤博信氏執筆分)
黒田基樹『戦国の房総と北条氏』岩田書院 2008年
簗瀬裕一「真里谷城跡出土の遺物の歴史的位置-天文六年「新地」の城との関係を中心に-」(佐藤博信編『中世東国の政治構造』岩田書院 2007年、黒田基樹編『武田信長』戎光祥出版 2011年、に再録)
小高春雄「真里谷「新地」の城について」『千葉城郭研究』第3号 1994年(同前黒田基樹編『武田信長』)
その3 猿田神社と足利晴氏(前編)
旭市(旧海上町)見広から、県道71号線銚子旭線を台地上に上るところで、真南に突き出た半島状の出張部が左手に見えます。これが見広城跡です。城主島田三河守の伝承をもつ城で、この道を抑える役割を果たしています。
見広から台地上を上りきった所で、県道73号線銚子海上線が分かれ、銚子市小舟木へと向かっています。そのまま県道71号線を進むとJR倉橋駅前を通り、次の猿田駅を経て、中島城(本「研究員の部屋」千葉六党の城 中島城1・2で紹介済)に至ります。猿田駅のすぐ近くに猿田神社が鎮座しています。同社については、後編で取り上げます。
さて、県道73号線を小船木町方面に進むその途中から、野尻町方面へも道は分岐しています。野尻町は、塩の流通に深く関った商人宮内氏の本拠地で、実際、太平洋岸の旧飯岡町で生産された塩がこの道を運ばれてきました。以下、当館所蔵の「原文書」と、「宮内家文書」(『戦国遺文 房総編』)で、この事に関る部分がありますので、紹介したいと思います。
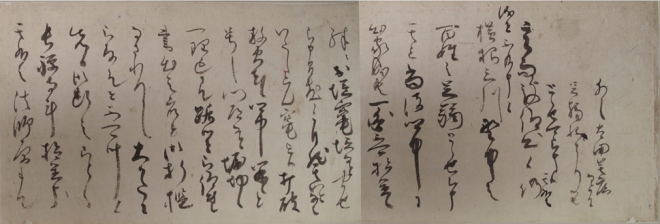 |
| 写真 年月日未詳千葉胤冨書状断簡 |
| 「原文書」千葉市立郷土博物館所蔵 |
この文書は、鈴木哲雄氏によれば、横根郷の百姓らが逃散したことに対する、千葉胤冨の対応を示したものとされます。村から逃げた大人に対し、「足弱」(老人や子ども)は村に残っていたのですが、それを許さず「とらせ」(捕らせ)ることを命じています。また、この間、塩竈を使うようなことがあれば、これを「打破」り「放火」することも命じています。
文中に「横根・三川・野中」と地名が出ていますが、これらは旭市(横根と三川は旧飯岡町)の九十九里平野北東端の地域です。「塩竈において塩など焼かせ申すまじく候」とあるように、この一帯は塩の生産地でした。「千葉胤冨判物」(原文書)によれば、「塩荷より五文役」、「塩舟の出役」、「地摺の役」という税(労役も含むか)が課せられていました。
「宮内家文書」の元亀3年(1572)閏正月3日付の「千葉胤冨黒印状写」によれば、流通商人の宮内清右衛門尉に対し、7貫500文を納めるよう命じています。宮内氏は三川で五反の田を持ち、塩の生産に関っていたことがわかります。また、「御舟」の生産に携わっているので、500文は免除すると追而書きにあります。「御舟」とあることから、千葉氏あるいは海上氏の舟の製造に関わっていたのでしょうか。宮内氏の本拠野尻に隣接して小船木があり(銚子市小船木町)、舟の製造に用いられる木材の供出地であったことが伺われます。
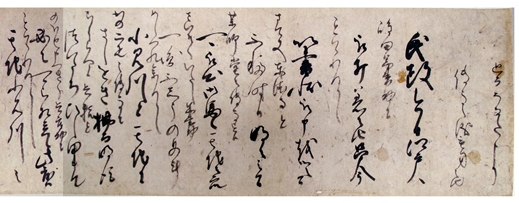 |
| 写真 元亀2年ヵ8月28日付宛先不詳千葉胤冨書状(前半部) |
| 「原文書」千葉市立郷土博物館所蔵 |
見広城主と伝承される島田氏は、一族と思われる島田図書助が伝馬に関るなど流通に関わっていました。元亀2年(1571)ヵ8月28日付宛先不詳「胤冨書状」からは、以下のように島田図書助が伝馬に関っていたことがわかります。写真上の行間追而書一行目に「島田図書助に」、以下「ことハられへく候」(同二行目)、「さて又東徳寺と」(同三行目)、「薬師堂之伝馬をハ」(同四行目)、「さいそくいたし図書助」(同五行目)、「めしつれ参へく候」(同六行目)と記されています。
「天文10年(1541)3月21日付海上堀内妙見社棟札写」(宮内家文書)に「島田図書助秀常」が、奉行人として記載されており、官途名を同一とすることから、元亀2年に登場する図書助の親にあたる人物かと思われます。堀内妙見社は中島城に近接して建立されており、代々の海上本宗家が崇拝していました。その妙見社建立の奉行人を務めていたのですから、島田氏は、海上氏の重臣級と考えられます。
見広城主とされる島田三河守と、この図書助が同一の系統か否か不明ですが、重要な街道を抑える城主三河守と、伝馬に関る人物である図書助とは近い一族、もしくは近親関係にあったのではないでしょうか。
【参考文献】
『海上郡誌』千葉県海上郡教育会 1917年
『匝瑳郡誌』千葉県匝瑳郡教育界 1921年
小笠原長和「戦国末期における下総千葉氏」『中世房総の政治と文化』吉川弘文館 1985年(初出1970年)
滝川恒昭「銚子野尻 ~今むかし~」『千葉県史料財団だより』1993年
遠山成一「戦国後期下総における陸上交通について」(石渡洋平編著『旧国重要論文集成 下総国』戎光祥出版 2019年(初出1994年)
石渡洋平「戦国期下総海上氏の展開と動向」『駒沢史学』83号 2014年
鈴木哲雄「海上千葉氏の領国支配―網代・製塩・「郷中開」―」『都留文科大学大学院紀要』第27集、2023年
その4 猿田神社と足利晴氏(後編)
さて県道71号線を見広から銚子方面に向かうと、総武本線に沿う形で道が伸び、やがて猿田駅に至ります。駅の手前を左に入ると大きな鳥居があり、総武本線を渡る跨線橋があって境内に入ります。猿田彦を祀る猿田神社(さるだじんじゃ)です。猿田彦は、瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)の天孫降臨の際、道案内をしたとされ、交通の神とされます。銚子市の猿田神社は大同2年(807)の創建とされ、源頼朝や足利氏、千葉氏らの崇拝を受けてきたと伝承されてきました。
 |
| 写真 猿田神社拝殿 |
飯岡方面から野尻町・高田町など香取内海へ抜ける「塩の道」沿いに、交通の神を祀る同社が存在するのも意味があることと考えられます。そして、同社には足利晴氏が奉納したという金印が所蔵されています。『海上郡誌』によると「天文の際関東管領(ママ)足利左兵衛督晴氏、北条氏綱と意を合わせて当国の国司御弓に住める義明朝臣を追はんとて、下総古河より発向其の節当社へ参拝神宝を奉納す」(旧字体は新字体に直す)とされます。足利晴氏が、小弓公方義明を追討するため下総古河から発向した事実は、史料等では確認できませんが、こうした伝承が存在したのかもしれません。
実際、天文7年(1538)10月におきた第1次国府合戦は、足利晴氏が北条氏綱に義明の「退治」を命じたものです。昨年度の特別展でも展示した史料に「先年亡父氏綱応 上意令進発」(「北条氏康条々」東京大学史料編纂所所蔵伊佐早文書)とあり、上意(晴氏の命令)に応じて氏綱が戦ったことがわかります。
晴氏が猿田神社に金印を奉納する意味を考えると、同社は導きの神(ニニギノミコトを道案内したところから)であり、交通の神であったことがまずあげられます。さらに銚子周辺を支配していた海上氏は、古くからの古河公方の奉公衆であったことが大きいと思われます。
これは想像になりますが、別稿(千葉市内の城 千葉六党の城 中島城1・2)で書いたように、海上氏の富の根源ともいえる「塩の道」を扼する同社への古河公方からの奉納は、海上氏にとって意義深いものであったと思われます。なお、前編でも紹介した飯岡と野尻とを結ぶ、この「塩の道」を最初に指摘されたのは、滝川恒昭氏でした。
 |
 |
| 写真 金印(レプリカ) | 写真 金印の印影(印文不詳) |
先日、筆者は宮司様のご厚意で金印レプリカ(昭和45年:1970年作製)を拝覧して参りました。上記写真は、その時に撮影したものです。印影は未解読です。「覇」の文字に見えますが、どなたかご教示いただければ幸に存じます。
続いて、匝瑳市生尾の老尾(おいお)神社には、「足利晴氏千葉胤富状を下して本社に大宮司大祢宜を匝海二郡諸社々の長たるへきを沙汰せられたり」(『匝瑳郡誌』)との伝承があります。このことについて『八日市場市史 上巻』では、「信頼できる写し」にもとづいて「天文二十三年」付の足利晴氏「下知状」なるものを紹介しています。なお、『戦国遺文 古河公方編』(佐藤博信編 2009年3刷り)には、744号「足利晴氏判物写」として、同文書が紹介されていますが、「本文書、なお検討を要す」とされています。
その後、東庄町教育委員会所蔵の旧東保胤氏文書の写し(これが『八日市場市史』にいう写しヵ)、を写真版で拝見する機会に恵まれました。書かれている文言でやや不自然な表現もあり、全面的に「信頼できる」か、やはり疑問があります。しかし、この「天文二十三年(1554)甲寅八月十二日」という年が、おおきな意味を持っていると考えます。
すなわち、この年の7月24日に晴氏は、子息義氏(当時はまだ梅千代王丸と幼名を名のる)と一緒にいた葛西(東京都)を離れ、古河へ帰座しました。そして、「古河城の普請を行い、一戦を交える覚悟を示した」(佐藤博信『中世東国の権力と構造』第2.部第四章第六節 天文時間の惹起-晴氏・藤氏の古河籠城-、2013年:初出2010年)とされます。すなわち、晴氏父子は小山氏らとともに「反旗を翻した」(同前)わけです。
晴氏は、すでに(不本意ながら)家督を譲った梅千代王丸(北条氏康の娘芳春院殿の子)との間で確執があり、梅千代王丸に家督をとって代わられた子息藤氏とともに、古河への籠城を決意したようです。しかし、この行動は公方家臣団の一部の支持を得ただけで、10月上旬には梅千代王側(北条氏側)に下り、晴氏は相模秦野(神奈川県)へ幽閉され、政治生命を絶たれることになりました。
晴氏の老尾神社への文書は、このような政治的背景で発給された可能性があります。すなわち、葛西の梅千代王に対抗し、古河城から古河公方としての権威で同社へ発給した、ということです。なぜ、老尾神社なのかは不明ですが、鹿島神宮(茨城県鹿嶋市)にも晴氏は多くの文書(巻数請取状)を発給しており、また猿田神社の晴氏奉納とされる金印の存在があります。鹿島・銚子・匝瑳地域に、晴氏の影がかたまって見えるのは興味深いことです。
なお、老尾神社の晴氏文書の存在ついては、滝川恒昭氏の御教示をいただきました。
擱筆にあたり、猿田神社宮司の猿田様には、金印の拝覧および写真の掲載につき、ご諒解賜り深謝申し上げます。また、晴氏下知状写の写真については、江澤一樹氏の御厚意により拝見いたしました。『海上郡誌』は外山信司氏にご教示いただきました。
『千葉氏史料集』編さんノート
坂井法曄(千葉市立郷土博物館史料研究員)
- 千葉氏における正直の系譜(おぼえがき〔2〕) ―十善の国王、新皇将門の諂佞、千葉宗家の滅亡など―
- 千葉氏における正直の系譜(おぼえがき〔1〕) ―十善の国王、新皇将門の諂佞、千葉宗家の滅亡など―
- 「千九曜之旗」は存在せず ―『源平闘諍録』の一文字を読み直す―
- 清宮家本『千学集抜粋』の書き込みについて
- 『千学集』誤読ばなし ―紙魚のいたずら?―
- 『千学集』と『千葉妙見大縁起絵巻』の断章 ― 川を渡る馬と水位、および絵巻と詞書の齟齬 ―
- 特殊な文字を読む(『千学集抜粋』から)
- 『千学集』メモ①(その成立過程と作者のことなど)
- 『千学集』メモ②(抜粋・清宮家本の筆者・書名について)
「千九曜之旗」は存在せず ―『源平闘諍録』の一文字を読み直す―
はじめに
『平家物語』の異本である『源平闘諍録』は、千葉一族の活躍を特筆した軍記物として知られています。スペースの関係で、全文を収録することはかないませんが、『千葉氏史料集』(仮称、以下同)にも、千葉氏の動向をつづった「巻五」を抄録すべく、鋭意作業をすすめています。
その巻五に「妙見大菩薩之本地事」という一節があります。同節は、源頼朝の問いに千葉常胤が答えるかたちで、一族の崇敬する妙見菩薩の由緒を語ったものです。常胤が答えていうには、
そのむかし「蚕飼河(こがいがわ)の合戦」において、童子に化身して平将門を守護した妙見菩薩が、将門に対し、みずからの本地(本来の姿)と垂迹(仮りの姿)をあかし、また誓願とその利生(神仏が衆生に利益を施すこと)を語り、そして北方の角に向かって妙見菩薩の名号を唱え、これよりは笠験(かさじるし)に九曜の旗を掲げよ、と説示して、どこへともなく姿を消した・・・。
とのこと。ちなみに「九曜の旗」について『源平闘諍録』は「今に月星と号するもの」と割書しています。そしてこの「今に月星と号する」「九曜の旗」こそ、千葉氏の家紋や千葉市章のルーツであることは、周知のとおりです。
これまで『源平闘諍録』は、多くの先学によって翻刻や研究が積み重ねられてきましたが、さらに研究をすすめるべく精読していたところ、わずか一文字ながら、標題に掲げた既刊書の読みを改めることになりました。小稿はそのささやかな報告です。
1)先行刊本等について
まずは『源平闘諍録』の主な刊本・影印を掲げましょう。
①山下宏明編著『源平闘諍録と研究(未刊国文資料 第2期第14冊)』(未刊国文資料刊行会,1963年)
②早川厚一・弓削繁・山下宏明編著『内閣文庫蔵源平闘諍録』(和泉書院,1980年)
③千葉市立郷土博物館編刊『妙見信仰調査報告書(三)』(1994年)
④福田豊彦・服部幸造注釈『源平闘諍録』上下2巻(講談社学術文庫,1999-2000年)
⑤松尾葦江・山本岳史・小口雅史・遠藤祐太郎解題『源平闘諍録 将門記抜書 陸奥話記(内閣文庫所蔵史籍叢刊 古代中世篇第8巻)』(汲古書院,2012年)
①は『源平闘諍録』の全文を翻刻収録し、その内容について考究した著書で、今でも多くの研究者によって活用されています。②は内閣文庫に所蔵される写本の影印(図版)を収載し、さらに各巻の難読文字やオコトテンの付点箇所を摘記。また解題を設けるなど、研究上の便宜をはかっています。③は当館の刊行物で、『源平闘諍録』巻一・巻五を抄録。あわせて『妙見実録千集記』の翻刻文と、関連論文3編が収録されています。④は『源平闘諍録』の全文を書き下して収録し、詳細な注釈と解題を収めます。文庫版の、現下もっとも入手しやすい学術的かつ啓発的な書籍です。⑤は2色刷によって朱筆部がわかるよう、改めて刊行された影印本で、解題では研究史を要説。また②と同じく難読箇所を摘記し収録します。
その他、未完ですが、早川厚一「源平闘諍録全釈」(『名古屋学院大学研究年報』18,2005年~継続中、他誌にも掲載)は、文字どおり『源平闘諍録』全文の訳注を進める労作で、完結が鶴首されます。それから近年の研究では、源健一郎「源平闘諍録の成立環境―関東天台の動向から―」(関西軍記物語研究会編『軍記物語の窓』6集、和泉書院,2022年)によって、作者に関する先行研究およびその問題点、また多くの視角を学ぶことができました。
なお現在「国立公文書館デジタルアーカイブ(www.digital.archives.go.jp)」に、『源平闘諍録』全体の鮮明なデジタル画像が公開されていて、『千葉氏史料集』の底本にこれを用いたほか、小稿下掲の図版としても活用させていただきました。上掲の先行研究・機関に深く感謝申し上げます。
2)「妙見大菩薩之本地事」の一文字をめぐる
本題に入りましょう。問題箇所は下掲の【図1】朱線部です。
 |
| 【図1】 |
一瞥して右さがりの特徴的な書風が看取されます。前述どおり、当該部は「蚕飼河の合戦」において、童子に化した妙見菩薩が平将門を守護し、本地を明かした上で「将門よ、北方の角に向かって吾が名号を唱えよ。そしてこれよりは、笠験(かさじるし)に九曜の旗を掲げよ」(取意)と説示し、姿を消したという一節です。
ただし前掲①以降の既刊書をはじめ、管見に入った先行論著は、いずれも「可差千九曜之旗(千九曜の旗を差すべし)」(【図1】朱線部)と翻刻、あるいは引用しています。つまり「九曜」に「千」が冠されて「千九曜」とされているのです。中には「千九曜」に「せんくえう」のルビを振ったもの、語訳に「千九曜」を立項したもの、また「千九曜」が平良文をへて千葉氏に伝承し、家紋とされた、と解説したものもあります。問題は「千九曜」の「千」の字です。
私見をいえば、当該文字は「千」ではなく「于」と読むべきです。すなわち【図1】朱線部は「可差于九曜之旗(九曜の旗を差すべし)」となります。客観的にこれを示しましょう。下掲【図2】をご覧下さい。
 |
| 【図2】 |
左には問題箇所の図版、そして右側には『源平闘諍録』の原文に散見される「千」と「于」を掲げました。「千」の字から見ていくと、右より「千万輩」「千葉介」「千余騎」「千田ノ庄」です。ここに見られるとおり、写主は「千」を書く場合、一画目を左斜め下に払ってから、二画目を書いていることが看取されます。
つづいて「于」を見ましょう。右から「于今」「于時」「于景時」ですが、「千」の字形とは明らかに異なります。そして比較すれば一目瞭然、ここに掲げた「于」の字形は「于九曜」の「于」とまったくの同形といえるでしょう。
念のため、内閣文庫に所蔵されるもう一つの写本(副本)からも、同じ文字を拾って確認しましたが、結果は下掲【図3】のとおり全同でした。これによって問題の箇所は「千九曜」ではなく「于九曜」であることが明らかとなったのです。
 |
| 【図3】 |
なお「可差于九曜之旗」にみられる「于」は前置詞(置き字=訓読時に読まない文字)で、場所・対象等をあらわす際に用いられます。参考として『源平闘諍録』にみられる前置詞「于」の用例をあげておきました(下掲【図4】)。
 |
| 【図4】 |
右が問題箇所の図版と釈文で「九曜の旗を差すべし」と訓読し「于」は読みません。中央は「君に相随(あいしたが)い奉る」と読み、やはり「于」は読みません。そして左も「景時に免ずべし」で、むろん「于」は読みません。
このように問題の朱線部は「可差于九曜之旗(九曜の旗を差すべし)」と読まなければならず、もとより「千九曜之旗(千九曜の旗)」なるものは存在しなかった、と結論されるのです。「千」か「于」か、たかが一文字、されど一文字です。
おわりに
昭和時代、やはり「千」か「于」かをめぐって、物議を醸したことがありました。それは日本天台宗の祖、最澄筆『天台法華宗年分縁起』の一節です。問題となった箇所は「国宝とは何物ぞ。宝とは道心なり、道心ある人を名づけて国宝となす。故に古人の言わく、径寸十枚(※金銀財宝のこと)、是れ国宝にあらず。一隅を照らす、此れ則ち国宝なり」の「一隅を照らす」〔(※ )内=坂井注〕です。
それまで原文は「照于一隅」とされてきたため、訓読は「一隅を照らす」でしたが、研究者から最澄の自筆は明らかに「照千一隅」である、との指摘がなされたのです。最澄の自筆は国宝に指定されているため、当該部の図版は比較的多く紹介されていて、その図版を見るに、もはや字形は「于」ではなく「千」であることが明らかです。
それはともかく「千」と「于」は字形が類似するため、誤読されることもしばしばです。活字と違い、筆を用いて書かれた文字は、人によって字形がまちまちで、特に癖字は、繰り返し読まなければ、解読できないことが多々あります。『千葉氏史料集』に抄録する『源平闘諍録』巻五の筆勢も右さがりの癖字です。小稿で図示したように、異なる文字を並べて比較すれば、その違いは一目瞭然ですが、墨書に覆われた紙面に埋もれてしまうと、その違いに気づくことは容易ではありません(下掲【図5】)。
 |
| 【図5】 |
『千葉氏史料集』に抄録する『源平闘諍録』巻五については、今後さらに照校を重ねますが、字形や文意に注意しながら、繰り返し原文を読むことによって、また新たに見いだされることがあるかもしれません。
戦国期に房総で活躍した日我(にちが=1508~86)が「一字尽千思 一語廻万慮(一字に千思を尽くし、一語に万慮を廻らす)」(『いろは字』奥書)と語っているように、これからも、そんな思いで文書の一字一句と向き合い、編さんに従事する所存です。
清宮家本『千学集抜粋』の書き込みについて
『千葉氏史料集』(仮称、以下同)には、前回とりあげた『源平闘諍録』を抄録するほか、『千学集抜粋』(以下『千学集』)の全文を収録する予定です。『千学集』は、誤伝はみられるものの、今なお、中世の千葉氏をかたるに不可欠な史料です。既刊書として『房総叢書』・『戦国遺文(房総編)』、また当館編刊『妙見信仰調査報告書(二)』等がありますが、今回あらためて清宮家本を底本として、一から翻刻作業をすすめることにしました。
『千学集』の原本は、残念ながら失われてしまったようで、先行研究でも指摘されているように、清宮家本をさかのぼる写本は見つかっていません。『千葉氏史料集』の底本に清宮家本を選定したのは、かかる理由によります。
ちなみに清宮家本の伝えるところ「千学集と申すは、御家代々引付と、妙見御相伝の正月三日の夜の修正とハ、千文字・葉文字の二字を題として、よろつことの葉を続けて、年中の事を顕はし給ひて、妙見の御前にて慚愧懺悔をし、年中の悪念を払ひ祭ることの御鈴なり、是れ御一門及び国内繁昌の御祈念なり」とのこと。つまり毎年正月三日に行われる修正会(しゅしょうえ=国家安泰・五穀豊穣などを祈る法会)に合わせて、妙見菩薩に悪念払いと一族繁昌等を祈念していたようですが、『千学集』は、その由緒を記すために編まれた書物というのです。
 |
| 『千学集抜粋』(清宮家本・個人蔵) |
おそらくは一族の歴史について、かように妙見菩薩の加護のもとに歩んできたことをつづり、未来永劫その冥護を得ようとしたのでしょう。また構成については「この千学集は三巻にて、千文字一巻、葉文字一巻<上下にて二巻>なり」といっています。
その『千学集』を抜粋したのが清宮家本です。いまこれを通覧してみると、本文とは別に、天地端奥、行間の余白部に、細字によるあまたの書き込みが確認され(上掲図版)、また「イ」と注記して書き込まれたものも散見されます。「イ」とは「異本」のこと。もとは同じ書物でありながら、伝来の過程における加除修正等により、異なる内容をもつにいたった本を指します。あたかも『平家物語』の異本として『源平闘諍録』があるように、清宮家本にみえる「イ」の注記によって『千学集』にも異本のあったことがわかるのです。
『千学集』で語られる項目は、一節一節で完結している話も多いのですが、細字による書き込みは、各節に照応する内容が多く、しかも場所や登場人物の異なる記事がみえることから、いずれも異本の文章と思われるのです。ちなみにこれらの細字は、既刊書には収録されていません。
また清宮家本は「栗飯原」に「粟ナラン(〝栗〟は〝粟〟の誤記ではないか、の意)」と頭注をくわえるなど、底本となった『千学集』の本文について、いくつかのコメントをのこしています。
そこで『千葉氏史料集』では、清宮家本の余白に書き込まれた細字や異同の注記についても収録することにしました。細字の書き込みについては、ほぼ入力作業を終え、目下、どの節に関連する記事であるのか照合しています。ただ書き込みは、前後のページや行間にわたっているため、そのまま翻刻すると煩雑になってしまいます。
どのようなかたちで収録するかについては、いくつかの案が出されていて、照応する各節の末尾にポイントを落とす、あるいはフォントを変えて収めるなど、思案中です。いまだ校正が不充分なため、ここに紹介することはできませんが、細字を含めた全文を収録することによって、より詳細な『千学集』の世界と全容を知っていただけると思います。どうぞお楽しみに。
(付記)
『千学集抜粋』(清宮家本・個人蔵)の図版を掲載するにあたり、所蔵者よりご許可をいただきました。衷心より御礼を申し上げます。なお図版は次回も掲載させていただきます。
『千学集』誤読ばなし ― 紙魚のいたずら? ―
 |
| 【図1】(『千学集抜粋』清宮家本・個人蔵) |
まずは【図1】をご覧ください。前回から取りあげている『千学集』の一部です。①朱線部は「人々」と読み、後続の文章を加えると「人々まゐり(参)て」となります。次に②朱線部をみましょう。①下部の字形と同じに見えますが、「助々」ではおかしいので、私は「助之(の)」と読みました。前後を加えれば「御使は本庄図書之助の御下部三人」となります。
およそ①②朱線部の下部にみえる字形は「之(し)」か「々」か「候」で、字形だけでは判別は困難なため、文意によって読み分けることもしばしばです。
ところが②の読みは間違いでした。実は当初、『千学集』の校訂作業は、モノクロマイクロフィルムの引き伸ばし(【図1】)をもとに行っていたのですが、その後、カラー写真を拝見する僥倖にめぐまれ、改めて照合したところ、私が「之」と読んだ部分は、文字ではなく虫食いだったことがわかったのです(下掲【図2】左)。私の誤読(誤解)はこれにとどまりませんでした。下掲【図2】右は当初、モノクロによって「細燈を主るらん」と読みました。「主る」は「つかさどる」と読み「管理する」という語意があります。
問題は「主る」下の「らん」です。「らん」は推量の助動詞で「~だろう」と訳します。したがって「主るらん」は「管理するだろう」といった文意になるかと思いますが、文脈に違和感はもったものの、字形からそのように判断した次第です。
ところがカラー写真によって、私が「らん」とした箇所も虫食いであることがわかったのです(【図2】右)。正解は「細燈を主る(細燈を管理する)」でした。
 |
| 【図2】(『千学集抜粋』清宮家本・個人蔵) |
紙魚(シミ=紙を喰らう虫)のいたずら? とも思える珍事でしたが、虫食いで字形ができるという話は、早く漢訳仏典『大般涅槃経』巻二などにみられ、これを受けて天台大師智顗(538~597)は『摩訶止観』巻一下に、
「若但聞名口説。如蟲食木偶得成字。是蟲不知是字非字(もしただ名を聞いて口に説くは、虫の木を食らい、たまたま字を成すことを得たれども、この虫はこれ字なるか、字にあらざるかを知らざるが如し)」(『大正新脩大蔵経』46巻10頁b)
と譬えています。当文は「六即(ろくそく)」という修行段階の一つ「観行即(かんぎょうそく)」に関する説示ですが、智顗は「修行の途上にある者は、語意も分からず、ただ聞いた言葉をなぞっているのと同じである。それはあたかも、虫が木を食べ進め、文字の形を作したとしても、その虫が文字かどうかも分かっていないようなものだ」というのです。
私は虫食いを虫喰いとは知らず、これを文字として読んでしまったわけですが、畢竟するに、まだまだ修行が足りないということでしょう。くずし字解読の修行は果てしなくつづきます。
『千学集』と『千葉妙見大縁起絵巻』の断章 ― 川を渡る馬と水位、および絵巻と詞書の齟齬 ―
平良文と平将門は桓武天皇の末裔である・・・。『千学集』は、良文・将門の系譜をもって起筆されます。そして時は承平元年(931)、将門は謀反を起こし、良文をともなって上野国(群馬県)へ乱入。平国香と一戦を交えた、という物語がはじまるのです。おりしも戦場を流れる染谷川は、増水によって渡ることができません。そこに現れたのが小童に化身した妙見菩薩です。小童は瀬踏(せぶみ=足を踏み入れて川の深さを測ること)をして良文と将門を先導。二人は無事に染谷川を渡ったのみならず、合戦では妙見が拾い与えた矢をもって、みごと国香の大軍を打ち破った、というのです。こうして二人と妙見菩薩との間に、浅からぬ因縁がむすばれました。
 |
| 【図1】 |
そんな物語をつづる『千学集』ですが、この一節の中で、どうしても得心のゆかぬ一文がありました。それは【図1】拡大部の読みです。
ちなみに先行する写本・刊本では、次のように読んでいます。
馬のふと腹かくすにて渡す(内閣文庫本・大森金五郎写本【補注1】ほか)
馬ノフト腹カクスニテ渡ス(恩田信日渉園叢書)
馬の太腹隠すにて渡す (房総叢書)
馬のふと腹かゝすにて渡す(妙見信仰調査報告書2)
前文をまじえて読むと、小童が瀬踏をしたところ、染谷川の水かさは、瞬く間に下がり、そして「良文と将門を馬の太腹・・・・・にて対岸に渡した」となりましょう。しかし諸本アンダーライン部のように、馬の太腹を「かくす」なのか、あるいは「かゝす」なのか、さらに『房総叢書』は「かくす」を「隠す」と変換していますが、いずれであっても文意が判然としません。ただ悶々とするばかりでした。
 |
そんな中、この字画が目に焼きついていたからでしょうか。校訂作業をすすめていたところ、類似する「へからす(べからず)」の連綿(つづけ字:【図2】)を目にしてハッとしました。問題の箇所は「かくす」ではなく、「かゝす」でもなく、「からす」ではないか?
【図2】と【図3】の連綿は、長短の違いこそあれ、ともに「からす」と読んで問題はありません。【図3】をみると、写主はまず「馬の頭」と書いたあと、挿入線を用いて書き落とした「ふと腹からす」を追記したと考えられますが、先行書は、なぜか「頭」の一字を読んでいません(あるいは「頭」を「す〔須〕」と読んで衍字とみたか?)。
ともかく私見では、当該部の読みは「馬のふと腹からす頭にて渡す」です。あとは、この読みで、語意と文意が通じるかどうかです。まず「からす頭」を辞書で引いてみたところ、「からす‐がしら【烏頭】」がありました。語意は「(「烏頭」の訓読)馬の後足の外部に向かった関節。くわゆき」(『日本国語辞典』2版)です。また「馬の太腹」は下腹ともいい、文字どおり馬の大きな腹のこと(同前)。また「膨らんで垂れたところ」(『日葡辞書』)とも解説されます。つまり「馬の太腹・烏頭にて渡す」の文意は、「妙見菩薩が霊威により、増水した染谷川の水位を馬の太腹・烏頭まで下げ、良文と将門を事なく対岸へ渡した」となりましょう【補注2】(※太腹・烏頭の部位は【図4】を参看)。
 |
| 【図4】(『馬並馬具之圖』等を参照し描画) |
また『日国』には次のとおり、用例も挙げられていました。
*平家物語〔13C前〕一一・勝浦「塩干がたの、をりふし塩ひるさかりなれば、馬のからすがしら、ふと腹にたつ処もあり」
ここでは「引潮時になれば、馬の烏頭・太腹まで水位がさがる所もある」といっており、水位をしめす語句として「馬の烏頭・太腹」が用いられています。さらに『平家物語』の異本で、『千学集』とも関係の深い『源平闘諍録』八下(一谷・生田森合戦の事)にも用例があって、海面の様子をみた熊谷直家が「此の海は遠浅と覚へ候」といい、これにしたがって進んだところ「案の如く遠浅にて、馬の太腹・烏頭には過ぎず」(福田豊彦他注釈『源平闘諍録 下』講談社学術文庫。412P)といっています。これらは『千学集』の一節「馬の太腹・烏頭にて渡す」を理解するに、はなはだ有益な類例といえましょう。
また時代はさかのぼりますが、源頼信(968~1048)が香取の海を馬で渡った話が、次のとおり『今昔物語』などに見えます。
此ノ海ニハ浅キ道、堤ノ如クニテ、広サ一丈許ニテ直ク渡リアリ。深サ馬ノ太腹ニナム立ツナル(日本古典文学大系25『今昔物語集 四』386P)
本件については『宇治拾遺物語』巻十「河内守頼信、平忠恒ヲ責事」も、
この海の中には、堤のやうにて広さ一丈ばかりして、すぐに渡りたる道あるなり。深さは馬の太腹に立つと聞く…(中略)…誠に馬の太腹に立ちて渡る。
(新日本古典文学大系42『宇治拾遺物語 古本説話集』273P)
と、「烏頭」こそみえませんが、「馬の太腹」を水位をしめす語句として挙げているのです。おそらく当時の人々は「水深は馬の烏頭・太腹くらいだ」といえば、おおよその見当がついたのでしょう。むろん『千学集』の一節は挿話ですが、そんな想定のもとに書かれていることは間違いありません。
そして『千学集』当該部の改訂成果は、『千葉妙見大縁起絵巻』の詞書(ことばがき)にも及びます。詞書と『千学集』の本文が密接な関係にあることは、当館の『妙見信仰調査報告書』等にも報告されているので周知のことですが、このたび、詞書で解読されていなかった箇所を、読むことができました。
 |
| 染谷川で良文と将門を先導する妙見菩薩(左) |
| 紙本著色千葉妙見大縁起絵巻(千葉市栄福寺蔵:非公開) |
| 【図5】 |
【図5】は、その場面を描いたもの。当館の正面入り口にも大きなパネルをもって掲げています。問題は、これにともなう詞書(【図5】拡大部)で、既刊書では「馬焉ママ顕太腹渡」・「馬ノ□頸・太腹ニテ渡ル」等と読まれていました。しかし、ここまでご覧いただいた方はお気づきのとおり、まさしくは、
馬ノ烏頭・太腹ニテ渡ル
で、いうまでもなく、文意は『千学集』と同じです。前掲『千学集』の一節とともに改訂しなければなりません。またこれによって『千学集』と詞書との密接な関係が、あらためて確認された、ともいえましょう。
ただ詞書に重点をおいてみると、絵巻に描かれた水位は「馬の太腹・烏頭」よりも少し高いように見えます。『千葉妙見大縁起絵巻』の原形は、詞書のみの縁起で、後に絵が加えられたと考えられていますが【補注3】、あるいは絵師が、詞書「馬ノ烏頭・太腹ニテ渡ル」の文意を、充分に理解していなかった可能性もありましょう。絵巻における絵と詞書との齟齬は、なにも『千葉妙見大縁起絵巻』に限ったことではなく、『源氏物語絵巻』等でも指摘されることですが、このたび改訂した箇所については、同絵巻の制作工程を考えるにあたって、留意すべきかと思います。
ともかく『千学集』と『千葉妙見大縁起絵巻』詞書の改訂により、両書における水位を示す語句「馬の烏頭」の使用が確認されました。今後、前掲『平家物語』・『源平闘諍録』等に加え、両書が用例の参考文献として挙げられることもあるでしょう。
それから今回とりあげた『千学集』『千葉妙見大縁起絵巻』にみえる「染谷川の合戦」は、先行研究によって指摘されているとおり、場所や登場人物に違いはあるものの、内容は『源平闘諍録』巻五の語る「蚕飼河(小貝川)合戦」に類似し、また『相馬当家系図』や『禅福寺縁起』、『建長寺年代記』にも類する話がみえます。さらに妙見の矢拾説話についても、先行する同様の話が散見されますが、これらと『千学集』および詞書が、どのような関係にあるのか、研究はいまだ十全な達成をみていません【補注4】。
なお川を渡る馬については、阿部猛『鎌倉武士の世界』(東京堂出版,1994年。197P以下)、同「馬筏と後矢」(『日本史研究』34号,1994年)等に詳細で、馬の博物館編『鎌倉の武士と馬』(名著出版,1999年)とあわせて参照した次第です。深く感謝申し上げます。
【補注1】 大森金五郎の筆写本は神奈川県立金沢文庫蔵。大森本は全体的に丁寧な筆致で写しとられており、『房総叢書』第二輯は、大森本の披見により「御蔭で不明の點が大部明かになつた事は感謝に堪へぬ」(222P)といっている。また『千学集』の写本は、ここに列挙した他、東京大学史料編纂所架蔵本(「千葉県庁蔵書」の転写)がある(後日調査)。「千葉県庁蔵書」本は未確認。
【補注2】 なお「染谷川の合戦」については、類似する話が『下総国千葉郷妙見寺大縁起』・『妙見実録千集記』等(当館『研究紀要』9号,2003年。「資料編」参看)にもみえるが、他の物語では、妙見菩薩(小童)が瀬踏をした場面について、水かさが減じたのではなく、陸地となって渡ることができたとする。
【補注3】 丸井敬司『千葉氏と妙見信仰』(岩田書院,2013年)225P。丸井氏は詞書について「少なくても五人の筆跡が確認される」(同上228P)と指摘する。これより先、松原茂「千葉妙見大縁起絵巻と片山三清」(『妙見信仰調査報告書』1992年)も「詞書は新旧数種の手が混在して複雑な様相を呈する。改装時の補筆は、他の文献などから重複を無視して加えられたものをも含み、原初の形態に復することはもはや不可能に近い」といっており、現状、詞書を原初形態に復元することは困難をきわめるが、なにより「詞書」の字句が刊本によって異なっているので、まずは栄福寺本の正確な翻刻を行わねばなるまい。
【補注4】 本件については先行研究もふくめ、佐々木紀一「『源平闘諍録』蚕飼河合戦譚成立について」(『国語国文』894号,2009年)に詳細で、文献で語られる妙見菩薩の容姿と、彫像・絵像との相違にも着目している。
千葉氏における正直の系譜(おぼえがき〔1〕) ― 十善の国王、新皇将門の諂佞、千葉宗家の滅亡など ―
① 安徳天皇 帝徳の十善(『平家物語』)
源平の国のあらそひ、けふ(今日)をがぎりとぞ見えたりける(『平家物語』巻十一)
長きにわたった源平のいくさも、終わりを迎えようとしていました。敗戦に敗戦をかさね、西海の壇ノ浦へと追いつめられた平氏。決戦の舞台でも敗戦が濃厚となり、眼前に源氏の兵者がせまってきました。
かたきの手にはかかるまじ(同前)
最期をさとった二位尼(平時子)は、涙をおさえ、安徳天皇に語りかけます。
君はまだご存知ないでしょう。万乗の主(ばんじょうのあるじ=天子)となられるお方は、前世における十善(十戒)を受持した果報によって、帝位につかれるのです。しかしいま悪縁のために、その果報がつきてしまいました。もはやこれまでです。まずは東方に向かって天照太神においとまのご挨拶を申しあげ、続いて西方に向かい来迎をお祈りいたしましょう。(同前私訳)
天皇が「ちいさく、うつくしき御手をあはせ」称名すると、二位尼は幼帝を抱き「浪(なみ)の下にも都のさぶらふぞ」とて、船べりから海深くに身を投じたのです。その姿をまのあたりにした一門の人びともまた、次々と入水。ここに栄耀栄華をきわめ「この一門(平家)にあらざらむ人は皆人非人なるべし」(『平家物語』巻一)とおごりきわめた平家は滅亡しました。寿永4年(1185)3月のことでした。
もっともこれは族滅ではなく、諸行無常等をテーマとする『平家物語』のえがく終滅で、『平家物語』は盛者必衰・おごれる者の久しからざる様を語ればよいのです。実際『平家物語』は、安徳天皇の生母、建礼門院(平徳子)の余生を摘記してエピローグとしますし、平家には他にも生きながらえた人たちがいます【注1】。
しかし今はそのことよりも、二位尼が安徳天皇に語った「帝位に就く人は、前世で十善を受持した果報による」の一節と、千葉氏への連関を叙述することにしましょう。
まず帝位につく条件とされる前世の「十善」について、『日本国語大辞典(第2版)』は、語意を二つあげています。一つは、
(1)十悪を犯さないこと。不殺生・不偸盗(ちゅうとう)・不邪淫・不妄語・不綺語(きご)・不悪口(あっく)・不両舌・不貪欲・不瞋恚(しんい)・不邪見の一〇種の善をいう。十善業。十善戒。十善業道。
です。文字どおり殺生や盗みなど十の悪業を犯さないことを「十善」といいますが、もう一つは、
(2)(前世に(1)を行った果報によって、この世で天子の位を受けるとする仏教思想による)天皇、天子のこと。十善の君。また、天子の位。
です。『日国』の解説する(2) 【注2】は、二位尼の語り(前掲)と同義ですし、都を落ちた平時忠は「平家の方には、十善帝王(安徳天皇)、三種の神器を帯してわたらせ給」(『平家物語』巻七)といっています。かように十善は天皇の代名詞でもあり、このほかにも天皇を「十善王」、「十善の君」等と呼ぶ例は、『栄花物語』『将門記』『とはずがたり』『太平記』『御伽草子』など枚挙に暇がありません。
② 十善の不妄語と正直(八幡菩薩の託宣)
そんな十善ですが、日本国の守護神たる八幡神(後に神仏習合により大菩薩となる)の御託宣(お告げ)とあいまって、特に十善の一つにかぞえる「不妄語(ふもうご)=いつわりごとをしない」が重視されるようになります。その託宣とは、一つに、「十善の百王(天皇百代)を守護する」こと、また「正直の頭をすみかとする」ことです【注3】。この託宣は、ことわざ「正直の頭に神宿る」の典拠ともされ、また正直は「不妄語」に通じるものであり【注4】、あるいは「天照太神モタヾ正直ヲノミ御心トシ給ヘル」(『神皇正統記』*天照太神は天皇の祖神)【注5】君徳(君主の備えるべき徳)でもありました【注6】。
とくに鎌倉時代、鶴岡八幡宮が象徴するように、八幡菩薩は武家の棟梁も崇める神仏ですから、その加護を得るためにも、当時の人々が正直を重視し、心がけたことはいうまでもありません。たとえば叡尊や日蓮は、八幡菩薩の加護を得るためには正直が肝要であることを説示し【注7】、また為政者の側も、北条泰時は「性稟廉直、以道理為先、可謂唐堯・虞舜之再誕歟(生来の正直者で道理を先とした人だった。まさに中国伝説の王、堯・舜の再誕のようであった)」【注8】と評され、北条重時は「心を正直にもつ人は、今生もすなをに、後生も極楽にまいり、親のよきには、子も天下に召し出さるゝ事おほし」【注9】といっています。まさに正直は、鎌倉時代を代表する倫理思想のひとつでした【注10】。
しかし二位尼の語りにもみられるとおり、不妄語(正直)等の十善の果報も、悪縁【注11】によって尽きたり、これによって王位を失うこともある、というのです。
そしてこの因縁覃は、『平家物語』の異本で、千葉氏の活躍を特筆した『源平闘諍録』へと及びます。『源平闘諍録』が『平家物語』諸本の、どの系統に属するのかは明瞭ではありませんが、あるいは流布していた「平家」等(『平家物語』の前身【注12】)がもとになっているかもしれません。なお検討したいと思います。
③ 平将門の正直と諂侫 妙見菩薩の誓願(『源平闘諍録』『千学集抜萃』)
ここまで『平家物語』における二位尼の語りとその周辺について考えてみましたが、『源平闘諍録』をひらいてみると、そこには独自の因縁覃がつづられているのです。それは先に、このシリーズでもとりあげた巻五の場面です。再掲すると、戦場で平将門や良文を守護した小童が、本地(本来の姿)をあかして、次のように語りますり。
我れはこれ妙見大菩薩である。昔より今にいたるまで、心がいさましく慈悲深く、そして正直な者を守護するとの誓願をたててきた。汝はまさしく心が直な勇者である。だから我れは汝を守護するために来臨したのである。(私訳)
こうして将門は「妙見の御利生を蒙り、五ケ年の内に東八ケ国を打ち随へ、下総国相馬郡に京を立て、将門の親王(新皇)と号」しました。「正直なる者を守らん」と誓願した妙見菩薩の加護により、正直者の平将門は関八州を従え新皇になった、というのです。
ところがその後、将門は朝廷によって討伐されます。『源平闘諍録』の語るところ、その理由は次のようなものでした。
かくして新皇となった将門だったが、彼は正直な心を捨てて諂侫(てんねい)となってしまった。曲がった政治を行い、神や朝廷を恐れず、はばからず、仏神の田地を奪い取るなどした。そのようなわけで、妙見大菩薩は将門の家を出て、平良文のもとへと渡ったのである。将門は妙見に棄てられたのだ。(私訳)
「諂侫(てんねい)」は「諂曲(てんごく)」と同義で、心を曲げてこびへつらうこと、よこしまな心をもつことをいいます。将門は「正直」によって新皇となるも「諂侫」によって、その位を失ったというのです。これは八幡菩薩の託宣「正直乃人乃頂乎栖加土須。諂曲乃人乎波不稟(正直の人の頂〔いただき〕を栖〔すみか〕とす、諂曲〔てんごく〕の人をば稟〔う〕けず)」【注13】に照応するものです。
ちなみに『将門記』によると、将門は天慶2年(939)12月、八幡菩薩の使いという巫女のお告げによって、新皇になったということですが【注14】、この話がなぜ、『源平闘諍録』では、妙見菩薩の加護となっているのか、また妙見菩薩による「正直者を守護する」との誓願は、どのようなかたちで文献に現れてくるのか、など、不明な点は多く、今後も追尋しなければなりません。
ともかく『源平闘諍録』の一節からは「十善(正直等)によって帝位に就くも、これが尽きて(悪縁・諂曲)帝位を失う」という『平家物語』と同じ構図がみられますし、私は『源平闘諍録』の当文を読んだときに、まっさきに『平家物語』における二位尼の語りを想起しました。
ちなみに『源平闘諍録』は『平家物語』諸本とほぼ同じように起筆されています。
祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響き有り。沙羅隻樹の花の色は、盛者必衰の理を顕せり。驕れる人も久しからず、只春の夜の夢の如し。武き者も遂には殄(ほろ)びぬ、偏に風の前の塵に同じ。遠く異朝を訪へば、秦の趙高・漢の王莽・梁の周異・唐の禄山…(中略)…近く本朝を尋ぬれば、承平の将門・天慶の純友・康和の義親・平治の信頼、驕れる心も武き事も取々にこそ有りしかども(後略)
ここに諸行無常、盛者必衰、「武き者も遂には殄(ほろ)」ぶという、和漢の古事が列挙され、本朝の例として「承平の将門」があげられています。『平家物語』は安徳天皇の入水についても、「悲しきかな、無常の春の風、忽ちに花の御すがたをちらし、なさけなきかな」と、やはり無常のさまを語り、十善の君徳を重ね合わせ、天子の終焉を記しました。
いっぽう『源平闘諍録』は、安徳天皇の入水(因縁覃)については触れず【注15】、かわりに将門をもって、「正直(十善)により神仏の加護を得て新皇となるも、諂侫によってその位を失う」という物語をなしたのです。むろん日本六十六カ国の天子(安徳天皇)と、関八州の新皇(平将門)とでは格差があります。しかしこの因縁覃のいわんとするところは、「統治する国々の大小にかかわらず、正直は統治者(主君)が備えるべき徳であり、これを失えば、その位も失う」を説示することにありましょう。たとえそれが一国一郡一郷の主であろうともです。
『源平闘諍録』は続けます。
さて将門のもとを去って良文のもとへと渡られた妙見大菩薩は、さらに忠頼のもとに渡られた。こうして嫡々と相い伝えて七代目の千葉常胤にいたるのである。(私訳)
妙見菩薩が「正直者を守護し、諂侫者には宿らず」という菩薩である以上、平良文より千葉常胤にいたる人々【注16】もまた、正直を旨としてきたであろうことは、いうまでもありません。そして『源平闘諍録』に示す因縁譚は、『千学集抜萃』にも次のようなかたちで引きつがれています。
尊星王菩薩(妙見菩薩)は大変に慈悲深く、正直甲(こう)なる者を守るべし、との誓願を立てられた。正直甲とは、たとえば「千騎の主」と「百騎の主」があったとしよう。時に千騎の主が曲論をいい、百騎の主は正論を述べた。その際、権勢をおそれて曲論に従うような者は甲の人ではない。これを妙見菩薩は捨させ給うのだ。非道を非道とし、道理を道理とする人こそが正直甲であり、これを妙見菩薩は加護されるのである。(私訳)
「甲(こう)」とは「強く勇猛なこと。また、そのさま。剛勇」(『日本国語大辞典〔第2版〕』)のことで、「日本第一ノ甲ノ者ナリ(日本第一の勇士である)」【注17】などの用例があります。ともかく『千学集』のつづる当文と、『源平闘諍録』における妙見菩薩の語りとを勘合すれば、「正直甲」とは、正直で武剛の者、相手が誰であれ、正直に勇気を持って正邪をいえる人を指しましょう。
今回はここまで。次回は千葉一族における正直の諸相について考えたいと思います。
【注】
(1)角田文衞『平家後抄』(朝日新聞社,1978年)など。
(2)本件に関する仏説をあげれば、『仁王般若波羅蜜経(仁王経)』巻上に「十善菩薩発大心。長別三界苦輪海。中下品善粟散王。上品十善鉄輪王(十善の菩薩は大心を発して長く三界苦輪の海に渡る。中下品の善は粟散王となり、上品の十善は鉄輪王となる)」(『大正新脩大蔵経』8巻827頁b。※鉄輪王は人間世界を治める王の意)とあり、また『菩薩瓔珞本業経』巻下に「是人復行十善。若一劫二劫三劫修十信。受六天果報。上善有三品。上品鉄輪王化一天下。中品粟散王。下品人中王(この人また十善を行ず。若しは一劫・二劫・三劫に十信を修すれば、六天の果報を受く。十善に三品あり。上品は鉄輪王にして一天下を化す。中品は粟散王、下品は人中の王なり)」(『大正新脩大蔵経』24巻1017頁a)とみえる。なお漢訳仏典における国王の位置づけについては、松長有慶氏による一連の研究(『インド密教の構造〔松長有慶著作集二〕』法蔵館,1998年)に詳細である。
(3)重松明久校注『八幡宇佐宮御託宣集』(現代思潮社,1986年)90,147P、237,257P。原文は中野幡能校注『神道大系 神社編四十七 宇佐』53P以下参看。
(4)日蓮『諫暁八幡抄』(『日蓮〔日本思想大系14〕』368P)など。また日本国王における不妄語(十善)と正直について取りあげた論著に、高木豊『鎌倉仏教史研究』(岩波書店,1982年)、細川涼一「仏教改革者の天皇観」(『講座 前近代の天皇4』岩波書店,1995年)などがある。
(5)『神皇正統記 増鏡(日本古典文学大系87)』82P。
(6)正直を君徳とするのは、中国王朝からうけた影響と思われる。たとえば『詩経』に「嗟爾君子 無恒安息 靖共爾位 好是正直 神之聞之 介爾景福(ああ君子よ恒に安息するなかれ。なんじの位を靖共し、この正直を好みせよ。神の之を聞けば、なんじに景福をあたえん)」(『詩経 中〔新訳漢文大系111〕』395P)とあり、『貞観政要』では、李大亮の示した当文について太宗が賞で(『貞観政要 上〔新訳漢文大系95〕』176P)、太宗自身も虚心正直を旨として天下を治めてきたと語っている(同184P)。『礼記』では孔子が当文を君徳として示しているし(『礼記 下〔新訳漢文体系29〕』841P。同書は「君主は恭敬にしてその位を守り、正直を旨として民に臨まねばならぬ」と訳す)、さらに『史記』に「王道正直(王道は正直なり)」(『史記 五世家上〔新釈漢文大系85〕』269P)とみえるなど、これら漢籍の記事といい、前掲(注2)漢訳仏典の説示といい、本邦における正直と国王との関連は、中国からの影響をぬきにして語ることはできない。なお日蓮は「正直に二あり」として世間・出世の二義をあげている(前掲『諫暁八幡抄』)。鎌倉期における正直(しょうじき・せいちょく)の語意については、なお検討を重ねたい。
(7)『感身学正記 1(東洋文庫664)』247P、前掲『諫暁八幡抄』等。
(8)『民経記』仁治三年六月二十日条。ただし『民経記』同年六月二十六日条には、藤原兼経の仰せとして、泰時は臨終の際、東大寺・興福寺を焼き討ちにした平清盛のごとき高熱に襲われたといい、「極重悪人之故歟」と記録している。まさに「両極端の評価」(尾上陽介「大日本古記録 民経記 八」〔『東京大学史料編纂所所報』36号、2000年〕)がある。また類似する記事が『平戸記』同年六月二十日条にもみえる。
(9)『中世政治社会思想 上(日本思想大系21)』(岩波書店)333P。これに関し仏説に典拠を求めれば、『維摩経』に「當知直心是菩薩浄土(まさに知るべし直き心はこれ菩薩の浄土なり)」(『大正新脩大蔵経』14巻538b)とみえる。なお丸井敬司『千葉氏と妙見信仰』(岩田書院,2013年。100P以下)も、妙見信仰と正直に関連する資料として「極楽寺殿御消息」をとりあげている。
(10)中野幡能『八幡信仰』(塙書房,1985年)206P。鎌倉期成立の説話集『十訓抄』が『十善業道経』(十善に関する仏説)をもとに作成されたことはよくしられ、『同』中などに正直に関する説示がある。また鎌倉時代における正直の理解を示すものとして、『塵袋』巻十一がある。同書は「正直(せいちよく)」を立項し、『春秋左氏伝』を挙げて「心ヲスグニナスヲ正トハイヒ、人ノマガレルヲナヲスヲ直卜云フ卜釈シタルナリ。コレハ今マ少シ大事ニヤ」(『塵袋2〔東洋文庫725〕』248P)といっている。ここで『塵袋』が正直に関して漢籍に着目していることは、前掲(注6)と合わせて興味深い。
(11)安徳天皇の「十善の果報」を失わせた悪縁については、さまざまに語られるが、天皇の祖父、平清盛による悪行も指摘される(『平家物語 下〔新日本古典文学大系45〕』294P脚注など)。この点、日蓮が安徳天皇の入水にいたった背景として、承久の乱における後鳥羽院の事例とあわせ「関東呪咀」を例示していることは特徴的である(『本尊問答抄』前掲『日蓮〔日本思想大系14〕』348Pなど)。
(12)「平家」等については、さしあたり今成元昭『平家物語流伝考』(風間書房,1971年)79P以下、『平家物語研究 今成元昭仏教文学論纂第四巻』(法蔵館,2015年)34P以下を参照した。
(13)前掲『八幡宇佐宮御託宣集』272P。また龍樹は『大智度論』に、妄語する者について「善神遠之(善神これを遠のく)」(『大正新脩大蔵経』25巻158c)といっている。
(14)『将門記(新編日本古典文学全集41)』62P。
(15)『源平闘諍録』は零本とされるいっぽうで、当初より現形で完結しているとの説もある(早川厚一「源平闘諍録考 ―巻立てから見た巻八下の読みについて―」〔『中世文学』31,1986年〕、同「『源平闘諍録』は五冊本で成立したか」〔『名古屋学院大学研究年報』23号、2010年〕など)。その場合、安徳天皇の因縁覃は、当初より構想からはずれていた可能性もあろう。
(16)この系譜は『源平闘諍録』の描くところで、同書は平良文について、将門の伯父でありながら養子になったとする。
(17)『神皇正統記 増鏡(日本古典文学大系87)』186P。
千葉氏における正直の系譜(おぼえがき〔2〕) ― 十善の国王、新皇将門の諂佞、千葉宗家の滅亡など ―
前回『平家物語』にみえる二位尼の語り(前世で十善を積んだ果報により帝位に就く)をもとに、その淵源(仏説等)と展開(『源平闘諍録』等)をつづり、とりわけ十善にかぞえる不妄語(正直)が重視されたこと、および八幡や妙見は正直者を守護し、諂侫・諂曲を受けざる菩薩【注1】であることを縷説しました。
今回は千葉一族における正直のありようを列叙したいと思います。
④ 妙見菩薩に捧げる誓い(起請と願文「中山法華経寺文書」)
『源平闘諍録』は巻五において、妙見菩薩が正直をひるがえし諂侫となった将門のもとを去ったこと、また平良文のもとへ渡って以来、千葉常胤にいたる一族を守護してきたことを物語ります。これをうけて、千葉一族が妙見菩薩の加護を得るため、正直を旨としたであろうことはいうに及ばず、あわせて諂侫をいさめてきたであろうことも同断です。
その様相を示す資料の一つに、建長元年(1249)七月二十九日付「光綱書状」(「双紙要文」紙背文書=中山法華経寺蔵)【注2】があります。この書状は光綱が、主君(千葉氏)への忠義を誓ったものですが、書状の末尾に、
私の言葉に偽りがありましたなら、日本国中の神々の御罰、とりわけ妙見菩薩の御罰を蒙(こうむ)ります。(私訳)
と書かれています。このように自己の言動に偽りがあった場合、神仏の罰を蒙る旨を誓約した一文を「起請文言(きしょうもんごん)」といい、後年の「千葉胤清請文」(永徳2年=1382)にも「この条に偽りがあったなら八幡大菩薩・妙見大菩薩の御罰を蒙ります」(私訳)【注3】とみられます。前回ものべたましたが、十善の一つにかぞえる不妄語(ふもうご)とは「偽り言をせず=正直」ですから、正直を守護し、諂曲を受けずという妙見菩薩へ、正直の言葉を捧げることは、何よりの大事だったでしょう。
もう一つ「千葉胤貞願文写」【注4】(私訳)を掲げます。
敬白す、立願のこと。
妙見御前 田地一町
右、所願が成就したあかつきには、10日の内に進上いたします。
嘉暦元年(1326)七月二十一日 平胤貞(花押)
胤貞が、どのような願を立てたのかはわかりません。何か思うことがあったのでしょうか。ともかくその所願が成就したあかつきには、十日の内に妙見菩薩の御前に一町におよぶ田地を捧げる、との願文をしたためています。このように千葉一族は当主だけではなく、庶家や家人にいたるまで、妙見菩薩に正直の誓言を捧げ、加護を得てきました。
そんな千葉一族の中には、祈請(正直)を破る行為に対しての、義憤にも似た行動をとった人もいたようです。そのことを伝えるのが、次節に掲げる鎌倉時代成立の説話集『古今著聞集』です。
⑤ 千葉胤綱の闘諍 三浦義村の起請文破り(『古今著聞集』巻十五「闘諍」)
まずは当該部をかかげ、前後を追ってみましょう。
ある年の正月元旦、鎌倉幕府三代将軍、源実朝の御所に御家人達が群参していた。最上に着座するのは、幕府ナンバーⅡの三浦義村。そこに若年の千葉胤綱が、並みいる御家人をかきわけて、義村のさらに上座へ腰をおろした。義村は激怒していった。「下総の犬は寝床を知らぬようだ」。胤綱は間、髪をいれずに返した。「三浦の犬は友を食らうなり」と。(私訳)【注5】
痛烈きわめた一言に義村は言葉を返せなかったようです。胤綱のいう「友を食らうなり」とは、「和田合戦」における義村の裏切り行為を直言したものです。
時は建保元年(1213)5月、鎌倉幕府の政所(財政)トップの北条義時と、侍所(軍事)トップの和田義盛による抗争「和田合戦」が勃発。三浦義村は和田義盛との共闘を誓い、起請文までしたためました【注6】が、決起の直前、義村は義時側に寝返ったのです。これによっていくさは北条義時が勝利し、義時は幕府の財政と軍事を掌握。和田氏は族滅しました。
こうして北条義時は幕府における事実上の最高権力者に、サポートした義村は次位を手にしたわけですが、義村はまさに「友を食ら」い、その位を得たのです。千葉胤綱の一言「友を食らうなり」は「いかにも鋭くその間の事情をえぐった」【注7】痛快なエピソードといえるでしょう。
このエピソードからは、千葉一族が和田合戦における義村の動向を、非難していたことがうかがえます。起請文を破る(妄語・諂曲)という神仏への背信行為も、正直(不妄語)をモットーとし、妙見菩薩の冥利にあずかってきた千葉一族からすると、黙許できぬ行為だったに違いありません。
しかも三浦義村の裏切りは、諸人の知るところだったにもかかわらず、義村の威勢を恐れて、誰も口にすることはありませんでした。そんな中、妙見菩薩が守護する「正直甲(権勢を恐れず正邪をいう)」をもって義村にのぞんだのが胤綱だったのです。
ところで、当エピソードを考察した細川重男氏は、実朝の没年や、幕府の公式行事に参列する千葉氏当主(千葉介)の記事等を整理し、三浦義村と千葉胤綱の口論は、承久元年(1219)の一件と指摘しています【注8】。『吾妻鏡』によれば、同年、胤綱はかぞえで12歳。現代の感覚からすると「いまだ若者」(古今著聞集)どころではありません。
ただ胤綱の年齢については検討すべき問題があります。すなわち『吾妻鏡』は、安貞2年(1228)5月28日、「二十一歳」で没したとしますが、『本土寺過去帳』の記載は享年「三十一歳」【注9】です。「二」か「三」か。これによって、先の口論時の年齢も12歳か22歳かの何れかとなります【注10】。
ともあれこのエピソードは、正直を座右に据える千葉一族の面目躍如といえますが、『千学集抜萃』はじめ、千葉氏関係書物にはみえない話なので、ここに拾遺した次第です。
⑥ 千葉宗家の滅亡(『千学集抜萃』の一節)
ここまでを小括しておくと、まずは当時ひろく流布していた『平家物語』(あるいはその前身「平家」)の話(安徳天皇と十善)が、『源平闘諍録』(東国版)では、平将門の正直と諂侫譚として語られ、これが千葉一族へと伝わり、一族にとって妙見信仰と正直は不可分・不可欠な存在、精神的支柱となりました。また中山法華経寺文書等によって、妙見信仰は千葉宗家だけではなく、庶家や家人にも浸透していた様がうかがえます。
ただ将門が正直によって妙見菩薩の加護を得て新皇となるも、諂侫によって、その位を失ったという話を格言する以上、千葉一族の興亡もまた、このいましめと関連づけなければなりません。
『千学集抜萃』に閑話休題すると、同書は古河公方(権力)からの偏諱を拒み、妙見菩薩(正直)の御前にて元服・実名を決めた千葉孝胤を「正直甲」とたたえる【注11】いっぽうで、康正元年(1455)8月、千葉胤直が自刃して果てた千葉宗家の滅亡について、理由は胤直が非道を道理としたため、つまり諂侫だったというのです。すなわち前掲「正直甲」に続けて次のように語り伝えます。
千葉家では胤直の御代に、重臣の原越後守胤房と圓城寺下野守直重が家風をめぐって口論したが、これは直重がみずからの非道を道理とし、胤房の道理を非道としたために起きた諍いであった。ところがこの時、胤直は、円城寺直重は多勢で、原胤房は無勢だったため、直重に肩入れしたのである。この諂侫により妙見菩薩は胤直を捨て給うたのである。 これに関して次のような出来事があった。享徳3年正月2日の明け方、胤直の郎党、片野胤定が籠りをされていたところ、夢中に甲冑をまとった12歳ほどの小童が現れて、一首を詠じた。
神風に 吹ちらされて 胤直の すけもはしらも かなはざりけり
胤定が「それでは原の方はどうか」と小童に問うたところ、つづけて、
神風の 長閑なりける 時にこそ 高間か原の 末そ久しき
と詠んで姿を消した。この二首の神詠を、後世に伝えるため、左衛門太夫秀義が『千学集』に入集したのである。(私訳)
おそらく「神風に 吹ちらされて 胤直の すけもはしらも かなはざりけり」の一首は、諂侫によって神に見放され(神風に吹き散らされ)た胤直は、たとえ介・柱(千葉介・千葉家の柱)といえども、敵にかなうことはない、の意で、もう一首「神風の 長閑なりける 時にこそ 高間か原の 末そ久しき」は、神に守護された(神風の長閑なりける)原氏が勝利し行く末久しいことを詠ったものと思われます。「高間か原」は「高天原(たかまがはら)=神々の住む聖地」で、原胤房の「原」にかけているのでしょう。
宗家胤直の滅亡については『下総国千葉郷妙見寺大縁起』も「胤直国主の器量あらずして」とか「胤直神慮にも違ひ、天神の極る所にやありけん、かかる事は良文より以来、終に例なき事なりけり」【注12】等と辛辣な文言をつらねています。
ちなみに『源平闘諍録』は「良兼は多勢、将門は無勢なり」という状況下、妙見菩薩は無勢の将門を正直・剛のゆえに守護したといいますが【注13】、対して上掲のとおり、胤直は、円城寺直重は非道であるにもかかわらず、多勢ゆえに肩入れし、妙見菩薩に捨てられたというのです。軌を一にした正直諂侫譚といえましょう。
これら『千学集抜萃』、また『源平闘諍録』等の編纂物の記すところは、いずれもエピソードですが、前掲、中山法華経寺文書の誓言・起請文言でみたように、千葉一族にとって妙見信仰と正直は一体で、これを一族の精神的支柱とし、独自にたもつことは、一族の結束・統率につながったでしょうし、一族の歴史に大きな役割を果たしてきたと思うのです。
この先にむけて
過日、『千学集抜萃』の最古写本を伝える清宮家について調べていたところ、幕末~明治にかけて、房総に関する資料を収集整理し、みずからも著作をものした清宮秀堅(せいみや・ひでかた:1809~1879)の一代記『清宮秀堅先生小伝』が目にとまりました。筆者は秀堅の門人、桜井清治郎です。その桜井の語るところ、秀堅もまた「直キヲ愛シ曲レルヲ措ク」人だったといい【注14】、大いに感銘を受けました。
このエッセーでは、千葉氏における正直の系譜をかかげ、あわせてこれと不可分な妙見信仰をとりあげましたが、いまだ自分の中では消化しきれていないことが多々あります。よくしられるように、妙見菩薩は水神(『日本霊異記』【注15】)であり、また武神(『源平闘諍録』『千学集抜萃』等)でもあり、正直甲(剛)の守護神でもあります。その他、さまざまな側面をもちますが、最近、妙見菩薩はいったい反逆・謀反の神であったとの説に接し、一考を要すと思いました。
たとえば『千学集抜萃』は、『源平闘諍録』の描く蚕飼川(常陸国)合戦を、染谷川(上野国)合戦とし、妙見菩薩が〝謀反〟をおこした将門を守護した、とリメイクします。なぜ『千学集抜萃』は、わざわざ〝謀反〟を加えたのか、理解できずにいましたが、もともと星神は為政者に従わず討伐される側にあったようで(『日本書紀』【注16】)、描かれた合戦の舞台が上野国の群馬群(くるまぐん)だったことを踏まえると、なるほど、その下地はそろっていたのではないか、と思いつつあります(上野国は『神道集』に象徴される神話の宝庫)【注17】。これらは、なかなか実証的に論じることの困難な課題ですが、周縁を把握しておくこともまた、重事と認識させられました。
それから今回は、妙見信仰にスポットをあて叙述しましたけれども、「千葉の守護神は、曾場鷹大明神・堀内牛頭天王・結城の神明・御達報の稲荷大明神・千葉寺の龍蔵権現これなり。弓箭神と申は妙見・八幡・摩利支天大菩薩これなり」(『千学集抜萃』)というように、千葉一族の崇める神々は実に多彩です【注18】。
しかしこれらの子細は、今回のノートにはとても収めきれず、また書き尽くせず、一々を今後の課題として、このたびは擱筆いたします。
【注】
(1)前回とりあげた他にも、たとえば『沙石集』巻九に「正直ノ者ヲバ天是レヲ助ケ、幸ヲエシメ、諂曲ノ物ヲバ冥是レヲ罰シテ災イヲ與フ」(『沙石集〔日本古典文学大系85〕』371P)等とみえる。
(2)『千葉県の歴史 資料編 中世2(県内文書1)』1018P。本状については、野口実「千葉氏の嫡宗権と妙見信仰」(同『千葉氏の研究』名著出版,2000年)、『石井進著作集 第七巻 中世史料論の現在』(岩波書店,2005年。181P)等を参照されたい。
(3)『千葉県の歴史 資料編 中世2(県内文書1)』1126P。同書の注によると当文書には裏花押が据えられているものの、その花押形は、もう一通の胤清花押とは異なるという。この点、注意しておきたい。
(4)『同前』1111P。これより先、胤貞は「妙見御神田合二町」を寄進している(同)。土屋賢泰「千葉氏と妙見信仰」(千葉県郷土史研究連絡協議会編『論集 千葉氏研究の諸問題』千秋社、1977年)参照。
(5)『古今著聞集(日本古典文学大系84)』403P。なお両者は互いに「犬」と罵っているが、これは相手を卑下するための言葉である(森野宗明「下総犬と三浦犬」〔『日本語と国文学〕8号,1988年)。
(6)『吾妻鏡』建暦三年五月二日条。
(7)石井進「『古今著聞集』の鎌倉武士たち」(『古今著聞集〔日本古典文学大系84〕月報』1966年)。同『鎌倉幕府(日本の歴史07)』(中公文庫、2004年。300P以下)参照。
(8)細川重男「下総の子犬の話」(『古文書研究』52号,2000年)。
(9)『千葉県史料』本は没年齢を「廿一歳」と翻刻するが、天正本の原文(下二十七日)を確認するに、
千葉介胤綱〈安貞二戊子五月卅一才〉
である。
(10)『吾妻鏡』の記す胤綱の寂年齢については、前掲注(5)森野論文等が疑問を呈しており、福田豊彦「『源平闘諍録』の成立過程〔補論〕千葉介胤綱・時胤および千田泰胤の系譜上の位置」(『千葉県史研究』11号別冊,2003年)も『吾妻鏡』が記載を誤った可能性に言及。岡田清一氏(『千葉県の歴史 通史編 中世』千葉県,2007年。131P以下)は、『吾妻鏡』の記載は誤りとする。福田氏・岡田氏の指摘するように胤綱の没年を21歳とすると、前後の系譜・系図に無理が生じるいっぽう、系図自体、検討を要するかとも思われる。またこの話が事実であれば、12歳(満11歳)の言動であればともかく、22歳のそれとなれば、単なる口論ではすまなかったのではないか。ちなみに三浦義村の没年は延応元年(1239)、千葉胤綱のそれは安貞2年(1228)で、両者の口論を伝える『古今著聞集』の成立は建長6年(1254)とされる。当事者を知る世代で、すでにこの話が語られていたことがわかる。
(11)この前後における千葉氏の動向については、先行研究を含め、外山信司「戦国期千葉氏の元服」(佐藤博信編『中世東国の政治構造』岩田書院,2007年)を参照。外山氏は妙見の神前における元服儀式等を通じ、家督継承意識の表出や『千学集』成立事情を論じ「馬加千葉氏・佐倉千葉氏・原氏のもとで 『千学集』が整えられた」と指摘する。千葉嫡家の正統性を語るにあたり、妙見信仰が取り入れられたことは、福田豊彦「『源平闘諍録』その千葉氏関係の説話を中心として」(『日本文学研究大成 平家物語Ⅰ』国書刊行会,1990年)、前掲注(3)土屋論文、前掲注(2)野口論文等に論究されている。
(12)千葉市立郷土博物館編刊『妙見信仰調査報告書』(1992年)79~80P。
(13)福田豊彦・服部幸造注釈『源平闘諍録(下)』(講談社学術文庫,2000年)52P。
(14)小原大衛写本(千葉県立中央図書館蔵)による。その他、清宮秀堅の人となりを知る資料として、未見ながら秀堅の発信・受信した書簡などがあげられよう。これらの資料については(財)千葉県史料研究財団編『千葉県史編さん資料 千葉県地域資料現状記録調査報告書 佐原市清宮利右衛門家文書(正続)』第5集・6集(千葉県,1999・2000年)に書目が列挙されている。いずれ眼福の機会をえられればと思う。
(15)『日本霊異記(新日本古典文学大系30)』177P。『入唐求法巡礼行記1(東洋文庫157)』10P。これらはいずれも妙見菩薩が水難から救う菩薩であることを示している。
(16)『日本書紀』巻第二(『日本書紀 上〔日本古典文学大系67〕』140P・同頭注)に、次のごとく天津甕星は悪神であり、国を平定するため誅殺すべしとの話がみえる。
天神(あまつかみ)が経津主神(ふつぬしのかみ)と武甕槌神(たけみかづちのかみ)を遣わし、葦原中国(あしはらのなかつくに=日本の古称)平定したが、二人の神は「天に悪神がおります。名を天津甕星といいます。まずはこの神を誅殺して、その後に葦原中国を平定したいと思います」と進言された。(私訳)
(17)角川源義「上野国の中世神話」(『角川源義全集』3巻。角川書店,1988年)等を参照。また上野国には、八幡菩薩による正直守護の託宣をおさめた『宇佐宮八幡御託宣集』の写しも早くから伝わっていた(『神道大系 神社編 宇佐』解題)。それから川村湊『増補新版 牛頭天王と蘇民将来伝説』(作品社,2021年)に次の指摘がある。
「そうした信仰を持ち込んだのが、朝鮮半島から渡来した馬飼い集団であり、これら高句麗、新羅から渡ってきた騎馬民族としての渡来人が住み着いたのが河内国で、ここにまず妙見信仰のメッカが生まれた。次いで、北関東に移住し、その末裔たちが牧場を開き、馬飼いを業とした(群馬や相馬といった「馬」の字が付く地名はここから生まれてきた)。妙見信仰が北関東をホーム・グランドとしているのは、こうした歴史が積み重なっているからだ。妙見信仰が、叛逆、謀反のシンボルとなった理由は、こうした北関東に散らばった渡来系の牧民集団を背景とした武装勢力の台頭にあったというべきだろう。むろん、その最大の〝新星〟が平将門である」(298P以下)。
(18)その他、前掲注(4)資料のとおり、千葉胤貞は元応二年(1320)十二月一日付で「妙見御神田」を寄進しているが、同日付で「十羅刹御神田」も寄進している(『千葉県の歴史 資料編 中世2(県内文書1)』1110P)。もって千葉氏の多彩な信仰を知らなければならない。
特殊な文字を読む(『千学集抜粋』から)
現代と異なり、前近代の記録はすべて手書きによっていました。記録をとる、書き写すなど、〝書く〟ことを専門職とする人も多くいました。やがて彼らは作業を効率よく進めるため、文字を簡略化させました。略字・異体字の誕生です。現在用いられている漢字の多くは略字で、身近なものをいくつかあげると、駅は驛の略字、学は學の略字、鉄は鐵の略字、広は廣の略字、庁は廳の略字、等です。
また特に経典を書写したり、その注釈書を著す作業では、多様な異体字・略字が用いられました。たとえば釈尊(釈迦)は尺寸、菩薩はササ、醍醐は西西、声聞はメメ、涅槃は炎、畢竟は丸丸、等と表記し、また「竹云(竹に云く)」の二文字で、『法華玄義釈籖』という書物からの引用であることを表します(竹は籤の竹冠からとったもの)。
また速記に適した形として、草書・くずし字が誕生しました。現在、私たちが用いる平仮名も、原形は漢字で、これをくずしたものです。一例をあげれば「あいうえお」は、それぞれ「安以宇衣於」をくずした文字ですから、私たちも初等教育の段階で、くずし字を学んでいるのです。さらに本邦で和歌が読まれるようになると、仮名をつなげて書く、仮名連綿(れんめん)が誕生するなど、文字は用途に応じて様々な姿に形を変え、今日に伝わるのです。
しかし手書き自体が珍しくなった現代では、これら異体字・略字は、ほとんど用いることはありません。それでも「寿司(すし)」「楚者(そば)」「於手茂止(おてもと)」など、暖簾や箸袋に書かれたくずし字(変体仮名)を目にすることがあるでしょう。そして歴史(過去の記録)の研究にたずさわる者は、上掲のような様々な形の文字と向き合わなければなりません。
私も日々、これらの文字と向き合い、悪戦苦闘をしていますが、その手引きとなる書も多く出版されています。その中から一冊を選定するならば、やはり児玉幸多編『くずし字用例辞典』(東京堂出版)です。何といっても〝用例〟が魅力です。また多様な書体があげられている『大書源』3巻(二玄社)もオススメです。
またインターネットの普及にともない、電子字典も公開されています。特に奈良文化財研究所・東京大学史料編纂所・国文学研究資料館・国立国語研究所・京都大学人文科学研究所・漢字規範史データセット保存会、また台湾中央研究院歴史語言研究所等、国内外の研究機関が連携して公開する「史的文字データベース連携検索システム」は秀逸で、各機関が集積した膨大なくずし字・異体字等を、瞬時に調べ、披見することができる、本当に便利なシステムです。さらにくずし字解読アプリ「みをmiwo」の登場など、研究もずいぶんと変わりました。それでも最終的に頼るのは、自分の目と経験です。
当館では目下、千葉一族の歴史を語るに不可欠な『千学集抜粋』の校訂を重ねていますが、同書の中に、上掲の字典やシステムには見られない、特殊な文字が用いられていました。まずはその前後の一節を掲げましょう。
天正十二(三)年乙酉五月七日、三十世邦胤御捐館也、はしめ北条氏政の妹(娘)ひめを娶られける、その腹に十二にならせ給へる姫きみと、三にならせ給ふ御曹子のおハしける、国の面々揃ハさるゆへ、原豊後(前)守(胤長)・同大九郎(邦長)父子の養にて氏政の末子(直重)一人を請れて、十二歳なる姫に合せまつり、屋形に仰き申さるへきよし、北条氏、尤の事なれハと、天正十三(四)年丙戌十一月御馬を出され、佐倉へ御越しにて、かしまの城御取定となりける、
【私訳】天正13年(1585)5月7日、当主の千葉邦胤が没した。邦胤ははじめ北条氏政の娘(芳桂院殿)を娶り、姫君と御曹司(亀王丸=重胤)をもうけたが、亀王丸は邦胤が没した時、わずか3才だったため、一国の当主となるには早すぎた。そこで北条側へ、原胤長と邦長父子が後見となって、氏政の末子である直重を招請、12歳の姫君を妻とし、千葉家当主に迎え入れたいと伝えた。北条側は尤ものことであるといい、これを受けて北条氏直は、天正13年11月、佐倉に進軍し鹿島城を築いたのである。
『千学集抜粋』はこのように伝えます。この一件は当主邦胤の死没に端を発したとも、あるいは、それ以前からの、家中における北条派と反北条派による内紛がからんでいたともいわれますが、ともかく北条派は氏直に対して佐倉への進軍を求め、これに応じた氏直は佐倉領内に新たな城(鹿島城)を築きます。そして反対派を主導していた原親幹も、北条氏への忠節を誓う起請文を差し出して屈服。氏政の五男直重が千葉の家督を継承することとなりました。詳細は小笠原長和「戦国末期における下総千葉氏」(『中世房総の政治と文化』吉川弘文館,初出1970年)、黒田基樹「北条氏の佐倉領支配」(『戦国大名北条氏の領国支配』岩田書院,初出 1991年)、当館編刊の図録『戦国時代の千葉氏』(2017年)等を参照ください。黒田氏は上掲『千学集抜粋』の記事について「かなり信用しうるものと思われる」と指摘します。
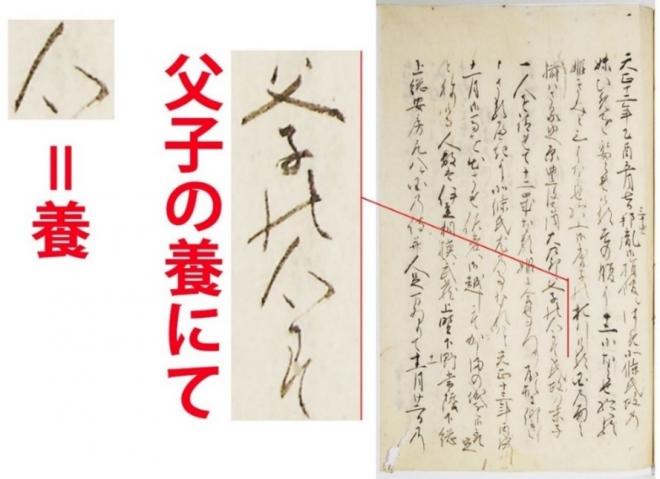 |
| 『千学集抜粋』(個人蔵) |
さて当文を伝える『千学集抜粋』の原文は、図版のとおりで、直重を当主として招請する一段は「原豊後守・同大九郎父子の養にて氏政の末子一人を請れて」です。ちなみに「養」には「うしろみ=後見」の語意があるので、当該部は「原胤長と邦長父子が後見となって、氏政の末子である直重を招請し」と私訳した次第です【補注1】。
ところで「養にて」と読んだ箇所【図版中央】ですが、これまでは「心にて」とか「人にて」と読まれていました。けれどもそれでは文意が通じませんし、字形【図版左】は「心」でも「人」でもなく、「人」のような字形の間に「 、」が打たれています。
このたび、この一字を「養にて」と読み改めたのですが、この字形「養」は、一般的にはあまり用いられていないのか、前掲の『くずし字用例辞典』にも採録されず、「史的文字データベース連携検索システム」で検索してもヒットしません。手元にある『異体字解読字典(新装版)』(柏書房)275P、『難字・異体字典』(国書刊行会)374Pに「養」の異体字が多く収載されるも、この字形はあげられていません。
では何を根拠に、この字形を「養」と読んだのかというと、仏教典籍に散見される同字形です。この字形は「供養(くよう)」「孝養(きょうよう)」など、仏教典籍に頻出する「養」の略字・異体字として多用されているため、「養」と判断することができました。文意としても通じると思います。ちなみに川澄勲編『仏教古文書字典』(山喜房仏書林)も、この字形を「養」として収載しており、同事典の末尾に掲げる「異体文字集」も同断です(有賀要延編『仏教難字大字典』〔国書刊行会〕には未載録)。参考までに同字典から具体的な「養」の異体字・くずし字を、わたくしに写して掲げましたのでご覧ください。また『千学集抜粋』に頻出する「養子」の字形を、左に4点掲げましたが、『千学集抜粋』では、異体字のほか、一般的な「養」のくずしも用いています。
 |
この他にも、字典に載っていないくずし字・異体字等は多く、私は古文書解読中にそんな文字と出会った時は、当該文字のコピーをとって、手持ちの字典に貼り付けることにしています。そうすることで、座右に据える字典類に未収載の文字が増補され、くずし字や異体字に関する知識を広げることができるのです。とはいえ、かくいう私も読めないくずし字・異体字の方が圧倒的に多く、解読に難儀する日々です。
昭和から平成にかけて、『中世法制史料集』をはじめとする基本テキストを編んだ佐藤進一氏は、次のように語ります。
最も信頼すべきテキストは原本の外にはないが、誰でも原本を利用するという訳にいかないとすれば、精巧な影印は公開された最良のテキストということになろう。しかし、この影印を利用するには、どうしても翻字という作業を経なければならない。翻字に当っては、文字の誤記や誤写を正し、欠字や虫損部分に可能な限り推定注を施し、錯簡・竄入・脱落を正すなど、校勘の作業が行なわれる。言ってみれば、翻字によって影印は生かされ、影印によって翻字の価値が証される。
*「よいテキストへの願い」(『早稲田大学蔵資料影印叢書 月報8』1985年)
以下省略しますが、佐藤氏はテキストに補注をほどこす場合にも確固たる裏付けが必要と指摘します。また佐藤氏に師事し、やはり『中世法制史料集』等の編纂に従事した笠松宏至氏は、
佐藤氏に師事して六〇年近く、私は古文書解読の三要素ともいうべき、くずし文字の解読、中世語彙の知識、そして文体のもつ論理性、それぞれに於ける氏の恐るべき能力に長く接してきた。 *「この書と過ごせた幸せ」(岩波書店『図書』746号,2011年)
とのこと。ここで笠松氏のあげる「古文書解読の三要素」、また前掲佐藤氏の一文を肝に銘じ、よりよい史料集を刊行するため、今後も校訂作業に従事してまいります。なお図版掲載にあたり所蔵者よりご許可を賜りました。衷心よりお礼を申し上げます。誠に有り難うございました。
【補注1】
「養にて」の「にて」は、あるいは「す(春)」にもみえる。実際『字典』類の「す」に、これとまったくの同型がみられる。ただし筆跡は個人差があるので、筆者の特徴を把握した上で判断をする必要がある。全体『千学集抜粋』(清宮家本)書写者が筆記する「にて」「す(春)」「は(盤)」は酷似する字形が散見される。そこで同書で用いられる「にて」「す」「は」を摘記して比較し、特徴と相違点を見いだした上で、当該文字を「にて」と判断した。下に掲げた図版を参照されたい。
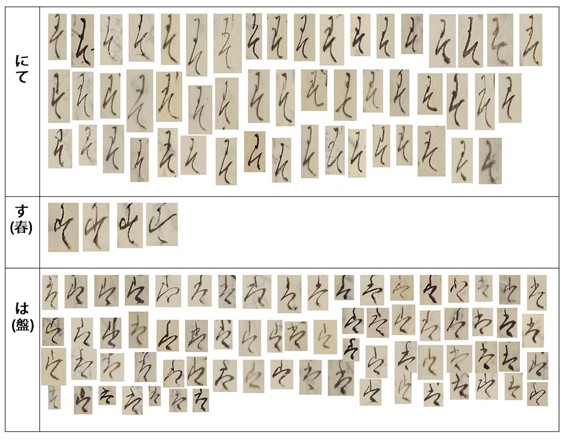 |
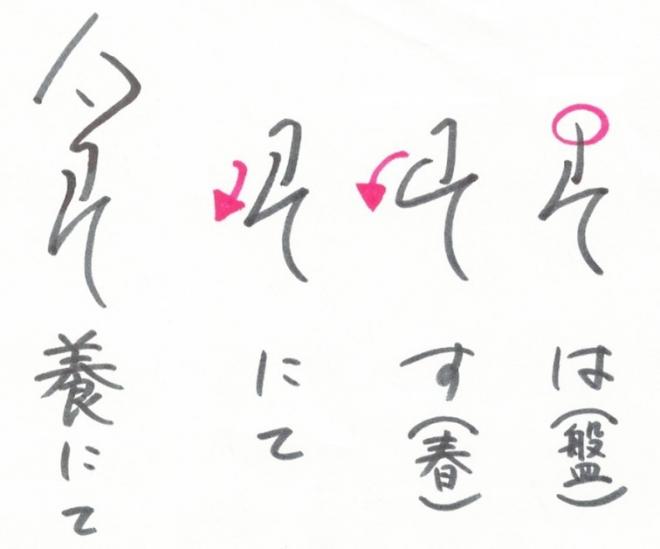 |
| *それぞれの字形で特徴的な入筆部や筆の流れを赤ペンで示した。 |
『千学集』メモ①(その成立過程と作者のことなど)
ようやく『千学集抜粋』(以下「抜粋」)諸本の、一回目の校訂作業を終えました。「抜粋」によると、標記の『千学集』は全3巻からなる書物だったとのこと。しかし残念なことに、たびかさなる火災【注1】で焼失してしまったのか、現在、原本はおろか、写本さえも確認されません。そんなことから『千学集』は逸書(書名だけが伝わる書物)として扱われ、「抜粋」から原形をしのぶしか、手立てがないとされています。
ただこれは私の希望的観測かもしれませんが、おそらく『千学集』3巻の写本は妙見宮金剛授寺と関わった寺社など、どこかにあるはずで、その発掘作業につとめなければと思う昨今です。今回はとりあえず、校訂作業や関連資料の披見によって気づいたこと、二、三を報告したいと思います。
「抜粋」を通覧すると、記事の執筆時に書き込んだと思われる年号が散見されます。ざっと挙げてみましょう(いまだ活字で紹介されていないものも含みます)。
永禄二年庚申まて七十九年也 *干支や前後の記事から「二」は「三」の誤記とみられる。
永禄三年(1560)庚申まて凡四百三十六年
永禄三年(1560)庚申まて凡三百八十六年也
永禄三年(1560)庚申まて凡百五年也
永禄三年(1560)庚申まて凡百二十年也
永禄三年(1560)庚申まて凡五十五年也
永禄三年(1560)庚申まて凡そ二百八十一年也
永禄三年(1560)庚申まて凡二百六十二年也
永禄三年(1560)庚申迄也
永禄三年(1560)庚申迄、凡六百廿七年也
天正二年(1574)甲戌まて凡三百四十三年也
天正四年(1576)丙子まて凡三十五年なり
天正十年(1582)壬午まてに四百六十一年
天正十年(1582)壬午まて凡五百九十二年也
天正十年(1582)壬午まて六十六年也
天正十三年(1585)乙酉迄凡四百六年也
永禄三年(1560)庚申より此世(寛文6年=1666)まて百五年也
これによって、上掲年のそれぞれに、当該記事が増補されたとわかります。かように『千学集』は書きたし書きつがれ、成立した書物です。むろん上掲の年はそれぞれに、何らかの意義があるはずです。特に頻出する「永禄三年」が、一つの画期であったことは炳焉で、同年にはじまり、千葉一族にも影響をあたえた小田原城の戦いにも留意しなければなりません。また金剛授寺住持や千葉氏当主の代替り、死没等もあげられましょう。これに関する記事を一つ示すと、
第十五 権大僧都覚全 廿九世 胤富養子〈千葉養運子〉
一、金剛授寺立て後、天正十年壬午まて凡五百九十二年也、
一、屋形様三十余世にならせられ、当寺は十五世なり、屋形様御二男をハ当座主になさるゝ也、
とあります。この記事により天正10年の増補は、金剛授寺15世覚全、千葉当主29世胤富の代に行われたことがわかります。それぞれの年記にこめられた意義については、なお検討したいと存じます。また上掲の年記はあくまでも「抜粋」に記されたもので、これ以外にもあまた増補されたであろうことは、いうまでもありません【注2】。
それから「抜粋」には、享徳3年(1454)正月2日、千葉胤直の郎党、片野胤定の夢中に現れた妙見が二首を詠じ、これを左衛門太夫秀義が『千学集』に入集した、との記事があります(原文=二首の御詠歌を左衛門太夫秀義、千学集の中へ書入おかれし也)。時期は定かではありませんが、『千葉妙見大縁起絵巻』を併読すると、秀義は当該期に活躍した人なので、『千学集』は1450年頃には、その下地ができあがっていたと推断されますし、頃日、左衛門太夫秀義その人が、『千学集』の作成に関わっているのではか、と思いつつあります。
「抜粋」によると妙見宮の神職は「八人の太夫、四人の早乙女」等からなっていましたが、「むかしより(妙見宮の)大禰宜殿をハ左衛門太夫と申ける」〔( )内筆者〕といわれ、「八人の太夫の事、第一左衛門太夫は」云々とあることから、「左衛門太夫」は妙見宮の筆頭職にあったことがわかります【注3】。
そのことを踏まえて「抜粋」の「二首の御詠歌を左衛門太夫秀義、千学集の中へ書入おかれし也」をみると、秀義は〝妙見宮の筆頭(左衛門太夫)として〟『千学集』の内容に関与する立場だったことがわかります。より踏み込んだ解釈を試みれば、この一節は「妙見宮筆頭の大禰宜である左衛門太夫秀義が、千学集を編んだ時に妙見の神詠二首を入集した」と敷衍することも可能ではないでしょうか。
一体『千学集』とは「千文字・葉文字の二字を題として、よろつことの葉を続けて、年中の事を顕ハし」たもので、多くの詠歌が収められていたと思われます。その一首が「抜粋」に引かれる「神代より とり伝へたる 鈴の音を 聞て〝千〟とせの はるにあふかな」で、左衛門太夫秀義が入集した二首も、千葉宗家の滅亡を予見し「年中の事を顕ハし」た神詠です。なお「左衛門太夫秀義、千学集の中へ書入おかれし也」のくだりは、まるで他書について述べているようで、若干の違和感をいだかせます。しかし追々述べるように、「抜粋」は、たんに『千学集』の本文を抜書したものではなく、メモをはじめ私的な書き入れがかなりあると判断されますので、異とするにたりません。
ともかく左衛門太夫秀義は『千学集』に神詠を収録するなど、『千学集』の編集に関わったことは間違いなく、『千学集』編者(あるいはその一人)として挙げるべき人物といえましょう。本件については、なお追尋しますが、諸賢のご高見をいただければ幸甚です。
その後、『千学集』は妙見宮の建立から遷宮にいたる、天文16(1547)~19年頃の記録をまとめて追加し、永禄3年(1560)にも多くの記事を追加。以降、上掲のとおり、天正2年(1574)、同4年、同10年、同13年、そして江戸時代にいたるまで、増訂作業は続けられたのです。
それから先日、邨岡良弼の『千葉日記』を読んでいて、興味深いと記事と出会いました。すなわち邨岡は日記に『千学集』を引用し「此書ハ天正二年の奥書ある本なり」(30丁ウ)と記しています。私が「抜粋」の年号に着目したのは、この記事を機縁としているのですが、邨岡のいう「天正二年の奥書ある本」によって、この時点で、記事が増補され、ひとまず擱筆された本のあったことがうかがえるのです。そこで上掲のように「抜粋」の年号を拾ってみたところ、予想どおり「天正二年甲戌まて凡三百四十三年也」と、同年に記事が増補されていたことがわかりました。邨岡がみたのは、この本だったのでしょう。引文も清宮家本とは異なっている箇所があって、「池内」(清宮家本)が「池田殿」(邨岡引文)となっています。
残念ながら、邨岡の披見した「天正二年の奥書」を有する『千学集』は所在不明ですが、おそらく『千学集』は天正2年に写された本だけではなく、上掲年のそれぞれに擱筆された本の写しが多数存在し、それを転写した諸本も数多くあったと考えられましょう【注4】。
なお邨岡は明治25年2月3日に、内閣文庫本の『千学集抜粋』も写しています【注5】が、その所在も不明です。
最後に小括をしめせば、『千学集』は、あるいは妙見宮大禰宜、左衛門太夫秀義によって起筆され、その後、増補をくりかえして成立した書物であり、中途で出回った諸本が多数存在したと考えられます。その一つが邨岡良弼が『千葉日記』に引用した「天正二年の奥書ある本」で、少なくとも幕末期には、諸本の存在は邨岡や清宮秀堅らの知るところでした。
清宮秀堅は「抜粋」を書写する前に、すでに『下総国旧事考』にて『千学集』を活用していますが、その件については、また次回のべたいと思います。
【注1】
『千葉市史 現代編』第三巻(1974年)によると「明治三十七年(一九〇四)の火災では社殿のほか、宝物古文書の大部分が失なわれ」、また「昭和二十年七月の空襲によって、建物のすべてを焼失した」(360P)という。
【注2】
たとえば次の「徳川家康判物」(天正19年=1591)は、宮寺の歴史を語るに不可欠な史料で、『千学集』にも記載があったと思われる。
寄進 妙見堂
下総国葛飾郡千葉郷之内弐百石之事
右、如先規令寄附訖、殊寺中可為不入、弥守此旨権行等、不可有怠慢之状如件、
天正十九年〈辛卯〉十一月日 大納言源朝臣(家康)(花押)
(『新修徳川家康文書の研究』201P)
このように家康から妙見堂に二百石が与えれた。「御尋之箇条(妙見堂由緒書・霊宝目録)」(千葉市立郷土博物館『研究紀要』9号24P)は本件に関して、
天正年中に至て、権現様当所御成の時節、当山妙見へ御参詣の砌、寺号御尋遊さるゝに付て、金剛授寺と申上処に、御上意として幸ひ妙見の別当寺なる程に妙見寺可然よし仰出さるゝの間、それより以来金剛授寺を改め妙見寺と号す、其上天下安全御武運長久の御寄付として、弐百石の御朱印其時の住持法印覚全奉拝納者也、
といっている。天正19年は金剛授寺から妙見寺へ寺号を改めた年でもあり、同年『千学集』にも、類似する記事が増補されたと思われる。なお『諸国寺社朱印状集成(埼玉県史料集 第6集)』(埼玉県立浦和図書館,1973年)所載のグラビアをみると、上掲の「徳川家康判物」は、花押型はかろうじて確認されるものの、墨で塗りつぶされている。
【注3】
「抜粋」によると、左衛門大夫は、千葉当主・座主が並座する正月3日の恒例神事(御鈴)において、妙見の御前にすすみ「万歳楽」を三度ささげていたという。
【注4】
土屋賢泰「『千学集抄』をめぐる問題」(川村優編『論集 房総史研究』名著出版,1982年)は、『下総国千葉郷妙見寺大縁起』の記事から「十七世紀半ばころに金剛授寺の縁起が住僧の交代などの際にもち去られて、坂尾(千葉市大宮町)の栄福寺に移ってしまっている事情」を読み取り、紀琴夫が『千学集抜萃』を書写した弘化3年(1846)当時、はたして『千学集』の原本が金剛授寺にあったかどうか、一考を要するとし、原本の所在は栄福寺か他の場所も想定されると指摘する。『千学集』諸本の存在や所在について考えるにあたり、留意すべきことである。ちなみに『和学講談所書籍目録』をひらいてみると、『下総国千葉郷妙見寺大縁起』の書目は挙げられているが、『千学集』はみえない。なぜ史料収集に余念のない塙保己一らが、詳細な『千学集』ではなく『縁起』を採ったのか疑問に思っていたが、その理由は、あるいは土屋氏の仮説どおり、当時の妙見寺に『縁起』はあっても『千学集』がなかったからではないか。なお和学講談所に所蔵されていた『下総国千葉郷妙見寺大縁起』は、現在、内閣文庫に所蔵され、首題下に「和學講談所」の蔵書印がおされている。
【注5】
大森金五郎筆写本『千学集抜粋』本奥書(神奈川県立金沢文庫蔵)。
『千学集』メモ②(抜粋・清宮家本の筆者・書名について)
「千学集抜萃(粋)」(以下「抜粋」)の書名については、清宮家本(現在確認される最古写本と思われる)の内題に「千学集抜萃 本題千学集内抜書」と書かれていて、諸本の伝える内題も全同です。書名どおりに解釈すれば、「抜粋」はまさしく『千学集』の本文を抜粋・抜書した書物となりますが、清宮家本を通覧するに、とてもそうとは思えぬ箇所が多数存在します。一例をしめせば「抜粋」に、
さて本所武蔵国藤田良文のおはすところ、文次郎いえゐのくらにあんちし奉りて、二人の娘をやおとめとして、みつから太鼓うちて神楽申上る也、そのゝち秩父の大宮へ移らせ給ふなり、又鎌倉の村岡に移りて村岡五郎と申也、
とあります。当文は平良文の郎党である文次郎が、妙見像を遷座したり、妙見像へ神楽を捧げていたこと等を伝える記事ですが、清宮家本(個人蔵)の当該部はどうなっているのかというと次のとおりです。
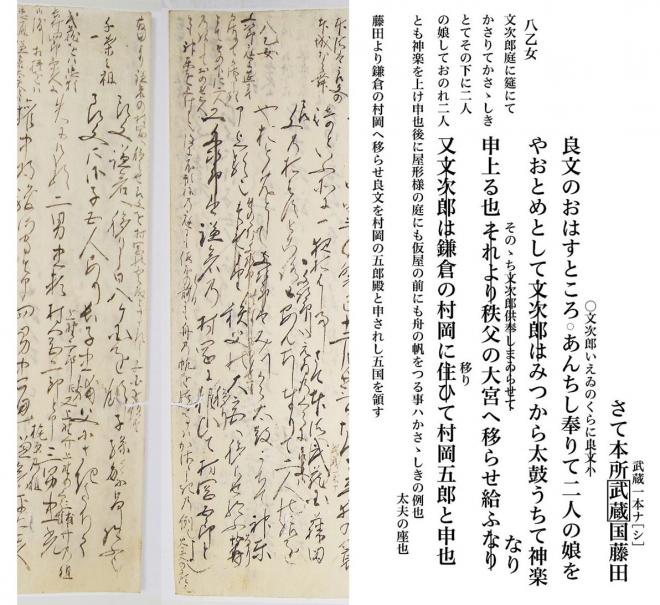 |
もはやたんなる誤写の訂正、書き直しとは思えない書きようです。上掲どおり清宮家本は、見せ消ちをくり返し、挿入符を用いて本文を補い、あるいは天地行間に細字をもって類似する文章(おそらくは異本)を書き加えるなど、本文に推敲のあとが歴然としていて、筆者が諸本を校合しながら、成文したとみなされるのです。その他にも、清宮家本には「イ」(異本のこと)の注記が散見されます。
そこで問題となるのは、清宮家本の筆者は誰か、ということですが、本書の奥(下図=個人蔵)に、
原本金剛授寺所蔵、丙午(弘化3年=1846)秋八月念四紀琴夫所手写也、
佐原 清宮氏所蔵[印](朱)
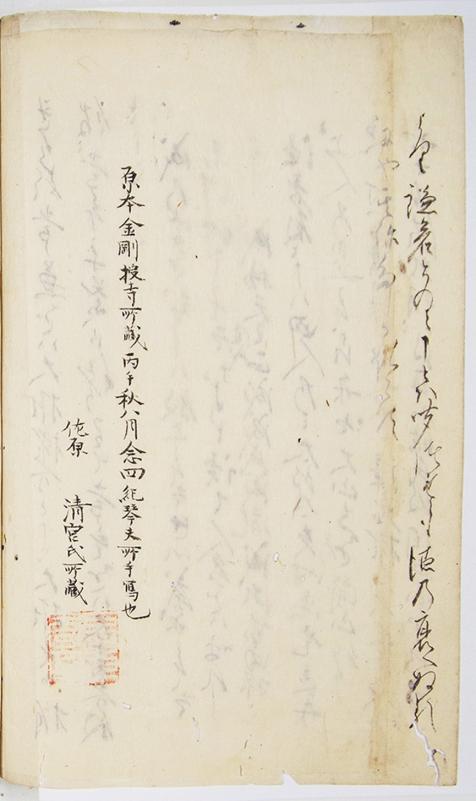 |
と見られます。しかしこの2行は本文の筆蹟とは明らかに異なり、またこの2行を記す料紙も、本紙(最終紙)の後部を切り取った上で、つぎたした形跡がみられ、その扱いは注意を要します。
また別紙2行の筆蹟は「原」「所」「蔵」をはじめ「紀」の糸偏など、かなり特徴的なので、これは筆者を特定する際の有力な判断材料となりましょう。本紙と別紙を一連のものとみなせば、本文は紀琴夫、別紙2行は清宮秀堅筆と思われますが、清宮家本の本文・別紙それぞれの筆者については、あらためて筆蹟照合や、かすれた印文を熟視して解読するなど、検討したいと思います。
いま少し別紙2行について記しておくと、千葉県立中央図書館所蔵本(恩田信の旧蔵本)には、別紙2行の一文は存在せず、本文も清宮家本と比較するに、あるいは別系統の写本とも考えられます。また内閣文庫所蔵本は、別紙2行の文を朱書しており、朱を用いたのは本文とは別筆とみての処置なのか、あるいは後に諸本と校合する中で書き加えたのか、内閣文庫本の本文と朱筆の筆蹟の異同など、これまた検討課題です。ちなみに内閣文庫本は「紀琴夫〝所〟手写也」を「紀琴夫〝書〟手写也」としており、その系統に属す大森金五郎写本も同断です【注】。
次に末尾2行にみえる紀琴夫ですが、彼は医師であり、それほど千葉一族や金剛授寺等に関する知識があったとも思えず、紀琴夫が『千学集』の主要部を取捨選択して抜粋し、上掲のように諸本を校合しながら成文したとは考え難いものがあります。
幸い清宮家本については、近く原本調査を予定しており、それによって清宮家本の本紙と別紙との関係、筆者や印文について、なんらかの成果を得られるでしょう。追ってご報告申し上げます。
ところで清宮秀堅は、弘化2年(1845)脱稿の『下総国旧事考』にて、すでに『千学集』を活用していますが、秀堅は『同』巻四(第二本31丁ウ)、および巻十一(第六本23丁ウ)に「千学集」・「千葉集〈一名金剛授寺大縁起〉」の書目をあげ、巻十一では「千葉集五巻〈一名金剛授寺大縁起〉」と、その巻数も記しています。ここにいう「千学集」「千葉集」は、同一の書籍と判断されますが、版によって表記の異なるところがあり、これまた原本調査を要しましょう。
それから書名については「抜粋」に関連する記事があって、
一、千学集と申は、御家代々引付と妙見御相伝の正月三日の夜の修正とハ、千文字・葉文字の二字を題として、よろつことの葉を続けて、年中の事を顕ハし給ひて、妙見の御前にて慚愧懺悔をし、年中の悪念を払ひ祭ることの御鈴なり、是御一門及国内繁昌の御祈念也、
神代よりとり伝へたる鈴の音を
聞て千とせのはるにあふかな
鈴の音にあしきをあつめふりすてゝ
よしとそおもふあら玉の春
此千学集は三巻にて、千文字一巻、葉文字一巻〈上下にて二巻〉なり、是ハ委しく御家事を注(シル)し申おくなり、
とあります。ここにいう「千文字・葉文字の二字を題として、よろつことの葉を続けて」、「千文字一巻、葉文字一巻〈上下にて二巻〉」からすると、書名が『千葉集』であれば得心がゆきますが、なぜ千〝葉〟ではなく千〝学〟となったのでしょうか。
奥山市松氏が『紀元二千六百年記念 房総叢書』3巻(1941年)に「なほ、書名は今『千學集』として知られて居るけれども、元來は『千葉集』と稱したものであらうかと思う」(169P)とするのも一案ですし、前掲の清宮秀堅ほか、大森金五郎も「千學集〈一名千葉集と云ふ〉」【注2】といい、また「千葉氏の盛時(ムサシ)の情況(サマ)を知らむにハこの千學集なむ尤善(イトヨケ)れ」【注3】と位置づけていた邨岡良弼は「千學集一〈一名千葉記〉」【注4】といっています。
どうして「千葉」ではなく「千学」なのか。また清宮秀堅『下総国旧事考』にいう「千葉集五巻〈一名金剛授寺大縁起〉」や、前回とりあげた邨岡良弼のいう「天正二年の奥書ある本」は現存しないのか。そして末寺の縁起などの記録類は、本寺にあげられることが常ですから、関係寺社の記録も調べる必要がありましょう【注5】。さらに『千学集』の原形をさぐるにあたってキーマンとなる、紀琴夫・清宮秀堅・邨岡良弼の三者についての調べなど、問題・課題は山積です。
次回は「抜粋」にみられる御達報(ごたっぽ)についてとりあげます。
【注1】この場合、文意は紀琴夫を「書手」として『千学集』を写してもらった、となろうか。ちなみに紀琴夫は「詩文・書道にも長じていた」(『干潟町史』1975年。1650P)という。いずれであれ、原本調査をまちたい。ちなみに大森金五郎写本は内閣文庫本に属するが、大森が底本としたのは邨岡良弼筆写本である。邨岡の写本は神宮文庫に所蔵されていることがわかったので、これまた調査を期したい。
【注2】大森金五郎「平忠常の事蹟追考」(『歴史地理』2巻4号,1900年)。なお大森は同稿にて「此書はもと金剛授寺所蔵であつたのを、佐原の清宮氏が手写したのである、千葉氏の由来及び妙見社の儀式等を記し、天正年間の記事を以て終る」といっている。大森による清宮家本の筆者や記事の終見に関する認識を端的に示している。当文は吉田東伍「千葉城址」(『大日本地名辞書』下巻,1907年=第2版。初版は未確認)に「歴史地理雑誌云」として引用される。ただし吉田は書名を「金剛寺千学集」とする。
【注3】邨岡良弼『千葉日記』明治十三年八月八日条。邨岡は「抜粋」も写していて、大森金五郎写本の本奥書に「明治二十五年二月三日以内閣文庫本写之 邨岡良弼[印]」とある。つまり『千葉日記』の記事によって邨岡もまた、「抜粋」の書写前に『千学集』を活用していたことがわかる。前掲【注1】のとおり、邨岡の写本は神宮文庫蔵。
【注4】邨岡良弼「下総國地誌材料書目」(『歴史地理』4巻7号,1902年)。
【注5】たとえば『妙見実録千集記』の冒頭には、「高野山蓮華三昧院に頼申時系図書登せ候」など、系図や一族の由緒が、折に触れて作成・提示されていたことが列挙されている(『改訂房総叢書』第二輯223~4P)。
(付記)当コラムに『千学集抜粋』の図版を掲載するにあたり、ご許可を賜りました所蔵者に甚深の謝意を表します。誠に有り難うございました。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください





