千葉市動物公園 > アカデミア・アニマリウム(教育・研究) > アカデミア・アニマリウム講演会 > ちばZOOフェスタ・2022~アカデミア・アニマリウム~
ここから本文です。
ちばZOOフェスタ・2022~アカデミア・アニマリウム~
更新日:2024年4月24日

動物園の社会的役割として、「種の保存」「調査研究」「教育普及」「レクリエーション」があります。千葉市動物公園では、さまざまな学校、研究・学術団体、企業との連携も含め、包括的な調査研究、教育普及活動を「アカデミア・アニマリウム」と称し、活動を推進しています。
「ちばZOOフェスタ・2022」では、その成果の一部を口頭発表とポスターで発表します。
口頭発表
日程
11/5(土)・6(日)
定員
130名
場所
動物科学館1Fレクチャールーム
ZOOM配信
現地での発表に加え、ZOOMでのライブ配信も行います。
下記のURL、もしくはQRコードを読み込み、ご参加ください。
URL :https://zoom.us/j/96229732297
QRコード:
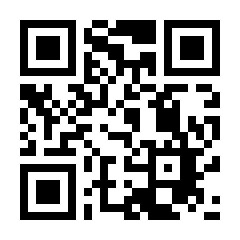
※アーカイブでの配信は行いません。
※一度に視聴できる人数が500名様までのため、同時視聴者数が多い場合ご覧いただけない可能性がございます。あらかじめご了承ください。
内容
①9:45~10:05
「アカデミア・アニマリウム」イントロダクション-動物園の歴史的経緯とその役割について-(発表者:千葉市動物公園長 鏑木 一誠)
アカデミア・アニマリウムの開催にあたり、イントロダクションとして、動物園の歴史的経緯と課題、そして社会的役割についてご紹介させて頂きます。
②10:10~10:25
メスのアジアゾウの夜間放飼によるQOLの向上(発表者:千葉市動物公園職員 水上 恭男)
当園のアジアゾウの雌は夏場になると収容が遅くなることが通年ありました。これらの元となる要因を推測し、飼育形態を屋内から屋外に変更することでどのような改善点がみられたのかを発表します。
③10:30~10:45
テンジクネズミの尿石症を予防するための餌の見直し(発表者:千葉市動物公園職員 林 七海)
テンジクネズミの尿石症は、テンジクネズミの泌尿器疾患で多く、以前、尿石症が原因で死亡した個体もいました。療法食で治療できず、また体が小さいことや、動物の体に負担がかかるため、手術で治療することも難しいです。ですが、テンジクネズミの尿石症は予防することが出来る病気なので、餌に含まれるカルシウム、水分、ビタミンCの量に着目し、餌を見直すことで発症を予防しました。
④10:55~11:10
カリフォルニアアシカのトレーニング方法の再考(発表者:千葉市動物公園職員 鈴木 克典)
当園ではカリフォルニアアシカの個体ごとにあった給餌管理のため、トレーニングを通じて餌を与えていました。しかし2019年の担当変更以降、担当者に対するオスの圧が強く危険を伴ったためトレーニングを中止しました。これによりアシカの給餌管理が出来ず肥満化や、個体を誘導できなくなる問題が発生してしまいました。そこで、トレーニング方法の再考し、オスとメスの立ち位置やトレーニング時間の見直しによりトレーニングの再開を目指しました。
⑤11:15~11:30
アミメキリンの健康管理に向けたトレーニング(発表者:千葉市動物公園職員 足立 仁之)
⑥11:35~11:50
レッサーパンダの幼獣の雌雄判別(発表者:千葉市動物公園職員 濱田 昌平)
⑦9:45~10:10
社会問題とアニマルウェルフェアをつなげる~屠体給餌を例に~(発表者:豊橋総合動植物公園 伴 和幸様)
野生下の採食に近づけるために,大型動物の死骸を毛皮や骨がついたまま与える「屠体給餌」が注目されています.国内では,鳥獣被害対策として駆除され,多くが廃棄されているイノシシやシカを活用した屠体給餌が普及し始めています.このような屠体給餌は,動物福祉の向上だけでなく資源を無駄にしない倫理的取り組みであり,動物園を通して獣害問題を知り,身近な野生動物との関わり方を学ぶ環境教育としての機能を併せ持っています.
⑧10:15~10:40
屠体給餌プロジェクトのいま(発表者:千葉市動物公園職員 中山 侑)
千葉市動物公園では皆様にご協力いただいた「屠体給餌クラウドファンディング」の支援金により、屠体給餌の科学的検証を進めています。具体的には、屠体給餌の栄養面での有用性や適切な栄養管理を行うための方法、また長期間に渡った屠体給餌によるライオンやハイエナの行動の変化を調べています。今回は現在の状況についてご報告させていただきます。
⑨10:45~11:00
屠体給餌によるハイエナの行動変化(発表者:東邦大学 行動生態学研究室学生)
千葉市動物公園では、ライオンやハイエナに皮や骨がついたままの肉を与える屠体給餌が行われています。屋内及び屋外で撮影された動画を用いて、給餌前後の動物たちの行動の変化について調査を進めております。今回の発表では、寝室におけるハイエナの行動の変化に焦点を当てて発表します。普段の展示場では見られない行動をお見せいたします。
⑩11:10~11:25
フタユビナマケモノの空間利用と活動について(発表者:茨城大学 動物福祉管理学研究室学生)
千葉市動物公園では、フタユビナマケモノは熱帯雨林を再現した屋内展示施設「バードホール」で飼育されています。
昼間はほとんど動かないナマケモノですが、日が暮れて夜を迎えると大きなバードホール内のあちこちを移動したり、
餌を食べたりと実はせっせと活動しているんです!(動きはのんびりですが...)
そんなナマケモノの 1 日の滞在場所や行動が季節と共にどのように変化するのかを明らかにする調査についてご紹介致します。
⑪11:30~11:45
飼育下チーターの放飼順に伴う発情行動と個体関係の変化(発表者:東京農業大学 野生動物学研究室学生)
チーターは絶滅の危機に瀕しており、動物園での積極的な繁殖が求められています。しかしながら、雌の発情には雌同士の優劣関係や雄との間接的な接触が影響することから、繁殖には各個体の放飼順や個体関係を考える必要があります。そこで本研究では、放飼順の違いが雌雄他個体の発情行動と個体関係をどのように変化させているかを明らかにすることで、動物園のチーターの繁殖に適切な飼育管理を行うことに貢献します。
⑫11:50~12:05
千葉市動物公園のハシビロコウにおける繁殖成功にむけた調査―個体間関係と営巣行動―(発表者:北里大学 動物行動学研究室学生)
飼育下におけるハシビロコウの繁殖は難しいとされており、動物園での繁殖成功は現在まで2例しか報告されていない。日本においてはハシビロコウを飼育している8施設のうち、無精卵ではあるが千葉市動物公園の個体でのみ産卵が確認されている。本研究では、繁殖阻害要因として個体間闘争と営巣行動に着目した観察をおこなうことで、季節変化により各行動回数がどのように変化していくか比較・検討をおこなった。
⑬12:10~12:25
千葉市動物公園のチーターの父子鑑定(発表者:東邦大学 行動生態学研究室学生)
チーターは、メスが一度に複数のオスと交尾をするという乱婚的な配偶システムをもちます。そのため、野生下ではきょうだいで異なる父親をもつことがあります。千葉市動物公園で6頭の子どもが産まれましたが、3頭のオスがメスと交尾をしていたので、父親が誰なのかわかりませんでした。そこで6頭の子どもの父親をそれぞれDNA解析により判定しました。本発表では、DNA鑑定の方法の詳細などについて発表します。
ポスター発表
ポスター掲示による発表
日時
11/5(土)~11/6(日)9:30~16:30
場所
動物科学館2階特別展示室
内容
- 口頭発表内容②~⑥を含む25枚のポスターを掲載
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください






